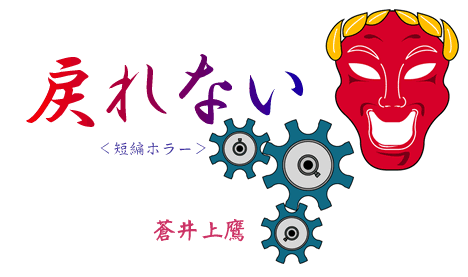
五十を越えてから、視力の衰えを勘で補うようになった。その夜、侵入者に気づいたのも、その勘のおかげかも知れない。布団に入っても目が冴えて眠れないので、寝酒の一杯もやろうかと階段を下りてきたところだった。奥の和室には、一昨日から遊びに来ている弟が寝ている。起こさないようにと足音を忍ばせたのだが、そんな気遣いが馬鹿馬鹿しくなるほど傍若無人な鼾(いびき)が聞こえてきて、思わず顔をしかめた。
ふと違和感を感じて足が止まったのはそのときだ。階段の下のスペースには移動ラック書架が設置してある。その隙間の一つの闇の厚みが、他と僅かばかり違うような気がしたのだ。
手探りでスイッチを押すと、電灯の光に一瞬目が眩んだ。眩んだのは自分だけではなかったようで、書架の陰に縮こまっていた侵入者は、立ち上がろうとしてよろけ、棚に頭をぶつけて再びうずくまった。全身黒ずくめで、人相を隠すためか、ホラー映画に出てくるような悪魔のマスクをかぶっている。
「誰だ。そこで何をしている」
さほど動揺せずにいられたのは、侵入者の体格がかなり貧弱なことを見て取ったからだ。どうやら丸腰のようだし、もし格闘になっても、まず負けまいと自信が持てた。
「いやいや。怪しい者じゃありません」
侵入者は、しゃがみこんだまま両手を振り回した。しわがれた声の感じでは五十代後半というところか。
「ふざけるな。そういう台詞を言うやつが一番怪しい」
玄関への脱出路を塞ぐ体勢を取りつつ、武器になりそうなものを探す。生憎なにもない。いっそ隣の居間に駆け込んで、すぐに警察に電話しようかと思案していると、その考えを読んだかのように、
「け、警察を呼ぶと後悔しますよ」
と震え声で侵入者は言った。
「後悔? どういうことだ」
「あなた、蛭川順二さんでしょう。警察を呼ぶと、あなたも困るんじゃありませんかと言ってるんです」
意外な言葉に、すぐに返事が思い浮かばない。
こちらが怯んだとみたか、侵入者は、勢いこんで言葉を続けた。
「さっきキッチンの窓からあなたを見ていたんですよ。ブランデーのボトルに何か入れてたでしょう。人に見られないようにこそこそと。それで気になって調べに入ったんです」
「何が『こそこそと』だ。お前こそ何だ。人の家の中を覗いたり勝手に入り込んだり、立派な泥棒じゃないか」
「泥棒じゃありませんよ。この地区の見回りとか、道に迷った人の案内とか、そんなことをいろいろと」
「見回りだって? ふざけるな」
悪魔のマスクをかぶった見回りなんて聞いたことがない。迷子が見たら泣くぞ、絶対。
「信用しませんか。それなら警察に電話すればいい。この辺りのおまわりさんの顔なら大抵知ってますからね。こっちは全然平気です」
はったりに決まっているのだが、妙に自信ありげなのが気になる。
「ただし、そうなったらわたしも知ってることを残らず警察に話しますよ。それでもいいんですか? あのボトルの中身を調べられたら、困るのはそっちじゃないんですかねえ。第一それはあなたのボトルじゃない。ご兄弟のだ。人のお酒に何を入れたんですか。まさか薬じゃないでしょう。え、どうなんです」
心臓の鼓動が高まるのが判った。
「――見たのか、本当に」
「まだ疑うんですか。それじゃもう少し詳しく言いましょう。あなたは、銀色のシガレットケースからチューブ状の容器を取り出して、その中に入っている粉末をブランデーに混ぜたんだ。ご兄弟は寝室に引っ込んだし、通いの家政婦は明日の朝にならないとやって来ないから、誰にも見られっこないと思ったのでしょうが、生憎と月が明るくてね――今はちょっと雲行きが怪しいですが」
その言葉の出るのを待っていたかのように、遠くで低く雷が鳴りだした。冬場の雷とは珍しい。どことなく不吉な感じがした。
侵入者の話を聞きながらも、自然と視線は左手の閉まったドアの方に向いてしまう。寝酒のブランデーは、そのドアの向こう、居間のキャビネットにしまってあるのだ。
「そこを動くなよ」
とうとう我慢できなくなってドアを開けた。照明をつけずにキャビネットから寝酒のボトルを引っつかみ、すぐに廊下に戻る。ボトルを照明にすかしてみると、底の方に微量の異物が沈殿しているようにも見えた。が、断言はできない。ただの気のせいかも知れない。
「そんな怖い目で見たって何も判りませんよ」
いつの間にか侵入者は立ち上がっていた。声はすっかり落ち着きを取り戻している。
「それで――お前はこれからどうするつもりだ」
訊きながら、口の中がからからに渇いていることに気づいた。酒が飲みたい。いっそこのボトルからラッパ飲みしてやろうかという気狂いじみた考えが頭に浮かぶ。
ところが返ってきた答は意外なものだった。
「別に。今のところは何も」
「何も?」
「ええ。このまま帰していただければ、わたしは何もしません」
「警察に通報しないのか」
侵入者は肩をすくめた。マスクで表情は見えないが、笑いをこらえているようでもあった。
「だって、あなた、このまま続けるつもりはないでしょう。わたしに知られていると判っていて、そんなことができるわけがない。一旦ご破算にするのが穏便というもの」
「それはそうだ」
兄弟の問題は、どこかできっちりかたをつける必要があったが、それはまた別の話だ。こいつとは関係ない。
「それなら結構です。今日はお互い何も見なかったことにしましょう。では、今日はこれで」
そう言うが早いか、侵入者の手が電灯のスイッチに伸びた。一瞬後、周囲は再び暗闇に包まれた。
「さようなら、蛭川順二さん」
「違う。わたしは」蛭川順二ではない、と言いかけたが、急に高まる雷鳴が、それをさえぎった。空気がぴりぴりと振動し、思わず立ちすくむ。
それでも逃走を防ごうと、勘を頼りに狙いを定めてつかみかかったが、両手は空を切るばかり。
「待て」
無駄だと知りつつ叫んだ。が、やはり何の効果もなかった。
十数秒の空しい一人相撲の後、再び照明をつけたときには、侵入者の姿はどこにもなかった。
調べると、玄関の鍵が開いていた。戸締りを忘れるなんて、今までに一度もなかったことだ。まったく不用心にもほどがあると、ずいぶん後悔した。
蛭川太一、一生の不覚である。
だが、悪いことばかりではない。不用心のおかげで思いがけない情報を入手できたのだから。人生何が幸いするか判らない。
まかり間違えば、後悔するどころではすまなかったのだ。弟の順二に毒を盛られて、今ごろ自分は死んでいたかも知れない。
あの侵入者が順二とわたしを取り違えてくれたおかげで、わたしを脅迫するつもりが、わたしの命を救う結果になったのは皮肉なことだ。もちろん、見回りなどという弁解は信用していない。多分泥棒の常習犯だろう。それでも警察への通報を思いとどまったのは、結果的に命を助けてもらったことへの感謝の意を表すためと、弟の処置を考える時間を稼ぐためだった。
翌朝、弟は何も知らないという顔で朝食の席に着いた。どうやら騒ぎの間も目を覚まさなかったらしい。だが開口一番、
「昨夜は飲まずに寝たみたいだね」
と、わたしの顔を覗き込んだのは、どういうつもりだったのか。
「最近は飲まないようにしているんだ。健康に悪いからな」
適当にはぐらかすと、一瞬怪訝そうな顔をしたが、すぐに気を取り直して、瞬く間に自分の分のトーストとハムエッグを胃袋に納めたかと思うと、身を乗り出して本題に取り掛かった。本題――例によって例のごとく、金の無心だ。こちらがまだ食べているのも、話を聞かされて食欲がなくなるのもお構いなしだ。
「少しだけ援助してもらえれば、個展が開けそうなんだよ。描いてみたい土地の候補も幾つかあって、少し腰を据えればいいものができそうな予感がするんだ」
「少し? どのくらいだ」
「大体一箇所につき一ヶ月くらいかな」
必要な金額を訊いたつもりだったが、あっさりはぐらかされた。
それにしても、能天気に言い放つ弟の顔を見ていると、同じ兄弟で――しかも容姿は瓜二つと言ってよいほど似ているのに――どうしてここまで性格が異なるのか、疑問が浮かんでくるのを禁じえない。親の遺産にしても、十年前均等に分配したのに、わたしがそれを事業で数倍に増やしたのに対し、弟はあっさり勤めをやめて、画家を標榜してあちこち放浪し、まともな作品は殆ど発表せぬまま遺産を食い潰すと、それまでに得たコネにすがってたかりめいた真似までするようになった。
昨夜、侵入者の言葉を聞いてもさほど驚かなかったのはそのためだ。この弟なら、遺産目当てにわたしを殺そうとしても不思議はない。
うつむいて考え込んでいるわたしに、弟は声をかけた。
「どうしたんだ。元気がないね」
「昨夜よく眠れなかったんだ」
「そうか。おれもいつもは不眠症気味なんだけど、ここに来るとぐっすりだよ。やっぱり兄さんの家だと安心するのかね」
わたしはしばらく黙ってコーヒーをかきまわしていたが、やがて意を決して、
「ところで、お前にやりたいものがある」と口火を切った。
「へえ? 何だ」
「酒だよ。最近肝臓も弱ってきてるから、少し控えようと思ってね。例えば、寝酒にしてるブランデーなんか、口を開けてから一年以上経つのに、なかなか減らない。いっそお前みたいな酒の味の判るやつに飲んでもらったほうがいいんじゃないか」
「え。あのブランデー?」
弟は目を丸くすると、動揺を隠すかのように、カップ半分残っていたコーヒーを一気に飲み干し咳き込んだ。
「ああ。確かお前の好きな銘柄だろう」
「うん。そう。好きだよ。確かに。でもね――」
人からモノをくれると言われて首を横に振ったことのない弟が、断る口実を探している。やはり、あのブランデーには何かあると思ったほうがよさそうだ。
「それとも、最近はウィスキー一筋かな」
「そ、そう。そうなんだ。もっぱらスコッチだね」
弟はジャケットの内ポケットから銀色のスキットルを取り出して振って見せた。
「それなら仕方ないな。また今度ということに――」
「いや、それだったら」弟は唇を舐めた。
「ん?」
「せっかくだから、あれをもらえないかな。ほら、あの――」
弟が挙げた銘柄は、数年前友人から贈られて、まだ口も切っていない逸品のシングルモルトだった。
その瞬間、頭の後ろで何かのスイッチが入るのを感じた。
「ああ、いいだろう。ただ、すぐには見つからない。探しておくから待ってくれ」
「ありがとう。悪いね」
「個展の件も考えておく。税理士と相談する必要があるから、もう少し具体的な見積もりを出してくれ」
「あ、うん。判った。今日にでもアトリエに戻るから、そうしたら早速」
金が手に入ると聞いたら、すぐ帰ろうとするこの現金さ。もはや溜め息も出なかった。
食事の後、弟がシャワーを浴びている隙に、簡単な荷物検査をした。
まずシガレットケースの中に、侵入者の言った通りの容器が見つかった。白い粉末がスプーン二杯分くらい残っている。
バッグの中からは、わたしの寝酒と同じ銘柄のブランデーが出てきた。これも予想通りだ。もし首尾よくわたしを毒殺したら、ボトルに毒が入っていたと悟られないようすりかえるつもりだったのだろう。弟の経済状態で、自分で飲むために買ったとは考えられなかった。このボトルを見つけたとき、わたしの疑惑はほぼ確信に変わった。
浴室で弟が鼻唄を歌っている。それを聞きながら、容器に残った粉末を、弟のスキットルの中に混ぜ入れた。指紋を残さないよう用心したことは言うまでもない。
この粉末が何であろうと、弟が入手したものであることは間違いない。もし万が一、わたしの健康を心配して、こっそり薬を入れてくれたのなら、自分も飲んで健康になるが良い。どうぞご勝手に。また、これが本当に猛毒だとしたら、飲んだ弟が死んだとしても、自業自得というものだ。
シャワーを浴びてさっぱりすると、弟は挨拶もそこそこに帰っていった。毒を仕込んだボトルの方は放ったままである。
わたしとしては、これが弟に与えた最後のチャンスのつもりだった。当面の援助は快く――おそらく弟の予想以上に快く――承諾したのだから、とりあえずでも殺人を思いとどまってくれるかと期待したのだが。もしそんな優しさが見えたなら、口実をつけてスキットルを取り上げようと思っていたのに――弟は戻れない死への直通ルートを選んだ。
それにしても、もし、弟の留守中にわたしが毒死して、ブランデーのグラスではなくボトルに毒が入っているのを見つけられたら、警察が計画殺人の線で捜査するのは火を見るより明らかなのだが、その点、弟はどう切り抜けるつもりだったのか。
わたしが酒をやめていると聞いて、当分手をつける心配はないと高をくくっていたのか、金策のついたことを誰かに連絡したら(多分借金取りだろう)、その日のうちに、また戻ってくるつもりだったのか。
今となっては全く判らない。
ただ、帰りの新幹線の中で、スキットルをあおったときの弟の気持は想像できる。つかみかけた大金の幻影が目の前にちらついて、さぞいい気分だったことだろう。
ある意味では、わたしは弟を安楽死させてやったとも言えよう。
毒を入手したのが弟自身だと判明したため、警察は自殺と結論づけた。わたしは殊更嘘はつかず、弟が作品をなかなか完成できずにいたこと、方々に借金があったらしいことを供述するに留めた。ただ、そのどちらについても、弟自身は全く気にしていなかったという些細な事実を黙っていただけだ。
他の人間に疑いがかかる恐れは、まずないと見てよかった。大体動機がない。一番身近なわたしにしても、弟を殺したいと憎んだわけではない。あれは単なる正当防衛だった。
弟の四十九日を終え、アトリエの整理も済ませたある日、わたしは久しぶりに自宅でのんびりしていた。よく晴れた日曜日で、季節はすっかり春である。
不意に電話が鳴った。
「先日は失礼いたしました」
あの侵入者だと、声を聞いてすぐに判ったが、とぼけることに決めた。あの夜、彼と話したのはわたしではない。《蛭川順二》だ。
「どなたですか」
「蛭川太一さんでしょう? 二ヶ月ほど前、お宅でお会いしたじゃありませんか。あの晩の雷はすごかったですな」
「記憶にありません。人違いでしょう」
電話の向こうでしゃがれた笑い声がした。
「ま、あの晩あなたは弟さんの振りをしていましたけどね。でも、もういいんです。芝居はやめましょう」
芝居ではなく、向こうが勝手に勘違いしただけなのだが、ここは細かいことにはこだわらないことにする。もっと気になることがあった。
「用件はなんだ」
「いえ、弟の順二さんを、無事お送りしましたので、ご報告までと思いまして」
「送る?」
「ええ。迷った方の案内をしていると、この間申し上げたかと思いますが。それから、太一さんにはお礼もせねばなりません。太一さんのご協力のおかげで、予想よりずっと早く順二さんをお送りすることができましたから」
「ちょっと待て。何も協力など――」
「隠すことはありませんよ。わたしは全部見ていたのですから」
なぜか、背筋に冷たいものが走った。
「未遂に終わったとはいえ、兄殺しを企んだのですから、その罰は逃れられません。だから、あの時点で順二さんの行き先は決まっていて、後戻りはできなかったのですよ。とは言ってもね。裁判やらなにやらで、長期戦になると覚悟しておりました。それが、太一さんの英断によって、期間を大幅に短縮した結果、どれだけコストが節約できたことか」
「さっきから『送る』と言っているが、弟をどこに送ったんだ。あいつならとっくに墓の中だ」
空いた拳を握り締めた。指先に、焼き場で骨を拾ったときの感触が甦る。
「本当に判りませんか? あなたほど聡明な方なら、とっくにお気づきかと思ったんですがねえ。まあ、焦らなくても、そのうち判りますよ。いずれ太一さんのこともお迎えにあがりますから。いくら自分の身を守るためとはいえ、弟殺しも大罪ですからね。あなたも、もう戻れないんです。お気の毒ですが観念してください。なに、諦めるための時間なら、まだ少しはありますから」
受話器を耳から離してじっと見つめた。話を聞いているうちに、相手の声が、受話器からではなく、どこか遠くから聞こえてくるような気がしたのだ。例えば天の彼方から。或いは地の底か。
言葉どおりに受け取るなら、わたしが話している相手は一人しか考えられない。だが、そんなことがありえるだろうか。
そう考えたとき、突然ある疑惑にとらわれた。
「あの夜、お前は――」弟と間違えたふりをして、故意に弟の計画を暴露し、わたしの殺意をかきたてて陥れたのではないか。
いや、それ以前に、弟すらも、何かの罠にかかっていたのではないか。
そう訊きたかったが言葉が出ない。想像したくないほど邪悪な発想だが、訊いたらあっさり肯定されそうで怖かった。
結局何も言わず、震える手で受話器を置いた。念のために、根元からコードを引き抜く。
ほんの僅か残っていた希望が消し飛んだのはこのときだ。
コードが外れた電話機が、目の前で再び鳴り出した。ベルの音は、あの夜の雷鳴のようだった。
Copyright(c): Uetaka Aoi 著作:蒼井 上鷹
◆「戻れない」の感想
*蒼井さんの作品集が 文華別館
に収録されています。