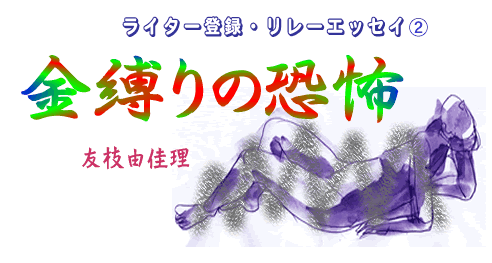
皆さんは『金縛り』という言葉をご存じだろうか。私にはアメリカに青い目の渋い叔父さまと一緒になった叔母がいるのだが、私の『金縛り』体験を話したらあきれはて、ついには夫婦揃って私を精神病患者扱いであった。とはいえ、精神科の医者に言わせればまさしくそうだと言うかもしれない。青い目の叔父さまは『金縛り』という言葉も知らなければ、その言葉に当たる英語さえも知らないという。だからついにはその叔父さまは英語で「君は精神科の病院へ行って治療してもらった方がいい」と真剣に言われてしまう有様であった。
ところで『金縛り』とは、普通、身体は眠っているのに意識だけは起きている状態のことをいう。ある人に言わせれば、それは霊的現象であると真剣に言うだろうし、またある人は身体が疲れているだけだと言うだろう。私は不思議なことが大好きだから、霊的現象だったらおもしろいのにと思っているのだが、別
にお墓参りに行ったって、曰いわく付きのトンネルを通ったって、幽霊にお会いしたことはないから、霊感というものはないだろう。金縛りに遭うときはたいがい疲れている時、かなり不安を抱えて本当に精神状態が悪い時、それから二度寝をした時が一番多い。やはり精神科の門を叩いた方がいいという叔父の言葉は正解である。
そんな私の『金縛り』体験であるが、その実例のおもしろさにたぶんあなたは笑ってしまうか、あきれてしまうか、もう私にははっきり想像できる。
まず第一にこんな『金縛り』体験。
昔ボロ家に住んでいたころ、私の部屋は祖父の集めた百科事典や古本、それから祖父の手作りの本が並んだ小さな部屋だった。明かりをつけないと暗くて、どんな虫が出てきてもおかしくないほどの部屋である。そんな部屋の持ち主である私は、蜘蛛くもが大嫌いだった。テレビに映る蜘蛛や写
真や絵でさえも手で顔を覆った。それなのに、古い家の天井はどす黒く、その裏には大きな家蜘蛛がひしめいていることを私は知っていた。小さな部屋で、従姉からもらった白いベッドに寝ていた私だが、そんな部屋だったから自室にもかかわらず、中に入る前にそこから見える範囲を眺め回して蜘蛛がいないかどうかを確かめるのである。次に首だけひょいと部屋の中に入れてそれまで死角になっていた部分を確かめる。そうしてやっと自分の部屋に入るのだった。それはお風呂に入る時も同様である。気づかないだけで、たぶん私の意識下は蜘蛛のことで頭がいっぱいだったのであろう。
ある朝、目覚まし時計に起こされた私は、眠さに負けて二度寝してしまった。そして次に目覚めたときは身体が動かなかったのである。当時はよくあることだったので、「ああ、またか」ぐらいの気持ちで、とりあえず、どうにかして手を動かそうと努めるのだが、いかんせん手も指も首さえも動かないのである。そんな私に神様のいたずらかと思うほど、とんでもないことが起きた。私の枕元へ、ある黒い物体が近づいてきたのである。首はそちらに向けることができなくても、視界の中に入ったから私はそれが何であるかすぐに分かった。そして大声を張り上げようとするのだが、声は消え入るような弱々しい声しか出ない。しかし危機一髪だったにもかかわらず、いつの間にか私は寝てしまったようだ。次に目覚めたときには、私は身体の自由を取り戻し、そしてすぐに起きあがり、枕元にも何もいないのを確かめた。あとで母に聞いても私の叫び声は聞こえなかったという。ここで皆さんはたぶん夢でも見たのだ、と思うだろう。
『金縛り』は数々あれど、次の話はもっとあなたがあきれてしまう話である。
新築し、四畳半だが私は洋室のきれいな部屋を与えてもらった。ベッドも古いベッドは兄貴にお下がりし(?)、私は新しいベッドで、それなりに悠々自適の毎日であった。
そんなある日の夜中、私はまたふと目覚めた。普段、夜中に目覚めることは絶対になかった。そして目覚めたとき、私は久しぶりで『金縛り』に遭った。身体はカチンコチンになり動かない。「ああ、またやってしまった」とは心の中でつぶやく言葉である。何せ本当に声がでているわけではないようだ。私の視界に小さな窓が見える。その窓はちゃんと鍵がしまっているはずだ。だが、いつの間にかガラス窓が開き、そこから男が入ってこようとしている。恐ろしかった。幽霊よりもよほど恐ろしかった。顔は分からない。ただ白いワイシャツのようなものを着ているだけだ。私は叫んだ、つもりであった。「お母さん、お母さん」。けれども私の声は少しも声になってはいないのだ。寝る前に絶対に鍵を閉めたはずである。ということは、これはいゆわる白日夢と同じだと私は冷静に考えた。夜中だけど白日夢。そう、目覚めているにもかかわらず私は夢を見ている。きっと私は金縛りがとける前に眠りに入ってゆくのだろう。そして、次に目覚めたときに初めて身体が自由を取り戻すのだ。
けれどもその日の私は、眠りに入ることなく金縛りが溶けたのである。こんなことは初めてだった。自由を取り戻した瞬間、もう男はいなかった。やはり夢だったとホッとした。それでも私は怖くてすぐに小さな窓に近寄った。鍵がしまっていることを確かめた。夢だと思った瞬間、自分でおかしくなった。笑いたかったが夜中だった。あとから考えてみれば、蜘蛛も男も、夢というよりは幻覚というものなのだろうと思う。
しかし、『金縛り』で笑える話ばかりではない。これは最も恐ろしい。
この時もまた二度寝をしてしまった時である。目覚めたとき身体が動かずにいた私はいつものことよとばかり、そのうちまた眠りに落ちるのだろうと、眠りに入るのを待っていた。しかしこの時もまた眠りには落ちずに身体の自由を取り戻した。ところが皆さん、眠りに入ることなく金縛りが溶けると、非常に身体が疲れてしまうことを知っているだろうか。起きあがるのにとても苦労するほど、体力を消耗しているのだ。
ようやく私はベッドの上で座った。背中を丸め、膝ひざから先を両側に曲げてばあちゃん座りをした。それが一番楽な座り方だったからだ。しかし、座ったはいいがやはり疲れでとても起きあがれるような状態ではなく、今度はそのままうつぶせになった。ふかふかの布団の上で顔をびったりくっつけて身体の力を抜いた。ほんのちょっとのつもりだった。しかしその瞬間、またしても金縛りにあってしまったのである。動かない。動けない。顔が布団にびったりくっついたまま動けない。目も口も鼻もふかふかの布団の生地にびったりくっついたままなのだ。息ができないまま数十秒経ったであろうか。ものすごく苦しくなったとき、ようやく金縛りが溶けた。叫ぶこともままならず、家族の誰一人として部屋を覗くものはいない。死ぬ
かと思った。もう絶対にうつぶせになんてならないと私は誓った。もうまっぴらだ。金縛りなんてもうごめんだ。
Copyright(c): Yukari Tomoedao 著作:友枝 由佳理
*友枝由佳理さんのエッセイ集が、文華別
館 に収録されています。