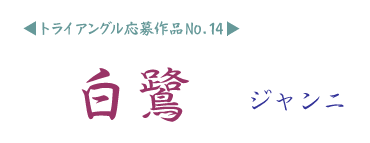
繋いだ指と指が弾かれたように引き千切れた。
純白に染まったホームに綿雪が静かにおり続けていた。足跡が幾つも、線路を横断して深々と待合室へ伸びている。駅員の口から吐き出された声が雪の合間に吸い込まれていった。薄く林檎の匂いが揺らいでいる。凍った舌の先が甘酸っぱさを感じた。
高らかな警笛が真直ぐに響いた。
辷り出した列車が興した幽かな空気の流れで、林檎の香がわからなくなった。目一杯にあげた窓の向こう側の世界がゆっくりと、歩く早さで小さくなっていった。不思議だった。
ゆきちゃん、ゆきちゃん。
声の一文字一文字が真綿の雪に附いて散らばり、拡がった。雪の舞う駅が遠退くほどに聞こえなくなる。ホームに佇む白いマフラーと景色の境目がなくなった。
重い硝子窓をおろすと銀色の音が消えて、車両が線路を擦る振動だけが残った。
都会の烏は利口である。狡賢いとも言うべきか、食べ物のある場所を熟知しているし、時には拾った硬貨で自ら鳩の餌の自動販売機を利用するという。
ゴミ収集所の緑青色の網を取り払おうとして難儀している一羽の烏を前に、由紀は追い払うこともできず立ち尽くしていた。
早く他へ行ってくれないかな。
そう思いながらも厭わしげな顔ひとつせず、由紀は軽く溜息をつく。仕方ないなといったふうに肩をすくめ、向かいのガードレールに腰を掛けた。ゴミ袋を足元に落とすと、中身の少ない袋は空気に押されて横に膨らんだ。
一人住まいでは出るゴミの量にも限りがある。自炊もするが、面倒な時や疲れている時には、コンビニエンスストアの弁当やファーストフードで賄うことも折あった。そういった日にゴミは多く出るが、週三日もある収集日はやはり由紀には多過ぎた。
由紀は烏と目が合わないように俯いて、通勤や通学で行き交う人達の歩みをぼんやりと追っていた。
背後の大通りには車が激しく往来している。騒音と煙が絶え間無かった。由紀の短い髪を揺らす冷たい風は鈍色で、ガスの匂いがした。
一限が休講になった。
携帯電話に友達からそうメールが届いたのは、着替えも化粧も済ませて靴を履いた矢先だった。
メールを返信して靴を脱ぐと不安に襲われた。取り立てるほどのことのない、瑣末な事柄が心に刺さるようになってからもう三週間が経つ。まるで上京したての頃の自分に戻ったようだった。
だから、ゴミを出しに行こうという思いつきは、何も予定がなくなってしまった所在無さを僅かに潤してくれた。烏がそれを引き延ばしてくれることも、由紀にとっては存外の喜びとなった。
掌から粉雪が辷り落ち、降り積もる雪に交じり合った。
花輪駅は藍白の空に包まれていた。緩やかにおりてくる沫雪に阻まれて震えている。鹿角花輪と刻まれた駅看板の上の冠雪が不意に垂った。銀色が聞こえた。
掌に載せた雪兎は片方だけ林檎の葉の耳をしていた。目も口もない片耳の兎を両手で覆った。
警笛が鳴り響いた。
凍えた鼻先から甘酸っぱさが離れて行った。
自分はカメレオンなのだと思う。
岩の上で緑色のカメレオンは、月を食べようとして夜空に向かって舌を伸ばした。東の空が白む頃、遂に月に舌が届いた。思ったほど美味しくなかった月に幻滅し、くたびれたカメレオンは体が金色になったまま元に戻らなくなった。
小さい頃、そんな童謡を気に入ってよく聴いていた。母や仲の良かった男の子と、きっと高市にいるカメレオンはみんな真白だね、と言い合っていたのを憶えている。
今の自分は何色だろうか。
電話で友人の悩みを聞いてやりながら、片手で雑誌を読んでいる自分は何色だろう。失恋した友達を慰めながら、頭では試験やレポートのことを考えている自分が、何色に染まってしまったのか、よくわからない。
東京に来てもう三年と半分が過ぎていた。
烏の羽がはためく音がして、由紀は顔を上げた。
ゴミ収集所の緑の覆いは乱れて、却って複雑に絡まり合っていた。諦めたのだろう、烏は首を斜めに傾がせて空へ飛び発って行った。埃にまみれた左翼の付け根には切り込みが入っていて、羽ばたく度に羽の内側が大袈裟に揺れていた。
歩道に由紀とゴミ袋が残った。
駅へ向かう人の往来は途絶えがちになっていた。車道を行き来する車も、先に比して減ったように思われる。長い間じっとしていたせいか、由紀は頬を刺す十二月の冷気に少し肌寒さを感じた。
緑のネットをあげると、由紀はゴミ袋を放って帰途に着いた。
別れよう。
登からそうメールが届いたのはちょうど一ヶ月前である。入学してすぐの五月から付き合い始めて三年を過ぎていたが、呆気ない別れであった。理由は聞かされていない。由紀の方から電話して訊くこともなかった。
おっけー。
そう返信して以来、顔を合わせていない。これからももう会うことはないだろう。
何がおっけー、だよ。由紀は平気を装っている自分が嫌だった。こんな時に手慣れた女なら可愛く泣きついて、縒りを戻すことも出来ただろう。だが、由紀には出来なかった。都会の女なら失恋を材料に、新しい恋を見つけることも簡単だろう。実際由紀は何人もの男友達に電話を掛けた。だが、新しい恋人は出来なかった。本当にもう自分が何色なのかわからない。就職活動前に慌てて取った色彩検定の資格も役に立たなかった。
登に対して、自分は軽いアディクションをしていたのかもしれない。学校が同じなのでほとんど毎日会っていたし、毎晩電話もした。それでも足りなくてメールもせびった。依存状態であることは薄々感じていたが、どうする事も出来なかった。大学で学んだ心理学用語の知識も何の足しにもならなかった。
付き合い始めてから、友達からの誘いも全て断って登とばかり一緒にいた。そのうちに誘いの電話も掛かって来なくなった。レポートや休講の情報だけが思い出したようにまわってくるだけになった。
二三日泣き明かしてそれきり、何もなくなってしまった。クリスマスは一緒にいようよ、と言ってくれる女友達もいない。
悴んだ両手をストーブに宛てると、手袋を脱いだ掌に血が通った。
待合室は脂の匂いに埋まっていた。体からはみ出るほどの風呂敷包を負った老婆が肩の雪を落としている。列車を待ち侘びて眠る幼子の黒髪に珠の水滴が弾けている。幽かな寝息が焔の燃える音の間を擦り抜けて、時間が留まっていた。窓の外に銀色が流れていた。
遠くから聞こえていた律動が近付いて来た。
扉が開かれた。動き出した時間の一つ一つがホームへ歩んでいった。
大きく吸い込んだ空気が喉の奥に冷たく、僅かに咳込んだ。
玄関を開けると、由紀の目に暗い一人部屋が映った。
遮光カーテンが引かれたままで、窓の端から僅かにだけ光が漏れて散らかった部屋を浮かび上がらせていた。
半年前に終わらせたはずの就職活動の資料が未だにベッドの脇に積み重なっている。造作もなく幾つか置かれたスーパーの袋はどれが食べ物で、どれがゴミだかわからなくなっていた。登が貸してくれた推理小説。本棚がない部屋で、何冊か買った文庫本と一緒に行き場を失っていた。テスト前に慌てて買った教科書や、疎遠になってしまった友達から借りて返せずにいる漫画本が大きさがばらばらのままに壁の袂に積もっている。ミニテーブルの上には出し放した食器がある。朝食に作った味噌汁の残り香が由紀の鼻を突いた。暗がりの中境界を失ってしまった物と物とが大きな塊になって、密やかに蠢いているような感じがした。電源を入れたままのコンピューターのファンの音が響いている。
融けて行く感覚が快かった。
登が幼い顔立ちで微笑んだり、そっと肩に手をまわしたりする度に、由紀の頭の中に温かいものが生まれた。何も考えられなくなって、ひたすら優しい気持ちが溢れた。東京の大学に馴染めずにいた一年生の由紀の氷の心を柔らかく砕いてくれたのが登だった。渋谷や下北沢を案内してくれた。恋愛の仕方も覚えた。登が辛い時には、抱きしめて懐で泣かせてあげた。胸に顔を埋めて壊れそうに泣きじゃくる登の短い髪を撫でていると、心の中に鴇色のもどかしさが心地良かった。
高市にいた頃に憧れていた東京の生活がそこにはあった。初めて連れて行ってもらったライブハウスやクラブでは登の友達がバンドやDJをやっていたし、登と一緒にクラブに通ううちに、広告界のトップクリエイター達とも知り合いになった。尊敬していたデザイナーにも一度だけ遭った。彼女は赤い眼鏡を掛けていて、細長い煙草を吸っていた。本当にカッコイイと思った。
そんな刺激的な生活にもいつしか慣れてしまった。朝帰りはやはり体に辛かった。都会の暮しに疲れていた自分に、登はオコジョやヤマネの写真集を贈ってくれた。優しかった。雪景色に佇むオコジョを眺める度毎に、自分はもう故郷には帰れないと思った。東京に馴染んだ自分は、洋服や化粧品をどこで買えばいいかよくわかっている。大型書店や外資系のレコード屋にもよく足を運ぶ。それに、登の側を離れられない。優しい気持ちが一瞬でも消失せてしまうのが怖い。気がつくと、登にアディクションしている自分がいた。実家には一度も帰っていない。大学に通いながら専門学校を出てイラストレイターになりたいという夢も、いつの間にか壊れてしまっていた。
登と別れて、何もなくなってしまった。
高市にいた頃、誰かがいつも雪降ろしを手伝ってくれた気がする。
幼馴染の男の子と歌いながら下校した帰り道の唄ももう思い出せない。
ふと部屋の隅に目を遣ると、そこには近所のレンタルビデオ屋の袋が折れ曲がって小さくなっていた。由紀は借りたまま見ても聴いてもいないビデオとCDがあったのを思い出した。返却期限はとうに過ぎている。
抑えていた思いが瞳から極みなく溢れ出した。
窓の外を流れる暮色の雲は闇に染まっていた。
鮮度の落ちた緋の稜線が空に溶け始めた。車内の灯りが硝子窓に映り、縹色の山の頂を遮っている。外の景色が薄れ行くほどに、世界は列車の内部だけになった。硝子には所々水滴が附着していた。臙脂色のマフラーに附いていたはずの花輪の雪の結晶は、随分前に融けて布地に染み込んでしまっていた。
向いに座っていた老婆が水筒を取り出した。湯気と幽かな緑茶の匂いが漂った。一口飲んで息を吐き出した時、窓はまた少しばかり曇った。
盛岡行きの終列車が安比高原を過ぎる頃、掌の雪兎はとうに気化し切っていた。
肌寒さを感じて、由紀はベッドから体を起こした。
遮光カーテンに採光を阻まれた薄暗い部屋が再度浮かび上がって来た。オーディオコンポの脇に未だ洗濯をしていない衣服が乱れていた。すぐ側に、脱ぎ放した白いコートが丸まっていて、さながら生き物のようであった。
壁掛けに目を遣ると、時刻は四時を廻っている。
由紀は目元に乾いた突っ張りを感じて目を擦った。電灯を点けるともなく、呆然と視線を漂わせていた。目覚めた瞬間の、自分がどこにいるのか何者なのかわからない感覚が終わらずに続けばいい、と由紀は思った。そうすれば一人暮しの孤独を感ぜずに済むのだから。こうやって寝覚めた時も、疲れて帰宅した時も、マンションの一人部屋にはいつも誰もおらず、灯りも点いていない。頭が冴え自分を確認するにつれて、由紀は砥ぎたての凶器のような不安に気付き始めた。酷く喉が渇いていた。
数歩歩いて台所に行くと、由紀は冷蔵庫を開け、ミネラルウォーターを取り出した。口に含むと、塩辛い味がした。ふと移した視線の先のコップには、歯ブラシが二本刺さっていた。
ペットボトルを戻した時、一枚の葉が目に留まった。
缶ビールやチューハイに紛れて折れ曲がりそうになっていた。冷蔵庫の橙色の光に照らされ、鈍く変色している。
由紀は訝しげに葉を手に取り、ゴミ箱に捨てようと部屋へ戻った。
ベッドの脇まで来て、由紀は手を止めた。
カーテンと壁の間から白い光がこぼれていた。
光の筋は薄く壁を伝って、枕元を藍鼠色に照らし出していた。
一枚の葉を手にしたまま、由紀は震える指でカーテンを開け放った。
窓の外は純白だった。
道路にも、街灯にも、向いの児童公園にも雪が降り積もっていた。歩道には足跡が幾つも斑に刻まれていた。公園で雪玉を投げ合う子供達の声がガラス越しに幽かに聞こえてきた。一面に小粒の雪が舞っていた。
由紀は勢いよく窓を開いた。部屋に冷気が傾れ込む。
目前の電線には一羽の烏が停まっていた。頼りなげな漆黒の頭と肩に雪を被って、震えている。二三歩足場を変えると烏は由紀の方を向いた。水混じりの雪で湿った目がしっかりと由紀を捉えた。
烏は首を傾げ、羽をばたつかせた。翼の雪が流れ、落下していった。やがて烏は藍白の空へ静かに飛び発ち、左に大きく旋回する。