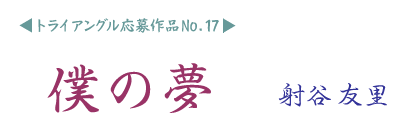
「なんだこりゃ。」
男は、押入れの整理をしていると、ダンボール箱の底から、埃まみれの文集が出て来た。
「どれどれ、俺は何て書いたんだったかな。」
ぱらぱらと、ページをめくる。
「『僕の夢』
僕は、お父さんのような、優しいパパになって、家族と世界旅行をしたいです。
それが、一番の夢です。』
つまんねぇ文章だな。これ、本当に俺か?」
男は、むっつりした顔をしていたが、次第に口元に笑みを浮かべた。
「はは、夢ってわからないよな…。」
道路の真ん中に男が立っている。しかも、サンタの袋のようなものをしっかりと握り締めているのだ。
「あっ!」
次の瞬間、彼はするりと袋の中にはいると、跡形もなく消えていた。
草太は、男が消えた場所へ走りよった。
よく見ると、真っ白いサンタの袋だと思ったものは、ただの布袋であった。
指先で目の前までつまみ上げる。
「うえ、汚ねぇ。まるで雑巾じゃないか。」
草太は、目の錯覚かもしれないと思ったが、あまりに大きな男が目の前から消えて、錯覚などではないと、思い直した。草太は、つい最近読んだばかりの、ミステリー小説を思い出していた。
「まさに、あれじゃないか。」
人間の「消失」だった。ただ、小説と違うところは、舞台が窓のない四角い箱のような建物や、孤島の洋館でもなかった。道路に落ちた白い布袋の中なのだ。あまりに舞台としては、貧弱だと思った。
その夜、宿題の算数のテキストを解いている時も、大好きな漫画を読んでいるときも、消えた男のことが頭を占領していた。草太は、この奇妙な出来事を、どう整理してよいものなのかと、頭を悩ませていた。
ただの見間違いとしてしまえば、楽に眠れるのにと、深くまくらに顔を押し付ける。うつ伏せになって、もう一度、男が消えた瞬間を思い出していた。草太は、思わず家に持ち帰った「雑巾」を睨んだ。
「この中に入るなんて、どう考えてもおかしいよな。第一、この中に入ったら、どこに出るんだよ。」
草太は、だんだん苛苛してきて、余計寝られなくなってしまった。
「ああ、もう! のどまで渇いてきちゃったよ。」
草太は、二階にある自分の部屋から、一階のリビングに降りていった。
もう、夜中の二時を回るところだった。
草太は、冷蔵庫の中から、発泡水を持って、自分の部屋に戻っていった。寝台の上に乱暴に腰を下ろすと、シュッという小気味よい音を立ててガラス瓶の栓を開けた。
微炭酸が喉の奥でパチパチとはじける。
ふと、草太は「雑巾」を置いてあるデスクに目を止める。
「あれ。そこに置いたはずなのに。」
草太は、「雑巾」を探す。部屋の中には落ちていないようだ。
草太は、じわりとじわりと何かが迫っている気がした。
「もしかして、あの男が?」
草太は、身震いをひとつした。まさか、あの男が取り返しに来たのだろうか。いや、もしかしたら、袋の中から出てきた可能性もある。
「どこかに隠れているのかもしれない。」
草太は、野球のバットを握り締め、部屋のドアを静かに開けた。
ぐにゃり、という嫌な感触が、足元でした。
恐る恐る、自分の足元に目をやる。
ひんやりとした物体が、足元から全身に伝ってくる気がした。鳥肌が立って、心拍数があがる。
「バナナだ。……臭い!」
今は真夏ではないとはいえ、食べ物は傷みやすい。思わず、鼻をつまんだ。鼻をつまみながら、足を拭くのには骨が折れた。
等身大の鏡を、見ると眉毛を八の字にした情けない自分の姿が映っていた。
「こんな目にあうなんて。元はといえば、あの男のせいだ。」
草太は、これ以上あの男に振り回されたくなかった。
「勝手にしろ。」
草太は、寝台に潜り込んで、深くまくらに顔をうずめる。五分もしないうちに、眠り込んでしまった。もし、男が今現れて草太の顔に落書きをしても、決して起きなかっただろう。
次の日、草太は学校の身支度をして、一階に下りていった。
「母さん、家にバナナなんてあった?」
草太は、牛乳をコップに注ぎながら、何気なく尋ねてみる。
「あら、昨日食べちゃったわよ。食べたかったの? いつも、あっても食べないくせに。」
母は、あきれた顔をしている。
「はやく食べて、学校に行きなさいよ。もうすぐ期末テストでしょ。しっかり勉強するのよ!」
母は、草太の背中をばしりと叩いた。母は、力が強いことを、自覚していない。
「痛いなぁ。わかったよ。行って来るよ。」
草太は、恨みがましい目をして、こっそり母の背中に向かって舌を出す。母は、食器の洗い物をしているにもかかわらず、振り向かずにこう言った。
「馬鹿なことしてないで、前向いて歩きなさいよ。あんた、すぐよそ見して転ぶんだから。」
草太は、すごすごと家を出た。どうやら、母の背中には大きな目があるらしい。
草太は、学校の授業にまったく身が入らなかった。
「草太のやつ、どうしたんだ。変なものでも、拾い食いしたんじゃないの。」
「つっこみ隊長が、突っ込んでこないぜ。」
友人たちが、からかってきても、いまいち反応出来ずにいた。
「放課後、体育館使えるってさ!」
息を切らして、少年たちは教室に戻ってきた。教室にいる少年たちは、放課後何をして遊ぶかを話し合い始めた。
放課後、草太はひとり、家路を急いだ。
あの角を曲がって、袋小路の奥に草太の家がある。この袋小路がある一本道で、あの男に会ったのだ。もし、今度男が出てきたら、自分はどうするのだろう。
一人の男が、草太の家の前に立っている。
「怪しいやつ! 何をしているんだろう。まさか、あの男だろうか?」
「わ?! びっくりした。」
草太は、男に体当たりしそうな勢いで、男のところへ走りよった。よく見ると、男は杖をもっていた。腰も曲がっていた上、真っ白な髭を生やしていた。俊敏な動きをした、あの男に似ても似つかない格好だった。
「あの、おじいさん、何しているんですか? 家に何か用ですか?」
草太は、恐る恐る聞いてみた。
「いや、実は私はかつてここで住んでいたから、懐かしく思ってね。私の部屋は、二階の右端の部屋だったんだ。」
彼が指をさしたところは、まさに草太の部屋だった。
「こんな、じいさんが家の前に立っていたら、気味が悪いよなぁ。」
彼は、ぼりぼりと頭をかいた。顔を良く見ると、どこか知っているひとのように思えた。懐かしさすら感じる。老人は、草太の露骨な視線にうろたえた様子はなく、にっこりと微笑んだ。
「少年、冒険は好きかね?」
突然、老人はこう尋ねた。
「もちろん大好きだよ。冒険小説も好きだし、ミステリーとかも好きだよ。でも、なぜ?」
草太は、好きなことを尋ねられて、つい敬語を忘れて言った。
「いやあ、私も小さかったころ、君のように、不思議を探して、眼をきらきらさせていたからね。」
彼は、気を悪くすることなく、優しく言った。
「僕の眼、きらきらしてるんですか?」
「ああ、好奇心の塊のような眼をしているよ。たまに、無鉄砲すぎるところも、よく似ている。」
老人は、まぶしそうに目を細めた。
「少年。もし、タイムマシンがあったら、君はどうする?」
「タイムマシン? どこへでも行けるの?」
「もちろんだよ。どの時代でも、どの国でも、行けるさ。君が望めばね。」
「う〜ん。そうだな。未来に行ってみたいかな。僕は、どんな大人になっているか、みてみたいよ。」
「そうか、行ってみたいか。」
「草太? 誰と話しているの?」
母親が、窓ごしに叫んだ。老人はぺこりと頭をさげ、
「じゃあ、また。」
と言って、去っていった。
「どなたなの? 会ったことある気がするけど。」
母は、首をかしげて、考え込んだ。
「さあ? 知らない人だよ。前、この家に住んでいたんだって。」
「何言っているの。そんなわけないじゃない。この家は、十年前に建てた家よ。あのおじいさん、どう若く見積もったって、60歳くらいよ。この家、まだないわよ。」
「ええ? じゃあ、あのおじいさん、嘘ついたってわけ?」
草太は、まゆをひそめて言った。
「そうは言ってないけど。もしかしたら、この家を建てる前の、土地の所有者だったのかもしれないわね。」
「きっと、おじいさんはここに住んでいたんだ。」
草太は、口の中で声に出さずに言った。
家族ではないのだから、あり得ないことだ。
しかし、草太は、直感でそう感じていた。
少年は、その夜「旅人」になる夢を見た。大きなサンタの袋のようなものを担いでいる。草太の身体がすっぽり隠れてしまうくらいの大きさだった。見慣れない景色が続いている。袋小路に「あの男」が立っている。草太は、袋を担いだまま、男のところへ歩いてゆく。
ゆっくり振り向いた男は、白髪で、白い髭を蓄えていた。先ほどまでは、たしかに黒髪の若い男であったのに、一瞬にして老人に変わってしまっていた。あたかも、玉手箱を開けてしまった、浦島太郎でのようだ。草太は、驚いて、口も利けなくなってしまっていた。老人は、草太の顔をじっと見すえていた。微動だに動かない。草太は、もっと近づこうとした。しかし、そこには、大きな鏡が一枚置いてあるだけであった。草太は、鏡に映った自分の姿を見て、驚愕した。真っ白な髪と髭を生やしている老人が、目の前に立っていた。それは、まさしく、年をとった自分の姿だったのだ。草太は、ショックで、悲鳴を上げた。草太は、自分の叫び声で眼が覚めてしまった。
額から、大量の汗が流れ出て、耳の横をつたった。
「あの老人は、僕自身だったのか?」
それならば、あの老人が草太の家に住んでいたことがあると言ったのにも、うなずける。あの老人は、タイムマシンで、やってきた自分なのだろうか。
「でも、そうだとしたら、彼は何をしにきたんだろう。」
草太は混乱する頭を、深くまくらに押し込んだ。まくらから、にゅっと二本の白い手が伸びて、草太の頭をしっかりとつかんでいた。ぷつりと音を立てて、草太の思考はとぎれた。
朝、ひどい頭痛で、草太は目を覚ました。
連日、奇妙な出来事が続いて、頭はパニック寸前なのかもしれない。鏡に映った自分の顔は、びっくりするほど覇気がなかった。
ダイニングにのそのそと下りていくと、母が珈琲を飲んでいた。白い湯気が空気に溶けてゆく。
「あ、草太おはよう。めずらしいわね、日曜なのに早起きなのね。……今日洗濯しないほうが良いかしら。」
草太は、椅子に座ってため息をついた。
「何よ、元気ないじゃないの。どこか具合悪いの?」
母親は、心配そうに覗き込む。
「僕という人間が分からなくなったよ。」
「なに、悟ったようなこと言っているのよ。今分かっているのは、ご飯をもりもり食べろってことよ。」
母は、ぱん、と草太の頭を軽く叩いた。
「いってぇ。頭痛いのに、よけい痛くなるじゃないか。」
草太は大げさに言って、後頭部をさすった。
「あら、ごめんなさいね。」
母は、いそいそと台所に向かった。
草太は、母の言いつけで、新聞を取りに玄関へ行った。玄関扉を開けると、明るい日差しが差してくる。眩しくて片目をつむった。白い光の中に、あの男が見えた気がした。草太はパジャマのまま、外へ走り出した。
男は、道路の真ん中にたたずんでいた。草太は、電柱の影に隠れて、男の様子をうかがっていた。
「ぼうず、隠れてないで出てこいよ。いるんだろう。」
草太は、心臓が飛び出るんじゃないかと思うほど、驚いた。
草太は、恐る恐る電柱の影から出てゆく。
「お前、何者なんだよ。未来人か?!」
「はは。未来人か、いいなぁそのネーミング。」
男は、心底おかしいと言うように、笑い続けている。
「何、笑っているんだよ。俺は知っているんだぞ! お前、「雑巾」みたいな袋に入って消えたの見てたんだからな!」
草太はむきになって、叫んだ。
「雑巾とは、ひどいな。これでも、有能な『タイムマシン』なんだぞ。まあ、年季が入っているからな……。汚いのは認めるさ。」
男は、愉快そうに口の端を少しだけ上げた。
「その袋の中を見せてよ。『タイムマシン』が本物か確かめたいんだ。」
「やだね。」
男は、薄笑いを浮かべて言った。
「このあいだ、知らないおじいさんが、家を訪ねてきたんだ。『タイムマシン』があったら、どこへ行きたいって。」
「はっ! そんな頭のおかしい男の話なんか知らないね。ぼうず、あんまり大人を信用しない方が良いぜ。」
「あのおじいさんは、未来から来たんだ。」
「まさか。そんなに『タイムマシン』があってたまるかよ。これは、俺が23歳の時に造ったものなんだよ。俺みたいな天才が他にいるわけねえだろ。」
男は、相変わらず薄笑いを浮かべていた。
「ぼうず、そのじいさんはきっと妄想家か、小説家だよ。これが、正真正銘の『タイムマシン』だよ。」
「じゃあ、証拠みせてよ。それが『タイムマシン』だっていうのならさ。」
「いいぜ。じゃあ、過去にさかのぼって、お前の部屋に、ちょっとした細工をしてくるぜ。」
「過去じゃ、駄目だよ。何かあったって、思い出せないかもしれないじゃないか。」「分かるはずさ。」
そう言って、今度は草太の目の前で、袋の中に足を入れた。男の体が、みるみるうちに袋の中に埋まってゆく。ただの「雑巾」は、彼の手によって真っ白の大きな袋に変わって、最後には光につつまれた。草太は、呆然と立ち尽くしていた。
「草太! もう、何しているの。風引くわよ。勝手に走り出すんだもの。はやく帰るわよ。」
母が怒鳴りながら、サンダルで駆けて来た。
草太は、朝食を食べたあと、宿題をするといって、自分の部屋にもどろうとした。
階段を上りきったところで、バナナが転がっているのに気づく。
「二度と引っかかるもんか。」
草太は、部屋のドアを勢いよく開けた。
「すまんな。馬鹿な私が君に、くだらんいたずらをしたようだ。」
寝台の上に、白髪の彼がいた。なぜか、傘をさしている。草太は、怪訝そうに彼を見つめた。
「ああ、雨が降っていたものでな。」
そういって大事そうに黒いこうもり傘をたたんで、腕にかけた。
「ねえ、あの男は、おじいさんなの? それとも、僕の未来の姿なの?」
「がっかりしたんじゃろう。あんまり、気を落とすんじゃないぞ。未来は、一つ限りじゃないからな。」
「じゃあ、『タイムマシン』を発明しないかもってこと?」
「そうだな、あるいはそうかもな。まあ、科学者になるのは、私の『23番目』の夢じゃったからな。」
彼は、愉快そうに笑っている。
「22番目はなんだったの?」
「総理大臣さ。未来はどこに向いているかなんて分からないものさ。おっと、時間だ。
見たいドラマが始まるんだ。じゃあ、失礼するよ。」
そういうと、彼はいそいそと、袋の中に入っていく。
「ねえ、いったい何しにきたのさ?」
草太は、ずっと気になっていたことを問いかける。
「なあに、若き日の悪戯を止めるためさ。無駄だったがな。」
彼は、煙のように、袋の中に消えていった。
草太は、首をかしげながら、宿題の作文に取り掛かろうとした。なんの因果か、作文の題材は『未来の自分』だった。作文用紙を取り出すと、草太は我が目を疑った。
「『僕の夢 持田草太
僕は、科学者になって『タイムマシン』を発明したいと思います。そうして、様々な時代に行ってみたいです。これが、僕の夢です。……』」
「やられた……。」
明らかに達筆で、若い23歳の自分が書いた文字ではなかった。
「止めたかった自分て、いつのだよ……。本当に、成長してないんだな。」
草太は、深くため息をついた。
「未来は、ひとつじゃないって言ったくせに。」
草太は、ひとりでに笑みがこぼれた。