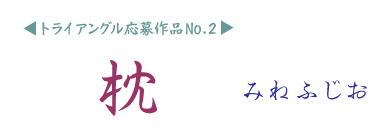
僕は枕の中を旅している。彼の夢の世界から落ちてしまい、気がつくと枕の中にいた。彼は僕を失ったことにまだ気がついていないようだ。
今日も僕は枕の中をさ迷い、彼の夢の中へ戻る方法を探している。
枕の中の、綿の海はダニ達の巣窟だ。薄い綿の膜越しにダニ達が移動している影をよく目撃する。時々彼らは僕に気がついたかのように動きを止める。僕は息を潜めて縮こまる。綿の膜の向こう、すぐ傍にいるダニ。この僕、侵入者の気配を察しているのか。
やがてまたダニは、ずずっ、ずずっ、と綿を擦りながらゆっくりと移動し始めた。
突然、足下の綿が盛り上がった。僕はバランスを失い倒れた。しまった。足の下にもダニがいたのだ。
綿を掻き分け目の前にダニが顔を出した。僕の体は綿の繊維に絡まって動けない。
ああっ!
カーテン越しに射し込む日の光の角度からおおよその時刻を察することができる。今は午前十一時過ぎぐらいだろうか。ソファーに寝転んだまま、腕を頭の上に伸ばして欠伸をした。自分の吐息の酒臭さにむっとしてしまう。
高層マンション二十三階の一室。ソファーまでお気に入りの枕を持ち込み、いつものごとく、だらだらと深夜放送を見ながらそのまま眠ってしまっていた。夜明け方、枕の中から声がしたような気がしたのだが、まさかそんな事はあるまい。
テーブルの上に置きっぱなしにしてあった水割り用のペットボトルの水を飲む。頭を掻くと、ポテトチップスのかすのようなフケが降ってきた。顔を洗おうと、散らかった部屋のゴミを踏まないよう気をつけながら洗面台へ行く。歯磨き粉の飛沫がこびり付いた鏡に疲れた顔の三十男が映っている。
「どうしてそう無気力体質なのよ!」
女房のヒステリックな声をもう聞くこともない。プロのイラストレーターになると志し会社を辞める際、俺は自分の夢を熱く語り、女房も賛同してくれた。が、まさか働き盛りの男が一日中酒を飲みながら家でごろごろしている状況になるとは思ってもみなかったであろう。俺自身でさえそうだ。一縷の望みに期待し堪えていた女房の我慢も飽和点を超え、とうとう出ていってしまった。俺は天狗になっていた。プロで食っていけると思っていた。しかしもてはやされた初期の作品以降、いつしか俺は力の無い抜け殻のようなイラストしか描けなくなってしまっていた。挿絵を依頼されてもイメージが湧かない。仕方なく気持ちのこもっていないイラストを出すうちに仕事は減っていった。スケッチブックに描き溜めておいた多少の素描を作品に仕上げてみようかと思ったが、それらも全て死んでいた。絵に宿る魂のごときものが抜け落ちてしまっていた。
俺の初期の作品を評価してくれた出版社の編集長が、窮乏を見かねて仕事を持ってきてくれた。だが、やはり描けない。イメージが湧かない。俺は一人で、自分の中の井戸を掘り続けた。暗闇の中、固い岩盤に阻まれ、もはや地上に戻る体力さえ使い果たそうとしている。
時間が腐ってしまいそうな毎日。昼過ぎに起きて、近所の定食屋に行き、飯を食いながらスポーツ新聞を読む。部屋に帰り、酒を飲みながらテレビを眺めているともう夜もいい時間だ。
顔を洗い、蛇口を閉めた。
「……僕と遊ぼうぜ」
ソファの方から、声がしたような。
もしょもしょと蠢くダニの蝕肢が迫る。とその時、激しく枕の中の世界が揺れた。彼が動いたのだ。ダニが気を取られ右往左往している隙に僕は逃げ出すことができた。
ダニの気配が感じられないところまで逃げ、僕は一息ついた。どうやら彼は目を覚ましたらしい。枕の外の世界で、巨人が起きあがる気配を感じる。
彼は僕を消失してしまったことに気がついてくれるだろうか。僕は彼の中に戻りたい……。
俺は腐りかけている。二十三階のベランダからダイブしたい妄想に駆られる。だが、今日はもうソファから起き上がる気もしない。
夢を見ていた。上下左右、方向感覚は皆無、真っ白な、何も無い空間で、俺は何かを探している。
「僕! どこにいる。……僕!」
…………
俺は僕を探していた。僕って誰だ。俺? 俺の大切な、何か?
「……僕!」
…………
「……僕!」
「……ここだよぅ」
今、聞えた。確かに、僕の声が!
「僕、今行くぞ!」
俺は僕の声がした方角に精神を集中させる。体がスーッ、と宙を流れるような感覚。いや、飛んでいる、自分の意志で。
「……ここだよぅ、……ここにいるよぅ」
僕の声が近づいてくる。俺はだんだんとスピードに乗ってきた。
耳鳴りがし始める。徐々に、ジェット機のエンジン音のような。いつしか頭蓋、眼球を揺さぶるほどの大音響になっている。
くうっ!
歯を食い縛り、耐える。
ついにに耳鳴りはピークに達し、バリバリと火花を散らしながら目、鼻、体中の穴から抜けていく。
ああっ!
と、静寂。俺の鼓動だけが響く。
目を開けると、真白な世界にぽつねんと、小さな子供が立っていた。懐かしい。俺は君をずっと前から知っていたような。
「……僕」
「……やっと来てくれたね」
僕がゆっくりと俺に手を差し伸べた。その手を握り返した時、俺の中で何かが弾けた。
ベランダで雀が鳴いている。カーテン越しに射し込む日の光がいつもより眩しい。朝日だ。久しぶりに早い時刻に目が覚めたようだ。俺は抱きかかえていた枕に顔を埋めしばし眠りの余韻に浸る。だんだんと頭が冴えてくる。珍しい、今日は二日酔いしていない。清々しい気分だ。よし、早起きしてコーヒーでも入れようか。
いったい何が起きたのか。一夜にして世界は色を取り戻していた。俺は自身の中から湧き起こるイメージの奔流を抑えきれずにいた。
依頼された童話の挿絵の仕事は断ろう。他人のイメージを絵にするなんて御免だ。俺は俺を表現するのだ。
一ヶ月後、出版社のビルの喫茶室で、俺は編集長と向かいあって座っていた。童話の一件がまだ尾を引いている。編集長は、もう俺に用はない、といった面持ちをしていた。
「その節は本当にすみませんでした」
先ほど、再会した際にも謝ったが、俺はもう一度頭を下げた。
「いや、もういいんだ」
編集長は面倒くさそうに言った。
俺は躊躇することなく、分厚いファイルを取り出した。
「見てもらいたいものというのは、これです」
この一ヶ月間で描き上げた作品は百数十枚にも及ぶ。そのすべてが自信作だ。だが、初めて客観的に見られるとなるとさすがに緊張した。俺のとんだ勘違いだったら。
編集長はやはり面倒くさそうにファイルを開いた。一枚、また一枚とイラストを捲っていく。やがて編集長の背が背もたれから離れ、表情が硬く引き締まっていく。
お互いに無言のまま、小一時間ほど過ぎた。最後の一枚を見終えた編集長がファイルを閉じた。再び背もたれに体を預ける。心なしか震えているような気がする。もしかすると怒っているのか。
編集長は俺を見た。
「……なあ、個展を開いてみる気はないか」