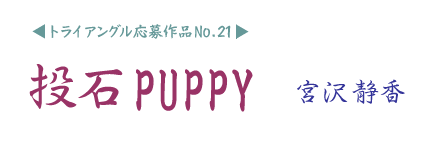
ヴァチカンに楯突いた司教は歴史上に23人。俺に尻を突き出してよがってるデリヘル嬢は23歳で、前後運動に励む俺の歳も23。そうこう考えると、23って妙にガッツィー。
でも現実はそんなに綺麗なものじゃない。正義に燃えた司教たちは例外なく投獄されたし、この女なんか燃えたくなくても燃えなきゃならない重労働。俺にしたって最悪な歳の真っ只中だってんだから、23なんて本当はロクな数じゃない。早いトコ23歳をやめないと向こう23年くらい報われないぜ。避難勧告発令中さ。
「もっとケツ出せよ!」
俺はピストン・スピードを上げて缶ビールをあおり、それから女の背中にビールをたらした。「ひゃっ」と女は鳴いた。明かりを消してるせいか背中が青く錆びついて見える。長方形をしたそれは薄闇にぼやっと浮かんで、まるで新種の生物みたいだ。
それにしても、ロフトでアキラが相手してる女の声ってかなりイッてる。息を荒くするんじゃなくてチベット僧の読経みたいなタイプ。加えてやたらと低いトーン。安アパートの音響効果もあって、下で聞いてるとヘンな気分になってくる。チベットに行って学ばなければならない、チベットに行って学ばなければならない、なんて呪いをかけられてる感じ。上の2人はとっくに現地まで飛んじゃってるのかも。このまんまじゃ俺たち4人、チベットで「こんにちは」なんてことになっちまう。そういえばアキラも23歳。上の女も23だっけ。
「声出して行こうぜ!」
とアキラ。ガン! なんて物音も激しくて。あいつらいったい何やってんだ? 目の前の女は相変わらず。俺はといえば冷めたふりして結構イキそうで。そう。みんなどこかへ行きたがってる。今いるところから逃げたくてウズウズしてる。逃げようとしてるヤツ。逃げられないヤツに逃げたヤツ。3日前、女が俺から逃げてった。あぁあ。アキラの部屋って寒くてしょうがねぇ。
コトを終えた俺は女からもらった名刺を眺めていた。店名と店の電話番号の他には「小林」とだけ印刷してあった。デリヘル嬢・小林、か。ふぅん。なかなかイイ響きだ。シャワーの音が聞こえる。目線を移せばガラスに浮かぶ影がストリップ・ガールみたいにセクシー。きっと湯気まみれなアンビエンスも甘辛いイメージ。シャワーを浴びる女ってファンタジーだね。結局は何ものにも触れずに自分勝手な想像を膨らますのが一番だってこと。そうすれば誰も俺からは逃げないだろうさ。けど、ロフトからはリアルなピロウ・トークがひっきりなしに落ちてくる。俺の頭に降り積もって、まるで雪空の下にいるみたいに感じるのは何故? 女に逃げられた後に女を買うことほど虚しいのってないぜ。
「あのさぁ、寒いんだけど」
と俺がいうと、
「しょうがねぇよな。もう暖房器具もねぇし毛布もねぇし」
とアキラが顔を覗かせた。
「寒がる前に服着ろよ」
「……まったくその通り」
俺は新しい缶ビールのプル・タブを引っ張った。泡が飛んできて太ももの内側にひっかかった。今度はビールの雨かよ。この部屋ってば何だって降ってきやがる。はいはい。こんなところで服も着ずにいる俺が悪いのさ。みんな俺が悪いのさ。
俺が服を着終わると小林がバス・ルームから出てきた。体に纏った橙色のタオルが宇宙服みたいに鈍く光っていた。
「おかえり」
と俺はいった。
「ただいま。ねぇ由美、空いたよ」
はあい、と上にいた由美って女がハシゴに足をかけた。シーツも巻いていなかったし下着も着けていなかった。おぼろに霞む彼女の小さな尻が、俺には満月に見えた。明け方に消え行く可愛らしい満月さ。征服欲を存分に掻き立てやがる、なんて思ってたらそれはゆっくりと大きくなって、落ちてきた。強大なパワーを放ちながら迫ってきた。俺はビールの缶を咥えながらずっと見てた。バカでっかいお月さまだったぜ。やがて俺の鼻先でプルンと止まると、吹き出物のクレーターまで確認できた。それはそのまま水平移動して、名残惜しくもバス・ルームへと消えたんだ。俺ときたらまるっきりなっちゃいなかった。飲み過ぎの気があるにしても、まったくなんて夜なんだ。月まで降ってくるなんて。
「あたしにもそれちょうだい」
後ろから小林の長い指がしゅるるって伸びてきて、俺の握った缶ビールを奪って行った。振り返るとピンクのロング・モヘア・ニットがまぶしかった。航空母艦のような胸をして、目はアーチェリーの的みたいにクルクル。脚なんかゴールデン・ゲイト・ブリッジだった。
「ぜんぜん入ってないじゃん。新しいのもらってイイ?」
「イイんじゃない?」
小林は冷蔵庫から缶ビールを2本取り出してその内の1本を俺に寄越した。そして俺の隣に座って毛布に包まり、「寒いよね、ここ」といいながら枕を抱いた。
俺と小林は同窓会で久々に会った者たちがするように他愛もない話を始めた。お互いの今までについて。お互いのこれからについて。23歳という呪われた年齢について。
「あたしもそう思う。サイフ落としたのも前の店クビになったのもみんな23になってからだもん」
「俺なんか23になってから3回もクビになってんだぜ。ウェイターと服屋と配管工事。決まってこういわれんの。どうせ俳優にゃなれねぇよってさ」
「23を過ぎたら急に良くなったりして」
そういいながら小林はまた冷蔵庫を開けた。
「実は俺さ、あした誕生日なんだ。23歳から逃げんの、さっさと」
「あと1時間ちょいじゃん。自分ばっかりずるくない?」
「引き上げられてる感じがするよね、引き上げられてる感じが。そうだ、プレゼント代わりに電話番号とか教えない?」
小林は躊躇しながらも名刺の裏に電話番号を書いた。
「デタラメ書いてんじゃない?」
「かけてみれば?」
ダイアルすると彼女のバッグの中からマーチ風のメロディが流れた。それを聴きながら、俺は辛かった23歳からついに抜け出せるんだって思った。
「あのさ、日付が変わったら俺に電話する気ない? おめでとうって」
「あー……いいよ。してあげる。おめでとうって」
そこで由美が戻ってきて、アキラも降りてきて、俺はささやかながらも23歳居残り組から祝福された。明かりが消えたままの部屋で。
大通りで待っている車まで小林と由美を送ろう、なんて風に話がまとまって、俺たち4人は立ち上がった。それからお互いを無言で見渡した。こういうのってなんかイイ感じ。誰も褒めてくれないけど、真夜中の木立ちみたいに素敵じゃない? 先頭を行く俺はドア・ノブに手をかけて右に回した。玄関を開けると、白かった。雪が降っていて、アパート前の駐車スペースにも、小路にも軒の植木にも5センチくらい積もっていた。どうりで寒い訳だ。
「げー。シャブだらけ」
と由美がいった。
「ぽん! ぽん!」
と小林がガキみたいに駆け出した。こいつらの内側って相当よじれてるんだろうけど、ハシャぐ気持ちは良く分かる。いつ魂を乗っ取られても不思議のない肉体的にも精神的にもヘヴィな仕事を終えて、さて帰ろうかって時に世界が真っ白に染まってるんだから。真正面の外灯はクリーミィな雪を照らして、そのスポット・ライトの中には誰の足跡もなかった。風もなく、雪の結晶はまっすぐに落ちていた。まるで何の障害もないみたいに。まるで世界が平和で満ち溢れているように。俺も平和な人間になるのさ。あともう少しで悪いニュースとは無縁の人間になるのさ。
「おら!」
と由美が小林に向かって雪玉を投げた。
「温泉行きてぇ!」
と小林も投げ返した。その玉は俺の脇を抜けて玄関にいたアキラに当たった。
「アハハ」
と小林たちが笑った。アキラも笑って、俺も笑った。小林と由美は次々に雪を投げて、アキラとアキラの部屋の玄関は雪だらけになった。アキラも「何なんだよ」なんていいながら楽しそうに雪を投げ返す。俺も小林&由美に雪を投げた。
「ねぇ!」
と小林がいった。
「温泉行きたくない? 4人で温泉にさ!」
いつかこうなるような気がしてた。こうやって笑いながら、ツキのない1年とお別れできるだろうって。風俗嬢の電話番号を手に入れて得もいわれぬ予感に胸をときめかせるだろうって。俺は笑い通しだった。小林も、由美もアキラもそうだった。
「アハハハハハハ!」
「うるせぇんだよバカったれ!」
誰かの怒声に俺たちは動きを止めた。アパートに向かって右端、階段脇の101号室の前に男が立っていた。年の頃は30過ぎ。パジャマ姿なんだけど強面の、紛うことなきヤクザもん――。そういえば、ここ1年ずっとそうだった。ことある毎に必ず邪魔が入ってきやがった。けっ。混みまくった電車は今ごろ雪で往生さ。環状線ではあっちでこっちでスリップ事故だ。挙げ句はこのボス・キャラ。23歳ってのは難儀すぎるぜ。
「人が寝てる側で何やってんだよ!」
こんなにトリッキーなヤツには関らない方がイイと直感した。俺が「すみません」と頭を下げると、アキラも玄関から出てきて「ごめんなさい。静かにします」と頭を下げた。俺とアキラは頭頂部を小突かれて、更に深く頭を下げた。時々、俺なんかは生まれてこなきゃ良かったと思う。存在しなきゃ良かったと思う。でもここにいるもんをどうしようがある? 死ぬか? 死ねやしない。怒りにまかせて破壊を繰り返すか? そんなことできやしねぇ。どうしようがあるよ? どうもこうもできないって。男は言語不明瞭な捨て台詞を残して101号室へと消えた。俺は情けなさそうに顔を上げた。小林たちは跡形もなく消えていた。夢か幻かってな具合さ。その通り。俺はいつも夢の中にいる。いつもぼんやりしていて、いつも自分の都合良く戯れるだけ。夢の真ん中で駄々をこねるだけ。これからどうなる? 俺は年を取る。これからどうする? 分かんねぇよ。雪が降ってる。冷たくて忌々しい人生、いつだって存分に楽しめばイイさ。何だってイイんだよ。どうせ個人の自由だ。
「なぁ」
とアキラがいった。
「戻ろうぜ」
戻る? どこへ? いつへ? 俺は足かせみたいな雪を掴んで101号室の手前へ投げた。
「どこに?」
「部屋だよ。俺の部屋」
戻りしな、俺はもう一度雪を投げた。
アキラの部屋ってやっぱり寒い。アルコールで温まろうとしても冷えたビールしかないから飲めば飲むほど寒さがつのる。そんな中、俺はエラーな感覚を抱いていた。フリーズしながら、置き時計と小林型にへこんだ枕を見つめていた。ロフトでは、アキラがどこかに電話中。どんな時でもめげないヤツさ。俺はアキラの会話を邪魔してやろうと訊いてみた。
「ボールってなかったっけ?」
音もなくゴム・ボールが降ってきた。悪い冗談みたいなピンク色。俺はボールを弄びながら、これが地球だったらイイのにって思った。ピンクの快楽に染まった地球を手中に収められるのにって。秒針の音が聞こえる。24時へと進んで行く。俺は釈放を待つ囚人のようにその時を待った。
「まじかよ」
と俺は呟いた。日付が変わった途端に携帯が震えて、小林の電話番号が暗い部屋で光り輝いたんだ。
俺は俺が23歳から脱出したことを直感した。そして23歳の時には味わえなかった確かな喜びを勇んで飲み込んだ。祝、誕生日。俺は小林型の枕に頭を沈めて電話に出た。
聞こえてきたのは男の声だった。落ち着き払った口調で「本日はありがとうございました」なんて抜かしやがる。小林のことを訊いたら「上がらせて戴きました」だと。小林の持っていた携帯は店のヤツだったのかもな。まぁイイさ。誕生日に初めて喋ったのがデリヘルの営業だなんて、俺もずいぶんと立派な大人になったもんだ。
電話を切った俺は冷たい床に横たわったままでボールを上に放り始めた。行き場のない不満が込められたそのボールは投げても投げても俺に戻ってきた。まるで凶弾みたいに俺の頭やら胸をめがけて降ってきた。どうやら俺は23歳から逃げ遅れたらしい。向こう23年はきっとハードになるだろう。
「チッ」
俺は起き上がって枕にボールをぶつけてみた。枕の発する呻きが心地良かった。そうだ。この枕を小林型1号と名付けよう。そしてイヤなことが起こる度にボールをぶつけるんだ。いや、こいつを見かけたら必ずボールをぶつけてやる。俺は何度も何度もボールをぶつけた。ぼすっという音がする毎に、俺の不満が消失したような気がした。ははは。は。そんな気がしただけさ。邪魔なものやイヤな感覚が突然消え失せるなんて、そんなにちゃらちゃらした話なんかどこにもないって。
コーランに出てくる預言者は23人目が最後。ビリー・ミリガンが葬った人格の数も23。どちらにも共通してんのは、それ以上はナシってことだ。今だって、やっと23時を超えたと思ったら0時に逆戻りなんだから。俺までゼロになった気分さ。23ってのはとにかく危険な数だね。見かけたら一目散に逃げた方がイイ。じゃないと未来がなくなっちまうぜ。こいつは避難勧告どころじゃない。戒厳令さ。