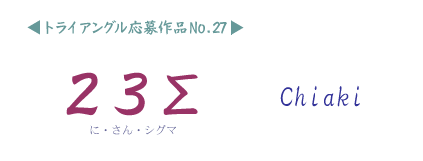
アパートは、横にしたハシゴのように並んでいて、私たちの住んでいる17棟はハシゴの最後の段になるんだよ。ママはそう言ってノートに二本、横線を引くと「いち、に、さん」と数えながら縦線で区切っていった。途中で数をまちがえたから苦しまぎれに、
「とにかく、このハシゴの最後が17-18棟。ちゃんと覚えておくんだよ」
僕の頭を小突いたけど、なんで僕の頭なんだよ。
「ノブはほんとに物覚えが悪いからね。だれに似たのかね」
パパはテレビの前にあぐらをかいて鼻の穴をふくらまし、ボタンをパチパチ叩いてゲームに夢中なふりをしている。
「それで、17-18棟のまわりは田の字みたいに区切られて、左下の四角がアパートとすると、その右側が田んぼ、左上の四角が公園で、右が雑木林になるわけ。雑木林のさらに右が幼稚園。公園から見えると思うけど、アパートの右隅の一階が私たちの家なんだ。赤いバスタオルをベランダに吊るしておくから、もう迷うんじゃないよ」
ママは鉛筆を放り出して首をねじると、パパに文句を言った。
「ねえ、クーラーはいつ取りつけるのさ。ノブが夏休みに入る前に絶対つけてよね」
ママが、てのひらを団扇がわりにヒラヒラさせながら念をおしたが、パパはあいかわらずテレビに集中したまま応えた。
「台所の窓を開けたら涼しくならないか」
ママが手と頭とを互い違いにイヤイヤと振った。
「引っ越し荷物がまだバラバラじゃん。見られたら恥ずかしいよ、絶対にだめ」
ママはお腹をさすって「ふうっ」と息を吐いた。四才の僕は、秋には「お兄ちゃん」になるそうだ。だからもっとしっかりしなさい、ママは言うけど「しっかりしなさい」はママのくちぐせ、ぼくはちっとも気にしない。ぼくをノブと呼びすてにするママに、
「僕の名前は伸治(しんじ)なのにどうしてノブって呼ぶの、だったら始めからノブにしたらいいのに」
「伸治の伸はノブともいうし、伸治をちぢめてノブ。わかった」
でもなんかへんだな。
「どうしてシンがノビルなの、シャープペンシルみたいでおかしいよ」
「そんなこと気にしない、きにしない」
ぼくの頭をポンと叩いて笑いとばす。ぼくはパパのひざにすり寄って、あぐらの上にのっかった。一緒にゲームをすることにした。
「今日、ノブにひらがな教えたんだけどさ。どう書いたと思うパパ。教室って書かせたら<しょうしつ>なのよ、キとシの区別もつかないなんて、あたしゃもう気分消失だわ。ねえ、ちょっと聞いてるのパパ、ちょっとパパったら。ほーんとにあんたは頼りにならないんだからもう」
ママは、おすもうさんのようにノッシノッシと外またで歩いてきた。僕とパパがべったりくっついてママの相手をしないので、イライラしたママはテレビのコンセントを引き抜いた。唖然とする僕たちにむかって、足をドンと踏み鳴らすとお腹をつきだした。
「いつまで遊んだら気がすむの、あんたたち。タンスに服をかけて、自分の洗濯物をしまいなさい。それから本棚を組み立てて、蛍光灯も取り替えて、あーなんてことを、宅配ピザをこんなに食い散らかして。こらこらっ、チーズを拾って食うんじゃないのノブ、トマトもだめだって、汚いつーの。あんたたち相手にしてると、あー頭いたくなってきた」
息をきらしたママがフゥフゥいいながらトイレにこもったので、パパと僕は顔をみあわせ肩をすくめると、またテレビのスイッチを入れたのだった。
僕は、アパートがいくつ並んで田の字がどうこうなんてこと、すこしも覚えられなかった。新しい幼稚園は雑木林と田んぼに囲まれていることも知らなかった。
パパが会社を辞めて実家の八百屋を継ぐことにしたので、ぼくたちは東京から埼玉に引っ越したのだ。
「俺の田舎じゃ幼稚園でABCだのヒラガナなんか勉強させないから、逃げ出したりせず気楽に遊べばいいさ」
パパはそういって頭をなでるけどママは、
「まだ名前が書けないなんて、あたしがはずかしいよ。ほんとにバカなんだからノブは、もっとしっかりしなさい」
僕の頭をひっぱたくのだ。だのに公園では、
「先生から嫌味を言われたわ。シンちゃんは幼稚園でいちばんかけっこが早いですって。転入した日に先生ふりきって幼稚園から逃げ出しちゃうんだものね。あたしもう恥ずかしくて、」
困ったような嬉しいような、へんな顔して団地のママたちに自慢していた。同級生が何人も住んでいる団地では、みんな女学生に戻ったみたいにぺちゃくちゃ喋るのだそうだ。
「あのさ、高校生が夜中に公園で騒ぐようになったじゃない。なんだか、さかりのついた猫みたいで嫌よねぇ。それにさ、あたし見ちゃったの。その、あの、不純異性行為っていうのかしら、あれよ。私のとこは三階でしょ、ベランダから公園がよく見えるのよね」
そのあと花がしぼむように皆が声をひそめて頭を寄せ合ったので、ぼくには話がよく聞こえなかった。だからママのスカートを引っぱった。
「ママ、ふじんせいこういってなに」
「婦人・性行為!」
いっせいに声がして、つぼみが開くように皆がのけぞった。
「こらノブ、邪魔すんじゃないの。あっち行って、しっ」
ママは、ノラ猫でも追うように僕を砂場に押しやった。
大人たちはときどき変なことを言ったりしたり、僕には訳がわからない。訊ねても、ちっとも説明してくれない。それなのに勉強の時には、
「なんでこんな字が判らないの、まったく」
などと、わかるように説明もしないで自分勝手なことをいうのだ。
ジュンちゃんとアッちゃんがスコップで砂あそびしていた。二人とも僕より小さい子供じゃないか。ほんとは砂遊びなんてしたくないけど、しかたなく砂場に座りこんだ。ママたちの話し声が聞こえてくる
「3棟の竹中さんちの娘さんが家出したの知ってる。まだ高校二年生よ。夏休みになると家出人の捜索依頼が増えるって、うちの旦那が悲鳴あげてたけどさ。まさか晩ごはん食べてる我が家に奥さんが頼みにくるとは思わなかった。あっ、これぜったいに内緒だからね」
ぼくは不思議でならなかった。「ぜったい内緒」なのにどうして話すのかな。ママに聞いてみたいけどまた叱られるのかな。
アッちゃんが砂のおまんじゅうをくれた。
「このリンゴがジュンちゃんで、こっちのメロンがシンちゃんね」
どちらもまんまるの砂ダンゴ、ジュンちゃんと僕は、どっちがリンゴでどこがメロンか、砂ダンゴをみくらべたまま「ありがとう」も言えなかった。
絶対ないしょといいながら話をしたがる女の人と、砂ダンゴのこっちがリンゴでこっちがメロンだと言い張るアッちゃんは、きっと親子にちがいないと僕は思った。わけのわからないことを言う点では、どちらもたいへん似ていたからだ。
ママがお腹をさすりながら「どっこいしょ」とベンチに尻もちをついた。これは僕の妹をいたわるというよりも、これからゆっくり井戸端会議を始めるという合図みたいな気がして、僕はためいきがでた。
アッちゃんが、「みんなでお城を作りましょ」というけれど、それはジュンちゃんにまかせて僕はさっさとブランコのほうに歩いていった。ちいさい子の相手はごめんだよ。
ブランコに乗ろうとしたけれど女の子が先に飛びついて、お下げが地面にこすれるくらい胸をそらせ、細くて長いあしを青空にはねあげた。ブランコの縄がキュルキュルなった。女の子はフンという顔をして、前歯が二本欠けたその隙間から三角のとがった舌を突きだした。
この女の子どこかで見たことがある。えーと、そうだ幼稚園のタンポポ組の子だ。いつも僕の邪魔をしてまわる嫌な女の子、かけっこが一番早かったけど僕が入園してから二番になって、それで僕にいじわるするみたいだ。
僕より背が高いし足も長いし身体も大きいし、ちょっとこわい。あきらめて滑り台の階段を登ろうとすると、ブランコからぱっと飛んできて僕の横から割り込んでくる。しかも滑り台の途中で足をふんばるから、後ろの僕はすべれないじゃないか。
「ちょっとそこどいて、僕がすべるんだから」
「あら、勝手にすべったら。この滑り台はあんたのものってわけじゃないでしょ」
「でも、」
「でもなによ、文句いう前にすべってきなさいよ」
なんだがママみたいにつんつんした喋りかたをする。この子の背中にぶつかったら、きっと頭を叩かれる。
そのときネコの泣き声がきこえたのでぼくは立ちあがった。公園の隅の笹藪に捨て猫がいるのを思い出した。どこかのお婆ちゃんが残り物を藪の中に押しこんでいるのを、たびたび見ている。滑り台ですべったあげく女の子に頭を叩かれるくらいなら、子猫と遊んだほうがましだ。僕は飛行機みたいに両手を横に広げて勢いよく階段を駆けおりると、笹薮めがけて走った。すると女の子がパタパタ後ろを追いかけて僕を驚かせたけど、何もしていない僕が叩かれるいわれはない。
「あらそうかしら。雑木林にはいったら、頭を叩かれるのは確実よ。女の子はとくに危ないから一人で入っちゃ絶対だめって、お母さんが言ってたもん」
そういいながらも背伸びして、背丈よりも高く茂る藪やぶをながめまわした。
「あっちのほうから聞こえるわ、行ってみましょ」
「入っちゃだめって、さっき自分で言ったばかりじゃないか」
困った僕はママたちの方を振りかえったが、みんな背中をむけてベンチに座っており、笑いながらしきりにうなずく横顔が見えた。
「そうよ、一人じゃだめってことよ。でも二人でも駄目って事にはならないわ。さあ、手をつないで」
僕のママもアッちゃんも、アッちゃんのママもこの女の子も、どうして皆おかしなことばかり言うのだろう。それともママが言うように、僕の頭の方が変なのかな。
女の子は笹薮を片手でかきわけながら、僕の手を引いてどんどん中に入っていった。顔じゅうを笹の葉が引っかいたけれど、だんだんまばらになって、緑の葉を繁らせた雑木にかわっていった。人が踏みしめた細い道もあり、ところどころ白いビニール袋や錆びた空き缶が転がっていた。女の子は手の力をゆるめて、
「だから言ったでしょ、二人ならだいじょうぶだって」
木陰まで来ると立ちどまり、髪の毛にからみついた小枝やクモの巣を払いのけた。どこかでカラスが鳴いている。
「猫の泣き声がしないよ。逃げたのかな」
「お馬鹿さんね、子猫は用心して隠れているものよ。それはね、独りでお留守番しているとき誰か知らない人が尋ねてきても、黙って隠れているのと同じことよ、わかるでしょ。お母さんが夕方、仕事に行く前に必ず言うことだから、今じゃ逆さまからだって暗誦できるわ。……、あたしほんとはね、独りでお母さんの帰りを待つのは寂しいから、子猫を飼いたいの。もう名前も考えてあるのよ。あなたのおうちにペットはいるの」
「いないけど、もうすぐ妹ができるってママがいってた」
「まあいやだ、ペットと生まれてくる赤ちゃんを一緒にするなんて。あなた頭がおかしいんじゃないの」
そういってから女の子は急にしゃがんで、ひざを抱えたまま黙りこんだ。ときどき猫のようにこぶしで顔をなでた。風がシャラシャラと笹の葉を鳴らした。木立の隙間からゴルフボールのような白い日差しが地面に落ちて揺れた。
ぼくが泣かしたんじゃない。ぜったいに僕のせいじゃないけど、こんな時どうしたらいいのかわからないまま、
「ねえ、子猫を探しにいこうよ」
腕を掴んでむりに身体をひきあげた。でも女の子のしゃっくりがなかなかおさまらず、しかたなく僕が先に立って歩いた。こんなときは歌をうたうと元気になる。
「ぼ、ぼ、ぼくらは少年たんていだん。ボ、ボ、僕等は少年探団・・・」
少年探偵団が何なのか知らないけれど、とにかく歌をうたうと、うきうきして身体が軽くなった。女の子もハミングしながら後についてきた。
「ねえ、赤ちゃんがどこから生まれてくるか、あなた知ってる」
とつぜん背中から言われたのでびっくりしたけど、立ち止まったり振りかえったりはしなかった。どうして女の子は変なことばかり言いたがるのかな。
「知ってるよ。僕はね、ウンコみたいにお尻からポトンと落ちたんだってママが教えてくれたよ」
幼稚園の広場でジュンちゃんがウンコするのを見たことがあるけど、きっと僕もヘビのようにグルグル巻いて生まれてきたんだと思う。だって僕はヘビ年生まれだもの。
「あははは」
女の子が青空を見上げてわらったので、僕もなんだかおかしくなって一緒に笑った。それからニ三歩すすんだ時、「ガア」とカラスが鳴いて叢から飛びだしたのでドキッとした。女の子が笑うのをやめて、震える声で「もう帰ろうよ」とぼくの手を強く握る。こんなにコロコロ気分の変わる女の子には会ったことがない。ぼくは腹がたってきた。
「どうして、子猫を探すんじゃないか」
「いいから、もう帰ろうよ」
僕の背中にぴったり身体をよせる女の子、首をすくめて見上げる木の枝にピンク色のパンティがさがっていた。幽霊でもみたかのように怯える女の子は、「もう帰る」と繰り返した。
「どうしてパンツなんかが恐いのさ、おかしいよ。いくじなし」
そう言ってなじると女の子は怒るどころか泣きそうな顔になって、とうとう僕の手を振りきって逃げていった。
だから女の子は怖がりで弱虫でだめなんだ。ぼくはパンツなんかちっとも恐くないから、歌をうたいながら、さらに進んでいった。
あのね、パパの歌は「ぼくらはしょうねんたんていだん」で、僕のヒラガナは「ま゛くらはしょねんたんてだん」だとママが嘆いた。
「なんで<ぼ>を<ま゛>に省略しちゃうわけ。それに<う>も<い>も抜けてるじゃない、あんたいったいなに考えてんの。枕に濁点が付くもんですか」
ママがぷりぷり怒って僕の頭を小突くけど「枕に濁点」てなんのことだろう。
テレビゲームをしていたパパがいきなり笑いだして「枕は少年探偵団だあ」とふざけたけれど、ママがじろりと睨んでパパを黙らせた。
「書き取りはもういいから、こんどはアルファベットと数字をいくよ」
ママがカードをめくって僕の鼻先に突き出してくる。
「えーと、それはママのお腹だからD、次はおっぱいだからB、それからえーと、えーとジュンちゃんのウンコだからそれは、」
「ジュンちゃんのウンコぉ〜」
ママの声が裏返った。Mのカードがママを仰天させるとは思っていなかった、僕のほうこそ驚いた。
「だってジュンちゃんがウンコしてる足の格好に似ているもん」
ママはMのカードと僕の顔とを交互にみくらべ、それから蛍光灯を見上げて鼻息をふかした。
「あー、ノブの相手してると頭痛くなってくる」
テーブルに両肘ついて額を支えた。よかった、もう勉強は終わりのようだ。なにげなくカードをめくっていると、僕はあることに気がついた。カードを選んで並べると23Σとなった。
「ほらママ、Σが脚で3がおっぱい、首と頭は2かな、ねえ見てみて、そっくりだよ」
ママは「めんどくさいなぁ」という顔で23Σと並んだガードをちらりと見てから言った。
「それじゃMが横倒しで寝ちゃってるよ」
「そうだよ、裸の女の人も脚をMみたいにして寝てた」
ママが急にふり向いてパパを怒鳴りつけた。
「パパ、えっちな週刊誌は置いといちゃだめって言ってあるでしょ」
「ママ、ちがうよ。今日、子猫を追いかけて雑木林に入ったんだ。そこに裸の女の人が寝てた。首をこんなふうにして」
ぼくは自分の頭をおもいっきり横に傾けたが、女の人のようにはうまく曲げられなかった。おかしいな。このカードの2のように、ポキリと横に曲がるはずなんだけど。