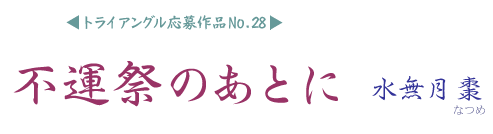
そのとき
急にすさまじい音がきこえた。
パパは,私をつきとばした。
ママの声がきこえた。
私は妹の名前をよんだ。
妹がママに放り投げられて私の両手におさまった。
私は妹を抱いて
気を失った。
12月31日のことだった。
第一章
私は少しほほえみ、掃除機をかたづけた。そろそろおばさんたちが帰ってくるころだ。
私の名前は青沢文子(あやこ)。私が両親と自分の家を失ったのは2年前の12月。自動車事故だった。
私は屋根裏部屋に上がった。1番隅っこの小さな部屋、そこが私と妹の部屋だった。
「輪子、おわったよ。」
「おねえちゃん。」
部屋には、古ぼけた小さなテーブルと椅子、本棚、ベッドがそれぞれ1つずつある。妹の輪子はそのテーブルに座って本を読んでいた。
「カタカナも読めるようになったよ、おねえちゃん。」
「うん、そう、よかった。」
私は黄色いエプロンを取りながら羽根布団に腰掛けた。妹は7歳、私は12歳。私達ふたりは、父の弟の、この家に引き取られた。ここにはふたり、息子が居る。私達は、学校にいけない。だから、輪子には、私がいろいろおしえてきた。ひらがな、カタカナ、漢字、足し算、引き算。両親が死ぬ前、私は100冊近くの本をもっていた。でも、20冊を残して、みんな売った。自活していかねばならないとここの一家を一目見てすぐにわかったから。ここの息子達にいじめられたことはないが(兄の方とて、私より3歳も年下だ)、ここの親ふたりに、私達と口をきいてはならないときつくとめられているらしかった。私はひとりでこの家の家事をこなさなければならない。洗濯、皿洗い、掃除、片付け、繕い物。妹は、私の邪魔になることを恐れて、めったに部屋の外へ出ようとはしなかった。叔母、叔父は、私のことをにらむ、そしてさりげなく私のことをいびる。私はできるだけ、彼らが外出している時に家の仕事をするようにしている。
「おねえちゃん、これ、なんてよむの?」
妹が言った。
「どこ?」
「ここ、3行目のところ。」
「うん、これは“たぐい”。」
輪子は私のことを見つめた。私はピンときた。
「今日は日曜日だったね。じゃあ、5時くらいに行こうか?美術館。」
妹はにっこりした。
私達の父は画家だった。知っている人はけっこう多い。デ・キリコのような感じの作風で、人気があった。私と輪子はバスに乗ってよく美術館に行く。本を売ったお金で買った23枚綴りの回数券のうち、2枚を料金箱に入れてバスを降りた。小さな美術館に入る。外はもう夕暮れ時、人もまばらな時間に、父の絵の前に座り込み、美術館のひんやりとして落ち着いた空気を吸うのが、私と輪子は大好きだった。
「あっちゃん、りんちゃん、ひさしぶり。」
背の低い40代のおじさん。守衛の長森さんがにこにこしてあいさつしてくれた。この人とは生まれた時からのつきあいだ。
「長森さん、ひさしぶり。」
私もおじぎした。この美術館に父の作品は4点ほど有った。どれもいい絵だ。私は輪子を膝に座らせ、1メートル40センチの絵を見つめた。
全体的に茶色と赤の占める、小さなひろばの絵。輪子はほっぺたに赤みがさし、目を見ひらいて私に言った。
「おねえちゃん、今日はどこであそぶ?」
これこそが私と輪子の作り出したあそびなのである。私は笑って言った。
「じゃあかくれんぼしようか。」
「わぁっ、さんせい!」
私達は絵の中に入り、あそび始めた。
つまり、空想であそぶのである。
「ジャンケンほいっ!」
まず、ひろばの真中で、私と輪子はジャンケンをした。ひろばには、夕日が差し込んでいる。
「おねえちゃんの負け!ふふふっ鬼になってね。」
「んーむ、しようがないなー!!」
私はうめいて茶色いところどころ三角の窓の空いた壁に目を押し当てた。
「いち・・・にぃ・・・さん・・・し・・・」
「もういいかい!?」
「まァだだよ!!」
「ごぉ・・・ろく・・・しち・・・はち・・・きゅう・・・。もういいかい?」
遠く離れたところから妹の返事が返ってきた。私は探し始めた。2つ目の壁の裏、石碑の後ろ。
「さては・・・?」
私は絵を飛び出し、また隣の絵に飛び込んだ。黒とレンガ色とふかみどりの絵だ。3、4人の人が、大きなテーブルで食事をしている。マスカットや、リンゴ、オレンジ、洋梨などが、山積みになった大皿の後ろ。
「みーっけた!」
「うわーい!!」
私達は1時間ほどそこであそんだ。かくれんぼのほかに、おいかけっこやおままごと。さんざんあそんだあと、長森さんに言われた。
「おいおい、あっちゃん、もう6時だぞ。そろそろ・・・。」
「はい、帰ります。」
私が答えると長森さんは、急に気遣わしげな表情になった。
「ここに来たくなったらいつでもおいで。」
「はい、ありがとうございます。」
「うーむ、できるものならうちがひきとってあげたいんだが・・・3LDKのマンションではなァ・・・。」
「どうも、私もです。おくさんによろしく言ってください。」
「バイバイ、ナガモリさん、またね。」
「バイバイ、りんちゃん。」
輪子も長森さんに手を振った。バス停に歩いていると輪子が私を見上げた。
「あの・・・おねえちゃん。」
「うん、私もおなかすいたから、ハンバーガー、買って帰ろうか。」
「・・・」
「大丈夫だよ。お金はまだ残ってる。」
私と輪子はお店に入り、ハンバーガーの小、二つとフライドポテトを買って帰った。
夜、星を見ながらハンバーガーを輪子と食べていると、私は満ち足りた気分だった。ここの息子二人より、私と輪子の方が幸せだと実感した。
第二章
私は輪子にお話をしてやった。いつもいつも、夜寝る時は、腕枕で、お話をしてやる。終わりがたには、輪子は必ず眠った。小さな窓から星を眺め、私は黙っていろんなことを思い出してゆく。大人になって、仕事が見つかるだろうかなどと考えるのは落ち込むばかりなので、きっぱりとやめにした。
「今だけを考えること。」
私はいつも、自分に言い聞かせた。そして死んだように、眠りに落ちた。
毎日毎日、私は仕事をこなした。山のような洗濯物、目がくらみそうな皿の山。私がこたえないので、叔父と叔母のイビリはエスカレートした。毎日のように叔母にどなられ、叔父に足を引っかけられた。“30代で、まだ若いくせして・・・コンジョウ悪!”と文句の一つも言ってやりたかったが、虐待がひどくなるだけなので、絶対言わなかった。肌がひどく荒れ、いつも疲れきっていた。美術館に行く回数もめっきり減った。たまに行って長森さんを飛び上がらせてしまった。
「あっちゃん!ひどいよ。寝てないんじゃないの?ホントに大丈夫?」
輪子が心配そうな顔で、私を見上げた。われながら、生きていけるのが不思議だった。
その年の12月、最悪のことが起こった。輪子が風邪をこじらせたのだ。クスリを買うだけのお金もない。叔母に言うと、笑って100円玉を投げつけられた。はらわたが煮えくり返った。水でしぼったタオルを輪子の頭に乗せ、私はうつむいてため息をついた。もうズタズタだった。でも、死ぬわけにはいかなかった。リンゴを台所から盗んで輪子に食べさせた。輪子が眠ると、あてもなく散歩に出かけ、広場をさまよった。あの美術館に、これほどまで行きたいと思ったことは生まれてはじめてだと思った。長森さんなら、なんとかしてくれるかもしれなかったが、お金は30円ほどしかなく、今輪子のそばを離れるわけにはいかなかった。八方ふさがりだった。警察に走りこめば良かったものを、頼みの交番はひどく遠いところにあった。
その夜、輪子は落ち着いていた。私はひとまずほっとした。小さな椅子に腰掛け、私はのろのろと眠りだした。ボーン、ボーンと1階で、時計が鳴る。たった1秒過ぎただけだと思ったのに・・・本当は1時間も経っていた。
「輪子・・・?」
妹は、そこにいなかった。ベッドはまだあたたかく、ノートのきれはしが置いてあった。
「・・・お父さんとお母さんが来ました。」
私は朦朧とした頭でそれだけ読み、朦朧とした身体で1階に下りた。叔母の財布。100円を静かにつかみ、私はバス停に向かった。
どうやってここに来たのか。まったく覚えがないが、とにかく私は美術館を歩いていた。外は月明かりに照らされ、星が出ている。美術館の中も割と明るく、ちゃんとまっすぐに歩けた。いつもの場所で、私は立ち止まった。小さい椅子にゆっくり座る。顔にまつわりついた髪を私は払いのけ、腕を組んで目をつむり、今までのように、絵の中へ入った。
いつものひろばは夜になっていた。私は真中で立ちつくした。白い息がふわーっと上へのぼり、私は周りを見た。誰も居ない。3つの壁、石碑、みんな探してみたが、誰も居なかった。隣の絵にも、その隣の絵にも。妹は居なかった。
私はぼんやりと、また立ちつくした。そして絵から飛び出した。ふたたび髪を払いのけ、私は考えた。そして立ち上がり、絵に触れてみた。
第三章
私は絵の中に、本当に絵の中に入っていった。つまり、身体が入ってしまったわけなのだ。別に驚かなかった。私はまた、探し始めた。
「輪子?」
私は呼びかけた。
「おねえちゃん!」
「輪子?どこ?」
「こっちこっち!」
「輪子・・・?」
私は、はじめて、広場の一番おくのところに、アーチがあるのに気付いた。
「輪子?そこにいるの?」
「おねえちゃん!早く!」
輪子の顔が、アーチの向こうから覗いた。アーチは、閉まりかけていた。私は迷わず、輪子のところに走っていった。後ろで、アーチが閉まった。
1ヵ月後に、長森さんが奥さんに言った。
「美代子、あの絵のこと、覚えてるか?」
「あぁ、青沢さんの絵ですか?あの広場の絵と、食事会の絵。」
「そう、そう。あの絵、『不運祭のあとに』って名前だが・・・不思議なんだ・・・聞きたいか?」
「ええ!どこが不思議なんです?聞きたいわ。」
「うん、あの絵に、ときどきあっちゃんがりんちゃんと来るんだよ。」
「どういうことです?」
「ふふふ、つまり、こう言ったら分るかな。食事会の絵、あの絵に居る人間の数、ときどき多くなるんだよ。」
「え!?本当に?」
「そう、2日に1回くらい、女の子が2人、食べに来るんだ。もちろん、知っているのは私くらいのものだけどね。広場にも、女の子がときどきあそんでる。つまりは、あれは文子ちゃんと輪子ちゃんなんだよ。」
「そう。」
奥さんは微笑んだ。
「そうね。あっちゃんが来るのね。」
「そう、あっちゃん達は、いつもあの絵であそんでた。あの子達が消失(きえう)せて1ヵ月経つ。」
長森さんは笑いながら言った。
「ふふ・・・あの子達はあの絵に引越してしまったんだなあ。」
2人は小さな2人の少女を思い出し、静かに微笑んでいた。