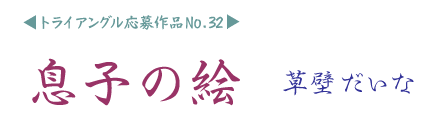
・・・・・・あじさいって、こんな色だったっけなぁ。
残業帰りなんかに、例えば駅裏の饅頭屋の、明かりの消えた店先に鉢があって、それが街灯に照らされているのが目に止まると、ふとそんなことを思ったりする。
花の色や、それが咲いていることすら気付かずに、人の頭しか見えないすし詰め電車に乗って職場に出向き、世間が静まり返った黒の中を、最終に近い線で帰る日々を淡々と繰り返してきた。しかしかと言って、そんな生活に不満もなく毎日訪れる時間を会社という場所でつぶしていた私だったけれど、最近はそんな気の抜けた生活のツケがまわってきたのか、その会社で何かと『ポンミス』と呼ばれる失態をやらかし続けていた。
今日などは業者への発注ミスで顧客から苦情が殺到して、部署をあげてのとてつもない騒ぎとなった。顧客リストには長年のお得意様も多数入っていただけに、なおさら早急の対応が必要だったが、即座にフォローの仕様も浮かばず、自分だけがただモタモタして、普段どおり時間ばかりが過ぎた一日だった。
ここのところ、下の赤ん坊の夜泣きでよく眠れていなかったのも事実だが、それにしてもトラブル続きであることに自分自身も自覚はしていた。仕事に影響が出るのは今回が初めてではないだけに、そろそろ悪い予感がしていた。
「今なら退職金の率も高いんですよ」
そして案の定、今どき黒ぶち眼鏡のひげの濃い上司から、遠まわしのリストラ打診がやってきた。
今職を失うと、妻と幼子二人を抱えて路頭に迷うだろうな。
しかしそんな、ほぼ現実味を帯びた退職事情は後回しで、とにかく顧客対応が先だった。
今日は何度頭を下げただろう。
腰が痛い。
頭も痛い。
そうしてせっかく気付いた花の色も、何事もなかったかのように忘れさってしまう。
*
そんな風に疲れきった心持ちでマンションのドアを開けると、いきなり上の息子の泣き声が聞えてきた。
今年買ってもらったばかりの学習机のまわりに、筆箱やらノートやら訳のわからないカード類やらが散乱していて、そんな中でパジャマ姿の息子は、ひたすら泣きじゃくっていた。
妻はそんな息子に背を向けて、同じように泣きわめいている赤ん坊に、無言でミルクを与えようとしている。妻の背中からは、明らかに神経質にイラついた空気が放散されていた。ここのところ子供たちの風呂もまかせっきりで不平もあるのか、私が部屋に入ってきても、おかえりの言葉すら出てこない。
「どうしたんだ」
泣いている息子の目線に合わせるように私は、腰をかがめて問い掛けた。
息子は、
「色えんぴつが足りない」
と言って、私の首に彼の短い両手をまわしてまとわりついてきた。
「色えんぴつがね、一本無いの。二十三本しかないの」
見れば、机の上に置かれた二十四色入りのアルミケースの中の、プラスチック製のしきりが一本分空間になっている。
「明日学校で使うのに。一本無くなっちゃったぁ」
なんだ、色えんぴつ。
これだけの混乱状況に対してのあまりにも安易すぎる答えに、すっかり力が抜けて、クレーム処理疲れの自分は多少むかついた。
妻の無関心な背中が、更にそんないらだちをかき立てた。
「パパ、探して。ねぇパパ、探してぇ」
「うるさい。自分で探しなさい」
耳元での泣き声がうっとうしくて私は、抱きついていた息子の手をほどいて、その小さな体ごと床にはねのけた。すると息子はそのままの勢いで、派手に両足を上げてしりもちをついた。
たかが色えんぴつが消えたくらいで、何だっていうんだ。こっちは会社のデスクが消失するかもしれないというのに。
息子の泣き声が、更に大きくなった。
「パパなんか大嫌い。パパなんか、どっかへ行っちゃえ」
息子はふくれて泣きながら、布団が敷かれた隣の部屋のふすまを、勢いよく音を立てて閉めた。
「『どっかへ行っちゃえ』ですってよ」
ミルクで腹の膨れた赤ん坊が、ベビーベッドで寝息を立て始めたことに落ち着いたのか、妻は意味有り気な笑いを浮かべてこちらを見ていた。
色えんぴつ事件に関して何をするでも無かった妻が、そんなことだけ口を挟んでくるのが腹立たしかったが、確かにその含み笑いの根拠はあったりした。
子供というものはまれに不思議な能力を持っていたりするもので、透視やテレパシーや、思えば私の小学校の同級生にも、やたら正夢を見るという奴がいたが、息子も時に、彼が口走ることが現実になるという、珍しい特技を持ち合わせていた。
とはいえ、そう摩訶不思議なものではなく、例えば先日なんかも妻の母親が「ソフトクリームを買ってやる」と、息子の手をひいて行き付けの店に出向いていった。
そしてその時、目的地に向かう途中息子は、大好きなチョコ味を要求したらしいが、妻の母は、
「チョコレートは虫歯になるからダメだよ」
と、別の味にするよう勧めたそうだった。
虫歯を気にするのなら、そもそも甘いソフトクリーム自体を買ってやろうとしなければいいものだと思うのだが、年寄りの観念はいまいち理解しがたいもので、とにかくそこで、いじけた息子は、
「お店のソフトクリーム、チョコだけになればいいんだ。チョコだけ売ってればいいのに」
と大声でさけんだという。
するとその日に限って店のソフトクリームは、どういう訳かバニラもストロベリーも全て売り切れで、まさにチョコ味のみ販売されていた。
妻の母も孫に買ってやると言った手前、拒絶したはずのチョコソフトを、しぶしぶ買わされる流れとなったそうだ。
そんな感じで、予言とかそういうミステリアス系ではなく、単に彼の願望を表現すると、叶ったかのように映る偶然がたまたま起きる、とまぁその程度のものだった。
「どっか行っちゃえ」
それが息子の心底の願いなら、もしかしたら明日あたり私は、彼の知らないどこか遠くへでも行っているのかもしれない。
そして今の私としては、そのお望み通り、どこにでも行きたい気分であった。
翌日、例のクレームの関係で再び遅い帰宅をすると、息子は既に布団に入って、すやすやと眠っていた。
そして彼の枕もとに、何やら丸みをおびた一枚の画用紙が、無造作に転がっていた。
「今日学校で、父の日の絵を描いたらしいの」
妻は、オムツ替えが終わってごきげんの子を抱いて、共に微笑み合いながら言った。
「色えんぴつが足りなくて、うまく描けなかったんですって」
赤ん坊をあやしながらの妻は、こっちに向かって言っているのか、抱いている子に話しかけているのか、見分けのつきにくい視線の置き方で話した。
丸まった紙を広げてみると、ゆがんだ『おとうさん』のひらがな文字の下に、眼鏡をかけた、いかにも私をモデルにしてくれたのだろうという絵が、画用紙いっぱいにえがかれていた。
どうやら昨日無くなっていたのは、肌の色に使うパールオレンジという色だったらしく、その色を使うべき箇所は、違う色で塗られていた。
緑。
私の顔全体が、緑色に塗りつぶされていた。
息子のおだやかな寝息が聞えてくる。
夕べあんなに怒りながらも、こうして父の顔を描いてくれたことに対して、いとおしさを感じた。
が、それにしても、もっとそれらしい色があっただろうに。
ピンクとか、せめて茶色とか・・・・・・。
一体なぜ、緑なんだ。
*
週末は、下の子が産まれて初めての、家族四人でのハイキングを予定していた仕事のトラブルの方は予想以上に速く片付き、来週にはメーカーへの対応のメドがたちそうで、難しい上司の機嫌もおさまり、これで落ち着いて家族サービスが出来そうだ、と思っていた。
が、そんな時に限って、下の子が熱を出してしまった。
しかし、息子もてるてるぼうずを作ってまでして楽しみにしていたし、せっかくの梅雨の晴れ間だということもあって、やむなく息子と私の二人で行くことに決まった。
父と二人きりの外出となったが、意外にも息子は不平を言わず、母がこしらえたお弁当とビニールシートを詰めたリュックサックをヨイショと背負い、幼稚園時代から使っている水筒を肩にかけて、ニコニコと私の後をついてきた。
私たちは電車に乗って、目的地である初心者向けのハイキングコースに向かった。
息子は私の隣の席に座って、まだまだ床に着かない短い足をブラブラさせて、黙って窓を流れる景色を目で追っていた。
仕事のトラブルからも、赤ん坊の泣き声からも開放された私は、息子と並んで外を眺めながら、窓の景色がどんどん変わっていくという当たり前のことを、とても新しい気分で見送っていた。
そして時々低い位置から私を見上げて、にっこりと笑う息子の顔を見て、
『この子って、こんな顔で笑ってたんだなぁ』
と思った。
そういえば、下が産まれてから半年、この子にゆっくりかまってやることがあまりなかったかもしれない。寂しい思いをさせてしまっていたかなぁ。
仕事のノルマに追われて、かわいいはずの我が子に八つ当たりまでして、そんなことにすら気付くことなく日々を過ごしていた自分に、多少なりとも反省をした。
無人の駅には文字通り誰も居ず、それでも訪れた人向けの近辺地図が書かれた案内板は、必要以上に大きく駅前の自販機の横に備え付けられていた。
私たちはその案内地図を参考に、車線も歩道も無く、民家の点在するその道をまっすぐ山間の方向に進んだ。
息子は相変わらず楽しそうにはしゃいでいた。
そして私も、なんだか楽しかった。
民家の石垣の隙間に小さな毛虫を見つけては「あおむしくん」と言って小枝で突っついたり、ひっつきむしと呼ばれる雑草を私の服に投げつけては「くっ付いた、くっ付いた」と喜び、お弁当を広げてはいつも食べているソーセージをひたすら「おいしい」と言ってほおばり・・・・・・。
そんなほんのささいなことに二人で笑い声をあげながら、小さな手と大きな手を握り合って、私たちはとつとつと歩いた。
日も傾きはじめ、そろそろ家に戻ろうかと思い始めた時、ふと見ると道端に、アロエが群れて植わってあった。
自然のものなのか、誰かこの近所の人が植えているものなのかよくわからなかったそれらは、先週まで続いた雨のおかげで水分をたくさん吸収して、生き生きと膨れ上がっていた。
「これなあに?」
「これはアロエと言ってね。この汁を塗ると、お肌がツルツルになるんだよ」
息子の問いに私は答えた。
「こんなトゲトゲ、どうやって塗るの?」
「こうするのさ」
私は生い茂るそれらのうちの一本をもぎって、その切り口からにじみ出てきた薄緑色の汁を、直接息子のホッペにすりつけた。
息子の頬に、緑色のラインが1本入った。
「これ付けたら、ママもツルツルになる?」
「なるかもね」
「パパもやってみて」
「やってみようか」
私は自分の頬に、次々と流れ出てくるその汁を、たっぷりとすり付けた。
「僕もする」
私と息子は、それぞれ一本ずつのアロエを握って、自分につけたり相手につけたりして、顔中を緑の汁で隈なく塗りつぶした。
太陽が沈みかけてあたり一面がオレンジ色に変わり始めた頃、私たちは緑色の顔を日に照らして、まるで笑顔の足りなかった時間を埋めるかのように、いつまでも二人笑いつづけていた。