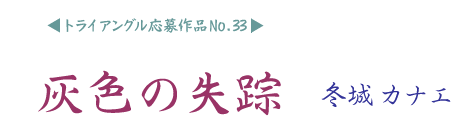
騒ぎは画用紙のすぐ横で起っていた。一本足りないことに最初に気づいたのは『あか』だった。保育園での静かなお昼寝の時間。子供たちに気づかれないよう、彼は仲間たちに声をかけた。なあ、誰か居なくないか、と。
色エンピツたちは、画用紙の横に寝転がったまま、隣のエンピツを不安げに見たりちょっと身体を起こしてみたりした。
「確かに、一本足りないな」
そっと、囁くように応えたのは『きいろ』だった。
彼ら色エンビツたちは、専用のケースに入れてもらえずに、書きかけの絵が書いてある画用紙の横にまとめて寄せられていた。それというのも、彼らのオーナーである少女がお昼寝の直前まで、絵を描くのに熱中していたからであった。
いくら専用のケースに収まりたくても、彼らにはオーナーの意向に逆らう権利はない。
「誰だ、居ないのは?」
『あか』が少し厳しい口調で言った。彼にはこの色エンピツ24色セットを率いるリーダーとしての自覚があった。一本でも欠けてしまっては規律が乱れてしまうというのが彼の考えだった。
「無理よ、ケースに入ってみなくちゃ分からないと思うわ」
色エンピツたちが口々に騒ぐ中で、リーダーにそう進言したのは『ももいろ』だった。彼女は『あか』と色相が近いだけあって仲が良かった。付き合ってるんじゃないかと邪推する者もいるくらいだ。
しかし『ももいろ』の言葉に『あか』は沈黙した。
いくら子供たちが寝ているからといって、今は昼間だ。昼間に動き出すことは色エンビツの常識から外れている。
彼が悩んでいると、ケースに入ったままの『しろ』が声を上げた。
「私が少し身体を起こして、誰か来ないか見張っているから、君たちもこっちへ戻ってみたらどうだい?」
「そうだよ。そうしよう」
彼の意見にすぐ賛成したのは『きいろ』。すぐにコロコロと転がってケースの方に向かってしまう。彼はつい先ほど、大きなヒマワリの花を書くという大仕事を終えた後だったので、正直なところ、妙なトラブルでこの満ち足りた気持ちを邪魔されたくないと思っていた。
他の色エンピツたちも、そろそろとケースへ向かう。渋い顔をしていた『あか』もやがてケースに向かって自分の身体を横たえた。
そして順番に並んでみて初めて、彼らは仲間のうち誰が居なくなっていたのかを知った。
『こげちゃ』と『くろ』の間にぽっかりと空いた溝。
そう、消失していたのは『はいいろ』の姿だった。
「アイツか! そうか! あー、気づかなかったなあ」
『だいだい』が甲高い声で苦笑しながら言った。
「アイツ、存在感ないもんな……」
ピク、とその言葉に色エンピツ全員が反応した。それは誰もが思っていたことだったのだ。
ある者は『はいいろ』のことを哀れに思い、ある者は『はいいろ』のことを気付いてやれなかった自分を責めた。
ただし、彼を仲間と考えていることは誰も同じだった。
なぜなら、1本欠けた状態では彼らは用を足しえないからだ。もう少し正確に言うと、23本ではオーナーに捨てられる可能性だってある。それだけは避けねばならない。
「机から落ちたとしか考えられないな……」
突然、そう言ったのは『あかむらさき』だった。暗い声だった。
誰かが彼を見て、すぐに目をそらせる。
水を打ったように、場が静まり返った。
机から落ちる─。それは彼らにとって何よりも恐ろしい事故だった。色エンピツは普通のエンピツと違ってか弱く、チョークや消しゴムと違って飛べない。机の高さから落下し、床に身体を叩きつけられればタダでは済まない。
そして何を隠そう『あかむらさき』こそ、そういった落下事故の犠牲者であったのだ。
彼は24本のうち二番目に背が短いが、それは労働の対価ではなかった。彼はオーナーの不注意により机から落とされ、芯を折られてしまった。オーナーはエンピツ削りでごりごりと彼を削った。その結果が今の短さなのだ。
『はいいろ』も下に落ちてしまったのなら同じ運命を辿るだろう……。そこにいる誰もがそう思った。
「ねえ、ちょっと下を覗いてみようよ」
静寂を破り、努めて明るい声で『みどり』が言った。彼女も『はいいろ』の姿が机の上にないことは気付いていた。しかし落ちて折れてしまうなんて、あんまりだと思った。
「そうだな。よし、みんなで手分けして下を覗いてみよう」
彼女の言葉に『あか』が同意する。『あか』はこの中で一番背が短く、オーナーによる高い使用頻度を誇っている。だから彼はリーダーなのだ。
『あか』に促され、彼らはすぐに机の四方へと散らばった。端から少しだけ頭を出して下を覗き込む。そうやって『はいいろ』の姿を探した。
「あっ、」
誰かが声を上げたので色エンピツたちは一斉にそこに集まった。
床にあったのは一つの枕だった。
なぜかそこに枕が落ちていた。花柄のプリント地のカバーがついた、小さなまくらだった。オーナーの幼児に嫌われてここに置かれたのか、それは分からなかったが、とにかくそこに枕があったのだ。
皆は顔を見合わせた。
間違いない。『はいいろ』がいつの間にか居なくなったのは、この枕の上に落ちたからだ。物音がしなかったのはそのせいで、彼はどこかへと転がっていってしまったのだろう。
「どうすりゃいいんだ……」
「──助けに行くしかないな」
誰かが言った言葉に『あか』が答えた。それがいやに重たく響いた。
結局、『はいいろ』救出チームは4本になった。『あか』と、のんびり屋の『こげちゃ』。論客の『くろ』。それにアイドル的存在である『ももいろ』だった。みな、自ら志願した。
しかし枕の上に降りるのは、それなりに難しいことだった。
横に転がったままうまく落ち、枕で跳ね返り、なるべく衝撃を受けないように床に転がらなくてはならない。
色エンピツはデリケートな文房具だ。落ちて二つに割れて、ワークシェアリングができるクレヨンとは訳が違う。4本は恐怖と戦いながら、一本ずつ順番に、机のへりから飛び出した。
先に降りた『あか』が後続の者を手助けしたので、チームの4本は無事に床に降り立つことができた。彼らは胸をなでおろし、手分けして転がり『はいいろ』の姿を探し始めた。
やがて『ももいろ』が声を上げて皆を呼んだ。4本は即座に彼女の元へ集まった。
困惑した様子で彼女が指し示したのは、タンスの隅に転がっている2本の色エンビツの姿。
そのうち一本は、間違いなく彼らの仲間の『はいいろ』だった。
脇には、もう一本の色エンピツの姿。2本は仲良く寄り添うようにスヤスヤと眠っていた。
彼らは同じ『はいいろ』だった。
「──おい!」
声に怒気を込めて、『あか』が『はいいろ』を小突いた。「起きろ! 何してるんだ、こんなところで!」
ぶるんと身体を震わせて『はいいろ』は目を覚ました。キョトンとした顔で回りを見る。
「なんだ、お前たちどうしたの? こんなトコで」
不思議そうに仲間を一人ずつ見てから、隣のもう一本の『はいいろ』を揺り動かし、目を覚まさせようとする。
「『はいいろ』。ここで何をしているのか、話してもらおうか」
『あか』がそう言うと、『はいいろ』は小馬鹿にするように肩をすくめた。
「見ての通りだよ。『あか』。俺はもう君たちのところには戻らない」
「なんだって?」
声を荒げて『あか』が詰め寄ろうとしたとき、もう一本の『はいいろ』が目を覚ました。
「え……何? どうしたの?」
彼女は、いつの間にか5本の見知らぬ色エンピツに囲まれているのに気づいて、不安そうに身を縮める。
「心配しなくていいよ、こいつらは俺の元の仲間だ」
「待てよ『はいいろ』。どういうことだよ?」
『あか』が、今度は詰問するように言った。『はいいろ』は同じ色のパートナーをいたわるように撫でてから、仲間の方を振り返った。
「お前らは、一日中ケースに収まったままオーナーに使われない苦しみを味わったことがあるか?」
それは突然の鋭い言葉だった。
彼はゆっくりと『あか』に視線を向ける。
「お前はいいさ、太陽や笑顔を描くのにいつも使ってもらえる。だが、たまにしか使ってもらえない俺が描くものがなんだか分かるか? 俺はな、コンクリートのビルや、アスファルトの道路しか描かせてもらえないんだ。空を描いたって、どんよりした曇り空だけだ! お前らなんかに俺の気持ちが分かるはずがない」
彼が、そう強い口調で言うと、誰もが何も言い返せなかった。
「明るい太陽や、色とりどりの花。笑い合う人々や、緑あふれる森──。そんなものを描くことにずっと俺は憧れていた。でも、俺には一生かかっても不可能なんだ。この絶望感がお前らに分かるはずがない。俺は孤独だった。……けど、やっと運命のパートナーにめぐり合ったんだ」
彼は傍らにいるもう一本の『はいいろ』を見た。
「彼女は俺の気持ちを全て分かってくれる。彼女こそ、俺のことを分かってくれるたったひとりの色エンピツだ」
二本の色エンピツは見つめ合う。
「俺は昼寝前にオーナーに机から落とされた。そのときはもう終わりだと思った。けど、俺は枕の上に落ちた。俺は折れなかった。神が俺に味方してくれたんだ。そして彼女にも出会わせてくれた。色エンピツとして生まれて、こんなに満ち足りた気分を味わったことは一度もない」
息せき切ったような発言に、皆黙って下を向いた。
「……確かに、君の気持ちを本当には分かってやれないかもしれないが」
そっと『くろ』が口を挟んだ。
「私たちは隣だし、それなりに仲良くやっていたと思っているんだが、違うかな? そもそも、色エンピツはそれぞれ色が違ってこそ、色エンピツだろう? その彼女は君の良い友人にはなるだろう。しかしずっと一緒にやっていけないはずだ。なぜなら、君たちは全く同じ色なんだから」
キッと『はいいろ』は『くろ』を睨んだ。
「そうかよ。この際だから、ハッキリ言ってやる。あんたはいつもそうやって先輩面して知ったような口をきくが、俺のことを理解しようとなんてこれっぽっちも思っちゃいないんだ。オーナーがミッキーマウスを描きたいって言ったときの俺の気持ちが分かるか? あんたの出番はあっても俺の出番はない。俺の別名がネズミ色なのにだぞ!」
「な、なあ『はいいろ』」
半ば慌てて『こげちゃ』が言った。
「おれもさ、オーナーに使われるときはロクなモン描かされないよ。ほらウンチとかさ、子供って好きだろ? そういうの。でもさ、たとえどんなものであってもそれはおれにしか描けないものだから……。なんていったらいいか、ええと、その……」
「考え直すわけにいかないのか?」
やがて『あか』が静かに問い掛けるように言った。『はいいろ』はかつてのリーダーの姿を見、こくりとうなづいた。
「分かってるさ、アンタの考え」
視線を外さずに、『はいいろ』は続けた。「俺が抜ければアンタらは23本。オーナーは親にねだって新しい色エンピツセットを買うかもしれない。自分たちがそうして捨てられてしまうことを……恐れてるんだ」
「そうだよ、その通りだ」
『あか』は潔くうなづいた。
「考え直してくれ。仲間を犠牲にしたくはないだろう?」
「そりゃあお前らには済まないと思うところもあるが、無理だよ。もう決めたんだから。俺は彼女と二人で旅に出る。もう二度とセットには戻らない」
『はいいろ』の言葉はにべもなかった。続けて『あか』に向かって言い放つ。
「それにお前はたぶん平気だよ。添削用に残されたりさ、赤エンピツはセットがなくなっても生き残っていくっていう話をよく聞くから」
「──そういう問題じゃないんだよ!」
突然『あか』は怒鳴った。彼は怒っていた。文字通り真っ赤になって。
「お前は『あかむらさき』のことを考えてやったことがあるのか!? 怪我をしているアイツが頑張って毎日働いているってのに、お前はそんな利己的な理由で、アイツを見捨てるのか!」
『あか』の剣幕に、『はいいろ』思わずたじろんだ。
「アイツのことは気の毒だと思うけど……。でも仕方ないよ」
「仕方ない、だと!?」
「待って!」
『ももいろ』が二本の間に割り込んだ。彼女は『はいいろ』の方を向いて、問い掛けるように続けた。
「ねえ、聞いて『はいいろ』。あのね『あかむらさき』は……本当は“中折れ”なの」
「えっ……!?」
『はいいろ』はもちろんのこと、他の色エンピツも驚いて彼女を見た。どうやらその事実を聞いたのは皆初めてだったようだ。
“中折れ”とは、色エンピツの中の芯が複雑に折れてしまった状態のことを差す。そのことがオーナーに知れれば、確実に捨てられてしまう。まさに色エンピツにとっては死につながる怪我であった。
「彼、わたしにだけ教えてくれたの」
『ももいろ』は控えめに言ったが、その言葉には熱いものがこもっていた。
「彼はやがて捨てられてしまうかもしれない。だからわたしは彼を守りたいの。お願い。力を貸して。わたしたちにはあなたが必要よ」
「そんなこと言われたって……」
衝撃の事実を聞いて、『はいいろ』の心が揺らいだようだった。彼はうつむき、困ったように床の模様を見つめた。それから隣にたたずむ同色のパートナーをちらりと見る。
「『ももいろ』。そういう君なら分かるはずだ。……実は、この彼女も“中折れ”なんだ」
「ええっ?」
「俺は机から落ちたとき無事だったが、彼女は深刻な怪我を負ってしまった。俺も彼女を守ってやりたい。彼女と一緒に居てやりたい。だから……」
「そうだ! ゾウだ!」
突然『こげちゃ』が言った。
皆が驚いて彼を見る。『こげちゃ』はパッと明るい表情になって、『はいいろ』の目の前に立った。
「君にしか描けないものがあるじゃないか。ゾウにサイにカバ! みんな灰色じゃないか」
嬉しそうに続ける『こげちゃ』。
「おれは馬鹿だからうまく説明できないけれど……。灰色ってそんなに悪い色じゃないと思うんだ。君はきっと自分の魅力にちゃんと気づいていないんだよ。だってゾウだってサイだってカバだって、みんな灰色だろ? 子供の人気の動物じゃないか。それにさ、アザラシは何色だい? アザラシのタマちゃんって何色だよ? 君には分かるだろ?」
「灰色、だよ……」
放心したように『はいいろ』が答えた。
「君はコンクリートやアスファルトを書くのがイヤなのかもしれない。けど、オーナーたちは楽しんで君を使うはずだよ。君はほかでもない、灰色なんだ。他の誰でも出せない色を書ける、君は『灰色』なんだ」
「一緒にやろう『はいいろ』」
立ち尽くす『はいいろ』に、『くろ』が静かに、優しく問い掛けた。「私がタマちゃんのヒゲや目を描こう。あとはずっと君の出番だ。なあ、出会った頃のように、一緒に楽しく働こう。一緒にタマちゃんを描こうじゃないか」
「『くろ』……」
『はいいろ』は隣人たちを代わる代わる見た。「俺──」
と、彼が何か言いかけた時、脇にいた同色のパートナーが、するりと離れた。
「わたし、帰るね」
彼女が見せたのは精一杯の微笑みだった。もちろん『はいいろ』は血相を変えた。
「どうして!? 君は“中折れ”なんだよ。捨てられてしまうかもしれないのに!」
「いいのよ。わたし目が覚めたわ。わたしは色エンピツ。子供に夢を与えるのが仕事なんだもの。あなたはあなたの居場所に帰って。わたしもわたしの場所に帰るね。残された時間を使って、タマちゃんやゾウを描けるように頑張るから、あなたも頑張って」
『はいいろ』は彼女を見つめ、何かを言いかけたが──やめた。
がくりと頭を垂れて、言った。
「ごめんよ」
「どうして謝るの? さあ、早く行って」
『はいいろ』は、もう一度ごめんと言うと、仲間の方を振り返った。仲間たちは揃って彼のことを見つめていた。
「あの、俺、ひどいこと言って──」
『はいいろ』は何を言ったらいいのか分からず視線をめぐらせた。
「あのさ」
『あか』がパッと笑顔を浮かべて、『はいいろ』に近寄った。
「とにかく、さ。お前が無事でよかったよ」
「ありがとう。本当にありがとう」
震える『はいいろ』の身体を皆が抱擁した。
それが、欠けていた色エンピツセットが24本セットに戻った瞬間であった。