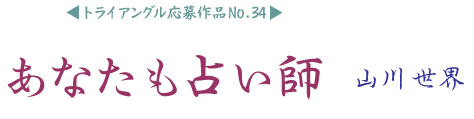
私の問いかけに対し男は物憂げに振り返った。そして無表情に「あぁ」とだけ発し、受け取った財布をポケットにねじ込むと、ガニマタで去っていった。
なんたることか。ひとことの礼もなく、人を浮浪者でも見るようにねめまわしていきやがった。まるで、寝床からゴミ出しの指図をする、妻に劣らぬ倣岸なやつだ。怒りに震える私のこめかみには、赤血球の大群が押し寄せ、その時頭蓋の奥で「カチッ」という小さな音がした。
「ちょっと、あんた」
おもわぬ方向から呼びかけられて振り向くと、小柄な老人が見台(けんだい)に座っていた。
いかにも吊るしの背広は丈が短く、袖口からはくたびれたワイシャツが覗き、胸元のループタイが揺れている。定年間際の国語教師風であり、見台がなければ占い師には見えない。
「拾ってやったのにえらい災難やったな。あんたやったら大丈夫そうや、これ、ちょっとだけ見といてんか」
そういうと傍らに置いてあった黒鞄を突き出した。
老人はふんばった両手を軸に、あんば競技の要領で見台からにじり出ると、股間をつまみながら、地下街への階段をそろりそろりと下りてゆく。鞄を抱えた私はそのようすを呆然と見送っていた。
しまった。断わるタイミングを逃してしまった。太極拳のようにつかみどころのない関西弁に翻弄され、言語中枢が一時的にフリーズしていたに違いない。どうしていつもこうなのか、お人好しにもほどがある。
そんな自分の性格にやり場のない憤りを感じ、すこしブルーになって遠くを見た。通り向こうに建ち並ぶビルの上空には、紅色の夕日に照らされた異形の雲がたなびいている。春風が街路樹を揺らすたび、ビルに映る影が形を変えてゆく。あちこちのドアからは、終業した会社員が間欠泉のように吐き出されてくる。
自己嫌悪に陥りそうになったが、この機会に見台を観察してやろうと開き直り座ってみた。意外にも、道ゆく人はこちらを気にするようすがない。通行人にとって手相見の存在など、電飾看板や自販機のように映るのかもしれない。
行灯(あんどん)は四角い樹脂の台座に、行書体で『手相』と書かれた障子風のカバーを被せるつくりで、底部には電池挿入口とON・OFFスイッチがある。見台にはちょっとした物入れがあり、使い捨てカイロやミネラルウォーター、黒ぶちの大きなルーペ、それに本が何冊か入っていた。表紙には『この本一冊であなたも占い師』とある。
さてはニセ占い師だったのか、そう思い、残りの本を引っ張り出すと、すべて同じタイトルだった。なるほど、自費出版の占い本をなじみの客に売っているらしい。
他にも面白いものがないかと物色していると、会社員風の男ふたりが歩いてきた。平日の夕方にも関わらず、どこかで一杯引っかけてきたような赤ら顔で、慣性の法則のままに不規則に接近してくる。大柄な男がこちらを指差して何かをいい、もうひとりの肩を叩いた。それを聞いた隣の男は手を振って断わっている。何かいやな予感がした。私は酔っ払いが苦手だ。あのエンドレステープのような繰言に、何度夜明かしさせられたかわからない。
「だからお前が先に観てもらえって、ヒックッ。あのね、俺が思うにねぇ、お前が手を出した瞬間にねぇ、あなたの手相は最悪です! なぁんていわれると思うよ。ヒヒヒ」
どうやら先輩らしき男は、占いに乗り気でない後輩をけしかけ、占い師が凶相を指摘すれば、それを肴に一杯飲んでやろうという魂胆らしい。
冗談じゃない。私は老人から鞄を預かっているだけだ。それも一方的に押しつけられたのであって、引き受けたわけではない。手相なんか観るものか、絶対断わってやる。
私は手相を観ていた。
どうして世の中にはこうも強引な人が多いのだろうか。
ただの店番で、手相など観ることはできないと答えたら、ほらみろ、お前の手相があんまりひどいから、占い師が逃げ腰じゃないか、さては観てもらうのが怖いのだな、この臆病者め! などと挑発するものだから、後輩らしき男がムキになり、店番でもなんでもいいから、とっとと観やがれっ! ってことになって、いま私は手相を観ている。
まったく情けないやら、腹が立つやらで、『玉子ぬきの月見そば』を注文された店員のように、私の心は混沌としているのだった。
私は物入れからルーペを取り出した。
豚足のように短い指だ。ピアニストだったりしたら三日は笑うな。
やわらかそうな掌のわりには、指のつけ根にうっすらと運転ダコができている。たしか私が営業の仕事をしていた時は、こんな掌だったような気がする。爪の裏には僅かに黄色い粉が付着している。よし、決めた。
「あなたは車の営業マンです。昼食はカレーでしたね」
「おぉぉ」ふたりの男がシンクロで感嘆の声をあげた。
やったぞ。私もやればできるのだ。
……バカだ、当ててどうする。
ほらみろ、身を乗り出してきて、がぜん興味を持ち始めたではないか。デタラメだ、デタラメをいわなければならない。そう思えば思うほど、常識的なことばかりが浮かんできた。返答に窮した私は、苦し紛れで男の顔を見た。誰かに似ている。そうだ三村だ。小学生のころ、廃品回収車をパロって牛乳回収車と名乗り、牛乳嫌いの子供の牛乳をかたっぱしから飲んで回り、ついには腹をくだし廊下で漏らしたバカがいた。これだ。いいデタラメが思いついた。ははは、あんな経験そうそうあるもんじゃない。
「あなたは小学生のころ、牛乳を飲みすぎて廊下で漏らしましたね」
会心のデタラメだから自信満々の口調になった。
なぜか男は短くウッとうなった。顔色も真っ青だ。
しまった。顔が似ているだけなのに体験までそっくりだったなんて。もうダメだ。じじいは何をしているんだ。小便ぐらい早くしろ。いつまで待たせるつもりだ。
気がつくと周りは人だかりになっていた。
どうしても金を払うという先輩格の男に、店番であることを改めて説明し、プロではないから金は受け取らないと断わった。すると男はあろうことか、うしろで見ていた二人組みのOLにむかって、
「この人が受け取らないからお金が浮いちゃったぁ。おねぇちゃんたち、これで観てもらいなさぁい」と、数枚の千円札を渡した。
観衆から嬌声とどよめきが起こった。
ああ、このオヤジはなんと余計なことをしてくれるのだ。
再び私は手相を観ている。
「結婚運を観てください」
真っ赤なルージュをこれでもかと塗った、タラコ唇の女が真剣な顔をしていった。
メリハリのない胴の上に、オカッパ頭の扁平な大顔が鎮座するさまは、まるで木彫りのこけしだ。メイクは子供の塗り絵のように奔放である。アイラインは太すぎてまるで歌舞伎役者の隈取のようだ。領土を逸脱したルージュは、ファンデーションを蹂躙するだけでは飽き足らず、前歯の一角に橋頭堡を築いている。
私は女が差し出した掌をルーペで見た。結婚線なんてどこにあるのか知らないぞ。消失したのか? 大体、手相占いに根拠なんてあるのかな。どう見てもこれは掌を曲げやすいためのしわだろう。しかし、こんなものに意味を持たせて商売にしたやつは天才だな。街頭商売だから冬は辛いだろうけど、適当なことをしゃべれば金になる、元手いらずの丸儲けだ。それにしても、じじいは遅いな。年寄りの小便は時間がかかるのは解るけれど、もう三十分以上経っている。いくらなんでもこんなにかかるかな。まさかボケていて、今ごろ家で風呂に入っているなんてことはないよな。いかん、いかん。ルーペを覗いていると変なことばかり考えてしまう。早くこの女をかたづけて見台から離れないと、延々とこんなことをやるわけにはいかないのだ。こんどこそ真のデタラメをいって、愛想尽かしをさせてやる。
私は気合を入れ、女の唇から連想した歌手の人生を当てはめてしゃべった。
「あなたは若いころに苦労したでしょう。特に十五、十六、十七歳とあなたの人生は暗かったはずです。十八歳で結婚するも離婚。その後再婚し、同じ男性と離婚再婚を繰り返します」
完璧だ。賭けてもいい。もしそんな女が偶然ここにきていたら、丸裸で逆立ちして町内一周してやる。
「わぁぁ」
タラコが見台に突っ伏して泣き崩れると、もうひとりの小柄で目の離れたふぐのような女が、タラコの背中に向かって問いかけた。
「どうしたの、当たっているの?」
タラコは伏せたままうなずいた。
裸で逆立ちである。
いつの間にか日が暮れて肌寒くなってきた。人だかりはさらに大きくなり、後ろの方では若者が飛びはねて中を見ようとしている。人が集まっていると覗きたくなるらしい。
「ちょっと、ごめんなさいよ」
ごり押し通しの呪文が聞こえると、物理的には不可能と思われる人だかりの隙間から、肉の塊のような怪婦人がひり出てきた。スイカを丸呑みした蛇のように、パンパンに膨れた事務服の袖からは、腸詰に似た形状のものが突き出ている。さすがに大仕事であったのか、数枚の紙幣を鷲づかみにしたまま、肩で息をしている。
肉塊は息を整えると、見台で泣き伏しているタラコを一瞥した。その残忍な眼差は、ソフトバイクを見下ろす大型トラックの運転手を連想させた。
何かやりそうだと思っていると、案の定、塊は反動をつけた自分の尻を、座っているタラコの尻の側面に叩きつけた。タラコはカーリングのストーンのように、そのままの姿勢ではじき飛ばされた。折り悪く、宝くじ売り場の店員が竹箒で掃いていたものだから、歩道の摩擦係数が激減していて、あっという間に肉眼では確認できないところまで滑っていった。
「あんた、当るそうじゃない。観てもらうわよ」
そういうと、塊はしわくちゃの千円札を伸ばして見台に並べた。
発した言葉を文法的に解釈すると、どうも私の意思は尊重されないようである。
「な、何を占いましょうか」
おそるおそる尋ねる私を見据えて、塊は噛みつくように吼えた。
「いったい亭主はどこにいるのよ!」
あんたが喰ったんじゃないの、と心の中で毒づいてから、冷静になって考えた。
どうも今日はデタラメをいおうとすると当ってしまう。もともとそんなに当るはずがないのだから、懼れることなく推理すればいいのだ。私はたしかに優柔不断な性格だが、過ちは謙虚に反省するという長所も持っているのである。
深呼吸をして気持ちを鎮め、逃げた亭主の気持ちになって考えた。
――案外婿養子の可能性もあるな。その場合、うちには塊の親とか出戻りの小姑なんかもいるだろう。きっと気兼ねしながらの食事で、とても腹いっぱいは食べられないぞ。うちに家族がいない時には、思い出したような空腹に襲われそうだ。そんな時にかぎって好物の鰹のタタキが冷蔵庫に入っている。見なかったことにして一旦ドアを閉めるが、あきらめきれない。二、三切れなら気づかれないだろうと、それを肴にビールを飲む。ふと見ると皿のタタキが半分に減っている。動揺して一気に酔いが醒める。だが冷静に考えると、家族が帰るまでにスーパーで買い戻しておけばよいのだから、これは全部食べられるわけだ。安心して二本目のビールの栓を抜き、うで枕でテレビなんか見ていると不覚にも寝てしまう。目が覚めて時計を見るとずいぶん時間が経っている。もたもたしているとスーパーが閉ってしまう。あたふたと出かけ、店の前まできたところで財布忘れに気づく。あわててうちに帰り、財布を持って店に戻るとすでに閉店している。すかさず他の店に飛び込むが、あいにく鰹のタタキは売り切れだ。もう日はとっぷり暮れて、あちこちでシャッターを下ろす音がする。慌てて駆け回るが手に入れることができない。血迷って豆腐屋に飛び込んでしまい鼻先で笑われる。茫然自失のまま商店街を歩き、いつの間にか公園のベンチに座っている。こうなるともう帰れない。どこにいくだろう。実家や知人のうちはすぐ塊に発見される。見つかれば半殺しは免れない。そうだ、警備員がリストラになって、会社の警備室が空いている。小さな会社だから、社長に頼めば何とかなるかもしれない。ついでに、問い合わせがあっても、口裏を合わせて退職したことにしてもらおう。
妄想、否、推理を終えて私は顔を上げた。ずいぶん長くひとり言を呟いていたようで、みんな妙な顔をしてこちらを見ている。
「判りました。ご主人は鰹のタタキを盗み食いしたことをいい出せず、行方をくらませたのです。退職したというのは表向きで、実は警備室でかくまわれています」
それを聞いた塊の顔がみるみる紅潮してきた。
いかん、いいかげんな占いに気を悪くしたようだ。
塊は激しく見台を叩いた。
「ハゲ社長がグルだったのか、クソッ、下手な芝居打ちやがって。どこにもいないと思ったら、警備室に逃げ込んでいたんだな。あのバカ殺してやる!」
塊がすくっと立ち上がり、振り向いて観衆を睨むと、『十戒』の名シーンのように人間の海が開いた。塊はその道を威風堂々と立ち去っていった。私を含めみんな呆気に取られている。まさか占いが殺人幇助にはならないよな。
いくらお人好しの私といえども、ここまで異常な展開になると、これはおかしいと感じた。もっと早く気づくべきだった。大体、用を足しにいっただけのじじいが、何時間も帰ってこないなんてありえない。
私はそれとなく観察した。辺りにそれらしいワゴン車はないか、黒いショルダーバッグを持って不自然に佇んでいる人間はいないか、植え込みの中に隠しカメラはないか。しかし不審なところは見当たらなかった。まあ、どこか遠くのビルから撮影しているに違いない。そういえば最近、この手の番組を見かけなくなったが、何度もリメイクされている定番企画だ。もしプラカードを持った若手タレントが登場したら、大げさに驚いたほうがいいのかな。
さて、次は誰が来るのやら。好き放題デタラメをいえばいいのだから気楽なもんだ。ヤラセだから何をいっても的中するに決まっている。
「ウラナッテクダサイ」
突然妙な日本語が聞こえた。
スーツを着た男の隣に、口髭を生やし、黒いベレー帽に軍服を着た貫禄のある男が立っている。
一瞬ふき出しそうになった。いま大騒ぎになっている中東の独裁者ではないか。正確にいえばその人のそっくりさんだ。通訳つきとは念入りだな。それにしてもよく似ている。たしかその大統領がお忍びで日本に来ているという噂はあるが、まさかこんなドッキリに本人が出演するわけがないから、影武者のひとりかもしれない。この出演料で電気製品でも土産に買って帰るのだろう。
影武者は私の前に手を差し出した。やはりアラブ人の手は黒い。腹も黒いのだろうか。しかし、これだけ似ていると本人の意思に関わらず影武者にされるな。ひょっとして整形だろうか。影武者って儲かるのかな。それにしてもいいかげんな構成だな。手相占いなんて知るはずのないアラブ人が、とまどいもなく掌を出すかね。そうか、構成作家は視聴者なんかバカにしているんだな。そうに決まっている。こういう企画モノは、収録されてもオンエアされるとは限らないって誰かがいってたな。おもしろいVTRだけが流されるわけだ。やっぱり撮られたからには出たいな。
私は顔を上げ占い師になりきって告げた。
「アメリカ人に広島、長崎での蛮行を思い知らすため、核爆弾を落としてやりなさい」
私の答えに通訳は大げさにのけぞって驚いた。
おいおい、ちょっとオーバーアクションだろう。たぶんスタッフの知り合いの素人外人だろうけど、私がプロデューサーだったら次は使わないよ。ふふふ、私の芝居は番組的にはOKじゃないかな。もし武装解除しなさいなんていってたら、たぶん没なんだよな。だから、ちゃんと無茶をいってやったんだ。なんて協力的な素人なんだろう。
通訳が影武者に説明している。
それにしても訳文がずいぶん長いな。そんなに長文をしゃべった覚えはないぞ。意外な答えだったのか、影武者が私のほうを不安げに見たから、励ますように深くうなずいてやった。
それを見た影武者は、意を決したような表情になり、通訳から受け取った携帯でなにやら声高に指示し始めた。アラビア語だからチンプンカンプンだ。こいつはなかなか演技がうまいな。やっぱり普段から本物のつもりで、暮らしているから自然に芝居が身についたんだろう。
気がつくと観衆がいなくなっていた。いつの間にか救急車がきていて、その周りに野次馬が集っている。やがて担架を抱えた救急隊員が、地下街への階段を走り下りてゆく。一体何があったのだろう。
それからさまざまな客が訪れた。テレビで観た大企業の社長には暴落する前に自社株を売り抜けろといってやったし、悩める元三冠王には嫁さんと離婚しろといってやった。みんな私の答えを託宣のように神妙に聞いて帰った。
それにしてもテレビの撮影というものは長時間にわたるものだ。夕方に始めて、すでに二十三時だから延々六時間は撮っている。交差点のところでは、ホワイトハウスがどうしたとか叫びながら、血相変えて号外を配っているが、そんなことには興味がない。いま私が知りたいのは、この番組がいつ放送されるのかということである。