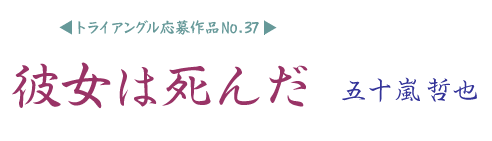
上気した滑らかな肌に汗が粒となって浮かんでいる。全体にしっとりとした湿り気を帯びたその肌は、繊細な光沢をもって滑らかな曲面を形成していた。特に、肩から腰まで伸びるラインが美しい。鎖骨の隆起や腰のくびれなどは、身体の内側から染み出る熱気か水分かによって、普段より余計に丸みを帯びて見えるようだった。薄暗い部屋に灯った淡いオレンジ色の照明で、彼女の肌は鈍い黄金色の輝きを帯びている。僕はそんな彼女の身体を、片足を睡眠に突っ込んだような意識で、ぼんやりと眺めていた。ちょっとした幸福を感じる瞬間だ。それは小さいながらもとても暖かい、ミニチュアの太陽のような幸福感だった。
それまで僕の胸を、手を広げたりすぼめたりして撫でていた彼女が、同じ姿勢をとり続けるのが辛くなったのか、うつ伏せの状態のまま身を捩じらせた。ヘッドボードに頭をもたれかけて仰向けに寝ていた僕の頬に、僅かな風が当たる。彼女の肘に押しつぶされた枕から吐き出された風だ。
「ねえ、ひとつ聞いていい?」
彼女は枕の上に身を乗り出すような体勢で、僕に尋ねた。
「それ自体が既に質問だよ」
「あなたは自分の仕事を世界を造る事だって言ったけど、具体的にどういう事なの?」
彼女は僕の言葉を無視して質問した。
「そうだなぁ」と、僕は少しの間考えをめぐらす。「――映画のさ、『マトリックス』は観た? 仰け反って銃弾をかわすヤツ」
「うん、あるよ」と彼女は大きく頷く。腋の向こうに、押し潰された乳房が見えている。僕はふと、理由も無しに、どうしようもなく悲しい気持ちになった。
「基本的にあれと同じなんだ。コンピュータ上に、仮想世界を構築する。素粒子単位でデータを入力して、現実の宇宙と同じ物理法則を設定するんだ。ただ、『マトリックス』は現実世界にいる人間の意識を仮想世界に接続するっていう感じだったけど、実際はそんな事できないというのが現実との唯一の違いかな」
「じゃあ、鈴木光司の『ループ』みたいな感じ?」
「そうそう、あれが一番近い。『ループ』、読んだんだ?」
彼女は再び大きく頷く。それに合わせて前髪も大きく揺れる。綺麗な髪だ。
「『ループ』の仮想世界も、実際は現実のものと結構な違いがあるんだけどね。たとえば、あの小説では、主人公が最後に仮想世界内に入るよね。あそこではまるで本人が直接その仮想世界に入り込んだように書いてあるけど、実際それは主人公と同じ人格や記憶を持った別の人間が仮想世界内に構築されると言った方が正しいんだ。あのニュートリノ放射による体細胞の分解さえなければ、現実世界と仮想世界の両方に主人公が同時に存在できたわけだからね。それに、あの小説では仮想世界の発展のしかたがむちゃくちゃだ」
彼女は微笑みながら首を捻り、「良くわからないわ」と言った。無理もない。話している僕だって、実は完全に理解しているわけではないのだ。
「そうだろうね」と僕は言った。
「それ、どういう意味?」と彼女は怒った顔になる。
「違うよ、バカにしてるわけじゃない。僕だって全然わかってないんだ。あのね、僕の仕事はあくまでその一部なんだ。プログラミングの手伝いと、出力、要するにグラフィックの担当を兼ねてる」
「余計にわけがわからないわ」
「じゃあ実際にバカなんだよ」と言って僕はフッと笑った。彼女は「言ったなぁ」と言って枕で僕の顔を叩こうとした。上げた手のせいで露わになった胸に視線を持っていかれた為、一瞬防御が遅れたが、無事防ぎ切る事ができた。枕を押さえ込むと、彼女はくやしそうに頬を膨らませた。その時、僕は再び激しい悲しみに襲われた。そして突然頭を駆け巡るイメージ。風景。車の映像、タイヤが路面に擦り付けられる音、同時に喚起される焦げ臭い匂い。流れる血の筋。
突如湧いた奇妙な感覚を努めて無視して、彼女がしきりに引き抜こうとしている枕を押さえつけながら、僕は言った。
「それから、そう、言い忘れてたけど、実際に現実に近い仮想世界を作り上げる事が出来るのは、ずっと後になってからなんだ。それこそ、百年や二百年は後にね」
「生きてる間には完成しないって事?」彼女は眉を吊り上げ、信じられない、といった表情を作る。
「うん、まだ全然技術が追いついてないんだ。だから今は研究段階というか、先駆けたいくつかの実験が行われてるだけ。しかも、その実験の成果如何では、この先プロジェクトの凍結もありえるらしいしね。ま、世界を造るなんていうのは大見栄を切っただけってこと」
僕がそう言うと、彼女は「なあんだ」という具合に溜め息をついた。
「でも、不思議だよね」
「何が?」
彼女は顔を僕の胸に近づけて訊いた。
「世界が再現できるって事さ」僕は答えた。「素粒子単位で再現した世界は、それがたとえ虚構であっても、現実世界と同じなんだ。だから、そこに住む人間にとっては、その世界は、僕らにとってのこの世界と同じということになる。僕ら『外側』の人間にとっては、彼らの全ての行動が初めから決定されていることが判ってるのに、彼らは僕ら同様に自由意志を持っているつもりなんだ」
「なんで初めから決定されてるって判るの?」彼女は尋ねた。
「始点が、つまり初めの状態が定まっていれば、何度やり直しても同じ結果になるからさ。もちろん、理論上、ではあるけどね。それで、つまり僕たちの世界もそれと同じなんだ。僕たちが自由に思考しているつもりでも、実はそれは宇宙が始まった瞬間から決定していた事になる」
「嘘でしょう?」と彼女は声を張り上げた。
「嘘じゃないよ。まあ、説明し辛いんだけどね……。『ホーキング、宇宙を語る』は読んだ?」
「読んでないわよ」そう言って彼女は笑った。「あなたじゃないんだから」
「あの本には、こんな一節があるんだ。『……もし完全な統一理論が本当に存在するとすれば、それは我々の行為をも多分決定しているだろう。これはつまり、この理論をわれわれが探求することによって得られるだろう結果も、この理論自身によって決定されているということだ!』ってね」
「よく覚えてるわね」彼女は僕の左腕の下にもぐりこみながら言った。
「大好きな一節だからね」僕は鼻を鳴らして言った。「物理的必然性がないのは、宇宙の始まりだけ。あとは計画通り、まったく必然的にコトが進んでる」そして僕は、必然性に支配されているこの宇宙が、美しいと思う。「その事実の前では、あらゆる意味が消失する。もともと、僕は意味っていう概念自体好きじゃないけどね。すべてが本来意味の無いものなのに、勝手に意味を定義して、しかも自分たちがそれに振り回されてる」そう言いながら僕は寝返りをうって、僕の胸板を枕にしていた彼女を両腕で抱え込んだ。彼女が囁いた。
「ねえ、キスして」
僕は苦労して首を捻りながら、胸のあたりにある彼女の顔に自分の顔を近づけた。すぐに、彼女が唇を押し付けてくる。しばらくそのままでいて、それから首の位置を戻すと、僕は彼女の頭を自分の胸に押し付けた。彼女の息が、鳩尾のあたりに感じられる。
僕たちはそのまま眠りについた。
窓から差し込む日光の眩しさに目を覚ますと、既に時計は九時二十三分を指していた。随分長く寝ていた事になる。長い夢を見たのも、恐らくそのせいだろう。僕は両腕を大きく広げてのびをした。両手の甲に冷たいシーツの感触がある。わかっていた事だが、彼女はいない。
あの時、彼女を永遠に失った事を、僕は悲しんだ。たとえそれが宇宙が始まった時から決定されていた事であったとしても、あの日運転ミスをした自動車によって流された血に対して、僕は悲しまずにはいられなかった。それは、決して美しくなんかなかった。
かつて「大好きな一節」などと言ったが、今では僕はその宇宙における全てを支配する必然性を憎んですらいる。
――そう、必然的に。