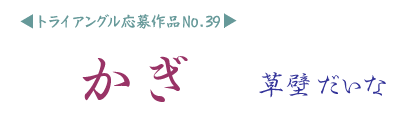
「クリスマスの日は、帰れそうもないんだ」
これがここ数年、年末恒例の家族への口ぐせとなっていた。
洋菓子材料の卸会社勤めのため、この時期各メーカーの受発注に奔走していて、クリスマスどころか年末年始に至るまで、起きている我が子となかなか出会えずにいた。
『あと一軒か』
今日は生クリームの変敗苦情が入り、代替品を持参しつつ謝罪にまわっているところだった。
街頭の電飾は昼夜の区別も付かない程鮮やかで、ショッピングモールの入り口では、即席のサンタクロースが歳末大売出しのチラシ配りをしている。
『今日中に済ませてしまおう』
僕は足早に横断歩道を渡り、サンタのチラシを素通りして、通りでタクシーを拾おうとした。
その時、同じ様に後ろから急ぎ足で駈けて来た男性が、僕の肩とぶつかりがてら、昨日の雪がとけ溜まった所に勢いよく足を突っ込みんだ。
そしてそのはずみで泥の塊が、僕の左の革靴にずしりとかぶさった。
「失礼」
足の事情は知ってか知らずか、男性はその言葉を残してさっさと人ごみに消えていった。
取り残された僕は自分の足元を見た。片方にだけ、だんだんと冷たい感触がしみてくる。
ついてない。
仕方がないと思えばどうとでも出来たのに、僕は今この出来事ですべてのやる気が消失してしまった。
タクシーが違う人を乗せて走り去っていく。
『疲れてんだなあ』
そう思うと残り一軒分の生クリームが、カバンの中で急に重く感じられるようになった。
「ホントに失礼ですよね」
すると突然そんな声が、僕のすぐ脇から聞こえてきた。
見れば、さっきから居たのだろうか。
黒いベレー帽に黒いコートをはおった、いかにもみすぼらし気な老人が、ビール箱を反した椅子の上で時折鼻をすすりながら、腰をおろしてうずくまっている。帽子からのぞく白髪まじりの髪以外はすべて黒づくめだったので、まるで置き去りにされたゴミ袋みたいで、目にも留まらなかったのかもしれない。
老人の周囲には、少し手前に傾いた台に、かなづちや釘、汚れきった布、数種類の靴クリームなどが、無造作に置かれてあった。
『くつみがき?』
「磨いて差し上げましょうか?」
僕の心を読むかのように老人はそう言うと、自分の前に置いてある、同じように空箱を反しただけの腰掛けに僕を促した。
その時の僕はもう、靴の汚れなどどうでもよかった。
ただ、どこかに座りたかった。
座る場所が欲しくて僕は促されるまま老人の前に席をとり、汚れたての靴を脱いだ。
「これほど立派な牛革は、なるたけ水に触れない方がいいです。
そもそも革靴の手入れはですね・・・・・・」
老人は僕の靴の中に水気を吸う詰め物をしながら、革靴手入れの仕方について説明をし始めた。
近くで見ると老人は一層にみすぼらしかった。
ベレー帽のゴムは若干ゆるんでいるようで、帽子の形が頭に沿っていなかったし、コートのボタンは全部かけられてはいるのだけれど、色の違うものが幾つか混じっていた。
そして靴の向きを変えるごとに鼻をすすり、たまにむせ返るような咳もまじるようになっていた。
それに引き換え街には、どの店からか心地よいキャロルが流れてきていて、歩く人々もそれに合わせて浮き足立ち、靴の汚れを気にしそうな人など、僕を含めてここには居ないようだった。
そんな風邪ぎみなのならこんな場所で客を待つより、家に帰って風呂にでもはいったらどうなんだ、と思いながら僕は、老人の革靴論をなんとなく耳に残しつつ、泥を拭き取る皺枯れた手元を黙って眺めていた。
「ここらへんも、景色が変わりましたよね」
ひととおり講釈の済んだ老人は、手元から目をそらすことなくそう続けた。
老人はそうは言うが、僕がこの土地に住むようになったのは転勤で来た2年前からで、それでも僕の記憶では、このステーションビルもロータリーも、立体駐車場もショッピングモールも、その頃から既に出来ていて、変わったことと言えば、駅前の並木にムクドリが異様に群がるようになったことぐらいだった。
「ここに店を出して、ながいのかい?」
「今の仕事は短いのですが、その前のもありますからね。
以前は鍵作りをしていたんですよ」
「鍵?ここでかい?」
「ええ。ここでです」
最近では靴磨きという姿もあまり見かけなくなったが、道端で鍵作りという話はこれまでにも聞いたことがなかったので、僕は少々驚いた。
「固定客はなかなか居ませんでしたが、時に評判はよろしかったのですよ。
自転車の鍵をなくした学生さんや、マンションのキーを失った主婦とかがよく利用してくれていました」
そういえば僕も駅の駐輪所までたどりついてからよく、自転車の鍵が無いことに気が付いたものだ。ここで店を開くことは意外と親切かもしれない。
「合鍵を作るだけではなく、ロックを開けることもしました。コインロッカーや左ハンドルの車なんかも。
そういえばこんな日でしたかね。あの子が来たのは」
「あの子?」
「五、六才の男の子なんですがね、小さな木箱を持ってきて、開けて欲しいと言うんです」
僕はドキリとした。上の息子と同じくらいだ。先月買ってやった自転車に早く乗れるようになりたいと言っていたのに、なかなか練習につきあってやれない。今夜ももう小さな妹と一緒にベッドに入ってしまっただろうか。
老人は靴クリームを丁寧に塗りながら、ふと底をかえして言った。
「大分傷んでますね。打ち直しますか?」
「うんそうだな、お願いしよう」
僕は木箱の少年の話に少し興味を感じて、気にもしていない靴底の修理を頼んでしまった。
「その子がどうかしたのかい?」
「その子?・・・・・・ああ、木箱のあの子ですか。
開けて欲しいと言ったんです。おととしのクリスマスにママからもらったプレゼントが入っているって」
老人は空を見上げた。
雪。
真っ黒だったはずの空から、次々と真っ白い粒が落ちてきて、老人の暗い肩や頭に、積もっては消えてを繰り返していた。
*
「こんな夜でしたよ、あの子がきたのは。たしかイブの前日の、二十三日の夜。
こんな風に雪が、積もりそうで積もらず降っていて・・・・・・。
あんな遅い時間にあんな若いお客さんは初めてだったので、少し驚きました。
色白に紺のダッフルコートがよく映る少年で、丸顔が毛糸の帽子でくるまれて、一層丸く見えていました。
『一人で来たの?』
と聞くと、少年は悪びれもせず、
『そうだよ』
と、答えました。
少年が持ってきた木箱はよく見るとオルゴールで、手の込んだ彫刻が施された、宝物を収めるのにはうってつけの高級感のある箱でした。
『今日はママは居ないのかい?』
『いつも居ないよ』
私の問いに少年は、ふてくされたようにそう答えました。
『ママは忙しくて、いつも家にいないんだ。なんだか一緒に暮らしていないみたい。
でも、朝起きると枕元には毎日違う服が揃えてあるし、夕方帰るとおやつと夕食が、覆いがかぶさって食卓に並んでる。
ママは居るはずなのに、でもやっぱり居ないんだ』
少年はつまらなそうにうつむくと、手袋のはまった両手を意味も無く組んだりはずしたりしました。
『でもクリスマスには、素敵なプレゼントをくれるんだろう?例えば、こんな・・・・・・』
私は小さなかぎ穴をカチャカチャいわせながら、中身のわからない小箱に目をやりました。
すると少年は急に顔をパッと明るくさせました。
『そうだよ。去年なんかはウルトラマンコスモスの人形がとどいたんだ。実物大のだよ。リモコンで動くし、こっちが話しかけると、「シュワッチ」なんてしゃべり返してくるんだ。今もベッドの横に飾ってあるよ』
けれどまた、少年は暗い声になりました。
『だけどその日、ママは帰らなかった。パパも遅くて、クリスマスケーキはおばあちゃんと二人で食べたんだ』
そう言うと少年は黙りました。
少年の沈黙とはうらはらに、何組ものカップルが、彼の後ろを楽しげに通り過ぎていきました。そして私たちの間には、かぎ穴をいじる無機質な音だけが残っていました。
木箱は思いのほか、開けるのに手間がかかりました。
単純そうに見える鍵ほど、壊れてしまうと元に戻すのに苦労するものです。
少年は黙って見ていました。何分もじっと、前髪に雪が積もって、それが雫になってとけ落ちても、少年は黙ってそこに居ました。
そうしてどれほどの時間が過ぎたころか、『カチリ』という音がして、急に軽い感触が手のひらに伝わってきました。
『開いたよ』
私は目の前の少年に、木箱を渡しました。
少年は黙ってそれを受け取りました。そしてそれを、嬉そうに、懐かしそうに見つめました。
彼はそっと木箱の蓋を開きました。あらかじめゼンマイの巻かれたそれから、いつかどこかで聴いたような、幼い、かわいらしいメロディが流れてきました。
そうしてその中から、なにかしらやわらかい光をもった、あたたかいものがふわりと現れ、それが、小雪が降りてくる聖夜の空に、ゆっくり舞い上がっていきました。
少年の手には、カラの木箱がありました。
『それは何かい?』
『キスだよ』
『キス』
少年は、穏やかに微笑んでいました。
『おととしのクリスマスにママがくれたんだよ』
彼は、雪の結晶が付いた小さな手袋で、静かに木箱の蓋を閉じました。
『そんな大切なものを、逃がしてしまっていいのかい?』
『いいんだよ』
少年は笑って言いました。
『いいんだよ。今年もまたもらえるから』
*
そう言って少年は、木箱を大事そうに抱きかかえて、駅に向かう人ごみにまぎれていきました。」
老人は懐かしむように、駅へ向かう雑踏の背中をながめていた。つられて僕も同じ方に目をやった。ムードのよい二人づれが多い中、クリスマスカラーのマフラーや手袋を身に着けた、一組の家族が目にとまった。彼らのそれらの色あいと笑顔があたたかく、雪の寒さを一瞬忘れさせる風景だった。
「出来ましたよ」
老人の声にわれに帰って見ると、前には、靴底が丁寧に打ち直されて靴クリームで仕上げられた、片方の革靴があった。
「その後少年とは会ったかい?」
「それっきりです。もう宝物に鍵をしめておく必要など、無くなったのならいいですね・・・・・・」
老人はそう言ってうっすらと微笑みをうかべた。
僕は新しくなった靴を左足につけ、それまで通りのもう片方と共に立ち上がってみた。なんだか履き心地が良くなったような、それまでと変わらないような、ただ、気分だけは新鮮だった。
僕は靴磨きの老人に代金を払うと、礼を言ってその場を離れた。そうして内ポケットにある自宅への定期券を、心で確認した。
振り返って見ると老人は、やっぱり黒いベレー帽に黒いコートをはおって、鼻をすすりながら、ゴミのようにうずくまっている。
彼のおかげで僕は、なくしかけていた大切なものに気付くことが出来たようだ。
いい話を聞かせてもらった。
革靴の手入れ方法は、すっかり忘れてしまったけれど。