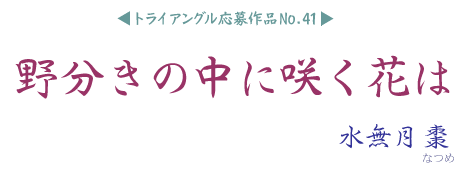
小さい頃から秋子(しゅうこ)は宝石や、花など綺麗なものに目をとめる癖があった。だからこそ、その店を見つけることが出来たのだろう。その日は金曜日で、四年生は三時前に家に帰ることが出来た。秋子がゆっくりと人の通らぬ道をうつむいて歩いていた時、いきなり視界に見覚えの無い店が入ったのだ。
…お店、なのかなぁ…。
カフェの様な小さな西洋館。なんとなく、その摩訶不思議な雰囲気に魅かれ、秋子はふらりとその館に近づいていった。
「わぁ…」
文句のつけようのない磨き方をされたウィンドゥには色とりどりの鉱物や首飾りがみごとな配色で並べられていた。
…トルコ石、ルビー、アメジスト…あぁ、あれは琥珀かしら…。
感心しきって眺めまわしていた秋子は、ドアの開く“ガチャッ”という音におどろいて飛び上がった。
「…じゃあ、また来週ね。」
にこやかな女性の声が聞こえて、ウィンドゥの横の出入り口からその声の主と一人の男性が出てきた。女性はそのまま秋子に気づくことなく行ってしまう。男性はどうやら店主らしい。女性が去った後、吐息をついてふとウィンドゥを見やった。秋子と目が合い、秋子はギクッとした。三十代後半というところだろうか。とても端麗な男性である。秋子に微笑みかけ、落ち着いた声で挨拶をした。
「こんにちは。」
「どうも、こんにちは。」秋子はぺこりとおじぎした。
「…何か、お嬢さんのお気に召す物がありましたかな?」
「あ、あの、綺麗だなぁって。」
彼はうれしげな顔をした。
「ありがとう。…良ければ店内も見てください。うちの宝石は、どっちかというと観賞用だから。」
秋子は少し遠慮しながらも店内に足を踏み入れた。
「すごい!きれい…」
店の壁ぎわにはサイドテーブルが幾つか並べられ、天鵞絨(ビロード)の布の上にはウィンドゥの物とはまた違った装身具が飾られている。どれひとつとして同じ様なデザインのものは無く、見ていると吸い込まれそうな気持ちになる。店の一番奥にはカウンターがあり、その向こう側に彼が座って秋子を見ていた。カウンターの傍らの窓から夕日が差し込んでいる。
カウンターの前に置かれた椅子を主人は手で指し示し、「どうぞ。」と秋子をかけさせた。
「お嬢さんはこの近くにすんでいるの?」
「うん、そう。この道をまっすぐ行って、右に折れたところ。」少し間を置いて秋子は彼に尋ねた。
「この前まで、あたし気がつかなかったわ、このお店。失礼なんだけど、前から、あった?」
彼は笑った。「ああ。きっと魔法でもかかっていたんだ。」
「そのせいであたしが見落としてたってこと?」
彼は頷いた。
「…変なの。」と言ってしまった後で秋子はちょっと舌を出した。
「生意気な口きいちゃったわね。…ごめんなさい。母さんにもよく叱られるわ。」
「悪いことじゃない。」と彼が言った。
「それは自分の意見をしっかり言えるということだから。…私は戒城(かいじょう)貴月(たかつき)と言うんだ。」
「あたし、秋子よ。大江秋子。秋の子って書くの。」
「ほう。私の好きな名だ。」
秋子は彼を見つめた。彼が言う。
「私は秋分の日の夕方に生まれて、私の母は私に“貴秋”とつけたかったらしい。ほんとはね。…母の名も、“秋子”と言うんだ。」
「ふうん。」
「話題がかわるけど…学校楽しい?」
「全然!いじっめ子はいるし、勉強は面白くないし、先生はきらいだし…。最悪。」
ははは…と貴月が声を上げて笑う。と、その時振り子時計が三回なった。
「あ、もう三時だ。母さんが怒るわ…。」
「じゃあ帰った方が良い。…楽しかったよ。」
秋子は「ありがとう」と言って店を出た。
「…魔法がかかったのは、さてどちらかな。」貴月がふと囁いた。
「え…。」
秋子が振り向くと、貴月はにこっとして店内に戻ってしまった。ドアにも夕日が当たっている。道端に、今は蕾ばかりの秋桜が揺れていた。
秋子の母は再婚したばかりだった。離婚して、一年もせぬうちに新しい夫を迎え入れた。秋子にとっての新しい父は物静かで優しく、良い人ではあるのだが、今まで十年間、同じ家で生活をともにしてきた父親といきなり離され、“この人が新しい父親”などと言われてもすぐになじめるものではない。秋子は無意識のうち、家にいることを避けるようになった。
翌週の、前と同じ日に秋子は貴月のもとを訪れた。中に誰かいるのだろうか。話し声がしている。
「…秋子さん?」
「あ…。」中から貴月が出てきた。
「やあ、来てくれたんだ。」
「お客さん?あたし、邪魔しちゃった?」
「いいんだよ。…彼女は私の話し相手兼、お得意様。…奈々恵さん、秋子さんだ。」
「あら。」
女性がカウンターの前に腰掛けている。その人は店の隅からサッと椅子を引いてきて秋子に座るように促した。
…この前の女の人だ…
彼女はにこにこして秋子を見ている。
「はじめまして。私、田原奈々恵っていいます。お話聞いてましたわ。」奈々恵は時計を見た。
「残念!仕事に行かなくっちゃ。…ということで、失礼いたしますわ。」
「もう?」と、貴月が妙な顔をする。
「ええ。何か?」
「いや…。」
「変なの!」と、呟いて奈々恵はバッグを持ち、出て行った。秋子はひそっと貴月に囁いた。
「…貴月さんなら怒んないと思うから言うね。あたし、今日、学校さぼっちゃった。」
秋子の想像通り、貴月は感心したような、困った様な微笑み方をした。
「それはすごい。しかし、ご両親に知れたらどうするのかな?」
「大丈夫だと思うわ。うちの母さん、今大変なのよ。新しい父さんのご機嫌とりで。」
秋子の声は、無理に毒づいたせいでひどくうらがえっていた。貴月は黙っている。カウンターの上で手を組み、そこに顎をのせて秋子を見ている。
「そう。」と、静かにあいづちをうち、急に話題を変えた。
「寒くなってきたね。…私の生まれた所では、今ごろ紅葉が綺麗だと思うよ。」
「帰りたいの?」秋子が気まぐれに問いかける。
「とても。…小さい頃、弟達と庭で遊びまわった記憶があってね。」
「弟さんがいるの?」
「ええ。私の下に三人。私は長男なのに出来が悪くて、父の頭痛の種だった。」
「あたしはひとりっこだから。」秋子はすねた様な声を出した。
「淋しいや。…みじめになってくる。」
「そう。」と、貴月。
「でも、貴月さんとか、父さん母さんは良いな。あたしみたいな子供と違って、自分で何でも出来るし、いつでも誰か、側にいてくれるじゃない。」
貴月がため息をつく。
「さて、本当にそうだか。」外で木々がざわざわと音をたてている。
「…貴方は、ここに住んでいるの?別の場所から来ているの?」秋子が尋ねる。
「ここに住んでいるよ。この店の裏手に家があるから。」
「そうなの。…あ。あたし、時々ここに来ちゃだめかな。邪魔だったらいいけど。…学校が終ってから。」
貴月は微笑んだ。
「午後からは私も退屈だし。…いつでもおいで。」
奈々恵は25歳。近くのカフェで働いているという。秋子は彼女と世間話をするのが好きだった。貴月が言った。
「この店には、21個、宝石がある。…ひとつひとつ、違う種類のね。」
「へえ…たくさん。もう他に、欲しい宝石はないの?」秋子は尋ねた。貴月は首を振った。
「…いや、柘榴石と、紅水晶を手に入れようと思って。」
「ガーネットと、ローズクォーツ?じゃ、これから探すの?」
「実はもう見つけてある。…それより先に、私は花嫁を見つけないと。奈々恵さんがなってくれると嬉しいんだが。」
秋子はふと気づいた。明日は9月23日。貴月の誕生日だ。
空は曇っている。今日は日曜日だから、学校はない。そのかわり、父がいる。午後から貴月の所へ行こうか行くまいか、秋子はずっと迷っていたのだ。
…宝石店って日曜もやってるのかしら。そうね、今日は公園かどこかで遊んでよう。貴月さんも、毎日子供の話し相手はいやでしょう…
秋子は上着を着て、玄関の方へ行こうとした。が、いきなり背後から母が呼びかけてきた。
「秋子、どこ行くの?」
「公園。と、友達んとこ。」
母の顔が心なしか険しくなった。
「やめなさい。すぐ、雨が降りだすわ。それに…、貴方このごろろくに家にいないじゃない!」
秋子は母を見つめた。
「いやだ。あたしは家にいたくないの。」
「だめ。今日はお父さんと…。」
「いや!」
「秋子ッ」
ピシャッと音をさせ、母は秋子の頬を打った。打った方も、打たれた方もしばらく呆然としていたが、秋子の方が先に我にかえり、ぱっと外へ飛び出した。すでに雨が降りだしている。土砂降りに近い。秋子の足は宝石店に向かっていた。顔に、髪がくっついて、とれない。いつのまにか、風も吹き始めていた。木々が、何か得体の知れぬ生き物の様に揺れ動いている。秋子は立ち止まった。内部に暗闇を秘めた西洋館が視界に入った。
…貴月さん、いるんだろうか…
秋子は店の横にまわり、唐草をかたどった格子越しに窓のむこうの店内を見つめた。貴月と、奈々恵がいる。貴月はぞっとするほど冷たい表情をしている。奈々恵は逃げようとしていた。急に貴月が、奈々恵に掌をかざす。その手から不思議な光が放たれたかと思うと、それは奈々恵を包みこみ、彼女の身体は煙の様に蒸発し、カチャン!という音がこだました。それは指輪の落ちる音で、奈々恵の消えた場所にはみごとな柘榴石の指輪があった。貴月は無表情のままそれを拾い上げ、サイドテーブルの上に置いた。彼は微かな足音を聞き、顔を上げた。窓の向こうに秋子が走って行こうとしている。
「…待ちなさい。」
貴月は店からかけ出し、秋子の腕をつかんだ。秋子は貴月を見た。貴月はおだやかな眼差しで言った。
「…入りなさい。風邪をひくよ。」
「…」
秋子ははっとした。いったいいつの間に眠ってしまったのだろう。雨は小降りになり、銀鼠色の雲が窓から見えた。もう夕刻らしい。
「…やあ、起きた?」
秋子が寝ていた部屋は店の奥にあった。そこから出、秋子はいつもの椅子に腰掛けた。貴月が少し悲しげな顔で秋子に言った。
「今日は、私の生まれた日だ。」
彼はカウンターの上に飾られた秋桜を見つめている。道に咲いていた物だ。
「…怖かったでしょ。秋子さん。」
秋子はうなずいた。彼ははっきりした口調で語った。
「私は魔界の皇帝である父にテストを受けたんだ。誕生日にちなんで、23人、人間を宝石に変えろと。一年後の四時までにそれができなきゃ妖魔として認められない。」
「あたしが、その23人目?」
貴月はうなずいた。秋子に手をかざす。秋子は動かない。硬い枕に顔を押し付けた様な息苦しさを感じた。背後の時計は四時一分前を指している。秋子は溜息をついた。
「いいや。最後の一個になるよ。」
貴月の手から青い光が放たれた。秋子は目をつむった。…しかし、何も起こらない。秋子は目を開けた。…カウンターの秋桜が、そのまま紅水晶に変化している。貴月がにやっとしてみせる。その瞬間、時計がカチリと音をさせ、四時を指した。店の奥からすさまじい風が吹き上がり、秋子は後ろに押し倒された。…何もかも吹き飛ばされた様だった。
「試練は失敗。規定通り、お前は現世より消失せねばならぬ。」
天界と下界のはざまで皇(おう)が言い渡した。秀麗だが、ひどく虚ろな目をしている。
「…西へゆけ。太陽の沈む方へ。陽の沈むと同時に、そなたは灰になる。一番苦しまずにすむ処罰のしかただ。」
貴月は微笑をうかべて深く頭を下げ、そのまま去った。
「哀れな子よ。元々人界の娘であった母の血を濃くうけついだばかりに。」
皇は誰に言うともなく呟いた。
「やあ、ここにいたのか。」
気がつくと秋子は学校の門の前に立っていて、むこうから雨傘を持って歩いて来る父の姿が見えた。
「お母さんが待ってるよ。お菓子用意して。」
あたり一面夕日にてらされて真っ赤だった。秋子も、父も、二人の歩く道も。道端に、やはり真っ赤になって秋桜がうつむいていた。