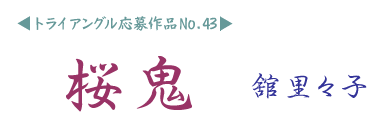
妙なことになった。吉岡は酒をちびちび舐めながら考えた。さて、俺はこのままどうすべきなのだろう。移動すべきか居座るべきか。それとも、女を追い出すべきか。
(いやいや、いくらなんでもそれは……)
ちらりと隣を盗み見れば、女はほてった顔で桜を見上げ、気持ち良さげに鼻歌を唄っている。手にはしっかりと缶ビール。
(四十と少し。いや、五十過ぎかもしれないな。ずいぶん若作りしているようだが、年頃の娘がいると言っていたし……)
興奮し、とまどいながら、吉岡はさりげなく女を観察する。結い上げられた髪は、濡れた鴉のようにしっとりと黒。汗ばんだ額に張りついたほつれ毛も美しく、白く滑らかな肌は匂い立つよう。細い肩、しなやかな腰、その身を包むのは、鮮やかな緋色の地に枝垂れ桜が染め抜かれ、袂に花びらの落ちる着物。
(……美人だよなあ)
吉岡はひっそりと感歎の息を漏らした。
今どき見慣れない着物姿の艶やかさ。声をかけられたとき、吉岡は夢でも見たような心持ちがしたものだったが、今では気配を探るのに気もそぞろ。桜散る闇夜の、街灯と灯篭のぼんやりとした明かりの下、女の姿態は妖気さえ漂わせている。
――と、もぞもぞと腰を動かして、女が呟いた。
「今夜はなんだか、蒸し暑いですわねえ」
膝を崩してくつろいだ姿勢になって、着物の裾から女の足が膝から下、ぬっと姿を現した。白く艶かしいふくらはぎ。吉岡は思わずそれに見入った。
我に返ったのは、青いビニールシートの上に転がる、酒のビンのぶつかり合う音で。慌てて顔を上げれば、すぐ目の前に女の顔、興味深げに見つめる二つの瞳。
女はにっこりと微笑って言った。
「あらあら、少し飲みすぎのようですわねえ」
吉岡はさっと顔を赤らめて身を引くが、女はさもおかしそうに、白い顔にそこだけ紅い唇をほころばせて笑い出す。二人のあいだを桜の花びらが、ひらりひらり。
(……これじゃあ、なにかあっても不思議はないよな)
吉岡は、手に持った酒を一気にあおいだ。とろりと酔いが駆け巡り、花の匂いか女の香か、甘い香りが鼻孔をくすぐり、吉岡の理性の消失を企てる。
そもそも、声をかけたのは女が先だった。
「ねえお兄さん。この辺りで財布を落としたのだけど、ご存知ないかしらねえ」
近隣の住人に、散歩道として親しまれている公園である。とっぷりと日は沈み、桜並木に吊り下げられた灯篭に、明かりが灯りはじめた頃だった。遠くからはまだ、宴会客の調子外れの唄が聞こえていた。
「……財布、というと?」
緋色の着物が光を放つのか、女の白い肌が闇に浮き立って見えた。吉岡は公園の外れで一人、ビニールシートに座っての花見客。
「利休鼠の地にウサギの絵柄が入っていて。それから、手の平サイズのがま口で。娘が京都に遊びに行ったときのお土産にと、もらったものなんですけどね……」
と、女はシートに膝をつき、無防備に吉岡に顔を寄せた。
女が捜しているのは財布そのもの、お金がなくて困っているのではない様子だった。聞けば女は居酒屋の女将をしていて、今日は馴染み客に誘われての花見。帰りしな、財布がなくなっているのに気付いて、一人戻ってきたと言う。
吉岡は待ち人来たらず、時間を持て余していたこともあって、一緒に捜してやることにした。そしてしばらくの後、やっと気付いたことには、女の白足袋にうっすらとにじむ紅の色。
「あらまあ、下草にやられたのかもしれませんわねえ」
指摘すれば、ちっとも気がつかなかったとでも言うように、女は困ったように笑って言った。しかし、地面を鳴らして足を庇うような歩き方、放ってはおけない。
「痛みませんか。どうです、少し休んでいかれては?」
吉岡は自分の用意した場所を指差して言った。
もし女が拒むようなら、吉岡とて無理強いはしなかっただろう。そもそも、一人で夜桜を愛でている四十過ぎの男など、警戒されて当たり前だ。
だが、一度は遠慮してみせたものの、女は拍子抜けするくらい、あっさり吉岡の隣に腰を下ろした。さすがは女将、酒の相手は手馴れたもので、以来こうして二人並んで手には酒、頭上に桜と風雅人の真似事をしている。
そこで吉岡はあれこれと考える。
夜桜の見物客のために、灯篭がそこかしこに吊り下げられてはいるものの、すでに大方の宴会客は引き上げてしまい、今ではただの人気のない夜の公園。このロケーションで見知らぬ男と二人きり、席を同伴するというのだから、女もその気があるに違いない。
(据え膳食わぬは男の恥、とも言うし……)
浮気の虫がぞろぞろぞろぞろ這い出てくるのを止められず、ちらりちらりと脳裏に浮かんでくる人影をうち消そうと、吉岡は胸の内でいろいろ言い訳をこしらえる。
(そもそも、今夜こんな所に、俺を一人で来させたアイツが悪い)
吉岡には妻がいる。今年で四八歳になる三つ上の姉さん女房で、名は菊子。
職場恋愛の末のスピード結婚。はじめの頃こそ、出会った頃の情熱をそのままに、誰もが認めるオシドリ夫婦だった。だが吉岡の生来からの浮気癖がもたげてくると、その冷却ぶりは凄まじく早かった。
「最近、帰りが遅いようですけど、いったいどこで何をしているんです?」
「お前こそ、着付け教室だか何か知らんが、ずいぶん遊びまわっているらしいな」
嫌味の応酬あり、気紛れな優しさあり、腹のうちを探り合う、一歩も譲らぬ攻防戦。だがそのうちに疲労が見えたか、あるときを境に罵りあう言葉がぱたりと止んだ。休戦協定の締結である。強いていうなら折れたのは菊子だった。
旦那の浮気癖は、男の本能みたいなもので、飲ませる薬はないと観念したのか、最後に帰ってくるのは自分の元とタカをくくったのか。あるいは菊子が種を持たない体であると判明したのが、その大きな一因であったのには間違いない。
夜の営みに不満が募り、ついには菊子がそれを拒むようになったのも、やはり元を質せばそこに行き着くのだろう。
「不満なら、よそでやればいいじゃありませんか」
この菊子の言葉を皮切りに、吉岡の浮気は半ば公然と行われるようになったのだった。
――半年前、愛犬のコロンが食中毒で死んでしまうまでは。
「十二年も生きたんだ。もう充分だろう」
慰めのつもりだった。
マルチーズを飼いはじめたのは、子供のいない淋しさを埋め合わせるため、菊子が勝手にしたことだった。吉岡は初めから犬に愛着などなかったから、散歩はおろか抱き上げた試しもなかった。それでこの言葉だから、吉岡としては精一杯の思いやり。
だが菊子はこれに激怒した。
「充分? 充分ですって!? コロンは毒入りのご飯を食べさせられたんですよ。警察にも見てもらったんですからね。間違いないわ、誰かが毒の入った食べ物を公園にばら撒いたのよ。コロンは殺されたのよ。それを、充分ですって!?」
今までにない妻の迫力に、吉岡はたじろいだ。
(……拾い食いさせた飼い主の責任は、どうなるんだよ)
頭を過ぎったのは、至極まっとうな意見だけれども、口にすれば火に油を注ぐことになるのは明らか。吉岡は懸命に菊子を慰めようとした。
「それが運命だったんだ。仕方がないだろう。お前がいくら泣いたところで、生き返るわけでもなし。金なら出すから、ちゃんと供養してやれ」
「……その程度ですか?」
「――何?」
逆効果だった。
「運命だなんて、簡単に片付けないでよ。……あなたっていつもそう。子供が作れないと分かった時も、仕方がないって簡単に諦めてしまって。いったい私をなんだと思っているんですか。家事をこなすだけの女ですか」
積年の不満が爆発したようだった。菊子の青白い顔のなかで、愛犬の死がそうさせたのか、落ち窪んだ目だけが生気に満ちてギラギラと輝いていた。
「今もそうよ。どうせまた若い女と浮気しているんでしょう。私がそれを知って、何も感じていないとでも思っているの?」
休戦協定が成立して以来、たまに嫌味を聞かされることはあっても、真正面から激しく罵られることの絶えた生活。すっかり気圧されて、吉岡は二の句が継げなかった。
「もういいわ。私も我慢の限界です。別れてください」
「……え?」
菊子は引き出しから茶色の封筒を持ってきて、吉岡に差し出した。中には一枚の素っ気ない紙切れ――吉岡の署名を入れれば完成する離婚届と、他には数枚の、吉岡が若い女性とホテルに入るところの、隠し撮り写真。
「証拠がありますからね。慰謝料は払っていただきます」
有無を言わせぬ口調だった。浮気は全て見逃してくれるものだと思い込んでいたから、これは吉岡にとって晴天の霹靂だった。
「ま、待ってくれ。そんな」
「それが嫌なら、他の女とは全部、縁を切ってください」
吉岡を正面から見据えて、菊子は冷え冷えとする声で言い放った。
「それにしても、みんな遅いですわねえ。なにをしていらっしゃるのかしら?」
着物の女が言う。え、と吉岡は我に返ってあたりを見回す。
「みんなって、誰かと待ち合わせでも?」
遠くから聞こえていた喧騒も今では絶え、闇の中、花びらが静かにしんしんとふり積もる。あたりは一面の花絨毯。それが光を反射するのか、あたりは妙にうす明るい。
女はきょとんとして、吉岡の赤ら顔を見つめ、それからころころと優雅に笑い出した。
「あら、嫌だ。違いますよ。吉岡さんのことですよ。誰かと待ち合わせしてらっしゃるんでしょう? さっきからキョロキョロと、周りを気にしていらっしゃるから」
吉岡はそれを聞いて安堵する。
「ああ、なんだ、違いますよ。わたしはただ……」
言いかけて、しかし語尾をうやむやにする。まさか、あなたと二人で楽しむための言い訳を練っているから、落ち着きがないのですよ、などとは言えるはずがない。それに、と吉岡は思う。
(すっぽかされたなんて、格好が悪いこと、この上ない)
しかも、その相手が若い女で浮気の相手、関係を清算するために呼び出したのだ、とは口が裂けても言えることではない。
離婚の危機を迎えてからこっち、吉岡は菊子との仲を修復するのに、全力を注いだ。
今までに手を出したのは、遊び慣れた若い女ばかりだった。金の切れ目が縁の切れ目、後腐れなく別れられる相手を選んでいたつもりだった。
愛情の有無はともかくとして、吉岡は菊子との生活に満足していたし、それを破壊するつもりはなかったのだ。結婚と恋愛は別――これは何も、女の特権的思考ではない。
(まだ菊子は、俺とやり直す意志がある……)
――他の女とは全部、縁を切ってください。
この言葉が、どれだけ吉岡を安堵させたことだろう。吉岡はその場で投降した。浮気を認め、菊子に平身低頭謝った。お前の気持ちは良く分かった。もう女には手を出さない。だから離婚なんて言わないでくれ――。
「本気ですか。信じていいんですか?」
「ああ、もちろん。当たり前じゃないか。俺が一番大事にしているのは誰か、お前だって分かっているだろう?」
あの時見せた、菊子の冷めた視線。信じていないのは明白で、だから吉岡は、同僚との付き合いもそこそこに、帰宅時間を早め、できるだけ誠意を見せようと努力した。
「やろうと思えば、早く帰って来られるんですね」
無数のとげのある台詞に反して、食卓に並んだおかずの品数が、修復の進み具合を如実に表わしていた。まだ同じ床に入るのを許してはくれないが、それも時間の問題だろうと吉岡は思っている。
(あとは、彼女と切れることさえできれば)
残された問題はあと一つ。菊子に突きつけられた写真の女性との関係を、清算することである。それだけは確実に、終わらせねばなるまい。
「ただ、何ですの?」
自分の考えに没頭していた吉岡は、意味をつかめず、え、と女に聞き返した。
「だから、ここで。さっき何か言いかけましたでしょう」
女はやんわりと笑って、吉岡の空になった酒カップに、自分のビールを継ぎ足す。ああ、と吉岡は呟いて、苦笑を浮かべた。さて、どうやって質問から逃れようか。
「ええと、ハナオニをね、待っていたんですよ」
「ハナオニ」
女は小首を傾げる。吉岡は花びらを払いのけ、現れた地面に『桜鬼』と指で書いた。
「坂口安吾の小説、知りませんか? 桜の樹の下には桜の精が住んでいるそうで、それも桜の満開の時期にだけ、姿を現すのだそうですよ」
「桜の精が」
「ええ。とても美しい女性の姿をしているとか。そう、ちょうど、貴女のような」
女は大きく目を見開いた。それから、まあ、と破顔する。
「お上手な方。それにロマンチストでいらっしゃるのねえ」
「いえいえ、お世辞なんかじゃないですよ。こんな綺麗な方が女将をしている店があったなんて、わたしも世間を知らないと、驚いているんですよ」
吉岡は真面目な顔をして女を見つめる。女は頬を染めて、ころころと笑い声を立てた。
「もう、こんな年増を捕まえておいて。上手いんだから」
相手の乗ってくる手応えの良さに、自分もまだまだ捨てたもんじゃないと、吉岡は内心で胸をはる。あともう一押しだ。
「それにしても、さすがに夜は冷えますねえ。酒もなくなってしまったし……」
どうしようか、と困惑するふりをして女の顔を窺った。この意味が分からないほど、女も鈍感ではなかった。一瞬目を見開いたが、すぐに意を解して、女は艶やかに笑った。
「それじゃあ、ウチのお店へ……あ、いいえ」
女は途中で言いよどむ。「いえ、ウチのは、他のお客の目がありますから、余所のお店にしましょうよ。ほら、誰にも邪魔されないところで、ねえ……?」
女は吉岡の二の腕にそっと身を寄せてきた。首筋に暖かい吐息がかかる。決定だった。
吉岡は、顔がにやついてくるのを必死に堪えつつも、寄り添う女の体を見下ろして、緋色の着物の下に隠された豊満な肢体を夢想する。そして女に誘われるままに腰を上げ、いそいそと花見道具を片付け始めた。
*** *** ***
「それにしても無事で良かったわ。計画とはいえ、香子があんな男に触れられるなんて、想像しただけでぞっとするもの」
窓辺から差し込む夕日が、ホテルの一室を照らす。見事な五月晴れだった。あれから一ヶ月、なんて時間の進みが遅かったこと! 菊子はベッドの上で枕を腕に抱き、ソファーでくつろぐ女――香子の、引き締まった足をうっとりと眺めた。
「まあ」香子は呆れた顔して、くすくすと笑った。
「心配してるの? それとも嫉妬?」
「いやだわ、もちろん両方に決まっているじゃない!」
「嬉しい」香子は立ち上ると、少女のように頬を赤く染める菊子の隣に腰を下ろした。交錯する視線。二人は唇を重ね、ふふふ、と波がさざめくように笑いあう。
こんな風に、もう何度密会を重ねただろう、と菊子は思う。香子と知り合ったのは、着付け教室がきっかけだった。先生と生徒。菊子が夫の浮気を相談しているうちに、なんとなくこうなったのだ。もっとも香子は、シグナルを感じた、と言うけれど。
淋しさが引き合わせた、とは思わない。それでは余りに陳腐すぎる。うなじの艶かしさや、綺麗な指先、触りたくなる肌。女同士だからこそ、共鳴するところがあったのだ。
「あの娘には、可哀想なことをしたわね」
ぽつりと菊子は呟く。香子に抱きすくめられ、どの香水よりも極上の、甘い匂いがその身を包んだ。「済んだことよ。忘れましょう」と耳元で囁く声。
菊子は夫に、条件を出していた。桜の花が散るまでに決着をつけられなければ、別れて下さい、と。あの女好きが別れられるはずがない、と踏んでいたのだ。家庭内別居にはうんざりしていた。香子との新しい生活に踏み出したかった。それを、あの女。
名前をなんと言ったか。入社して一年目の、二十三歳のあばずれ女。夫とは金が結んだ関係、こちらの思惑をどこで知ったか、金をせびって来たのだった。
愛人止めるのも続けるのも、どちらでも構わないのよ。でも吉岡さん、本当のことを知ったらどうするかしら? 慰謝料の額も減るわよね、きっと。
もっとも許し難いのは、香子をけなしたことだった。美しい香子。人形のように完璧で、人形以上に麗しい香子。彼女との関係を、気が知れない、とあの娘は言ったのだ。
「愛してるわ、香子」
菊子は囁き返す。だが、それももう終わったことだ。彼らは無理心中をしたのだから。私は一人残された、哀れな未亡人なのだから。私たちを疑う者など、どこにもいやしないのだから。