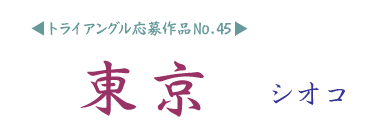
某年某月某日、六本木のはやりのクラブに、とあるセミナーから派生した六人のグループがあらわれた。彼らは今日まで面識もなく、同じセミナーに出席したという以外、何の共通点もなかった。セミナーで意気投合して街にくり出したアドレナリン過多の集団から、はじき出されるようにして流れてきた連中だった。
グループの先頭を切っているのは、この店まで案内してきたA輝(えーてる)という男。場慣れした様子でウェイターに話しかけ、DJに手をふり、奥のテーブル席についた。A輝は、髪型にも服装にも派手なところはなかったが、見る者が見ればそれとわかるテイストはきっちりと押さえていた。なにより彼には恵まれた容姿があった。よけいな装飾品は必要なかった。
それとは対照的に、A輝の隣に座ったB作は、やたらとブランドのロゴマークが目立つ格好をしていた。しかし、いまどきの若者らしく、それなりにうまいコーディネイトをしていた。
「いやあ、オレ、この店、前からチェックしてたんすよ、今をときめくミスターNKがプロデュ−スした店ですよね」
「え、そうだっけ?おれは近くだからよく来るだけだけど」
「えっ、六本木に住んでるんすか!いいなー。この辺、高いんでしょ」
A輝は女のところに居候している身で、家賃は知らなかった。
「うん、でも渋谷寄りのアパートだからそうでもない。ここまで原チャリですぐだし」
B作は一瞬、拍子抜けした顔をしたが、すぐに気をとりなおして、A輝がくわえた
タバコにさっとライターを差し出した。マンションと言っといたほうがよかったかな、
というA輝の後悔は、B作の次の言葉で吹き飛んだ。
「でも、やっぱ、いいっすよねー、オレなんか江戸川区っすよ、橋の向こうっすよ。
夜、遊びに行くとこっていったら、親戚がやってるスナックくらいっすよー」
A輝は急にくつろいだ気分になって、この店の売り物のひとつである座り心地のいい皮張りのソファにもたれかかり、腕を広げた。
「いやー、しかし、あれだよね。今日はおれ、バイトで代理出席なんだけどさー。
セミナーってみんなあんな感じなの?
なにが「ビジネスの心得」だあ?
あんな退屈な話を聞く会だって知ってたら、おれ、来なかったよ。
まあ、ただテープ回して、飲み食いしてりゃあいいから楽勝なんだけどさー」
A輝の発言に相槌を打つ者はいなかった。
その中でB作だけがフォローにまわった。
「いやあ、オレもあんまり気は進まなかったんすがねー、
親が会社やってて、跡をつがなきゃいけないんで、しぶしぶ出席したわけで」
天井に煙を吹き上げていたA輝は横目でチラッとB作を見た。
「最近はセミナーでも、ああいうパーティー形式が流行ってるんですってね。
わたし、こういうときしか着れない服もあるし、ためになる話は聞けるしで、
参加したわけ。いずれ自分の店を持ちたいと思ってるし」
B作の隣に座ったC美が言った。華のある顔だちで、スレンダーな身体つきをしてる。光沢のある短かめのドレスから、すらりと形のいい脚が伸びていた。ここにいる四人の男性のうち、少なくともA輝とB作の二人は、彼女がいるから今まで帰らずにいたのだ。
とはいえ、狙った女にはすぐに声をかけないのがA輝の主義だ。B作にきっかけを作るように合図した。ところがB作は以外にシャイだった。
「し、C美さんの家はどこなの?」
「えー、恥ずかしいなー。
ふたりともまだ23区だからいいじゃないですかー。
わたしは東村山なんですー」
なあんだ都下かあ、と心の内でつぶやいた二人(A輝、B作)だが、とりあえず可愛いから許すことにした。C美も自分の美しさはじゅうぶん心得てるようで、二人に--、とくにB作に向けてとびきりの笑顔を返した。C美は最初、A輝のセンスのよさに惹かれていたのだが、B作の家が会社を経営してると聞いて、がぜんB作に興味が湧いてきた。
先月、高校のときから小遣いをもらってきた鉄工所の社長に捨てられて、先ゆきの不安を覚えていたところだった。二十歳をすぎた女には興味がないというのが社長の言い分だった。お店の開店資金まであと一歩というところまで来ていたのに。
C美の向かいに座っているD子は、終始、沈黙したままだった。もっさりとしたワンピースに身を包み、今まで一度もパーマをかけたり、染めたりしたことのないような黒髪を、顔の半面に垂らしていた。ただでさえ暗い印象を与えるのに、カクテルグラスをみつめて物思いにふけるその姿は、よけいに付近をどんよりさせていた。
C美がたずねた。
「D子さんはどちらから?」
ちょうどはやりの曲がカットインされ、フロアから歓声があがったところだった。
「.......です」
「え?なんていったの?」
「埼玉です」
ダサイタマかぁ。
不遜な笑みを浮かべて、A輝、B作、C美の三人は同時にソファに沈みこんだ。
D子の隣のE次郎がはじめて声を発したのはその時だった。
「ばってんが、東京ちゅーとこはすごかとこですなー」
その野太い声は、厚い音の壁にとつぜん空いたブラックホールのように周囲を飲みこんた。E次郎の向かいに座る先の三人は凍りついた。
「すげー、E次郎さん、もしかして九州出身?
そんなレアな訛り、オレはじめて聞いたよ」
B作が小馬鹿にした調子で言い、A輝とC美は苦笑した。
E次郎の体型は短躯でやや肥満気味、服の趣味は話にならなかった。
「ばってんが、こぎゃんとこは熊本にはなかですもん。
クラブちゅーのは、もっと狭くてごみごみしとるて聞いとったばってん、
ここはゆったりしてよかねー。
また東京の人たちゃあ、はー踊りのうまかー」
近くのテーブルの客が笑いながらE次郎を指差していた。C美はE次郎の吐く奇怪な気炎を避けるように手をかざして言った。
「E次郎さん、せっかく来たんだから記念に踊ってくればいいじゃない」
「いや、ワシは踊れんけん」
「じゃあD子さんがついていってあげれば。ね、それならいいでしょ?」
E次郎とD子は、C美に送りだされて中央のフロアに進み出た。ぎこちなく身体を揺らすD子と、不格好に両手をふりまわすE次郎の姿が客にまぎれて見えなくなると、C美はほっと胸をなでおろした。
最後に残ったのがFだった。
Fは、つば付き帽子とサングラス、TシャツにGパンというラフな格好で、とくべつ田舎臭いところもなければ、都会的でもない、いたってノーマルな男に見えた。
しかし、その顔は笑っておらず、A輝、B作、C美の三人と、テーブルをはさんで向き合ったFとの間には、気まずい沈黙が流れた。
ここは位置的にFの目の前にいるA輝が問いかける番だった。
「ところでFさんちはどこなの?」
「わたしの家は束草(ソクチョ)です」
「束草?そんなとこあったけ?」
「東北のほうじゃない?」
A輝の表情がけわしくなった。
「いや、なんか発音が違う、こいつ------日本人じゃないかも」
「はい、わたしハ北朝鮮からキました」
それを聞いたA輝の顔色が変わった。
「チョ○公がこんなとこで何してんだよ」
「ちょっと、それは---」とA輝の袖を引っぱるC美。
その手をふりはらうようにして、A輝は立ち上がった。
「いいんだよ、だいたいおれは、中国人とか、韓国人とか、台湾人とか、貧乏臭くって
おまけに妙な言葉を喋るアジア人が大嫌いなんだよ」
「あなたハ、アジア人じゃナイですか?」
A輝はテーブルの上の見えない鍵盤を叩くようにして言った。
「おれが、言ってるのは、日本人以外のアジア人だよ」
B作とC美は目を丸くしてA輝を見上げた。
そこに金髪碧眼の外国人がテーブルに近づいてきて、四人に話しかけた。
「Excuse me. Do you know a reasonably-priced place that serves good
Japanese-food? Because we're very starving」
「ほら、何か聞いてる、答えてあげなさいよ」C美はB作をこづいた。
「えーっと、えーっと、へへへへ」B作は笑ってごまかした。
A輝は「アー」と言って、しばらく手をひらひらさせていたが、出てきたのは三つの単語だけだった。
「イヤー、オーケイ、サンキュー」
Fは帽子をかぶりなおすふりをして、笑いをこらえていた。
「You can find one just opposite this club.」
答えたのはフロアからもどってきたD子だった。外国人はパッと明るい表情になって、D子と親しげに会話を交わしたあと、おおげさに感謝しながら去っていった。
「D子さん、すごかたい、英語ペラペラたい」
「五年もユニセフに勤めていれば自然にそうなりますよ。
日本には久しぶりに帰ってきたんですけど、また明日発つんです。
いつもへき地で子供たちばかり相手にしているので、たまには都会を味わいたくて近くに宿をとり、大人の雰囲気にひたりたくてここまできたんです」
「ばってんが、ユニセフの人がなしてあげなセミナーに?」
「協会から支給される補助金には限度があって、けっこう持ち出しが多いんです。
だから、何か自分で資金を生み出すビジネスをはじめたいと思って」
話がやばい方向へ流れはじめたぞと、ヒモ、ときどきフリータ−のA輝は思った。
彼は皆の目を覚まさせようとパチパチと指を鳴らした。
「ねえねえ、この後どうする?どっか場所うつして飲み直す?
おれ、とっておきのスポット知ってるんだけど。
そこ芸能人がよく来るとこでさー、こないだなんか----」
そこに制服を着た男が現れてE次郎に声をかけた。
「E次郎様、明日は朝から会議ですし、そろそろお帰りになりませんと。
店の前にお車まわしてもよろしいでしょうか?」
「ああ、そぎゃんたい。ちょうどよか。皆さん家まで送まっしょか?」
C美が興奮して飛び上がった。
「若いのに運転手つきなんて、あなた、どこかのボンボンなの?」
「まさかー、
ワシんちはすごい貧乏で、小さい時はなーんも買ってもらえんかった。
ワシに金ができたんは、ワシが発明した枕で一山あてたからですたい」
「もしかして! あなた「ヒーリング・ピロー」という枕を世界的に売り出して、
長者番付にのった人? えーっ、うそー、わたしもひとつ持ってるのよ」
「はあ、こぎゃん美人に使うてもろて、嬉しかねー」
「だってあれ、すっごい落ち込んだ気分の時でも、
頭を乗せて寝るだけで癒されるんだもん、ほんとヒットするはずよ。
わたし的にはもっと違う形にしたほうが若い子に受けると思うんだけど」
E次郎の顔が、一瞬、商売人の顔になり、すぐにもとの笑顔にもどった。
「そんなら、車ん中でゆっくりしゃべくりまっしょか」
C美の耳にはもうE次郎の訛りは聞こえなかった。
以下、C美に聞こえているとおりに記述する。
「それなら、車の中でゆっくりお話ししましょうか」
「えーっ、嬉しい! 車って? もしかしてBMW?ベンツ?」
「さあ、僕はよく知りませんが、中はわりと広くて、向かい合わせに座れます」
「きゃあ、行く行く。あ、E次郎さん、ここに何かついてるぅ」
C美は汚れてもいないE次郎の口元にハンカチをあてた。
「他の皆さんはどうなさいますか?」
「わたしはけっこうですわ。歩いて帰れますから」
D子が凛々しく笑った。
「オレは乗せてもらおうかな--------あ、やっぱ、いいっす」
C美に激しく睨まれて引き下がるB作。A輝は女の物であるバイクをセミナー会場から回収して帰らないと怒られるので、応じるわけにはいかなかった。Fはウエイターになにやら耳打されている最中で、E次郎の誘いは聞こえてないようだ。
「D子さん、これはわたしの名刺です。
ビジネスのことで何かお力になれるかもしれません。
いやあ、今夜は楽しかった。それじゃあ、行きますか」
E次郎が腕を差し出すと、C美は毛皮向きの小動物のようにその手にからまった。
A輝はこのまま引き下がれなかった。むしゃくしゃした気分がもどってきて、ウエイターについて席を離れようとしているFの肩に手をかけた。
「おい、まだ話は終ってないぜ」
突然、スポットライトがA輝に当たった。
「へーい、みんな、踊りを中断しちゃって申し訳ないけど、
今夜は珍しいお客さまが来てるんで紹介するね。
マスコミ嫌いでメディアにはめったに顔を出さない、
この店のプロデューサーでもあり、
世界的に有名なDJでもある、
ミスター、NK!」
皆のどよめきと拍手を受けて、ミスターノースコーリアこと、Fが手を上げた。
その時、FのうしろにいたA輝の姿は音をたてて消失した。