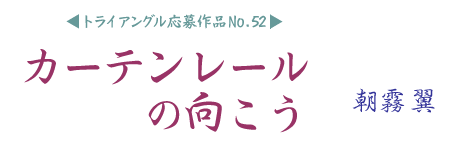
正座して枕を膝の上に置く。右手にカッターを握りしめたまま、両手を合掌させる。
「枕さんごめんなさい。こんな事はしちゃあイケナイと思いますけど、どのみち貴方は捨てるつもりだったので、最後に本来の使用目的とは違う所でも役に立ってください!」
憐れな枕への謝罪の言葉を叫び、準備完了。
カッターの刃をゆっくりと出す音が、部屋に静かに響く。刃を目一杯出したカッターをふりかざし、
「西村たぬきの馬鹿ヤロー!」
力いっぱい振り下ろす。カッターは、枕のド真中に突き刺さる。
「ザケんじゃねェょ! ぜってーぶっ殺してやる! 誰もてめぇになんか数学教わりたいなんて、頼んでねぇんだよ!」
突き刺したカッターを、心臓を抉るように動かす。裂けた布から血のように、ブラスチックのチップが零れる。
「おんどりゃぁぁぁぁぁ!」
最後に一発大きくふりかぶり、刺す。プラスチックしか流さなかった枕に、朱がさす。
「痛ったぁ……」
瞬間的な痛みに、後を引くジリジリした痛み。勢い余って、カッターは枕をつき抜け、私の太ももを傷つけたのだ。朱が広がり、私はまくらの布の上から、傷をおさえる。
「っ……」
ほどなくして血は止まり、枕どけると猫に引っかかれたような傷があった。痛みと血のわりには、傷は浅い。
ピリリリリリ ピリリリリリ ピリリリリリ
テーブルに置いてある携帯がけたたましく鳴る。バイブによる振動でテーブルの上から落ちるが、それでも音は鳴り止まない。
携帯を開くと非通知の文字。それでも私は迷わず出る。
「もしもし?」
電話の向こうの相手は、すぐに返事を返さず、私は傷ついた足のまま、カーテンの掛けられていない、ベランダに出る。
『大丈夫……? 二美ちゃん』
電話の向こうから聞こえたのは、声変わりしかけで止まってしまったような、中途半端に高い声。
「うん、平気。たいした事ないよ。もう血も止まったし」
『そう、よかった。女の子なんだから、体に傷のこすようなマネしちゃだめだよ?』
「わかってるって、私も女の子だもん」
『女の子にしては、口が悪いけどね。さっきは、何叫んでたの?』
「あっ、もう聞いてよ! 数学の西村たぬきがね、授業中ずぅっとぐちぐち説教たれんのよ、ムカツク! 高い授業料払ってるのはこっちだっつうに! 貴重な時間裂いて教えてやってるーとか、猿に教えた方がマシだーとか。私達の払った金から給料貰ってんのは何処のどいつだ!」
え〜っと、この会話を聞いて私と彼が友達、もしくは恋人同士だと思った方、大間違いです。
『身振り手振りしなくても、二美ちゃんの気持ちは声だけで十分わかるよ。ベランダで一人暴れてると、変人だよ?』
「余計な御世話! 変態ストーカー野郎なんかに言われたくない!」
これは冗談なんかではなく、まぎれもない事実だ。見知らぬ人からかかる、電話自分を監視しているような言動、暗くてこっちからはよく見えないけれど、向かいの部屋から私の部屋を覗いているらしい。ドミノ倒しのように規律良く並べられているマンションの棟だからこそ出来る技だ。女子高生の一人暮しは危険がいっぱい! ……私の危機感なんざ皆無に等しいけれど。公認ストーカーだし。
『そんなストーカーの僕と、こうして話してるだけで十分変人だよ』
電話の向こう側から、クスクスと笑い声が聞こえる。
「何笑ってんのよ」
『ん、だって……ねぇ? なんで二美ちゃんは僕とこうして話してくれてるのかなって』
「さぁね。ほら、私って普通じゃないしさ。小学校高学年の時の記憶は無いし、中学は不登校で精神科への通院。高校は何故か何故の一人暮。そして、きわめつけのストーカーと楽しく対談」
後ろを振り返れば、今まで自分の歩んできた道。幼稚園、小学校低学年、 、中学、高校。視点より早く、消しゴムで消したように消失する道。小学校高学年。消しゴムで消された記憶。人づてに、いじめられていた事と教室から飛び降りたことを聞いた。
「一人暮しは実験みたいなもんなんだけどね。実家からは徒歩十分だし」
『実験? なにそれ』
「ふふっ、ナイショ」
夜はふける。監視される自分、監視するアナタ。それでも私はアナタを信じてる。
「箱?」
次の日学校から帰ってみると、家の前に箱。
「何、これ? ……あれ、名前が書いてある。須藤岡? すとーおか、すとーぉかー。ストーカー? 何これ、変なのっ」
あいつからだ。得体の知れない謎の文字に、笑いが込み上げる、ちょうどその時、見透かすようにポケットの中味が振動した。
箱を左手にかかえ、携帯に出る。私が物を言うより早く、例の声が聞こえる。
『プレゼント見た?』
「あははははははははは!」
『何で笑うんだよ、ひどいな』
「だって、何考えてんのよ。須藤岡って、誰よ! 誰! まさか本名とか言うんじゃないでしょうね」
『さすがに違うよ。ただのシャレ、何かへこんでたから、元気付けようと思ったんだ』
「須藤岡で? 笑い過ぎて、余計に疲れるって!」
『あははっ、でもそれだけじゃないよ』
左手に箱をかかえたまま、携帯を肩とほっぺたの間に挟んで、家の鍵をあける。
「それだけじゃないって?」
『箱、開けてみせてよ』
「ちょっと待ってて」
開いたままの携帯と、箱をテーブルに置き、対になっている椅子をベランダに運ぶ。すぐさま携帯と箱を取りにもどり、携帯を耳に当て、椅子に座って箱を開ける。
「わぁっ、シックスブランドのまくらだ!」
箱の中には23の文字がプリントされた真っ赤な苺模様の枕――クッションと言った方がイメージが合うかもしれない――が入ってっていた。
『気に入った? たしか好きだったよね、そのシリーズ』
「うん、スキ。時計とか、テーブルクロスとかも持ってるもん」
『よかった。ちょっと恥ずかしかったんだよ、お店の中女の子ばっかで』
まだ見ぬ人が、シックスブランドのお店で、女の子に囲まれ、顔を赤くしているのを想像した。
『でもさ、何で23のいちごなの?』
「んー、それはね、私がこのブランドが好きな理由なんだけど、二は女。三は男、一は創造。それを全部足せば完全なる数六になる。ちなみに、二と三を足した五は結婚を意味する数字なんだって」
『ああ、それで23の一ごで、六(シックス)ブランドなんだ』
「うん。その話聞いてから、このブランドのファンなんだ。なんかさ、愛って……感じじやん」
『…………』
電話の向こうが静かになる。何か、変な事を言ってしまっただろうか?
「――――ねぇ……逢いたい」
口からもれたのは、自分でも驚くような思いと、飴玉のような涙だった。
『ごめん。会えばきっと、君を傷つけるから……ごめん、ね』
プツリと切れた回路が、冷たく電子音を奏でた。携帯がコンクリートに落ちる。空になった手で、シックスブランドの枕を抱きしめた。涙が止まらず、太陽の光が鉛の雲に遮られる。
「っ……助けっ、てぇ……誰かぁ――」
「どっこらしょぉ〜っと」
小学校の正門を乗り越える。【許可無く立ち入ることを禁ずる】とかいう看板は無視。
暗闇に浮かぶ校舎に遊具に、ライトアップされた運動場、妙な銅像がないだけマシなのかもしれない。
針金でカギを開け、昇降口を上り、目指す場所はただ一つ。私が飛び降りたという、元・六年三組の教室。
「たしか、三階の一番奥……」
人づての記憶と、低学年までの記憶を頼りに、階段を駆け上がる。
「あっ……」
三階に、足を踏み入れた途端、足が床に貼り付いたかのように、動かなくなる。忘れてしまった、この学校へのトラウマか、それともこれから行う事への恐怖か――?
「しっかりしなよ、私の足!」
気合いを入れる為、足を叩く。傷口に手がふれて痛んだが、もう、そんな事はどうでもいい。足を床から剥がし、先へ進む。
聞きなれた学校の引き戸の音。月明りに、仄かな外灯。昼間とは違う顔を持つ、夜の学校。月光に踊る蒼い影、生徒の気配の残る机。
ゆっくりと窓を開ける。冷たい夜の風。星月夜の空に、闇にゆれる草木。眼下の花壇からは、土の香りと枯草のニオイ。
消しゴムで消された記憶。ただそこにあるのは無。
傷だらけで目覚めた病室。私の記憶は空っぽだった。飛び降りる前後の記憶はもちろんの事、家族の事も、自分が何者なのかさえも――
半年かけて、家族の事を、幼稚園の時の事を、小学校の事を、記憶の欠片を拾い集めて、一生懸命つなぎ合わせた。
けれど、致命的にピースが欠けていた。小学校五年から今までの記憶。
医者は、外傷的な物より、精神的な要因が大きいと診断した。
窓から飛び出す原因となった記憶。それが消えて、道がわからなくなった。私は本当に二美? 私は何で飛び下りたの? 忘れてしまった私は何処? 私は本当に生きてるの?
ずっと探してきた記憶。意味が好きだといったシックスブランドも、退院したら、記憶に無いのに部屋にたくさん飾ってあった。だから集めた。また飛び下りたら大変と、記憶から遠ざけようとする家族。だから離れた。
カウンセリングにも通った。なのに、ほんの一欠けらの記憶さえも見つからない。
だから、あの時と同じ事をしようと思う。
窓枠に、足を掛ける。馬鹿な事は止めろと、ポケットの中で携帯が振動する。馬鹿な事だとわかってる。それでも私は、自分の歩んできた道が欲しい。
蒼い月光の中、冷たい夜の風の中、星月夜の空に、土の香りと枯れ草のニオイ。
私は宙に踊り出た。一瞬の浮遊感。風景がスローモーションで流れてく。例え、死んでも構わない。空っぽのまま、生きるのにはもう飽きた。
「二美!」
堕ちる風の中、声が聞こえた。携帯なんかからじゃない、鮮明な、肉声。
全身に衝撃が走る。
(……あれ? 思ったより衝撃が少ない?)
すっと瞳をあけると、私の下敷きになっている、学ラン姿の少年。
「二美……怪我ない?」
花壇に積まれた枯れ草の上に横になったまま、いつも携帯から聞こえていた声が少年から発せられる。そっと私を抱き支える腕は、想像より頼りなく、耳の下から聞こえる心音は速く、あたたかかった。
「うん、へーき」
僅かな笑みが漏れ、手を解いて起き上がる。
「ホント? 良かったっ!」
また、抱きしめてくる。草の絡み付いた黒い髪が、頬にふれる。
「しんじ……君」
唇から零れた声に、抱きしめていた手が、肩をつかみ引き離す。ようやくまともに見れた彼の顔は、少し子供っぽい黒目がちの目を、驚きに丸くしていた。
「思い出したの……?」
「ううん、違う。名札」
学生服の左胸についた、黄色いプラスチックを指差す。
「がっかりした?」
「うん……あっ、いや。大丈夫」
「ねぇ、私が思い出すって事は、私が知ってた人って事よね?」
襟元を乱暴に掴み、引き寄せる。
「貴方は、いったい何者? ストーカーの参志くん」
冷たい風が髪を玩び、枯草が舞う。
「君の事が、好きなんだ」
「そんな事知ってる」
自分でも、ゾクリとするような、冷たい声だった。
「……僕は――……」
傷つけられて、校舎の裏で泣く君。真っ赤に目を腫らして、目が溶けるんじゃないかと心配するほどで、僕はなぐさめる事しか出来きず、君は何故そこまで泣くのか、何があったのか、教えようとはしてくれなかった。
君が飛び降りた日さえ、何があったのか僕は知らされていない。なぐさめる事さえ、もう出来ない。
お見舞に行ったけれど、これ以上あの子を傷つけるなと、母親に追い返され、人づてにしか聞けない彼女の近況。それでもそれは、ゴシップ以外の何でもなかった。
中学に進学しても現れる事なく、家の前まで会いに行っても、引き返した。ただ、彼女を傷つけたくなかった。また、泣かしたくなかった。
そして、三年たった春の日の事だった。高校生になった君が、僕の部屋の前に引っ越して来たのは……
カーテンの隙間から見える君の姿。泣き顔しか見たことのない姿とは違って――目が離せなくなった。郵便物から携帯の番号を調べあげ、望遠鏡で部屋を覗く、自分のこの行為が、どう呼ばれる物なのかは知っていた。
歪んだ愛情に、それを受け入れるはずのない思い人。ただ秘密に、怖がらせないよう、辛い記憶を思い出さないよう、ただ秘密に、ただ密かに、想っていた。
かける気の無かった電話をかけてしまったのは、記憶を無くして、以前には決して見せない笑顔で、いつも笑っていた君が泣いていたから。
昔同じ、涙に濡れた君。何度も眺めた電話番号、メモを見なくても押せた。
電話に出た君は、拙い言葉を並べて必死に励まそうとするストーカーの僕に、笑って答えてくれた。寂しいと泣く君の涙が、少しでも乾くようにと、僕はふれられない君の涙をぬぐう。
次の日、いつものように君の部屋を覗くと、掛けられていたカーテンが、外されていた。
受け入れられるはずの無い、思いだった。
「君の事が好きなんだ」
胸元を掴んだ手が、逆に掴まれる。
「貴方が好きなのは、私じゃない。貴方が好きなのは、校舎の裏で泣いていた子でしょ? 私はそんな所で泣いてない。そんな記憶ない」
彼の告白を、私は冷めた心で聞いていた。
「違う! 僕が好きなのは君だけだ!」
「だから、それが違うっていうのよ。私は貴方の知ってる子じゃない」
掴まれた手を、ふりほどく。
「知ってるよ! ずっと見てきたんだから。僕は、君が好きなんだ。あの子の事は、好きじゃなかった。でも、君の事は愛してるんだよ。だから今日、いつもの時間になっても帰ってこない君が心配で、心配で、ここまで探しにきたんだ。あの子だったら、ここまでしない。愛してるんだよ、二美!」
泣き声を押し殺した様な声。私にふれる事はせず、俯いたまま私から顔を背ける。
「君が僕の言葉を信じられないなら、それでもイイ。それでも僕は君が好きだから……辛いことは思い出さなくていいじゃないか。自分が生きてきた道が、証拠が欲しいなら、僕が証明してあげる。二美、君は今ここでこうして生きてる。泣いて、笑って、怒って……過去も先も関係無い! 今だけで良い。僕が愛してるのは、今の君なんだ」
枯れ草に雨が降る。
校舎の裏で泣く子。アナタは誰を愛してた? あなたの気持ちなんて私は知らない。それでも、私は――――
「っ……ごめんなさい」
こんなにも思われて、こんなにも愛されて、歪むほどの思いに。
「わたしも、ね」
視界が、涙でうるむ。横隔膜が痙攣して、上手く話せない。
「すき…………なの。アナタの事。私も、参志君の事が好き……」
知らない私を知るストーカーに、私は思いをよせていた。回路越しの声に、温かさを想い、小さく痛む胸の思いが何なのか、ようやく思いついた。
これは、私の思いじゃないのかもしれない。忘れてしまった校舎裏のあの子の思いを、私が受け継いだだけなのかも知れない。それでも、私のこの思いは本物だから……
「ありがとう」
彼のささやかな言葉が、耳にふれる。彼の手が、涙に濡れた頬に、ふれる。
唇が、重ねられる。
カーテンを買いに行こう、大好きなシックスブランドのカーテン。貴方と一緒に、初めてのデート。
家族に紹介するのは、まだまだ先かもしれないけれど、貴方を私の家に招待するわ。
貴方がくれたクッションに、私の入れた紅茶と御手製のクッキー。
遠くから見つめないで、ずっとずっとそばにいて、道をまた失いたくないの、貴方を失いたくないの、
カーテンレールの向こうには、貴方が居て、私が居て、
歪んだ愛情でも、歪んだ道でも、
負と負を足せば歪みは大きくなるばかり。
それでも、思い重ねて掛け合えば、
きっと幸せになれるよね――――?