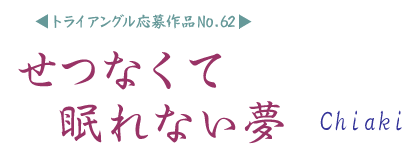
イルカになって空を泳ぐ。背中にぬくもり、くちばしに風。浮かんでいるのはいいけれど、ニンフの小舟がやってくる。吐息や呪文がからみつき、視線が身体を突き刺した。
「仲井、仲井辰巳」
背中の痛みが辰巳を覚醒させた。イスから立ちあがったひょうしに、つま先をいやというほど机にひっかけた。
「仲井辰巳、ボケっとしてないでこっちへ来い。おまえの答案なあ、houses burned down が消失した家になってるぞ、焼失だろうが。中学2年にもなって漢字もまともに書けないのか。しかも先月のテストがやっと13/25点で今月が15/25点、おまえ英語やる気あんのか」
丸めた教科書が頭に落ちてきたが、それだけではおさまらない。
「香坂みゆき、優秀だがムラがあるな。もっと集中しなけりゃいかんだろう。抜け殻みたいな仲井を見習うんじゃないぞ」
美人にはやさしい言葉だが、辰巳はクラスの笑い者だ。辰巳は上ばきを脱いで背中を丸め、くるぶしをヘソまで抱えあげた。ヨガのように窮屈なポーズのまま、蒸れて臭い指にふーふー息を吹きかけた。クラスメートが鼻先を掌で扇ぎながらしかめっ面をしたが、かまうものかと辰巳は無視した。
授業に集中できないのは確かだった。瞳孔がゆるみ焦点がさだまらず、先生の声が身体をすりぬける。バネを踏むようなフワフワした意識が、釣り糸にたぐられるように夢の中に引かれてゆく。
辰巳の場合、瞼を閉じて居眠りするのとは訳がちがう。背筋を伸ばしたまま瞬きも、呼吸さえも止めた。蝋人形のように固まるのだ。こうなると目の前で手を振られても、山田アケミのおかっぱ頭が接近しても反応しない。
むかし「ろくろっ首」という妖怪がいた。身体が眠っているあいだに首がすっぽ抜けて飛びまわり、人びとを驚かせたという。辰巳の場合、飛びまわるのは首ではなく魂だった。身体はセミの抜け殻のように教室に置き去りにされ、心だけがフワフワと天井に立ちのぼり、イルカとなって空間を泳いだ。これも見方によっては妖怪変化と言えなくもない。そういえば首はすっぽ抜けないまでも、喉がごつごつして声がしゃがれてきた。背丈は半年で20センチ以上も伸びている。
「バーカ、何にも知らねえのか。それを思春期つうの」
物知りの友人が辰巳の頭をひっぱたいた後、こう言って脅かした。
「ろくろっ首という妖怪は、飛びまわっている間に身体を動かされると、首がつながらずに死んでしまうと言うぞ。お前が白昼夢を見ている間に体を動かして、いっぺん殺したろか」
それは困る。まだ死にたくないし、魂が身体とつながらずボケたまま一生を送るのも嫌だ。
「また子供みたいなことを、毛も生えた男が言うことか」
再びガツンとくらわした物知りは辰巳の耳元でつぶやいた。
「お前、もうやったか」右手の拳を上下させる。
「なんだ、ジャンケンか」そう応えた辰巳は絞め殺されそうになった。
「ちょっと来い、このやろう」
それから友人はヒソヒソと説明したが、辰巳は始めて聴くことばかりだった。
「なんだ、そのことか」しかし辰巳は知ったかぶりをする。
ピストルはいじくりすぎると暴発する、女はきまって貧血になる、男女の関係は鍵と鍵穴、フーセンがないとエイズがこわいetc. 辰巳には判ったようでわからない奇妙な内容だった。いまひとつ腑に落ちないまま、優等生アケミのことを思い出した。
小太りの山田アケミの顔は三角おむすびだ。そこにYを刻んだように吊りあがった眼と低い鼻がついている。辰巳にたいして妙になれなれしいアケミが、マンガ本を開いて言った事がある。
「この主人公は自由がほしいわけよね。それで鎖を切って逃げ出すの。この人の長髪は束縛からの自由を表すわけね。最後は髪を切って雑踏の中に消えて行くじゃない。それはね、社会に適応してゆく、つまりは主人公の夢が挫折したことを暗示しているの。だからこの物語は若者が社会に抗いつつも結局、飲みこまれてゆくその現実の過酷さと、主人公の哀れさが主題なわけ。辰巳はこんな事がわからないの、あきれた。でもまあ子供みたいなところが可愛いけどね」
アケミに頬をつねられて辰巳は愕然とした。アケミはたしかに足柄山の金太郎もどきだがそれよりも、彼女の洞察力に目が覚める思いがしたものだ。そのとき辰巳は、波打ち際に置いてけぼりをくらったペットボトルのように、スカスカした頼りない気持ちで腕をはすかいにかまえ、我が身を抱いた記憶がある。
(みんな大人びているな)
小学校6年の秋、アケミの家に遊びに行った。部屋の窓は道路にむかって開いており、エンジンをふかす音がアケミの声と同様にやかましかった。寒いとふざけて辰巳がベッドに寝ころがり布団をかぶると、アケミもマンガを放りだして布団をめくってきた。そのとき、
「アケミちゃん、いるの」
ちょうど窓から顔をのぞかせた同級生と目が合ってしまった。
中学生になっても噂はついてまわった。
「ちがうちがう、絶対にちがう」
必死に否定してもどこかで火のてが上がった。山田アケミがミッキーマウスのバッジのように胸にとめて、みんなに自慢していた。
「いいじゃない、本当のことだもん」
オニギリ顔が口をとがらしてそっぽを向いた。辰巳はため息をつく。どうせ噂になるのなら香坂みゆきにしてほしかった。
幼稚園のころトイレでお医者さんごっこをした。香坂みゆきがスカートを胸までたくしあげて見せてくれたが、真っ白いおなかの中心にプクリと盛り上がる出ベソは(彼女はヘルニアだった)記憶にはっきりと残っている。三つ子の魂百までというけれど、コクリと頷いてパンツを下げたあの素直さも、相手が誰であったかも覚えていてほしい。辰巳は真剣にそう願った。
「いやらしい」と逃げまわっていた女の子が、中学生になると辰巳の後姿を眼で追うようになった。「占いの館」で手に入れた護符を握ってぶつぶつ呪文を呟く。辰巳がたびたび白昼夢に悩まされるのは、そのせいかも知れない。イルカになって空を泳いでいると急にまっ白な雲がわいてきて、くるまれ、抱かれ、絞られる。妖精から投網をうたれ、がんじがらめになることもある。そのときの胸のせつなさと息苦しさは、まったく魔法にかけられたとしか言いようがない。もう一つある。山田アケミの自慢話がいつのまにか、
「仲井辰巳は小学校のときから女たらし」という噂となった。知らないあいだに噂は、
「隣のクラスのあの娘とも、先輩の誰それさんとも」などと、とんでもない膨れあがりようだ。これはアケミの妖術にちがい。
「辰巳、お風呂だって言うのが聞こえないの」
新建材の壁をヒステリックに叩く母親、辰巳が階段をパタパタ降りていくと、妹がランドセルを背負ったままソファにうつぶしていた。
「タイルについた泡をちゃんと流してね、汚いんだからお兄ちゃんは」
いつもの憎まれ口はどうしたのだ。妹のかわりに母親がこたえた。
「ユミちゃんはシャワーにするからいいの。お父さんが遅くなるから、お風呂あがったら種火だけにしといてね」
「種火だけにしといてね、だと」
タイルにへばりついた泡も、浮かぶ湯垢も放っておいた。妹が風呂に入らないなら、それに越したことはない。頭をわしわしシャンプーして勢いよくお湯をかぶった。泡が胸を伝って股間にすべり落ち、睾丸をフッと撫でる。ぞわぞわした。泡が落ちるとうぶ毛が残った。もう数えられるほど太くなったが、まばらなので貧乏くさい。
ミケランジェロの彫刻あれは何といったか、そう「ダビデ」だ。ダビデの像は同じく包茎だが毛は生えてたかな。いろいろ想像していると、睾丸がナメクジのようにゆっくり伸び縮みした。同時に、くしゃみを誘うあの鼻のむず痒さ、それに似た感触が太ももを這いあがるので鮫肌ができた。おもわず肛門をすぼめて身震いすると、パンピングされた血液で海綿体がムクリと起きた。心臓にあわせて脈動し、うなずいた。くしゃみの前におこるケイレンか、しゃっくりをしているようにも見える。
「着替えはここに置いとくからね」
辰巳はあわてて身体を折りまげ髪を洗うふりをしたから、胸元でこすってしまった。とたんに止めようのない震えがきて、快感が唇や鼻の穴にまで飛びちった。
スリガラスの影が消えてもまだ辰巳は、エビのように身体を折ったまま頭から水を浴び続けた。それからタイルにへばりついた泡も、浮かんだ湯垢も、排水溝にからんだ髪の毛まできれいに掃除して風呂からあがった。
その夜はなかなか寝つけなかった。一つハードルを飛び越えてほっとした。これで皆の仲間に入れると嬉しくもあったが、なんとなく後ろめたい気もする。それに湯上りのせいか身体が火照る。蛍光灯の白い輪をながめていると香坂みゆきの肌に見えてきた。
香坂みゆきが髪をかきあげるときに見える腕のつけね、ケシゴムを拾うときに開いたセーラー服の胸元、スカートがめくれすぎてあらわになった太もも、考えるだけで息がつまった。鼻をほじくり、こぶしてぬぐうと鼻血がベットリついてきた。天井を見上げながら手探りで階段を降りてゆくと両親の声がきこえてくる。
「お赤飯のかわりに俺が明日、ケーキでも買ってこようか」
「だめよ、それじゃ逆効果。いろいろユミに尋ねるようなことは絶対しないでね、お父さん。あたし今度の日曜日、ユミと二人で下着やなんかを買いに行ってきます」
「子供だと思っていたのに、早いもんだな……。ユミの成人式では辰巳が23で俺が47、おまえは45才になるわけか」
「まだ44才と7ヶ月のはずです」
あれほどおてんばだった妹が、ひっそりと暮らすようになっている。
「ちょっとお兄ちゃん」
ドアの前で大声あげると間髪入れずノブを回して押し入ってきた妹が、ノックだけで用事を済ますようになった。以前はラジカセにあわせて飛び跳ねる手足が半開きのドアから見えていたのに、鍵までかけるようになった。
「お母さん、何かユミに告げ口でもしたのか」
まさかとは思うが風呂場で見られて、妹への忠告になったのかと不安になる。
「いったい何のことよ」
包丁を持ったまま振り向いた母親は、眼をぐしゃぐしゃにして鼻水をすすり上げていた。
「いや、何でもない。それよかカレーは、ニンジンぽっきりの豚肉ごろごろにしてくれよ」
話をはぐらかしたが、タンポポの綿毛がとぶように妹が離れてゆく。少し寂しい。
英語の授業は嫌だ、毎月テストがある。イルカになって逃避行しているあいだも、ページはめくられてゆく。香坂みゆきが何げなく山田アケミに呟いたことがある。
「英語のテスト、月末にずらしてくれないかな。毎回、あの日と重なっちゃう。ボンヤリして集中できないのよね」
それが聞こえて辰巳は、目の前が急に明るくなった。
(魂が抜けるのは俺ばかりではない。香坂みゆきもか)
香坂の白い肌がぐっと身近に迫ってきた。よし、クラスのトップ山田アケミは無理としても(別に並びたくも無いが)せめて香坂みゆきと肩を並べるくらい頑張るぞ。そう自分に言い聞かせてガッツポーズした。
「あんな、俺がもし固まってたら背中をグサリとやってくれ。死んでも文句はいわない」
「バーカ、死んだら文句が言えるかよ」
ボールペンでグサリとやられた。正気になって気づいたのだが、辰巳の斜め向かいの香坂みゆきは時々、「はぁ」と小さなためいきをつく。まっ白いえりくびをひねって肩を掻く、ふりをして後ろにちらりと流し目をおくる。風邪をひいたときの潤む瞳だ。辰巳はしびれて背中の痛みなんか吹っ飛んでしまう。香坂は魔法使いなのか。
辰巳もまねをして肩越しに振りかえると、斜め後ろの山田アケミがオニギリ顔をつきだしてウインクする。
(おのれアケミ)おまえが「ろくろっ首」なら、すぐさま退治してやるところだ。
しかしアケミの首回りはどっしりと太くて短い。とてもすっぽ抜けるとは思えない。現実に引きもどされた辰巳は教科書に眼をむけた。
「今ね、両親が旅行中なんだ。あたし独りでボケーとしてる訳なんだけど、よかったら遊びに来ない。待ってるから」
髪を黄色く染めたクラスメイトが辰巳に擦りよって耳うちしたことがある。
「来るくる、絶対にくる」すかさず返答すると、
「ちょっと待った」山田アケミがしゃしゃり出てきた。辰巳の腕を掴んで無理やり引きはがし、姐さんぶって説教した。
「それを言うなら来るくる、じゃなくて行くでしょうが、なにのぼせてんのよ。あのこはね、隠れてタバコを吸うし暴走族ともつるんでるよ。相手にしちゃだめ」
近ごろ辰巳は憑き物がおちたように白昼夢を見なくなった。勉強に集中できる。空を泳ぐ快感よりも香坂みゆきのまっ白いうなじ、みみたぶ、ちょっとめくれた下唇、半袖のすきまから見える脇毛の剃りあと、机でひしゃげた胸のふくらみ、これらの現実が辰巳の魂をしっかりと身体につなぎとめている。
(それはいいが……、)こんどは下半身が抜けだそうとする、これが困る。
授業中いきなり硬くなってズボンを突き上げた。こんなときは机におおいかぶさり、一生けんめい「割り算」をして気をそらせた。一番つらいのは名前を呼ばれて立ちあがるときだ。ヘッピリ腰のぶざまな姿勢になった。
「ちょっと腹具合が」などと言い訳したものの、休憩時間もトイレに立てなかった。
「仲井、さいきん真面目になったな」
「そりゃそうさ、いつまでも遊んでいられるか」
ヤケクソで強がったが、一難去ってまた一難とはこのことだ。
「ねえ、こんど映画見にいこうか」
こういう非常時に限って山田アケミが登場する。
「行きたきゃ他の奴を誘えよ。俺は行かない」
「そんなつれないこと言わないで。ミユキともう一人、女の子も一緒に行くんだからさ」
「香坂も行くのか。本当に香坂みゆきが行きたいと言ったのか」
そうか香坂みゆきが行くのか、と何度もつぶやいた辰巳は、腹のうえに組んだ両手で無意識に股間をおさえていた。
「あんたね、思い上がるのもいい加減にしなさいよ」
アケミが他人のイスを勝手に引きずって辰巳の側にどっかとすわった。
「自分がもてるなんてバカなこと考えないでよ。あんたみたいなボンヤリの隙だらけは、いくら女たらしと噂されたところで毒にも薬にもならない、ただの間抜けよ」
一息にまくしたてた後、「と女生徒はあんたを見くびっている」と他人のせいにした。
本当のところ好奇心旺盛な女生徒は、噂の辰巳に興味深々である。ロリポップのように舐めて味わってみたいと思っている子もいる。しかし鼻息荒く飛びかかるような生々しい男なら敬遠したい、というのが娘心だ。その点、自分自身の変化に困惑しているような未成熟の辰巳なら、大人になりかけの娘たちの好奇心の対象としてはうってつけだ。
「つまりママゴトしている子供がもて遊ぶ赤ちゃん人形よ、あんたは」
山田アケミが低い鼻をうごめかして「フン、どうだい」と顎をしゃくる。
(ええい、アケミの解説なんかクソくらえだ)
「俺はイルカでも妖怪でも、ろくろっ首でもロリポップでも、まして赤ちゃん人形でもねぇぞ」
辰巳があばれるとアケミが高笑いする。
「何わけのわからないこと叫んでるのよ。もっと大人になりなさいよ。それじゃ今度の日曜日に約束だからね。私たち、それぞれボーイフレンドを連れてくる事になっているんだから」
「ちょ、ちょっと待て。香坂みゆきに相手がいるのか」
「あたりまえよ、あんたの背中をしょっちゅう突ついてる」
学校から帰ると階段をドスドス上がった。風船がしぼんでゆくような、なさけない気持ちだった。妹の部屋からラジカセの音が聞こえているが、こちらからドアを叩いて妹にちょっかいをだすことは以前ならばまだしも、見えない垣根に拒絶されたようでもうできそうにもない。
子供のころ、父の膝に横すわりした母親が腕をからめてもたれかかる姿を目にした。それ以降、両親の部屋に近づく前にわざと歌をうたうようになった。いまそれと同じような気持ちで足を踏み鳴らして階段をあがり、妹の部屋を通りすぎた。妹になにを警告しようというのか、辰巳は自分でもあやふやで説明できない。それよりも、忍び足で歩く自分の姿を想像するとなんだかもの悲しく、みじめに思われた。
妹と二人でテレビを見ながら、いつのまにか妹を腕枕して眠ったことを思い出した。それから香坂みゆきと幼稚園のトイレで抱き合ったこと、山田あけみと布団の中で肩をぶつけあってふざけたこと、あのような時代にはもう戻れないのだろうか。
辰巳はカバンを投げ出してベッドに顔面から倒れこんだ。