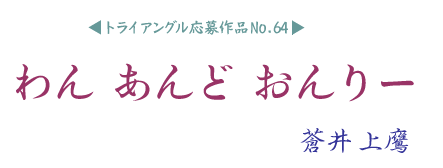
徹治(てつはる)が着替えて戻ると、夕飯の後片付けをしていた亜矢は口に手を当てた。
「どうしたんですか、その格好」
亜矢の視線は、徹治の薄汚れたコートに注がれている。
「出かけてくる」
「こんな時間に?」
言われて徹治は窓から外の様子を窺った。夕暮れの晴れた空にオーロラが波打っている。
「もう外に出ても大丈夫だろう。すぐそこだ――岳(がく)のところで、ちょっとな」
それを聞いて、亜矢は得心した表情になった。
「そう。もうそんな時期になったのね」
「一昨日使いが来た。今年も頼むとさ」
「大変ね、お義父さんも」
「仕方ないさ。代わりがいないんだ」しぶしぶというポーズをとるが、声の張りは隠しようもない。
「わたしもバカね」亜矢は笑った。「もう五年目なんだから、いい加減覚えてもいいはずなのに」
五年か、と徹治は感慨にふける。あの時は、まさかこんなことが自分の「仕事」になるとは思ってもいなかった。
発端は、夕飯の席でのありふれた会話だった。メインディッシュはいつもと同じ、塩辛をまぶした焼き飯だ。焼き飯といっても、一粒が小ぶりの稲荷寿司ほどもあるタワラマイを使っているので、アメリカンドッグの出来損ないのように見える。味も大してよくない。
「お義父さん、今日はお風呂に入ってくださいね。せっかく久しぶりに沸かしたんだし、十二月になったら何かとばたばたするから」亜矢が言った。
風呂嫌いの徹治は聞こえないふりをした。
「お茶漬けが食いたいなあ」
「お湯なら沸いてますよ。持ってきましょうか」
「いや、いい。お茶漬けってのは、米粒が口の中でさらっとほぐれるから良いんだ。こんな馬鹿でかいタワラマイをお茶漬けにしても、糊みたいに粘るだけで、うまくもなんともない」
徹治は自由のきく左手で箸を一杯に広げ、タワラマイを半分にねじ切った。
「我慢してよ、この辺で育つコメは、この種類だけなんだから」息子の哲夫が片手を上げて制した。その細い腕を赤黒い火ぶくれの跡が覆っている。日中の強い紫外線によるものだ。
「糊で思い出したが、焼き海苔も欠かせないな。軽く焙ったのを、こう細く切って。それに漬物だ。茄子の糠漬け。知ってるか? 糠床は洗っちゃいけない。代わりに毎日素手でかき混ぜたもんだ」
以前は、新鮮な魚を捌いたり、だしをふんだんにとった椀物をこしらえたりする場面を思い描いたものだが、年を取るごとに、シンプルな食べ物が恋しくなってくる。覇気がなくなったのか、それとも一層飢餓感が強まっているのか。
「無茶言わないでよ。海苔も茄子も手に入るわけないだろう」
「じゃあお握りでもいい」
「タワラマイで握り飯?」哲夫はうんざりした顔で自分の飯を一口食いちぎった。亜矢も俯いたまま黙っている。色素の薄い髪の毛が垂れ下がっているので、表情はわからない。
味のことで亜矢に文句を言っても仕方ないのは、徹治自身が一番わかっていた。こんな材料では、誰が料理してもろくな味にはならない。だが、つい憎まれ口を利いてしまう。
かつて徹治は腕の良い板前だった。世の中がこのように変わってしまう前のことだ。
「この前、新しい墓地を整地していたら、変わったものが見つかってね」その場の雰囲気を変えようと、哲夫が亜矢に話しかけた。
「新しい墓地って、どっちの?」
「四丁目の図書館跡の方だ」
「また、読みとれないヴィデオやCDでしょ」
コンピュータなどの電子機器や、それを用いた各種システムが一切使用不能になり、今のような半原始的生活に逆戻りしてから、そろそろ二十年になる。地磁気が急激に減少し、磁気嵐や放射線シャワーが猛威を振るった結果だ。
「いや、本だよ。紙で印刷された、普通の本」
「珍しいわね、どんな本?」
「『地酒ハンドブック』という題だ。自家製酒の製造販売が条件付で認可されたときに出た、酒造りのハウツー本らしい」
「酒か」徹治は軽い溜息をついた。もう何年も、ちゃんとした酒を飲んでいない。あるのは、自家製の梅酒モドキと、岳のところでタワラマイから造る『極光』だけ。どちらも飲めた味ではない。
「その本を読んで考えたんだけど、タワラマイって、食用より酒造用にむいているんじゃないかな。ほら、ここに芯のような白っぽい部分があるだろ。これは心白と言って、酒米の特徴らしいんだ」
「馬鹿言うな」徹治は顔をしかめる。「お前も『極光』を飲んだとき、吐き出していたじゃないか」
「確かにひどかった。でも、それは造り方が悪いせいかもしれない」哲夫は自分の食べかけのタワラマイをつついた。「質の良い酒は、精米――つまり、コメの表面を削って、いわば髄の部分だけで造る。つまり沢山削って、精米歩合を上げれば上げるほど、質はアップするわけ。そういうことは父さんのほうが良く覚えてるんじゃないの」
「吟醸や大吟醸なんてのがあったな」
「大吟醸なら、精米歩合五十パーセント以下だ」
「名前は忘れたが、確か精米歩合二十三パーセントなんていう凄い酒があった。数回しか飲んでないが、ありゃ、もう」徹治は口を閉じた。思い出しただけで唾が湧いてくる。
「当時は、その位が限界だったんだ。でも、もしタワラマイを使えば……」
「二十三パーセントどころか、十パーセント、いや、それ以下でもいけるな」
皿の上の巨大なコメに光が射して見えた。
「もちろん、当時と同じレベルの酒を造るのは無理だろうね。酒造りも、手順の大半をコンピュータで管理していたから、そのデータの殆どは消失しただろうし、当時のノウハウを持つ杜氏が、果たして何人生き延びていることやら。でも」哲夫が膝を乗り出した。「自分の手でどれだけのものが造れるか、試してみたいんだ」
「面白そうだな」哲夫の気持ちは理解できた。役場の開発課とは名ばかりで、実際の仕事は、墓堀りや火事場泥棒と大差ない。そんな仕事を続けるのが嫌になったのだろう。
徹治自身も、胸の奥で何かが蠢きだすのを感じていた。右腕を痛めて包丁を持てなくなって以来、久しく忘れていた感覚だ。
「それで、どうするつもりだ」
「まず、岳(がく)さんのところに技術指導をお願いしようと思う。あれでも老舗の酒造メーカーの社長だからね。手の内を全部明かせとは言わないけど、酵母くらいは分けてもらえるんじゃないかな。まんざら知らない間柄ではないし」
徹治は危ぶんだ。岳とは子供のころからのつきあいだが、昔から底意地の悪いことで有名だった。
哲夫が話をしている最中に、岳は何度も膝を叩いて笑い転げた。その度に、赤く弛んだ頬がふるえ、胴回りの余分な肉が波打つのが、応接室のヒカリゴケの微弱な光の下でも見て取れた。
「そんなに馬鹿げていますか?」哲夫は眼鏡に手をやった。声が震えている。
「いや、馬鹿げてはいない。確かにマニュアルどおりだ。ただし、昔のマニュアルだがね」
「今では通用しないということか」
テーブルに片手をついて乗り出す徹治から、岳は顔を背けた。
「臭いな、おい」
「気にするな、コートの皮の臭いだ。いいから質問に答えろ。哲夫の言うやり方じゃ駄目なのか」
「そりゃそうさ」ぐっと砕けた口調になった。「考えてもみろよ。コメはどうして酒になる?」
「……発酵するからだろ」
「じゃあ、発酵ってなんだ」
徹治は即答できなかった。
「酵母の菌がコメのブドウ糖を分解してアルコールに……」横から答えようとした哲夫を、岳は手を振って制した。
「腐ることだよ、簡単に言えば。人間の役に立つような腐り方を『発酵』と言う。それだけのことだ。でも菌が人間に気を遣ってくれると思うか? 放射線だかなんだかのせいで、日替わりで新しいウィルスが暴れまくるご時世だぞ」
岳の視線につられて、徹治も窓の外の墓地に目をやった。暗くて良くは見えないが、疫病で死んだ岳の家族や徹治の妻も、そのどこかに土葬されているはずだ。地味を回復させるための措置だが、効果が出るまでには、まだ時間がかかりそうだ。
やがて岳がぽつりと呟いた。
「……酒の麹だって昔とは違う。昔の方法でやっても、思った通りに働いてくれるとは限らない」
「それじゃ、岳さんとこの酒は……」哲夫がおそるおそる訊いた。
「残念ながら昔の酒とは縁もゆかりもない。うちの酵母のストックなんて、二十年前のあの騒ぎで全滅さ。今の『極光』は、自然に発酵しかけたタワラマイを、昔の藏の跡地で見つけて、それを元に造った。ほとんど偶然の産物だよ」
(道理でひどい味だ)
徹治は胸の中で毒づいた。
「幸い、うちは井戸だけは無事だった。酒米も酵母も杜氏も機械もデータも、みんな失ったが、水だけはおれの手に残った。教えてやろう。酒の味は、最後には水で決まるんだ。それだっていつ汚染されるかわからないがな」
「その水が、今造っている酒の、タワラマイや酵母にも最適だと言い切れますか」
哲夫の言葉に、岳の目が急に細くなった。
「言うじゃないか」
「それに水質なら、うちの井戸も負けません」哲夫はブリーフケースから書類を取り出した。「調査済です。ペーハーも硬度もミネラル含有率も」
「仮にそれが事実だとして、うちに何を期待しているんだ? え、哲夫君」
「は?」
「まさか、商売敵を育てるのに手を貸すほどのお人よしと思っているんじゃないだろうな」
「よくそんなことが言えるな」徹治は立ち上がり、左手の包みを岳に突きつけた。
「なんだこれは」
「開けてみろよ」
包みの中身は古い柳刃包丁だった。
「おれが店で使っていた柳刃だ。忘れたのか? お前の酒が売れるようになったのも、元はといえば、おれが口を利いて店で出してやったからじゃないか」
「いつの話だ」岳は鼻でわらった。「昔のことを今言ってどうする。どのみち、あのころの酒は二度と造れない。お前の料理だってそうだろう?」
「違う。手さえなんともなけりゃ、今だって……」
「ほう。じゃあ訊くが、魚や肉はどこで手に入れる? 味噌は、醤油はどうする?」
そう言われると言葉もない。徹治は唇を噛んだ。
「だいたいその包丁はなんだ。ろくに砥いでもいないし、アオサビにやられてぼろぼろじゃないか」岳は包丁を押し戻した。「忘れちまえよ、あのころのことは。今できることをやるだけだ」
その言葉通りに行動してこの二十年を生き延びてきた岳の目は、自信に満ちていた。
「こっちはもっと先のことを考えているんです」哲夫が言った。「タワラマイの大吟醸――いや超吟醸についてご相談したのも、そのためです」
「そうだな」岳は目を閉じて、考えるポーズをとった。「確かに悪くないアイデアだ」
「そう思うか」徹治はほっとして言った。
岳はゆっくりと目を開けた。
「早速使わせてもらおう。その『超吟醸』というフレーズを、うちの『金環』に」
「……何だ、キンカンてのは」
「今研究中のタワラマイ新酒の名前さ。もうすぐ試作品の仕込みが終わるところだ。できたら一本進呈するから楽しみにしてろよ」
岳は独りうなずきながら、立ち上がって会話の終了を示した。
「『金環 超吟醸』か。なかなか良い響きだ」
かなり遅い時刻だったが、月が出ていたため、用意したランプを灯す必要は無かった。
「何が『金環 超吟醸』だ、ひどいネーミングだ」哲夫はまだおさまらない様子だ。
徹治は黙っていた。岳の言うことはわかる。間違っていない。ただ、あの態度ばかりは腹に据えかねた。黙って引き下がるのでは腹の虫が治まらない。なんとか一本取る方法はないものか。
哲夫はまだ愚痴っている。
「……この際、うちは酵母抜きでやってみよう。昔は、人が口でコメを噛んで酒を造ったというじゃないか。人間だって発酵させる力はあるんだ」
(人間だって発酵させる力はある)
その言葉が、徹治にひらめきを与えた。
「どうしたの」ふいに立ち止まった徹治を見て、哲夫が訝しげに尋ねた。
「用事を思い出した。先に帰っていてくれ」
「父さん、まさか」哲夫が顔色を変えた。その目は徹治の懐に入れた手に向けられている。徹治は苦笑して首を振ると、懐の包みを哲夫に渡した。
「心配するな」徹治はコートの前をかき合わせ、夜道を引き返していった。
徹治が帰宅したのは、それから二時間後のことだった。さっきとは打って変わって陽気な調子で、鼻歌など歌いながら、息子夫婦の部屋の戸を叩く。
「どこに行ってたの。こんなに遅くまで」哲夫が目をこすりながら枕元の眼鏡を探った。亜矢は、布団に隠れるようにして服の乱れを直している。
「岳の酒蔵に行ってきた」その時の様子を思い出して、徹治はこらえきれずに笑い声を漏らした。
「中に忍び込んでみると、醸造用タンクの一つに、早速『金環 超吟醸』と貼り紙がしてあったよ。よっぽどあの名前が気に入ったんだな」
「まさか、岳さんの酒を盗んだんじゃないだろうね」哲夫が姿勢を正した。「犯罪だよ、それは」
「そんなことするものか。それどころか、岳の手助けをしてやった」
「はっきり言ってよ」
「お前も言っただろう。人間だって発酵させる力はあるって。それを身をもって実行したまでさ」
「さてはタンクに何か入れたね。唾? 痰?」
徹治はにやにやしながら首を振った。その髪の毛から水滴が周囲に飛び散る。
先に気づいたのは亜矢だった。
「義父さんどうして濡れてるの」
「わかった」一拍遅れて哲夫が叫んだ。「泳いだんでしょう、タンクの中で」
徹治の笑みが顔中に広がる。
「岳には試飲が済んだころにでも知らせてやるさ。おれの足でかき混ぜた酒を飲んだと知ったら、あいつ、どんな顔をすると思う?」
哲夫は顔を覆った。「体の雑菌で酒が台無しになるかもしれない」
亜矢が嘆いた。「まったくなんてことをしてくれたんです」
徹治は言った。「さすがに冷えたな。久々に風呂に入るか」
それから二ヶ月ほど経った一月下旬のこと。珍しく岳が徹治の家を訪れた。
「年始の挨拶にしては遅いじゃないか」玄関で迎えた徹治の言葉に、岳の顔は赤黒く変色した。
「よくもそうぬけぬけと……」
「一体何のことだ」
「とぼけるな。哲夫から全部聞いたぞ」
徹治は溜息をついた。あの晩以来、息子夫婦が、一夜として枕を高くして眠ったことがないのは知っている。だが、不安のあまり「自首」するような根性なしだとまでは思わなかった。
「いやあ、悪かった」ばれたら仕方がない。徹治は素直に頭を下げた。「お前があまり友達甲斐のないことを言うもんで、ついかっとなった。だが、別に酒に毒を入れたわけじゃない。このとおり、あやまるから許してくれ」
岳の返事はなかった。顔を伏せたまま拳を握り締めている。何かを抑えているようだ。首筋の血管がふくれ上がっているのが見て取れた。
「それにしても」徹治は意地悪な笑みを浮かべる。「あの時の話じゃ、去年の末には仕込みは終わったはず。その時すぐに来なかったってことは、飲んでみても変とは思わなかったわけだ」
「……たさ」岳は俯いたまま呟いた。
「何だって?」
「思ったさ」
「おおそうか」徹治はうなずいた。「それなら、おれが犯人だとわかるまで時間がかかったのか。ということは、哲夫が黙っていれば完全犯罪」
岳は顔を上げた。
「ふざけるな。お前の仕業だってことは初めからわかってた」
「へえ」徹治は少なからず驚いた。何一つ証拠は残していないつもりだったからだ。
「当たり前だ。あれからしばらくして藏に入ると、お前の臭いがぷんぷん残っていた。きっとろくでもないことをしたんだろうと思って調べたら……調べたら……」
突然岳の目から涙が溢れ出したので、徹治は思わず土間に降りた。
「おい、どうした」
「教えてくれ」岳は喚いた。「おれの酒に何をした」
「もう哲夫から聞いたんだろう。タンクで一風呂浴びただけだ」
「それだけか。本当にそれだけか」岳の巨体にしがみつかれて、徹治は呼吸ができなくなった。
「く、苦しい」
「中で小便でも漏らしたんじゃないのか」
「そ……そんな……年寄りじゃ……ない」
「嘘じゃないな」
肺の中の空気を使い果たした徹治は必死にうなずく。
「それなら」岳は徹治の両肩を掴み、激しく揺さぶった。「頼む。もう一度やってくれ」
(こいつ今、何て言った?)
徹治は自分の耳が信じられない。
「おい岳、落ち着け。一体どういうことだ」
岳が途切れ途切れに口走る言葉を総合すると、どうやら徹治の体から混入した雑菌の作用により、飛躍的に上質な酒ができたらしい。
「おれたちじゃ駄目なんだ」岳は絶叫した。「おれたちが何度タンクに浸かっても、お前がやったときの、あの最高の味は出せねえんだよ」
今年も、岳と哲夫は酒蔵で待っていた。薄闇の中で、銀色のタンクがぼんやりと光っている。徹治は手早く服を脱ぎ、控えている哲夫に手渡した。
「相変わらずひどい臭いだ」岳が大げさに鼻をつまんでみせる。お約束のリアクションだ。
「我慢しろよ。これが味の秘密なんだから」徹治は笑う。コートから下着に至るまで、この五年間洗濯もせずに保管されていたものばかりだ。菌の状態を当時のままに保つためだった。
「まだ菌の分析は終わらないのか」タンクの梯子を上りながら、徹治は哲夫に声をかけた。天辺から中を覗き込むと、液面は白く泡立っている。吟醸酒独特の陶然とさせる香が鼻腔を刺激した。
「早くしないと、秘密を墓場に持っていくぞ」
「菌ならほぼ特定できているんだ。後は培養して酒母に反映させるだけ。来年は父さん抜きでも酒を仕込めるようになるよ」哲夫が時計を用意しながら笑顔で答える。「それから、この菌を別のカビと相互作用させれば、味噌や醤油に替わる新しい調味料もつくれるかもしれない」
徹治が年一度の「仕事」を勤める交換条件として、哲夫を岳の酒蔵の研究員にさせたのだが、どうやら順調に成果をあげているようだ。本人も満足しているらしい。
「来年は、精米歩合三パーセントに挑戦するぞ。一升仕込むのにタワラマイが一俵要るから、名前は『米一俵』でどうだ」岳の声も明るい。酒の質が上がるにつれて、売れ行きの方もうなぎのぼりと聞く。
(しかしネーミングセンスの方は進歩がないな)
思っても口には出さない。皆が満足なら、それで良いと徹治は思う。よく考えると、単なる結果オーライという気もするが――まあ言うまい。
(それでも、一番得をしたのはおれかな)
哲夫のカウントに合わせて、右手を庇いながら半透明の液体に身を沈める。立ち泳ぎの要領で足を動かしながら、徹治はほくそえんだ。
(おかげで普段風呂に入らずにすむ大義名分ができたからな。そりゃそうさ。「糠床は洗っちゃいけない」)