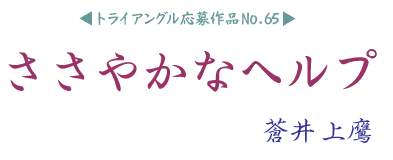
〈多々良浩介の場合〉
医師の横顔を見た多々良は、その若さに不安を覚えた。髭のないつるんとした顔に、無邪気そうな目。おそらく三十前だろう。
医師が椅子を回して、こちらへ向き直った。
「担当の新堂聡といいます。どうぞよろしく」
多々良は黙って頭を下げた。
「ご職業は」
「タクシーの運転手」
「今でも、ですか?」新堂の目は、多々良の真っ白な髪に向けられているようだ。
「そうだ」
「ご家族は」
「独りだ」いらいらした口調になっているのが自分でもわかる。結婚は一度もしていないし、親類もとうに亡くしたことなどは、予備質問の際に全て話してあるのだ。
そんな多々良の様子を見て、新堂は笑みを浮かべた。
「なんで同じことを何度も答えなきゃならないんだ、と思ってらっしゃいますね」
新堂はカルテを手に取った。
「ちゃんと予備質問は読ませていただきましたよ。ちなみに、ご相談の内容は『毎日が同じことの繰り返しで、何一つ思い出がない。生きてきたことが無意味に思えて、空しくて仕方がない』ですね」
「わかってるならさっさとなんとかしてくれ。医者は嫌いだが、ここは良いと仲間が言うから、義理で来たんだ。無理なら帰るから、はっきり言ってくれよ」新堂が何か言いかけたが、多々良は言葉を続けた。「おれは四十年以上運転手をやっている。今のおれの気持ちがわかるか? 四十年だぞ。先生が生まれる前からだ。毎日毎日同じような道ばかり走っていた。飽き飽きするのが当たり前だ」
「私もタクシーはたまに利用しますが、そんなときは、お客さんの噂話などで結構盛り上がりますよ」
「客とは話さない。みんな馬鹿か酔っ払いばかりだからな」
「きついことをおっしゃいますね」新堂はしばらく多々良の顔を見つめていたが、やがて表情を引き締めて口を開いた。
「多々良さんの気持ちがわかるかと訊かれましたね。確かに、私のような若輩者がわかると答えては嘘になります。しかし、私もこの仕事のプロです。多々良さんのような悩みを持つ方のお役にたてたことも何度もあります。今回もきっとうまくいくでしょう――ほんの少し、多々良さんに協力していただければ」
「協力?」
「人の心の中を、他人が勝手に変えるわけにはいかないのです。例えば、多々良さんの言う空しさを、消しゴムでこするように消してしまうことはできません」
「やっぱりな。ここに来れば楽になれると言う話だったが、あれは嘘か」
「嘘ではありません。この部屋を出る頃には、来る前の何倍も心が軽くなっているでしょう。でもそれは、半分は多々良さんご自身の力によるものです。その方法をお知りになりたいですか?」
多々良は黙ってうなずいた。なんとなく気圧されるものを感じ始めていた。
「多々良さんの人生は、空しくも無意味でもありません。今はただ、過去にあった様々なことが思い出せなくなっているだけです。今から、それを蘇らせるお手伝いをします」
新堂に促されて、多々良は立ち上がった。控えていた看護婦の案内で、今までカーテンで仕切られていた診察室の奥に入ると、寝心地の良さそうなベッドが据えられていた。
看護婦に言われるまま、多々良はベッドに横たわった。が、何か足らない。
「枕はないのか」
「ありますよ」新堂がベッドに歩み寄り、どこから取り出したのか、白い枕を多々良の頭の下に差し込んだ。スポンジともウレタンとも異なる不思議な感触で、ひんやりとしている。その心地よさに浸るうちに瞼が重くなり、視界がもやにつつまれたように霞んできた。
どこか遠くから、新堂の声が聞こえる。
「多々良さん、誰かお客さんのことを話していただけませんか? 誰でも構いません。最初に頭に浮かんだ人のことを」
「さっき言ったろ」客なんてみんな、と言いかけたとき、ある情景が浮かびあがってきた。
(ここはどこだ? 木の電信柱、丸い郵便ポストに赤電話、どれも今じゃ見かけないものばかりだ)
「すみません」助手席のドアをたたく音に、多々良は我に返った。仕事だ。ぼんやりしている場合ではない。
ドアを開けると、もこもこした灰色のかたまりが車内に飛び込んできた。
「城北大学までお願いします」乗ってきたのは学生らしい女の子だった。ここまで走ってきたのか、息を切らしている。
「城北大学? ここからだいぶありますよ。近くまで電車かバスで行ったほうが」
「間に合わないの。あと二十分で着かないと」
「二十分?」この時間帯の道路はかなり混む。普段なら、四十分でも足りないところだ。
多々良が渋ると、彼女は泣きそうになった。
「お願いします。入学試験なんです」
「そりゃ大変だ」多々良は弾かれたように身を起こし、クラッチレバーを握り締めた。
方向転換するとき、ミラーに自分の顔がちらと映った。帽子からはみ出ている髪は黒々としている。なぜだか違和感を覚えた。が、一瞬後にはそれも消える。
予想通り、車の量は多い。走り始めてすぐ、赤信号につかまった。
多々良は、横目で客の様子を観察した。初め灰色のかたまりと思ったのは、野暮ったいコートだった。赤い縁の眼鏡をかけ、長い髪をポニーテールにしている。鞄を胸に抱きしめ、腕時計と信号機とを交互に見ている。
「どうしてこんな見当違いのところにいるんですか」
「電車を間違えて」彼女は信号機から目を離さない。と、急に顔をくしゃくしゃにして、
「わたし駄目なんです。近眼で方向音痴で、肝心なときにへまばかりして」
「でも、城北大学って言えば名門だ。そこを受験するなんて優秀な証拠じゃないですか」
「間に合わなきゃ、その受験すらできません」
涙がこぼれ始めた。もう見ていられない。
「ああもう、わかったから泣かないで」言うなり多々良はハンドルを右に切った。
「どこへ行くんですか」
「黙って。舌噛んでも知らないよ」車の流れに強引に割り込み、そのまま横道に突っ込む。
この辺りの裏道は全て知り尽くしている。制限速度を無視すれば、何とか間に合うかもしれない。途中でパトカーに止められなければの話だが。
こんな無茶な運転は多々良も初めてだった。狭く曲がりくねった道を、ほとんどブレーキを踏まずに走り抜ける。大半が舗装されていない砂利道で、振動でものが二重に見え、手袋をはめていてもハンドルをとられそうになる。カーブを曲がるときに乗り上げたどぶ板が、タイヤの下で派手な音をたてた。
幸運だったのは、路上が無人だったことだ。警官はおろか歩行者が一人でもいたら、間違いなく事故を起こしていただろう。
大学の正門前に車が滑り込むのと、助手席のドアが開くのとがほぼ同時だった。
「急げ」
「あ、ありがとう」
彼女は転がるように外に出たかと思うと、酔っているかのように足元をふらつかせた。
「あと三分だ、走れ」多々良の声になんとか体勢を立て直し、入口に向かって駆けていく。それを見届けると、多々良は背もたれに倒れこんだ。今になって汗が吹き出してくる。窓を開けると、初春の風の冷たさが、むしろ快いほどだった。
頭が冷えるにつれて、現実が戻ってきた。
(いけね、金をもらってなかった)
参ったな立替かよと料金を確認しようとして、再び唖然とする。メーターは倒れたままだ。最初から立てるのを忘れていたのだ。
数秒後、北風の吹き込む車の中で、多々良は一人笑い転げていた。
「そっくりな話を聞いたことがあります」
話し終えた多々良がベッドから起き上がると、新堂は大きくうなずいた。
「そいつもただ乗りしたってか」
「いやいや。実は、私の母が入試に遅れそうになって、タクシーに助けてもらったことがあるんです。母は城北の医学部出身ですし――今の話、私の母のことじゃないでしょうね」
「それなら先生に立替分を払ってもらおうかな」そう言う多々良の口元はゆるんだままだ。
「ただ、母はそんなに方向音痴だったかな」新堂は考え込むように首を傾げた。多々良も今一度記憶を反芻しようとして――驚いた。断片的ではあるが、様々な人の顔が、仕草が、声が、頭の中に湧き上がってくる。まるで、今の話が呼び水となったかのように。
多々良は立ち上がった。
「これからゆっくり昔を思い出してみるよ。いくらでも話のタネが出てきそうだ」
「またお話を聞かせていただけますか」
「先生を乗せることがあったらな。ここにはもう来ない」憎まれ口をたたきながらも、退室するとき、多々良は深々と頭を下げた。
〈小菅麻耶の場合〉
「朝、目が覚めたら、あの子はいなくなってたんです。前の晩までなんともなかったのに」女は訴えた。
新堂聡は女のカルテを見直した。『小菅麻耶 二十二歳 女性』といった基本項目に続いて、妊娠十五週目に自宅で貧血を起こし倒れたこと、その際腹部を強打し、昏睡状態のままで流産したこと、流産の事実を認めることができず精神的に不安定な状態が続いていることなどが、医学用語で簡潔に書かれていた。
「体の調子はどうでした? 具合が悪いとか、いつもと違うと感じたことは?」
麻耶は考え込んだ。「いえ、特に思い当たりません」
「つわりは?」
「最初はかなりつらかったけど、アロマテラピーをいろいろ試したら、だいぶ楽になって」
頬がこけ、目に隈ができているのは、つわりや流産で体力を消耗したせいだろうか。
「お子さんの性別はご存知でしたか」
「知りません。生まれるのを楽しみに待とうって二人で決めたんです」
「二人?」
「かれ――夫とです」麻耶は口ごもったが、聡はそれ以上詮索しなかった。
それよりも問題なのは、麻耶が、まるで子供が迷子にでもなったかのように思い込んでいることだ。あたかも、家の周りを探せば、すぐに見つけて連れ戻せるかのように。
「あのう」麻耶の声に顔を上げると、思いつめた瞳が、聡のすぐ目の前にあった。
「なんでしょう」
「実は最近、よく夢を見るんです」
「最近というのは、お子さんが『いなく』なってからですか」
「その前からだったような気もします」
「ほう」何かの突破口になるかもしれない。「どんな夢か詳しく話していただけますか」
「言葉では言いにくいんですが」麻耶はぱさぱさの髪の毛をもどかしそうにかきあげた。「あたしの後ろに誰かいるんです。振り返ろうとしても体が動かないし、真っ暗で何も見えないのに、確かにいるのはわかるんです」
「その人は何か言いましたか」
「何かしゃべっている気配はします。でも、言葉は何も聞こえません」
「その人が誰だかわかりましたか」
「その時はわからなかったけど、今はなんとなく」
麻耶が言葉を切ったので、聡は目で続けるよう促した。
「……あの子じゃないかと思うんです。あの子、あたしに何か言おうとしてたんじゃないかな。でも聞こえなかった。なんで聞こえないんだろう。こんなにあたしは聞きたいのに。ねえ先生どうしてですか」
「興奮しないで」立ち上がった麻耶を再び座らせ、落ち着かせるために質問の方向を変える。今までの生い立ち、家族、仕事、趣味。会話を続けるうち、聡の頭の中で一つの解決案が形をとり始めた。
「ところで、お子さんのことですが」
十五分ほどたって、聡は話を戻した。
「子宮から胎児が消失したというケースは、私も初めてです。きっと何か特別なことが起こっているに違いありません」
「でも、他の病院では、体のほうはなんともないと……」
「違うやりかたを試してみましょう」
麻耶をベッドに寝かせ、頭の下に枕をあてがう。
「人間というのは私たちの想像以上に複雑微妙なものです。体に痕跡が残っていなくても、意識が何かを感じ取っている可能性があります。先ほど言われた夢の話もその一例です。その辺りをもう少し詳しく診てみましょう」
聡の柔らかい口調に、既に麻耶は半ば催眠状態に陥っていた。
……数十分後、麻耶は興奮しきっていた。両手は聡の白衣の袖を掴んで放さない。
「またあの子の夢を見ました。それが、今度ははっきり声が聞こえたんです。あの子言ってました。『今はダメ、もうちょっと待ってて』って。ほら、今不景気だし、あちこちで戦争は起こるし、生まれてきたって幸せになれるかどうかわからないでしょう? だから未来の、もっと良い時を探しに行くんだって」
「未来の『どこ』へ行ったのですか?」
「あたしのお腹の中にです」麻耶は微笑みながら臍の前で両手を組んだ。「知ってました? 子宮の奥に、時を越える抜け道のようなものがあるんだそうです。そこをつたって未来のあたしのお腹の中に行くって。考えてみれば当然よね。そういう道があるから、魂が赤ちゃんの体に入っていけるのよ」
「魂ですか、なるほど」聡はつぶやいた。
「先生、あたし、帰ります。あの子がまた来るまでに、準備しなきゃならないことがたくさんあるんです。急がないと」
麻耶は足早に診察室を出て行きかけたが、ドアを閉める直前に振り返り、聡に向かって晴れ晴れとした顔でもう一度笑った。
「『時を越える抜け道』ですか。すごい発想ですね」枕を取りあげながら看護婦が言った。
「やりすぎだったかな」聡は頭に手をやった。「潜在意識に残った流産の記憶を丸ごと消すのは無理だし、彼女に何とか前向きになってもらおうと、あんなイメージを与えたんだが、ただの逃げ道になりはしないか心配だな」
「彼女にはあの処置が必要だったと思います。いつまでもショックをひきずっているより、まずは未来に目を向けることが大事です」
「そう言ってくれると気が休まるよ」
「そういう気持で生きていけば、いつか真実を知っても、それと向き合えますよ。それに、将来生まれてくる彼女の子供が『あの子』の生まれ変わりでないと、誰が言えます?」
「君もロマンチックなことを言うね」聡は椅子の背にもたれた。窓の外は見事な夕焼けだ。「予約はあと何人残っている?」
「今日は以上です。お疲れさまでした」
(やれやれ、終わった)
全身が快い疲労感に満ちていた。聡は大きく伸びをして立ち上がり、先ほどまで患者たちが寝ていたベッドの上に大の字になった。
「新堂先生、そこは」看護婦が笑いを含んだ声でたしなめる。
「ちょっとだけだよ」聡は目を閉じた。
〈新堂聡の場合〉
「新堂さん」
低く温かい声に、彰子は目を開いた。
声の方へ顔を向けると、ベッドの傍らに、山羊髭の老医師が座っていた。
「うまくいきましたか? 聡はちゃんと……」あとは言葉にならない。
医師は安心させるように彰子の手をとった。
「全てうまくいきました。きっとお子さん――聡君も、自分の人生に満足していますよ」
「聡にどんな記憶を与えたんですか?」
「私と同じ職業についたことにしました」
医師は、聡が『担当』した患者たちについて簡単に説明した。老いたるタクシー運転手、若き母親、等々。
「よかった、みんな喜んでくれたみたいで」彰子はわが事のように言った。
「それは間違いありません」
「でも、本当にそんな人たちがいたんですか、先生が診た患者さんたちの中に? それとも、これも全部聡のために用意した作り話……」
医師は微笑むだけで、何も言わない。
「聡がお医者さんに」彰子の呟きは、半ば自分自身に向けられていた。
「不思議な気持ちです。妊娠したと知った時、この子は医者になるような気がしたから」
彰子は、昨日までかすかに膨らんでいた自分の下腹部に手を当てた。今はもう、そこを蹴り返してくるものはない。
「本当に医者になっていたら……いえ、医者でなくてもいい。ただ元気で育って……」
「そんなふうには考えないでください。聡君の意識には、自分が医者として立派に生きたという記憶が残ったはずです」
「そんなことが本当に可能なんでしょうか。まだ生まれてもいない赤ちゃんに、そんな複雑な記憶を与えることができるなんて」
「二十一週といえば、胎児の脳はかなり発達していますよ。少数ですが、似たような前例もあります。そうは言っても、確かに聡君の脳の発育は早かった。標準的な胎児の二十三〜四週に匹敵するほどでしたよ」
彰子は目をつぶった。医師はその手を軽くたたいた。
「とにかく、今はご自分の体を治すことが先決です」
彰子の身体に異常が見つかったのは、一ヶ月前のことだった。早めに手を打てば治療可能だが、そのためには胎児を犠牲にしなければならない。彰子たちは悩んだ。既に聡という名前までつけたこの命を失うことに耐えられなかったのだ。子供自身の体には何の問題もないことが、余計に決断を難しくさせた。
人間に架空の記憶を植えつける『手術』があると聞いたのは、そんなときだ。
(生まれてこれないのなら、ささやかな埋め合わせとして、生きたという記憶だけでも与えてやりたい)
ただしそのためには、脳が発達して意識を持つようになるまで待たなければならない。
何度も夫と話し合った後、彰子はこの病院を訪れた。入念な検査を経て、ついに『手術』に踏み切ったのは、妊娠二十一週、つまり、中絶が認められるぎりぎりの時期だった。
「……あの、夫は?」
「待合室でお待ちですよ。お呼びしましょうか」
「お願いします。それから」
彰子は身を起こし、医師の目を真っ直ぐに見た。
「もう一度あの人の前で話してやっていただけますか。聡がどう生きたかを」