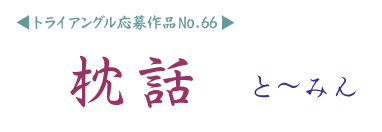
藤本は大学の構内を早足で行く。居並ぶ木々がみんな桜だったことを認識させられた花見の季節はもうとっくに終っていた。先日はつつじの茂みが自己主張をしていたけれど、それもいつしか消え失せていた。今はどんよりと低い曇り空を背景に緑の葉がしみいるような濃い色をたたえているだけだ。
雨はまだ降らない。ただ、もうすぐだという空気の危機感が額に汗をしみださせる。思わず拭った生え際のぬめりが気持ち悪いと藤本は思った。尻に手の甲をこすりつける。
唐突に擦り切れたジーンズは動きをとめる。食堂は昼の混雑を越した後で席にはまばらにしか人がいない。だというのに、開けはなされた入り口から漂う熱気にうんざりしたのだ。軽く肩をすくめ、藤本は踵を返そうとした。
また動きが止まる。藤本の目にガラス窓の向こうの見るだけで暑苦しいグレーのスーツを着こんだ男が映っている。ノートに何かを書き込んでいるようだった。彼は潮河雅直、友人だった。もっとも潮河が藤本を友人と思っているかどうかについては定かではなかったが。
藤本は潮河の背後に立って、ノートを覗き込もうとした。気配に気づいた潮河は、ぱたんと閉じて振り返った。藤本の目には閉じる寸前に一言「消失した女」と読めただけだった。
「よぉ」
椅子の背に深くもたれて潮河は言う。藤本と同じ23歳だが、こうやってスーツに身を包んでいる姿を見ると落ち着き過ぎていていくつか年長のようにも見える。顔の老け具合なら負けない自信はあるのだがと、藤本はこの二日剃っていない無精ひげを思った。
近づいてみても汗一つかいていないようだ。こういう奴は体のつくりから違っているのかもしれないと考える。口にしたのは別のことだった。
「お前が、就活か?」
潮河が大学院に進むと思っていたわけではなかった。だが、単に型どおりの就職活動が意外なような気がしたのだ。スーツが似合っていないわけではない。就職活動をしている学生一般よりもなじんでいるといえる。その変に似合う感じが、きっと違和感をもたらすのだと藤本は思った。潮河は白い歯を見せた。その表情は、目が細まって皮肉っぽい印象を与える。
「お前も就活中だろ」
言われて藤本は傍らの椅子に脱力したように腰を落していた。触れられたくない話題だった。六月も中旬、この時期になっても内定は一つも出ていない。何社受けたのかすら数えるのが面倒で、次がいつかと先ばかりが気になっていた。フキョウだの、キビシイだの言われているのを耳にしても、去年の今ごろは素知らぬ顔でバイトに明け暮れていたというのに。口元に寂しい笑みが浮ぶ。
その現実から逃避するために藤本はこの日、学内をうろうろして若い空気を吸っていたのだった。しかし、話を振ったのは自分の方だから、本当は誰かに就職活動の愚痴をこぼしたかったのかもしれない。とくにまだ決まっていない相手なら互いの傷をなめ合って多少は気分が晴れることもあるだろう。
「何が悪いんだろうな。一次試験っていえば一般常識みたいなもんだろ。そこで軒並み落されると、お前なんか必要ないって言われてるみたいで嫌になるな」
苦い顔をして藤本はつぶやいた。潮河は脇にあった黒い鞄を探っていた。取り出したのは厚い本だ。一次試験対策という文字とどこかで見たことがあるようなカラフルな絵柄が見えた。就職活動にも受験のように試験対策グッズが必要なのだと知ったのはこの二ヶ月くらいのことだ。潮河がとりだした問題集も藤本が先月買ったものと同じくらいまだ新しい堅さがある。指がページをめくる。
「相当と同じ意味の言葉は?」
開いたページの問題を出しているのだろう。潮河の女のような細長い指がとんとんと青いノートをつついている。
「相応」
間を置かず答えると、潮河は軽くうなずいて、次を読む。
「金言を別の言葉で言うと?」
「格言」
藤本はその問題集が自分のもっているものと全く同じだということに気づいていた。おかげであっさり答えが出せる。本番もこんな風に同じ問題が出てくれればいいのだが。
「そうだな、それじゃ」
余裕のある表情を見てとったのか、潮河はページを飛ばした。終わり三分の一辺りを開く。机に少し押さえてかたをつける。その辺りになると少し不安だ。
「空箱、可能性、虚無。この三つの言葉に共通しているのは?」
眉をひそめた。思い出せない。
「空箱と可能性と虚無・・・・・・」
藤本は首の後ろを掻いた。爪がぬれるような嫌な感じに思わず手を引っ込める。汗は冷めていた。広い食堂にただ一つの冷房がそよかに風をおくってきていた。ベストポジションだと今更ながらに気づいた。いや、そんなことはどうでもいい。何だっただろう。苛立ちが押さえ切れなくなった藤本は問題集を奪って、開いているページに目を通す。
「そんな問題、どこにある?」
ページは模擬試験の問題だった。藤本も何度か解いてみたところだ。そんな形式の問題はない。言葉自体出てきていない。藤本はむっとした。潮河は人を馬鹿にしている。そうだった。初めからこの男に愚痴を吐き出して気分を楽にしようと思ったのが間違いだった。睨んで立ち上がろうとした。
「ここさ」
そう言って潮河がばんと手をおいたのは、ノートの表紙だった。浮かしかけた腰をもう一度据え直して、藤本は思い出していた。そのノートは。
「お前就活、やっぱりまじめにやる気ないだろ」
「やる気はあるが、演劇も俺にとっては同じくらい人生において重要だと気づいてね」
ため息交じりに言うと潮河の表情はなんだか疲れているように見えた。そのノートは藤本が昔から演劇の脚本のネタを書き込んでいるノートだった。俺と他数名が、行動をそのネタ帳に書き込まれたことがあるらしいという噂だ。実際にはノートの中身は見せてもらえないし、演劇を見に行く趣味もなかったから知らない。
「で、答えは?」
「答え?」
「空箱だか虚無だか可能性だかの共通点。哲学みたいな眠くなる話なのか、それとも全部ローマ字で書けばKから始まるとか?」
さっさと立ち去ろうと思っていた藤本は思い直していた。クイズの答えは聞いておかないときっと後で気になって仕方がなくなる。
「ああ、なるほどそんなところが同じだったのか。それは気づかなかったな」
潮河はあっさりとつぶやいた。顔はいつものすました表情に戻っている。疲れて見えたのは目の錯覚だったのか。ふと藤本の頭に閃いた。
「消失した女って何だ? ミステリーか?」
ノートで唯一読めた文。潮河の目が縦方向に広げられた。
「読んでいたのか?」
トーンの下がった不機嫌な声。潮河をむっとさせるのに成功したらしい。
「いや、そこだけつい目に入っただけだ。それも関係あるんだろ?」
気をよくした藤本は、つけたすように言った。潮河の一瞬とがっていた口はすぐに元の平らな感じにならされる。横に一本ひいた唇。潮河の髪はさらりとしていて、細い。女みたいだと言えば今度こそ本気で怒るだろうか。
「仕方がないな、話の枕に聞いていくか?」
声の高さも元に戻っていた。
「枕?」
「ああ、そうだ。枕さ。消え失せてしまった女達の話は」
にやりと笑ったように見えた。潮河の話は、基本的に妙だ。中華料理と聞けば朱文字の看板を思うのはなぜか、ファミレスのハンバーグの横のコーンの不必要性とか、許せないのはむしろトマトの食感だとか、どうしようもないことで盛り上がった記憶がある。潮河の演劇の評判は耳にしないが、確かにそういうのが芸術家めいているというのかもしれない。
「そう、それは、中国の漢王朝末期の話だ」
潮河はノートを開いて話し始める。三国志の魏が立つ直前頃の時代設定だと言う。
皇帝には妃が五十人いた。皆、若く美しい娘達だった。女達は皇帝や高官の宴の度に舞を舞うのが一番表立った仕事だった。
その時期国は滅びようとしていた。王朝の力は日に日に弱まり、籠の鳥のように王宮の奥深くにかくまわれている妃たちの耳にもその衰退の足音は聞こえていた。皇帝は王朝の力を誇示すべく、大々的な宴を披くことにした。有力な豪族、各家の人々を招いて、見事な舞を見せようということになった。皇帝直々の命が李陵という男に下った。皇帝の権威を見せ付ける、すばらしい演出を考えださねばならなくなった。
「李陵は今で言うプロデューサとか演出家のような役割だ」
ひらひらとした様々な色彩の布を纏い妃たちは手足をのばす。舞上手がそろっている集団で、彼女らには若さもあった。他の妃たちに負けまいとする意欲があった。李は懸命に指導し、舞は華やぎと権威を漂わせ始める。
「彼は、皇帝万歳、天下泰平、など縁起のいい四語を音楽に合わせて形づくることにした」
李はそこで一人の妃に恋をする。五十人の皇帝の寵愛を受ける妃たちは皆地方に帰ればとても権力をもった家の娘たちである。皇帝の妃となれば一般人は目に触れることもなく、高官でも見て愛でるだけの高嶺の花。そんな花の一片が、敏腕の演出家を誘惑したのだ。
「李陵さま。あなたは、とてもお優しい」
舞の動きを指導しようと通りかかった時、女は李陵の肩に手をかけた。もたれかかるようにして耳元にささやいた。香りが鼻腔をくすぐった。李は、芸術家だった。美しいものが好きだった。美しく凛としている。その妃は蓮という。
「外庭で練習したいと、妾たちは申しておりますのに」
蓮の企みを、李は知らなかった。ただ、強い意志が瞳から伝わって来た。言われるままに、外庭を人払いして本番のように通し稽古を行うことにした。妃たちの舞の稽古場には李しか男は入れない。それを利用したのだろう。後は女官か宦官か、何にせよ少数の護衛。着替えを手伝う者達に、布や道具を運ぶもの。李が見るのは妃たちの動きだけである。たくさんの兵士は外で待機しているが、蓮はどうやってかその配置も把握していたらしい。
そう、本番さながらの外庭での舞が終った後、残っていたのは半数以下の妃達だった。消失した女は二十七人。
「私が謀ったことでございますから」
蓮はいた。李の間近に歩みより、また耳元に言葉をおいた。彼女は王宮にただよっている亡国の兆しを感じとっているという。そして、蓮は妃達のうちの年若い者を故郷に帰したのだと言った。
「無断で?」
「陛下はこの宴が成功いたしさえすれば、妾たちが何人いようかなど数えることはいたしませんでしょうから。顔も名前も覚えていてはくれませんのよ」
蓮はくすりと笑う。そんな表情を見るとまだあどけなくも見える。李の動悸は激しくなった。
「李さまなら、残ったものたちだけでも、十分に華やかにできますでしょう?」
舞うように軽やかに歩む女の大きな瞳が李を見ていた。
「空箱、可能性、虚無か。あまりいい言葉が浮ばないな」
李はつぶやいた。彼の頭は半分以下の人数になった妃達で舞う演目を考え始めていた。物語調にストーリーを追った展開で、所々に言葉を形作る。高台から観覧するので、あまり細かいことはできないのだ。
「そうだな、パンドラの箱をあけて様々な悪いモノたちが飛び出していったあと、空箱の中には虚無が訪れる。しかしその後、人はその中に可能性を見出したと……」
「潮河、お前ちゃんと考えてるのか?」
とうとう耐え切れず、藤本は声を挟んでしまった。途中まではノートを読んでいるように見せかけていたが、何時の間にかあらぬ方を見上げて物語っていた。夢見ごこちの視線がやっと我に返って藤本に向けられる。
「ああ、そうか、漢王朝は古すぎたか」
「あ?」
唖然とする藤本に、潮河は首を傾けた。目線の先、窓の外ではいつのまにか雨が降り始めていた。
「まっ、枕話だからな、何事も大目に見てくれ」
「あのな、パンドラの箱はないだろ、中国漢の時代にパンドラの箱は」
「なるほど」
うなずきながら、潮河は口元を覆った。傘をさした集団が、窓の外を走っているのが見える。もう授業が終る時間になっていた。もうすぐ、この食堂は湿っぽい匂いの漂う学生がたまりはじめるだろう。
「それに、何も結局説明していないじゃないか。空箱と虚無と可能性の共通点には触れてない。思い出したようにつけたしやがって。はじめからノートの中身を教えるつもりはなかったんだろ」
藤本は人が増えはじめる前に、食堂を出ようと考えはじめていた。話にけりをつけようと思っていると、潮河が立ち上がった。ノートと本を鞄につめる。
「だから、はじめから枕だといっているだろ」
潮河の顔が笑っているように見えた。眼球が落ち着き無く動いている。
「え?」
「そういえば、お前の名前は、藤本だったよな。これも同じだ。よかったな」
立ち上がろうとしていた藤本は思わずバランスをくずして、椅子に戻ってしまった。呆れた声が漏れる。
「俺の名前を確認するのは何度目だよ」
潮河には最近、顔を合わせるたびに名前を確認されている気がする。大学、いやその前の浪人時代からの知り合いだというのにたまにこんな風に聞かれることがある。毎日のように会っていた時はともかく、二三日たつと記憶があやふやになるのだといっていた。名前とはもう少し気軽に呼び合うのが友人ではないかと思うと、やはり潮河に友人と思われているのかどうか不安になる。
「間違って呼ぶよりはましだろ。これだって、話の枕になる」
潮河は悪びれない。
「だから、枕枕って何なんだ?」
「枕詞と同じだ。たらちねといえば母だ。俺は母よりもたらちねって言葉に心ひかれる。枕詞に意味はあまりないらしい。関連もいまいち良く分からない。しかし、たらちねといえば、母だ」
きっぱりといいきる。そんなに熱く語るようなことには思えないが、潮河にとっては重要なことなのだろう。
「だから何だ?」
「ようするに、ここまで一生懸命枕話を並べても意味なんてない。いや、多少は込めてみたけど、イマイチだったな」
藤本は立ち上がる。意味が分からない男だ。潮河がこんな奴だということは最初から分かっていた。そう、一言で言えば奇妙な奴だ。
「俺の就活に可能性があるってことか?」
藤本はつぶやいてみた。潮河は驚いたように目を丸めて、今度は唇をゆがめて笑った。
「そんなふうにも考えられるな。無駄話をしたかいがあった」
「何がいいたい?」
潮河は傘を手にとり、さっさと歩きはじめた。藤本は肩をつかんで振り向かせた。どうも最近蒸し暑くて、その上就職活動のストレスだかで気が短くなっているようだと、思い付いた。それでも、不機嫌な声は変えられない。
「23画っていう画数は、悪くないらしい。それがつまらない本題ってとこだ」
潮河は笑顔で答えた。藤本の手を振りきって、歩き出す。傘をさして雨の中を歩く。背筋が伸びているので、スーツが似合うのかもしれない。ひらひらと振る手首にやけに大き目の腕時計が光っていた。
「藤本、ね。あとは空箱に可能性に虚無も同じ、か」
確かにどれもちょうど23画である。共通点というのはこれのことだったのだ。つまらない。だがやっと納得はした。食堂を出ようとして藤本は立ち止まる。
「傘」
椅子の背にかけてあったはずだった。振り返って、だが、消え失せている。そうして気が付いた。そう潮河が今、まるで我が物顔でさして行った傘が自分のものだと。
「まったくあいつは……」
潮河はきっと今度会ったときに平然と返してくるのだろう。そういえば、以前にもこんなことがあった気がする。持つべきものは友人だと、その時しれと言っていた。そうだそれであんな奴を友人と認識してしまったのだ。向かいから傘を閉じながら五六人の学生が入ってくる。傘がぶつかって腕に水の感触がした。不愉快だ。舌打ちをしながら、ふと思い付いて宙に書く。
「潮河も、23画か。良いとはいえないな」
しとしとと降る雨を眼前に眺めながら藤本はつぶやいた。手にはいつのまにか乾いた首筋がふれる。