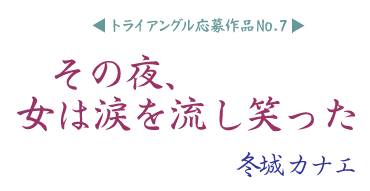
わたしは甚だ不機嫌だった。
直に頬が当たっているコンクリートの床は冷たいし、下の方になっている右足が変な方向にねじれていて、筋が痛くてしょうがない。
文句を言いたいけれど、口にはシーツの切れ端を突っ込まれている。
ただわたしの心を和ませてくれるのは両腕にしっかりと抱えた愛用のまくらだけ。まくらを抱えパジャマ姿のまま、縄でぐるぐる巻きに縛られているわたしは相当マヌケに見えるだろうが、見知らぬ男どもに寝込みを襲われ善戦した結果だ。その辺は大目に見て欲しい。
「……マジですか?」
薄暗い方、数メートル先にぼうっと立っていた影が言葉を発した。影は二つ。ここは工場跡地か何かなのだろう。その若い男の声はほんの少しのエコーがかかってわたしの耳に届いた。
「おう、マジよ」
返すもう一人の声は40代男性・ヤニの匂い付き。といったところ。
「殺れってさ。トシ坊はそういうつもりでこの女ァ連れてこさせたみたいだぜ」
「俺らがやるんですか?」
「そういうことらしい」
男二人は、とりあえずといった感じで側に近寄ってきた。
わたしはキッと鋭い目を二人に向ける。男たちは、顔を目出し帽で隠してはいなかった。
若い方の男は、紺色の作業服のようなものを着ていて髪は茶色。眉はなぜか絶えずハの字型であまり頼りがいのなさそうなタイプだ。
オヤジの方は、小太りの身体を白い線の入った黒ジャージで包んでいる。無精ひげに水色のレイバンのサングラス。
「まあいろいろ経験になるしよ。フミオ、お前がやれよ」
黒ジャージの方が困ったようにわたしから相方に視線をそらし言った。
「い、いやっスよ。なんで俺が」
眉毛ハの字のフミオも、怯えたように相方へと視線を返す。
「こないだのマージャンで買った3万円をチャラにしてあげますから、やってくださいよ」
「なんだと! だったら今すぐ3万円払って返すよ」
黒ジャージは尻のポケットから財布を出そうとする。フミオは慌ててそれを押しとどめて、今お釣りが出ないからとか、財布がないから受けとれないとか騒ぎ出す。黒ジャージはムリヤリ金を渡そうとする。わたしは呆れて咳払いでもしたい気分になった。
「だって、かわいそうじゃないですか」
やがてフミオが言った。
「彼女、台湾かどっかから来たんでしょ。せっかく日本で金持ちの旦那見つけて幸せに暮らしてたのに」
「そりゃ俺らにゃ関係ねぇだろ」
黒ジャージはポケットに手を突っ込んで続けた。「だいたい旦那は、もう死んじまったじゃねえか。あの世で一緒に暮らさせてやった方がむしろ幸せなんでねえの」
そうか。
わたしは心の中で嘆息した。──襲われた時、わたしを目覚めさせ、崩れるように倒れた夫の姿が脳裏をよぎった。彼はそのまま二度と起き上がらなかった。
あの時、夫はすでに死んでいたのだ。
わたしは悲しみというよりも、何か形容できない感情に捕らわれた。
わたしは台湾で生まれた。母親が日本人であったからどちらの国でも言葉には不自由していない。死んだ夫は、ヒラカワという靴メーカーの社長だった。会社が台湾に工場を作った関係でわたしは彼と知り合い、日本に渡った。二十歳の時だ。
あれから三年経っているが、結婚したのはわずか半年前。なかなか結婚しなかったその理由は、わたしが結婚を拒み続けたからだ。わたしは彼のことを愛してはいなかったし、彼の金を自由に使えることだけで満足していたから。
彼はそのことに気づいて、わたしをまともな人間にしようとした。十二才も年下のわたしと強引に結婚したのもその結果だ。同情心や優しさなど、その辺の野良犬にでもくれてやる方がまだマシだというのに。
「仕方ねぇ」
そろり、と黒ジャージがポケットから何かを取り出した。拳銃だった。ほれ、と隣のフミオにそれを渡そうとする。
「ちょうどまくら抱きかかえてやがるし、それに押し当てて引き金引けば、そんな大きな音は出ねえからさ」
「ホントに、マジ勘弁してくださいよ」
「よし、じゃあコレで決めよう」
黒ジャージはもう一方のポケットから一枚のコインを取り出した。十円玉だった。
「表が出たら、俺がやる。裏が出たら、お前がやる。──それでいいだろ?」
「はあ……」
納得していないフミオを尻目に黒ジャージはピンッとコインを弾いて手の甲で受け取りパッと開く。それを覗き込んだフミオは安堵したような表情を浮かべた。
「あっ、これ表っスよね」
「バーカ、知らねえのか? この建物が書いてある方が裏だろうがよ」
「えっ、そうでしたッけ?」
「うるせえな、ガタガタ言うなよ。男らしくねえぞ」
黒ジャージはフミオに押し付けるように拳銃を渡した。自分の手から銃が離れると、黒ジャージはホッとした様子でフミオからも離れる。
そのまま清々としたように、俺は向こうにいるからと言い残し、足早に闇の中へと歩いて行ってしまった。
その足音が聞こえなくなると、フミオは大きなため息をついて、拳銃を手にわたしの前にしゃがみ込んだ。
これ以上はないというくらい、困った表情を浮かべている。
やがてフミオは、いきなりコンクリートの床の上に正座し、両手を前に付いてわたしに頭を下げた。
「ごめんなさい! 旦那さん殺しちゃってごめんなさい。それから化けて出ないで下さい。俺ほんと幽霊ダメなんです!」
バカかコイツは。
“化ケテ出テヤル!”。わたしは腹いせに叫んでやった。ただし結果はムガムガと唸るだけ。
「えっ? 何?」
フミオは顔を上げこちらを見た。だからまた言ってやった。“死ンジマエ、コノ、フニャチン野郎!”
彼は目をパチパチやると、周りを見回してから、そーっとわたしの方に手を伸ばした。口に詰められたシーツの切れ端を摘む。
「これ、取ってあげるけど、大きな声出すと撃っちゃうからな」
念を押すように言うと、わたしの唾液だらけの布切れを引っ張りだす。
それだけでも開放感があった。新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んでいると、フミオが慌てたように銃を向けてきた。わたしはウッと息を止め、ゆっくり吐いた。
「なあ、日本語喋れるよな」
「まあね」
「名前は、なんていうの?」
「玉玲(ユーリン)よ。日本名は玲子」
大きな声を出さないという約束は守ってやることにした。とりあえずは。
「ごめんな、玲子さん。俺らのリーダーがあんたに顔を見られたから、殺せっていうんだ」
「あっそう」
わたしは片眉を上げてフミオを見、続けて言った。
「それでアンタたち、ウチからいくら盗ったの?」
「エッ? ──金庫の中身とか、宝石とか、いろいろかな? アン時、俺はあんた縛ってたし、その……」
縛られた女からそんなことを聞かれるとは思っていなかったのだろう。叫んだりせず冷静に問い掛けてくるわたしに、フミオは戸惑ったように拳銃を下げ、しどろもどろに答えた。
「それじゃほんとにあんたたちはただの強盗なのね。それで平川を殺して、わたしには顔を見られたから連れてきたと」
「そう、です」
うなづいたフミオはまた頭をがくりと下げた。すんません、とまた言った。
「ねえ、あのさ」
わたしは少し口調を変えて言った。「幽霊怖いんだったら、化けて出ないであげてもいいよ」
「ホント?」
コイツは本物の馬鹿だ。
「その代わり、ちょっと縄ゆるめてくれない? 手とかスゴく痛いの」
「そっ、それはダメだよ」
馬鹿にも分別はあるようだ。
「わたしね、平川と一生添い遂げるつもりだったの。でも彼、死んじゃったから、わたしもう生きていけない。殺されてもいい。──だからせめて痛くないようにして欲しいの。お願い」
とりあえずそう言ってみた。もちろん口から出まかせだ。
なのに、フミオはじっとわたしの顔を見下ろした。その目が潤み始め、じわりと涙が溜まってくる。
「ごめんよ、俺、ホントに殺す気はなかったんだ。けど、アンタの旦那さんが殴りかかってきたから、怖くなって」
フミオはごしごしと袖で涙をぬぐった。
「アンタの旦那さんは、最後までアンタのこと──」
──守ろうとしてた。
フミオは涙ぐみながら言った。
ちくりと何かに刺されたように心が痛んだ。彼がわたしのことを──。
だが、すぐにわたしは激しい怒りにとらわれた。おとなしくしていればあの男は殺されなかったのだ。殺した男も馬鹿だが、平川はもっと馬鹿だ。わたしを守るなどという、そんなくだらないことに気を回してあの男は死んだのだ。
わたしが黙っていると、フミオは鼻をグズクズ言わせながら、本当にわたしの縄をゆるめてくれた。
「……フミオ?」
その時、暗闇の方から知らない男の声がした。
「殺ったのか?」
声はフミオと同じか、それよりも若いぐらいだった。
フミオは驚いて振り返り、立ち上がる。
「いや、ごめん。まだ……」
「何やってんだよ!」
叱咤する声は先ほどの黒ジャージのものだ。暗がりに見えてきていた二人の影のうち、片方が歩を止めた。おそらくコイツがリーダーだ。
「お前ホントに意気地がねえなあ。よく強盗が勤まるよ」
「俺は鍵開け専門っスよ!」
怒ったように言い返すフミオ。彼はつかつかと二人の方に歩いていき、黒ジャージとてんやわんやの言い争いになる。
「クソ。拉致があかねえ。銃を貸せ」
やがて、ぼそりと言ったのはリーダーの男だった。口論をしていた二人は、ふっと押し黙った。そして、どちらかがリーダーに銃を手渡したようだ。
静寂の中、一人の男がゆっくりとこちらへ歩いてくる。
わたしの視界に入ってきたのは、驚いたことに高校生ぐらいの少年だった。黒いセーターにジーパン。手には銃を。白地に赤いラインの入ったスニーカーを履いている。
彼は冷たい目でわたしをただ無言で見下ろした。
だが、銃を向けられるその前に、わたしは彼に向かって言った。
「あんたの履いてるその靴、ヒラカワのスニーカーね」
何? と少年が目を細めた瞬間、わたしは動いた。
右手でまくらを縄から引き抜いて彼に投げつける。突然のことに少年はバランスを崩し、弾かれた銃が床を滑っていった。
「何を!」
少年は慌て、わたしを足で踏みつけようとする。わたしは転がってそれをかわし、ついでに縄から上半身を抜く。次に少年が蹴りつけようとするのも避けて、手を使って下半身の縄も外して立ち上がった。
今のわたしは寝込みではない。もう不覚はとらない。
この平川の靴を履いた少年が、平川の家を襲うことを思いついたのだろう。
わたしも夫が作った靴を履いていた。いつも。だが今は履いていない。裸足のわたしは腰をわずかに落とし、両腕を前と後ろに開いて構えをとる。
日本人の彼らにはわたしが何の武術を習得しているか分かるまい。
わたしの動きに驚いていたリーダーの少年も、拳を握り構えをとった。ボクシングか、空手か。
少年が動いた。間合いをつめて、右足の蹴りを放ってきた。力強くそして素早い蹴りだった。
だが所詮は素人の動きだ。わたしはただ一歩前に踏み出して右腕を伸ばし、肘でその足の膝を極め、払いのけるように威力を後ろへ逃がした。そのままもう一歩踏み出して少年の死角に入り込むと、ガラ空きの脇腹に拳を叩き込む。
右足を上げたままで脇腹に一撃を食らった彼はバランスを崩し、床に倒れこんだ。
少年は目を見開いてすぐ立ち上がった。そのまま叫びながらわたしに向かってきた。今までケンカに負けた屈辱を味わったことがないのかもしれない。拳を振り上げ走りこんでくる。
剛を制するは柔だ。本物の太極拳は健康のための踊りではない。相手の拳を横へひょいと避け、わたしは両腕を揃えて上げ、彼の突き出された腕の肘に振り下ろした。拳の威力が下に変わり、前かがみになった少年の腹部に、わたしは膝の蹴りを合わせてやる。もちろん氣を十分に込めて。
少年は腹を押さえ、腹に入っていたものを吐き出しながら床に倒れた。
「ひぃぇー」
その時、間抜けな声をあげて、わたしの背後から飛びかかってきたものが居た。振り返りざまに氣を込めた肘を叩き込んで、倒れたところを見下ろした。そいつは黒ジャージだった。腹を押え、ウンウンと唸りだす。
残るはただ一人。
視線をめぐらせ、わたしは銃を手にカタカタと震えるフミオの姿を見つけた。
「う、撃つぞ」
わたしは身体をほぐすように肩を上下させて、首を回して骨をポキポキと鳴らせた。ブラジャーの肩紐が下がっていたのを元に戻して、パジャマの襟をきちんと直した。フニャチンに銃を向けられたところで怖くなどなんともない。
「あんた鍵開け専門なんでしょ?」
尋ねると、フミオは答えられずただ震えているだけだった。
仕方ない。わたしは彼にゆっくりと近寄った。
「来るな!」
「わたしと一緒に組みましょうよ」
「──え?」
フミオは、また目をパチパチとやった。銃口がふっと下がる。
「あんた、いくつ?」
「に、にじゅうに」
「そう。わたしは23よ。一つわたしの方がお姐さんね」
──可愛がってあげる。
そう、告げた言葉がフミオの手から銃を落とした。
「でも、俺、あんたの旦那さんを……」
「いいのよ、そのことは。ただし、ウチから盗ったものはちゃんと返してね」
用を済ませたら、なるべく早くこの場を後にしようと決めた。
フミオの手を取ると、少し温かった。その温もりが引き金になって、わたしはまたあの馬鹿な男のことを思い出した。
死ななくてもいいのに、死んだ男。
わたしのような女を愛した馬鹿な男。
くだらない。
わたしは頭を振った。平川に近寄ったのは彼の金が欲しかったから。わたしが男に近寄るときは金が欲しいときだけ。わたしはずっとそうして生きてきた。
平川が死ねば、わたしはただの玉玲に戻る。何にも囚われないただの女に。
バカバカしい感傷は捨てよう。
平川玲子はこの世から消失するのだ。今日限りで。跡形もなく。
「ごめん、さよなら」
フミオが言った。それは床に倒れた仲間たちへの投げかけ。
その言葉に、我に返ったわたしは吹き出すように笑い出した。
「どうしたの?」
何がおかしいのか彼には分からないのだろう。
そのままわたしは笑い続けた。声を上げて笑った。涙が出てきてとめどなく流れたが、それでも笑い続けた。
ひとしきり笑った後、わたしはまたフミオの手を引いてポツリと呟いた。
「──再 会(ツァイホイ)」