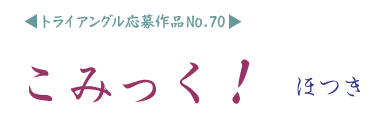
「──サン……ニー……イチ──」
──ゼロッ!
キョースケが唇でカタチつくる一瞬の前に、ガッシャーンッ! 第二理科室と理科準備室とを隔てていた扉は開かれた。それはもう、おもいっきり。力強く。
「はーい、29分59秒。ぎりぎりセぇーぃフ。ごっくろーさんッ」
腕時計のタイマーを消して、にっこりと、肩でハアハア息をしているアズサに微笑みかけるキョースケ。とてもではないが広いとは言いがたいこちら理科準備室内で、唯一の窓から射し込まれる陽の光を大量に浴びながら、何に使用されているのであろうか何にも使用などされていないのであろう準備室然とした、色気のない卓上でごろん、太陽に制服の上は脱がされてYシャツ姿の彼は寝転がっていた。
「ま、毎度あり……」
およそ30分間にも及ぶ全力疾走からなる急激な疲労により、その頭(こうべ)を垂れつつも、上目遣いにキョースケを睨む小林アズサ21歳独身は流石、前年度の町内デリバリーサービス選手権優勝者。目許に殺気をたずさえながらも、どこか笑顔だ。要因は、口許か? それとも頬か? 素晴らしいの一言に尽きる営業スマイルである。
「…………」
「…………」
「…………」
そしてそれからの6秒間。ハアハアと荒い彼女の息遣い以外は何も音のない、たっぷりのこの沈黙は、これが大会ならば少々の減点である。
本来ならば、指定の場所に到着後すぐ、お運びした商品の名を告げて、お客様にご注文との相違がないかを確認。それが済み次第、お代を要求し、受け取ったお代とほぼ交換に、「お熱いうちに」と手にある商品──ピザ屋の長女である彼女の場合はもちろん、ピザを、お渡ししなければならないのだ。
「すぅ〜……」
と、沈黙の6秒後。大きく息を吸った彼女は、
「……はぁ〜」
しっかりと吸い込んだ息の全てを吐き出し、すぅッ、と鋭くもう一度、短く息を吸い込むと、
「マッシュルームにオニオン、ピーマン、スウィートコーンにフレッシュトマトの、ベジタリアンピザ、9インチがお一つと、ベーコン、えのきにしめじ、マッシュルームと、焼き上がり後に焼きのりをトッピングいたしました、きのこスペシャル、こちらも9インチがお一つ。ご注文は以上の二品でよろしいでしょうか?」
早口に、けれどもハキハキとしていて歯切れの良い口調で聞き取りの易い声をあげた。
つい今しがたまで、目許にがっしり住み着いていた殺気はどこへやら。満面の笑みの彼女だったが、その、くどいほどにバカ丁寧な商品説明はもちろん本来は不必要なもので、彼女も、これが普段ならば口になどはしていない。それは、沈黙の間中ずっと、涼しげな笑顔で憎らしすぎるキョースケを、このままでいれば殺してしまいかねないと考えたアズサが、プロに徹する事により、自分はただの宅配人であり彼はただのその客である、と強く強く意識した結果であった。
「はいはい。よろしいですよ〜っと。──リン君、お財布。──で、おいくら? お姉さん」
最悪、お昼ご飯が抜きになってしまうかもしれないというリスクを背負いつつも、到着時刻まで計算し四時限中にピザのデリバリーを頼んでいるキョースケにはもちろん、それは面白くない。わかりやすく拗ねがら、彼は、寝転がせていたその身を起こした。
「消費税含みまして、2992円でございます」
「──だってさ」
唇を尖らせるキョースケ。彼が起き上がった事により、卓上に座らされ、伸ばしていた脚をまくら代わりにされていたリンは開放された。お役御免とばかりにため息を一つつきながら、彼は卓上から降り、折り目正しくたたまれていたキョースケの制服の内側にあるポケットから黒い色した財布を取り出す。
「はい。3000と、2円。お預かりいたします」
物憂げな表情を地としている割には、可愛らしく几帳面なキョースケの幼馴染。彼の名前は斎藤リン。
「10円のお返しね」
と、自分にはバリバリの営業口調だったくせに、リンに対すると微妙に砕けるアズサにまた、キョースケは頬をふくらませる。リンはそれに気が付いてはいるが、何も言わない。彼女は、気が付いてない。何故、宅配可能地域内ぎりぎりのすみにある男子校の理科準備室なんてわかりづらい場所を指定しておきながら、廊下から繋がる扉と、第一理科室から繋がる扉に鍵をかけてまで、彼が彼女の完璧デリバリー記録に傷をつけようとしているのか、その本当に、彼女は気が付いてない。
「それでは。またのご注文、お待ちしております」
決り文句と一緒に下げた上半身を起こし、準備室から出ようと姉さん、廊下に通じる扉に手をかけ、引っ張るも、
「んぐ……ぐ……」
鍵がかかっているので当然、開かない。
「ぷぷぷぷ……」
そんな人の失敗を、楽しそうに楽しそうにあざ笑うキョースケを背中に感じながら、アズサは般若の面で深呼吸。
「おほほほほ……。失礼いたしました」
振り返った彼女は、おでこのすみに青筋を立てながらも微笑んでいた。営業スマイル。キョースケは、気に入らない。あくまでも“店の人”でいるのなら、
「…………」
何か、何か手はないか。“店の人”へのいやがらせ。
早くしなければ。早く。彼女はもうすでに半歩、準備室から第二理科室へと足を踏み出してしまっていた。
「あー……、っと、お姉さん」
何か。何か。その何かが思い浮かぶよりかも先に、キョースケの薄い唇はもう、開かれていた。
それに、「はい?」と軽い声をあげて振り返ったアズサの表情からはもうすでに、怒りも営業用のスマイルも消え失せていた。素であった。それは、二人の間にこれっくらいのじゃれ合いなどはもう、全くの日常茶飯事なのであるという事の、言わば心的証明なのであった。
「…………」
と、場面を眺めるリンである。閑話休題。
「この……」
ピザを見ながらキョースケは言いかけるが、彼女ならばその具材から製法まで、問うた先からすぐさま答えを、それはそれは簡単に口にするだろう。キョースケには見える。それではまったくの逆効果だ。
が、開いてしまった唇は、もはや何もなしでは閉じられない。
「……9インチって、何センチでしたっけ?」
箱のサイドに書かれていた『9インチ』のデザイン画をその黒い瞳に映した彼は、口走ってしまう。そんな事、ピザ屋の人間ならば常識の内、なのを知っておきながら。キョースケは唇を噛んだ。
「23センチですよ、お客様」
ほらみろ、勝者の笑みだ。
──ったが。うなだれるキョースケの背後。おもむろに唇を開く少年が一人、居た。
「1インチは、約ですが2.54センチと計算されていますから。その計算上では9インチは22.86センチになります」
言わずと知れたリンである。
「う、ウチでは9インチで23センチでお出ししています。お、大きいんだから、いいでしょう」
「店によっては、9インチで25センチのピザを出しているところもあります。稀(まれ)ではありますが、例外と呼ぶほどに少ないわけでもなりません。やはり、25センチのピザは10インチとして扱っている店がほとんどではありますが、10インチですと、25.4センチですので、本当に正確に25センチのピザを10インチとして扱っているとすれば、誇大広告、ですかね。9インチで25センチのピザを売っている店は、それで、10インチとは表示しないようですね。もちろん、9インチとして23センチのピザを出している店も、22.86センチよりは大きいわけですから、悪いわけではありませんが、9インチで25センチのピザを標準と認識してしまっている人が見たら、23センチのピザは小さく感じてしまうかもしれません」
悪気は、からっきし。ゼロなのである。彼が彼のママのお腹にいる頃からの長い付き合いであるアズサには、それがしっかりとわかってしまっているだけに、ストレスが溜まる。頭と胃とが、痛くなる。まあ、そのストレスも、三歩歩けばそれだけで、スッキリさっぱり解消されてしまうのが、便利なアズサの脳みそなのだが。
「……失礼、しました」
すごすごと、準備室から出て行く彼女は知っていた。“無駄な知識”でリンと張り合う事の馬鹿馬鹿しさを。彼女持ち前の勢いで口を開きつづけていれば、リンになど、負けはしないが勝てもしないのだ。彼はただただ単純に、脳内の知識を引き出し参照しているだけに過ぎない。目の前の相手と口論や議論をしようとしているのではないのだ。人間は、辞書を相手に負かす事などは出来ないのである。
「……勝った」
また、二人きりに戻ってしまった狭い理科準備室。キョースケは、ぼそり呟いた。
「…………」
そして。自分が何をしでかしたのかようやく気が付いたリン。
「ショウシツ」
一言。口内で響かせると、ふっ、とため息をついた。
「消失。消えてなくなる事」
それを、上機嫌のキョースケが彼の真似をして後をつむいだが、間違いである。すぐさまにリンはそれを正した。
「蕭瑟(しょうしつ)。秋風がものさびしく吹く事。また、そのようなものさびしい音がする事。さびしいさま」
「そっか?」
「今日もまた、故・小渕元首相」
キョースケの瞳を誘うようにして、リンはゆっくりと卓上のピザに視線を移す。
「ま、俺のおごりって事で。食費が浮いて、ばんばんざいだねぇ、リン君。ほら、遠慮するなよ、俺とお前の仲じゃねぇか、ほら」
家業のせいか研究熱心な味オンチを姉にもってしまったせいか、ピザで育った小林キョースケは、美味しいも美味しくないも食べ飽きてしまっていて、ピザだとあまり量は食べられない。身体が受け付けないのだ。ましてやそれが冷めてしまっているのならなおの事、ピザを持った指先が口にまで運ばれる回数はほんのわずか。
「2992円」
リンは独り言ちった。それほど食べもしないなのに。毎回毎回……。
「ショウシツ」と、再び呟かれたリンの言葉に声高らか。キョースケが続く。
「焼失。焼けてなくなる事」
地である物憂げな表情で、今日もまたリンは彼の訂正をするのであった。
「娼嫉(しょうしつ)──」
彼らの日常は過ぎていく。