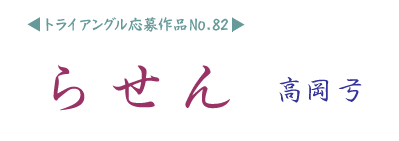
目を開けると、枕もとの時計の光が18:49と読めた。カーテンを閉めたままの部屋の空気は湿ってよどんでいる。のろのろと起きあがって台所へ行き、コップに水を汲む。生ぬるい水道水は喉に引っかかるような感じがする。
会社を辞めて2ヶ月が過ぎたころだったか、今日のようにいつのまにか眠りこんで目覚め、今が朝なのか夜なのかわからなくて不安になったことがあり、私は目覚し時計をAM / PM表示から24時間表示に変えた。それでも今がいつの何時なのか、時刻は知っていられるようになったけれど、時間の感覚がなくなったことに変わりはなかった。目が覚めたら適当に食事をし、眠くなったら眠る生活にとって、14:00であれ20:35であれ時刻はその数字以上の意味をもたない。OLだったころ、左手首の時計の針を睨んであと2分、とドトールの椅子にしがみつき、昼休みを引き伸ばそうとしていたあの時間と、今枕もとに貼りついている18:49は、ほんとうに同じものなのだろうかと不思議に思う。
私と妹が小さかったとき、お盆の数日はいつも祖父母の家に泊まりに行った。居間の柱には年代ものの振り子時計が掛かっていて、長針が一回りするごとにぼんぼんと鳴った。真夜中のしんとした暗闇を震わせるその鐘と、じっ、じっ、と響く秒針の音を私たちは好きではなかったけれど、毎朝起きるとすぐ時計のねじを巻き、神棚に手を合わせるのが祖父の日課だった。几帳面な祖父が亡くなってからは、ねじは数日に一度巻かれるだけになり、時刻もぼんぼんもまったくあてにならなくなって、いつしか時計の針は動かなくなった。孫の私たちもそれぞれ恋人ができたり、就職したりして、祖父の家に行くことも少なくなっていた。
ふたつ年の離れた妹の京子は、地元の赤十字病院で看護婦をしている。昔は小柄でやせっぽちだったのに、今は私よりずっと背が高い。去年の年末、実家に帰ったときの彼女は、髪型を変えて、ちょっとやせていた。
「会うの、半年ぶりくらいかな」
「麻子ちゃん、帰ってこないんだもん。会社辞めてヒマなくせに」
妹は鏡を覗きこみ、おでこにできた小さな吹き出物を気にしている。
「京子は仕事忙しいの?」
「うーん、勤務時間がバラバラなのが、わかってはいたけどちょっとね。夜勤が続くと、どこからどこまでが今日なのかわかんなくなっちゃうし、超不健康な仕事だと思う」
鏡越しに笑いかける妹の顔が、まるで知らない女のひとのように見えたのにすこしショックを受けたことを気づかれないように、私も笑ってそうだね、とうなずいた。
「にいさんごうきゅうから、ゼロになっちゃったよ」
23:59から、突然0:00へリセットされるテレビの時計表示を指差す私に、母はアイロンをかける手を休めずきわめてあっさりと、そういうものよ、と答えた。
「じゃあ今まで増えた時間は、どこに行っちゃうの?」
「増える? どっちかといえば、なくなるんじゃないかしら。今日は過ぎて昨日になって、明日が今日になるのよ」
母はぱりっとしわの伸びたワイシャツをていねいに畳んで、自分の右側に置いた。左側に積んであった洗いたての洗濯物の山はどんどん小さくなっていく。
「よくわかんない。じゃあゼロって明日なの? 今日なの?」
「ゼロはゼロよ。何にもなし。どっちでもなし。それより、いつまで起きてるつもり?」プレスされた衣類の山をまとめて左側に移し、母はアイロン台の脚をばちんばちんと折りたたみながら、私をちょっと睨むようにした。
それからしばらくの間、秒針を見ながら一分間が終わるのをカウントダウンするのが幼い私の癖になった。5、4、3、2、1、ゼロ――消失。やり直し。そうして時間は使ったり、切り刻まれたり、なくなったりするものになっていき、デジタル表示のゼロに違和感も薄れて、私は大人になった。
「1時より3時のほうが時間は多いよね」
「そうだなあ、1から3まで伸びてるからなあ」
目を細めると、祖父のしわはますます深くなる。やせた体を包む浴衣が、ひんやりとした廊下の暗がりに白く浮かび上がり、昨晩焚いた蚊取り線香の匂いがしている。横に立っていた祖父は骨ばった腕で私を抱き上げる。目の高さに来た文字盤で、じっ、じっ、秒針はぐるぐると回って、だんだん大きな数字を指していき、また1からくり返す。
「おかあさんがねえ、1時より3時のほうが時間がないっていうんだよ」
「そんなことないぞ、1時の麻子より3時の麻子のほうが大きくなってるからなあ。麻子の時間はじいちゃんが巻いてやるから、心配しないでいいぞ」
祖父の時計は、決してゼロを指さなかった。
次に目を覚ますと、真っ暗な部屋で携帯電話が鳴っていた。液晶画面の明るさが眼に刺さる。23:59。
「もしもし」
「麻子ちゃん? 私。元気? 今帰りなの」
妹の声を聞きながら、私は心の中で秒読みをはじめた。じっ、じっ、じっ。
「ねえ、京子」
枕もとの赤い数字が変わる。0:00。
「明日の朝、早起きして、おじいちゃんちに行かない?」
「はあ? 何よ、突然」
時間はだんだん減っていくわけではない、今日は消えたりしない。ゼロは消失ではなく、何かが一回りして戻ってくるしるし。12回鐘が鳴るあいだの、ながい境目。何かが毎日私に刻まれて、髪が伸びたり、肌荒れが治ったり、うずくまってはまた歩いたりして、ちょっとずつ変わっていく。いつかひとまわりして何度も、同じ場所に還る。少しずつずれながらひたひたと、重ねられていく。
思い出した。そういう時間を持っていたことを。そういう時間を生きていたひとを。
「ねじを巻くの。時間がまた、回りだすかもしれないから」