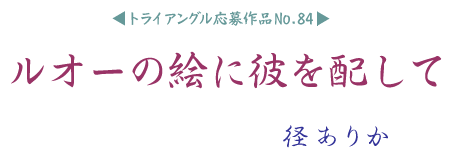
虹子は外で騒ぐ雀の声に目が覚めた。しばらくまくらを胸にあてがってうつ伏せていたが、ふらふらっと身を起こした。
昨夜晩くまでレポート作成に当っていたので、遅い目覚めになった。夢を見ていた名残りで、頭の中がしっくりしなかった。
カーテンを開けると、レースを透して、路地に夫婦らしき初老の二人連れが立ち、二階の虹子の部屋を窺っていた。
カーテンを開けたことで、中の動きを読み取ったものか。とっさに視線を外らしてあたふたと歩き出した。悪びれつつ逃げるように、路地に身を泳がせていく。
(いったい、誰かしら)
ふと、夢の中に見知らぬ夫婦が現れていたのを思いだした。その夢が何を意味するのか解釈にまよっていたが、今実際に夫婦が現れたとなると、若しやと気を回さざるを得なかった。
虹子はそそくさとパジャマから普段着に替え、部屋を飛び出して行った。
二人連れは百メートルほど行ったところに、未練ありげに立ち止っていた。
虹子が路地に出たのに気づくと、また逃げ腰になって、歩き出した。二人の後ろ姿は、人生そのものから逃げだしていくような、何とも言えない重い影を引き摺っていた。
「もし、もし」
虹子は、起きぬけでおどろになっている髪を手で整えつつ呼び掛けた。
二人は向うをむいたまま、背で待つふうに止まった。
「あの、富雄さんのお父さんとお母さんではありませんか?」
二人は観念したふうに、振り返った。
「あなたは?」
母親の方が眉を寄せて訊いた。額の広いところが富雄に似ていた。鼻梁の高いのは父親似だった。
「富雄さんとは友達でした。あのときイスラエルの聖地旅行に出掛けていて、告別式にも出られなくて御免なさい」
「それではあなたが丸岡虹子さん」
母親の目が輝いて、心もち頬も染まった。なぜ自分の名を覚えているのか意外だった。
「はい……」
「イスラエルからのお葉書が届いておりましたよ。富雄の郵便受けに。生前の富雄には渡りませんでしたけれど、霊前に供えさせていただきましたよ。ご親切にして頂いて有難う御座いました」
母親が頭を下げると、父親の方も頬がゆるんで、何か口ごもりながら頭を下げた。
礼を言われると、虹子はうしろめたい気持ちになった。告別式に出られなかったのは止むを得ないにしても、その後、この両親に慰めの手紙一本出さないでしまったからである。「それでお住いはどちらでございますの」
と母親が訊いてきた。かつての富雄の部屋を見上げたとき、人影の動く気配がしたのと、虹子がそのアパートから出てきたように思えて気になっていた。
「寿アパートの、前富雄さんの入っていたお部屋です」
神妙になっていく両親の顔が見て取れた。
「普通なら避けなさるでしょうに、わざわざ入って頂いて、富雄も喜んでいますことでしょう」
母親は言って、涙ぐんでいた。
「日当たりがいいし、静かで、富雄さんに感謝しているんですよ。あそこにいると時々富雄さんの夢も見ますし……」
ここまで言いかけて、また昨夜の夢に現れた夫婦もののことを思い浮かべていた。「今日は少し寝坊をしてしまいましたけれどね」
「失礼ですけど、授業の方は?」
「今日は午後からなんです。もしよろしければ、少しお憩みになっていつて下さい。恥ずかしいくらい、取り散らしておりますけれど」
母親はそそられて夫を振り返っていた。即決と言う素早さで、
「それではお言葉に甘えて、少しお邪魔させて頂こうかしら。あのまま生きていれば、この四月に卒業したことになりますので、息子の果たせなかった夢を大学を見て回るくらいのことで叶えてやりたいと思い、はるばるやって来たのでありますけど、あなた様にお会い出来て、こんなに嬉しいことは御座いません。ねえ、あなた」
と妻は、あなたも何か言いなさいよ、とばかり夫を手で突いた。夫は窓を見上げたときから、雰囲気に当てられでもしたらしく、寡黙になっていた。
「うん、まあ、そういう……」
などと、生半可なうべない方をしていた。かと思うと、これははっきり、
「大学はあちらの方でしたかな」
と西の方角へ体をひねって訊いたりした。
「はい、あの信号を右へ曲がって少し行ったところですわ」
アパートに来ると、両親を玄関に待たせて、虹子は一人で階段を駆け上がって行った。布団を上げ、塵を掃き出すと、その足で両親を迎えに下りた。出掛けている他人のスリッパを借りて、
「どうぞ」
と二人の前に並べ、虹子は後ろから両親の靴を手にして階段を上った。
「綺麗にしていなさること」
それが母親の部屋に入っての感想だった。そして(見違えるばかり)と続けたかったが、故人となった息子の生前の部屋を引合いにしてはならないと思ってよした。富雄が大学に入った年の秋、母親の所属する婦人会の旅行で上京した折、この部屋を訪れて、あまりの乱雑ぶりに呆れ返った。カーテンもなく、至る所洗濯物と塵の山だった。これが旅行の第一の目的ではなかったかと思われて、洗濯をし、カーテンを取り付け、部屋の掃除をし、食料を買い入れて、グループの所に戻ったのであった。
訃報を聞いて駆付けたときは、学生たちが荷物を片付けてくれていた。いよいよアパートを出ようとして、郵便受けを見ると、虹子のイスラエルからの絵葉書が、公告ビラに埋もれて入っていた。
富雄さんお元気?
今日、ガリラヤ湖を見てきました。それはそれは言語に絶して素晴らしい。セルリアンブルーの鏡といったところね。二千年前イエス・キリストが……とやりたいところだけど、「またか」と言われそうだから、今はよしておく。でも正直一緒に来たかったわ。
ざっと、こんな内容だった。
虹子の絵葉書が届いた頃、富雄はラグビー部の仲間三人とドライブに出て、飯山から長野に向かう辺りでカーブを曲り損ね、23メートル下の谷底に落下して三人ともに即死したのだった。
富雄は大学三年生に、虹子は二年生になったばかりの五月の連休だった。
成田に着き、仲間に電話を入れて、富雄の事故を知ったのである。電話の相手は、富雄の死を伝えているのに、虹子にはそれが呑み込めなかった。
バックの奥には、富雄にも喜んで貰えそうな土産をと、重いのを堪えて運んできたワインが忍ばせてあった。重いバックをさらに重くして虹子を悩ませてきたワインの受取り手が、成田に着いた途端に、この世から消失しているなんて信じられるだろうか。
受話器を置いて歩いているうち、虹子は立ちくらみにおそわれた。同行した教会員に支えられ、励まされて大学のある街の富雄のアパートに戻ったのである。部屋はもぬけの殻だった。
虹子は寮を出て閑静な部屋に移りたいと思っていたときだったので、管理人に言ってすぐ引っ越してきた。
「富雄とは、いつ頃から友達でいて下さったんですの」
二人は進めた座布団にゆったり坐り込むと、お茶を淹れに立った虹子の背に、母親が声を掛けた。
「あれは、私が一年生の夏休みでしたわ。アルバイト先で、同じ大学から来ていることが分かって、それからですの」
母親は自分の来たのが、富雄の一年生のときで、あの部屋の狼藉ぶりもむべなるかなと思えたのである。知り合ったから、男子学生の部屋を訪れるというわけでもあるまいが、今となっては、言い知れぬ懐かしさとなって目に浮かんできたのである。
そのときのアルバイト代が、虹子には翌年の聖地旅行の費用となり、富雄には日本縦断の自動車旅行となった。
虹子はそのアルバイトの帰り道、よく富雄と一緒になった。同じ大学からは他にも何人か来ていたが、寮からは虹子一人だった。寮はこのアパートを越えて一キロ先にある。
アルバイトが終った日、学生たちは骨休めと称して軽いコンパをした。富雄はウイスキーやビールで御機嫌だったが、クリスチャンの虹子は、ワインを少々口にしただけだった。会もお開きとなったときは、夜も相当更けていた。富雄は見違えるばかり快活になっており、荒い息遣いのなかから、いきなり歌が飛出したりした。
「あら、その歌、何ていうの」
聞き覚えのあるメロデーに、虹子は尋ねた。もしかして、聖歌にあった曲ではないかと思ったからだった。
「これは、俺の母校の校歌さ」
「そう」
折角の高揚が萎れていた。信仰のある者なら、呂律が回らなくなるまで飲むはずはなかったのである。
富雄のアパートの前まできて別れようとすると、
「送るよ。女性のひとり歩きは危ないから」
彼は言って、送って来た。高塀の続く淋しい路地で、確かに女のひとり歩きは危険な時間になっていた。
明日からは大学の後期の授業も始まり、富雄とはこれから、どんな関わりがあるのだろう。キャンパスでたまに顔を合わす程度になってしまうのか。それはとても寂しかった。自分の行っている教会に誘ってみようかしら。そう思っているとき、彼が口を切った。
「これでアルバイトは終り、直接会う機会はなくなるわけだけど‥‥。交際しない?」
女子寮の屋根が黒々と迫ってきていた。
「いいわ、友達なら」
虹子は、寮の窓に消え残っている灯の方に視線をやって言った。
顔を戻すと、富雄が握手の手を伸ばしてきた。虹子が手を出すと、握つた手に力が入って、いきなり引寄せようとした。虹子はそれを、腕を交差させて拒み、寮に向かって走った。期せずして、腕が十字の形になっていたのを、不思議に思いながら走っていた。
大学での空き時間や放課後、富雄に誘われると会っていた。虹子の方から電話をして誘うこともあった。けれども彼女の誘いは、もっぱら教会の伝道集会や礼拝に向けてのものだった。虹子は富雄に惹かれていくにつれて、彼をクリスチャンにしたい思いが募った。話し込んで帰りが遅くなると、彼は虹子を送ってきた。
そんなとき幾度か接吻を求められたが、その度に腕を交差させて拒んでいた。
「俺が、教会に行かないという理由だけか」
彼はむきになって言った。
「そうよ。神にも祝福された間でいたいの」
こう言ったが、本心は結婚するまでは接吻も許さないつもりだった。ただ彼が教会へ来て信仰を持てば、自ずと心もほどけていくだろうとは思った。けれどもそれは、そうなってみなければ分からないことだった。
クリスマスには、虹子の誘いにのって彼は教会の門をくぐった。しかしその後が続かなかった。
イスラエル旅行は、虹子のかねてからの願いであり、どうしても行きたかった。それにも誘ったが、
「俺には俺のスケジュールがある」
と、日本縦断の自動車旅行に繰り出して行った。車体に赤ペンキで大きく、△△大学、日本縦断の旅 と書きなぐって。
そのとき運転していたのは、富雄ではなかったが、たとえ彼であったとしても、事故に遭わないという保証はない。誰であれ、人は死と隣り合わせに生きているのだろうから。そんな中で最も大切なのは、日頃から死への備えをしておくことなのだろう。
虹子が残念でならないのは、富雄を導けないでしまったことだった。神を知らないでしまった者の死後はどうなっているのか。これは虹子にとって大きな問題となってきた。残されているのは、祈りのほかないのである。その祈りが、聞かれるかどうかも分からない。それでも夢で、人知を越えた示され方をされたりすると、かすかな望みにも縋りつきたくなるのだった。
昨夜の夢は、実際に富雄の両親が訪ねて来たことで、深い啓示のようにも思えた。これをどう二人に伝えたものか、小さな頭を悩ましていた。
お茶の用意をして、両親のところへ戻ってくると、父親の視線が強ばって壁に向けられていた。困ったものを見られてしまったと思ったが、後の祭りだった。
「あの写真は、富雄ではないかね」
終始模糊としていた父親が、こればかりはしっかりと語尾を押さえて訊いてきた。背を向けていた母親が、壁を振り返った。
「あら、あら」
と息子の写真を見つけたのはよかったが、写真の異様な貼られ方に戸惑っていた。
写真は路上の子犬でも見下ろしているところを、虹子が横から撮ったものであろう。子犬は入っていないが、富雄の膝から頭までが大きく引き伸ばされていた。そこまではいいが、彼の写真の隣に、ルオーの複製画を半分に切って、富雄と向い合せに貼ってあったのである。
「隣の絵の変な人物は何かね」
と父親が言った。
「ルオーのキリストです」
その絵はキリストの按手を受けている弟子の部分を切りぬいて、弟子のところに富雄を置いたのである。丁度、キリストの手が、富雄の頭頂に伸びようとしていた。
「キリス‥‥」
最後まで言わずに、父親は壁の絵から目を外らした。母親も前の姿勢に戻った。
気詰まりな空気に領されていたのを、
「このお茶おいしい」
母親の一声で、和らぎが戻ってきた。
父親の言う「変な人物」の隣に、それよりも小さく富雄を配したことが、不興をかったのだろうか。それとも、相手がキリストであったのが、いけなかったのだろうか。
両親の心根は分からなかった。虹子は絵と写真の組合せに何の説明も加えなかった。彼女なりに、こんな形ででも、眠っている富雄の霊を目覚めさせてやることが出来ればと、祈りをこめて貼ったのである。勿論そうしたのは、富雄が逝ってからである。
生前富雄は、虹子の心を惹きつけよう惹きつけようとしていた。唐突な接吻もそのせいと思えた。虹子もまた彼を教会へ引き付けようとしていた。二人の関係は、その行き違いに終っていた。
今富雄の両親を前にしても、やっぱりその食違いを強く意識していた。二人はそろそろここを離れようとしながら、当たり障りのない話へ回避しようとしていた。
「あなた、午後から授業と言ってらしたわね」
母親がそわそわと腰を浮かして言った。
「いえ、まだまだですわ。一緒に行って、学校を御案内しましょうか」
「どうぞ、我々には御心配なく。勝手に大学を一回りして帰りますから」
と父親が言った。
虹子はどうしても、これだけは伝えておきたくて言った。
「私、昨夜お二人が訪ねて来る夢を見たんですよ。そのときは誰であるか分からなかったんですけど、起きてもそのことが頭にあって、カーテンを開けるとお二人が見上げておられるので、ああ、もしかして富雄さんの御両親かと、慌てて呼び止めたんです」
虹子は今も、自分から離れて行こうとする者を引き止めるのに必死だった。
「まあ」
母親は呆れ顔になって、口を開いていたが、「夢にもそんな当たりもあるもんなんですね」
と彼女なりの結論を言った。
「神はこんな形で、啓示を与えるんですわ」
と虹子は言た。「自分の思いで見る夢もありますけど、はっきり上からくるものも時にあるんですわ。聖書にもそんな夢が何回か出てきますもの」
潮のように引いていくものが見えたが、どうしても今、与えられた種は播いておかなければならないと思っていた。
いつ芽を出してくるか、その時は神が握っている。富雄を導くことは出来なかったが、虹子の聖地での祈りは、日本縦断の車を駆っていた彼にも届けられたのではなかっただろうか。それでなければどうして、夢に見た両親が今ここに来ているなんてことがあるだろうか。
間もなく三人はアパートを出て、大学の門をくぐった。
富雄は一人っ子だった。その息子を失ったとなると、彼の生活した場所を、そうあっさりと離れて行けるものではない。
そこに気づくと、虹子は自らを鼓舞して、大学食堂まで引っ張って来たのであった。学生たちの若やいだ声が飛び交い、そこにおかれた二人は、寄ってくる息子の声を待っているようでもあった。
虹子が遠くの方へ、手招きの合図をしていた。一人の女子大生が走り込んできた。
「この人、紺野さんの妹さんです」
紺野とは、事故死した三人のうちの一人である。紺野の妹はテーブルに手を置いて、両親ににこやかに挨拶していた。葬儀のときこの妹も同席したが、混乱していてはっきりした面識はなかった。
薄地のブルーのブラウスが、食堂の窓から届く風に流れて、妹の肌にまといついていた。襟のところに、ネックレスの金の十字架が食い込んでいた。彼女の果敢な歓迎の身振りによって、その十字架がせり出してぶら下ってしまった。
虹子はあっと息を飲んだが、両親にさしたる動揺は見えなかった。いや、動揺など与えないほど、大学食堂の片隅のささやかな光景だった。