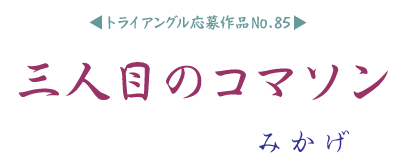
それがはじまったのは、ある日曜日の朝のことだった。前夜から降りつづく雨のために外出の予定をとりやめていた私は、遅い朝食をとろうとベットをぬけだし、キッチンへ向かう。しかしテーブルの上には、あるべきはずの食べ物がなかった。あるのは白い皿が二枚に、コーヒーカップがひとつだけ。どれも洗いたてみたいにぴかぴかで、料理がおかれたり、飲みものがそそがれた様子はなかった。
外出先から妻が戻ってくると(妻は予定通り、友人とショッピングをしてきたのだ)、そのことを問いただす。
「出かけるまえに言ったよね? 朝食を作ってテーブルの上に置いたって」
「ええ。半熟の目玉焼きふたつに、カリカリに焼いたベーコンを添えて。あとはレタスとトマトのサラダ。コーヒーを淹れてトーストを焼くのはあなたでしょ。いつものとおりよ、なにもかも」
朝の奇妙な出来事を伝えると、妻は突然、激しい口調に変わる。
「じゃあ、わたしが嘘をついてるっていうの? ほんとにちゃんと作ったんだから。あなたの言ってることが正しいなら、泥棒よ。それしか考えられなじゃない」
妻は受話器を取り上げ、ボタンを押しはじめる。私はあわてて制止する。
「泥棒はありえないよ。ここは高層マンションの二十三階だよ。セキュリティも万全だ。見るかぎり荒らされた形跡もないし。それにわざわざ日曜日の朝をねらうかい? それも朝食めあてに」
妻は納得しない。髪を振り乱して、力まかせに、彼女の腕を握った私の手を振りほどこうとする。これほど取り乱す妻を見るのははじめてだった。私はとにかくこの場を収拾しようと考える。
「ごめん、ぼくのかんちがいだよ。ねぼけまなこでぜんぶ平らげちゃったんだよ、きっと」
この日をさかいに、身のまわりのものがつぎつぎに不思議ななくなりかたをしはじめる。まず、リビングの飾り棚に置いていた石ころが消える。これは小学生のころ故郷の小川で拾ったもので、形がうさぎに似ているものだった。手にとってどこかに持ちだしたという記憶はなかった。明くる日には、読みかけの推理小説がなくなってしまう。それももう少しで犯人がわかるというときに。夜、枕元に置いて眠ったはずなのに、朝おきてみると跡形もなく消失していたのだ。その日は休日で、気晴らしに出かけようと玄関に向かうが、お気に入りのスニーカーが片方だけどうしても見あたらない。最後に履いたとき、ちゃんと靴箱にしまっておいたはずなのに。
妻を呼びつけてこれらのことについて訊いてみたくなるが、すんでのところでぐっとこらえる。このまえみたいに妻が怒りだすのは御免だ。それに私が無意識にどこかにやってしまったのかもしれない。その可能性も、ごくごくわずかだとは思うが、ないとは言い切れない。
しかし、避けようとしていた事態はそれから間もなく起こる。それは妻の問いかけからはじまる。
「ねえ、あの写真知らない? 高校の夏休みに行った海辺で、親友と一緒に写ってるやつ。あれ、いちばんのお気に入りなのよ。アルバムからその写真だけが、ぽろっと抜けてるの。まるでだれかにはがされたみたいに」
私は知らない、という。そんな写真があったことも知らない、と。
「嘘よ。結婚する前に何度か見せたでしょ。これは大好きな一枚なのって。それともうひとつ。テディベアの柄の枕カバー、見あたらないの。昨日洗濯してタンスにしまったところまではおぼえてるの。でもついさっき見たら、しまった場所にないの。あなた知ってるわよね、あの枕カバー、わたしが宝物みたく大事にしてるって」
「それは知ってる。きみはテディベアが好きで、枕カバーの柄のやつはとくに気に入ってた。毛並みのふさふさ具合がいいって」
「あなた、あの日曜日からなんだか態度がよそよそしいけど、もしかしてこれって何かのあてつけなのかしら?」
そのひとことで私の理性は感情に飲み込まれる。自分でも驚くような威圧的な声で、妻の不信をとがめる。妻の瞳に見たこともない深みが宿る。でも私は追及をやめることができない。
「あの日曜日から、ぼくのまわりでもいろいろとものがなくなってるんだ。赤の他人から見れば、がらくたみたいなものばかりなんだけどね。目のなかに入れても痛くないものもあったんだ」
絶対に自分ではないと妻は大きな声で反論する。こうして不毛な言葉の応酬が続く。平行線をたどったまま、どこにも出口は見えてこない。居心地の悪い沈黙がしばらく続いたあと、妻がぽつりとつぶやく。「ほんと、わたしたちのほかにだれかがいるみたいね」
「そうだ、きっと、もうひとりだれかがいるんだ」と私がつづく。「姿をみせない、いたずら好きのだれかが……」
「そうかもね。あのコマソンみたいなやつが。ほら、おぼえてる? 高校時代の同級生、いつも流行のコマーシャルソングばかり口ずさんでた……」
「ああ、あいつならやりかねないね。元クラスメイトの家にあがりこんで、勝手に何かを盗みだす。で、本人は悪気のない冗談のつもり」
「行き過ぎたいたずらで、よく謹慎をくらってたわね」
妻は新聞の折り込み広告の裏側に、マジックでコマソンを描きはじめる。電球みたいな頭に、黒目ばかりの大きなぎょろ目がふたつ。それが頭と同じくらいの大きさの胴体に載っている。きちんと背広を着て、ネクタイを締めている。
「頭は大きすぎたわね。世間の荒波に揉まれて、髪の毛はきれいさっぱり抜け落ちちゃった。学ランを脱いだ今は、吊し売りの安物のスーツ。落ち着きがなくて、いつも何かないかってぎょろぎょろあたりを見回してばかりなのはひどくなる一方で、とうとう黒目だけになっちゃった」
私は一本線のにやけた口元に牙を二本、つけ加える。「ものを盗んでいるところを見つかれば、がぶっとくるんだよ」
妻は冷蔵庫に磁石のクリップで、その絵を貼りつける。「これだけ大きな牙で噛みつかれたら、死んじゃうかもしれないわね」
「うん、そうだね」と私は言う。
それからも私の周辺からものはなくなりつづけた。相変わらず他人から見れば何の価値もないようなものばかりが。以前と違うのは、すべては姿を見せない、謎の同居人の仕業なのだと考えると、不思議と怒りはわいてこなくなったことだ。これはおそらく妻も同じだと思う。そうやって妻も自分を納得させているにちがいない。でもコマソン誕生以来、我々は一度もこの奇妙な居候について語ることはなかった。まるでそれが決して触れてはならない秘密であるかのように。
今朝、ドアの前で送りだしてくれる妻を振り返ったとき、彼女の肩越しにコマソンを見た。コマソンはダイニングのテーブルに腰かけ、太い短い腕で頬杖をついて大きな頭を支えながら、ぬらぬらとひかる瞳でじっと我々のほうを見つめていた。コマソンは私の視線に気づくと、億劫そうにぬっと立ち上がり、頭を重たげに左右に揺らしながら、のらりくらりと奧の部屋へと消えていった。私は妻にそのことは告げずに、ただ「行ってきます」とだけ言う。私が幻覚を見ただけかもしれないからだ。いや、そうに決まっている。
通勤の電車の中で、コマソンが妻に噛みつくところを想像する。あの鋭い牙で首筋に噛みつかれたら生きてはいないだろうな、と私は思う。