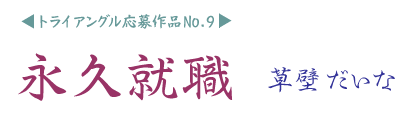
履歴書というものは、何枚書いてもうまくいかない。
元来、字などまじめに書かない性分で、内容の方も充実した項目はただの一つもなく、趣味はつんくファミリーにはまっているのを『音楽鑑賞』とし、特技欄については教科書隅のパラパラ漫画を『絵画』と称した。そんなお手軽な書類を、まっすぐ前を向いた文字で一時間もかけて書き上げたが、真剣にペンを持ちすぎていたために、汗をかいて、最初の方に書いた文字がにじんでしまっている。もう一度新しい用紙を取り出して、そうしてようやく出来たと思えば、印鑑の向きが逆になったり、または折り目の数が少なくてそれ用の封筒に入らなかったりする。
そんな苦労を伴う、内容の希薄な書類を、十数枚も作成しなくてはいけない。
コピーじゃダメなのだろうか。本当に面倒だ。
相変わらず就職難のご時世で、今や就職活動は三回生から始まり、四回生となった今では、職種や業務内容を吟味している余裕は無く、苦労して仕上げた履歴書たちはとにかく手当たり次第に、あらゆる企業に送付した。今日も授業欠席で、あまり名の聞かないとある企業に足を運び、人事担当社員と何を話したのかほとんど覚えていないが、とにかく疲れてその会社を後にした。
そんな帰り道のことだった。
下宿に程近い、人気の少ない公園の角に、見知らぬ年配の男性が立っていた。
そうして俺を見つけると、何の迷いも無く、こちらの方に近づいてきた。
「お誕生日、おめでとうございます」
あっけに取られる俺にその老人は、そう言うとおもむろに、今まで両手で抱えこんで持っていた茶色い包みを、おごそかに頭を下げながら、ゆっくりと差し出した。
自転車に乗った子供が、俺の背中をすりぬけたはずみで、自分はその男の方に押し出された形になり、思わず俺はそれを受け取ってしまった。
多忙な就職活動ですっかり忘れていたが、たしかに今日は自分の二十二回目の誕生日だった。
それにしてもどうしてこの老人が自分の誕生日を知っているのか、それ以前にどうして俺を知っているのか、不思議ではあったが、そういうことより何より、いわれの無いプレゼントが今自分の腕の中にあるというのが非常に気味悪く、今すぐにでもほおり出したい気分だった。
しかし、よくよく眺めると包みは、大きさの割には 軽く、ふわふわと軟らかい、味わったことの無い珍しい感触のものだった。
初めて触れる感触に驚いて、先程の不信感は棚に置いて、それをもんだりなぜたりしてみた。
触れば触るほど、中身に興味が湧いた。
「何ですか、これは?」
「まくらでございます」
「まくら?」
「はい。これを頭の下に敷いて寝ていただきますと、ちょうど一年後のご自分の姿を、夢として見ることが出来ます」
一年後の自分。そんなもの知って、何になるんだろう。
「お知りになりたくはありませんか? 例えば一年後は、どういった方とお付き合いをしているとか、どういった会社で働いているかとか・・・」
就職先か。一年後はどんな所で働いているのだろうか。希望職種に就けているだろうか。それとも就職浪人でもしているのだろうか。
それを知ることが出来れば、こんなにたくさんの企業の面接に出向く必要もなく、自分が就職する予定の会社にのみ足を運び、夢に出てきた職種を希望し、合理的に動けるのだけれど。
「ご信用なさらないお気持ちもわかります。 しかし、ものは試しにどうでしょう。
決して、後日法外なお値段をご請求にあがったり、またはご使用後に健康を害されるといったりするものではございません」
まぁ、こっちの迷惑にはならないのなら、ここのところ、面白いことも何も無い日々なわけで、話のたねにやってみようという気になった。
「じゃあ、一晩だけ・・・」
「ありがとうございます」老人は微笑んだ。
何故この男に礼を言われなければいけないのか、いまいちピンとこなかったが、あまり長くかかわるつもりもなかったので、そそくさとその場を離れようとした。
「それと・・・」 すると、老人は加えた。
「このまくらは使い捨てでして、一晩ご使用いただきますと、まくらは消えて無くなるしくみとなっておりますので」
下宿に戻って、その包みを開けてみた。
まくらは、断熱材のようなもので厳重にくるまれ、中から、薄いベージュのシルクのような布で覆われたそれが出現した。
一瞬、奇妙なにおいがただよった。
何だろう。昔どこかで嗅いだような・・・。
幼いころ風邪をひいた時、むりやりのど元に塗られたルゴールとかいう薬の匂いに似ていた。
まくらの感触は、初めてそれを持ったとき以上に、ふわふわとやわらかく、それだけが真空空間で浮いているような、何とも新鮮な感覚だった。
まだまだ腑に落ちなかったが、ま、ただ寝るだけで、損はしないのだから、物は試しにそれを敷いて眠ってみることにした。
確かに、夢を見た。
部屋のカレンダーは、ちょうど一年後の年号。本当に一年後の夢だった。
その部屋は・・・もちろんこの下宿ではない。
どこだろう、見覚えのある・・・それは、実家の居間だった。
実家の居間に、両親や親戚たちといった、見たことのある顔ぶればかりが集まっている。
皆が皆、一様に黒い服を着ていて、誰一人口を開く者も居ず、ときおり聞えるすすり泣きの声だけが、あたりに充満していた。
とても厳かなムードが漂うその部屋の奥の壁寄りの場所に、祭壇が組まれていて、その上に置かれた遺影は、まぎれもなく自分だった。
そこで営まれていたのは、まさしく自分の葬式だった。
「あ」そう思った瞬間、目が覚めた。 何とも生生しい夢だった。
そうして、見ると、あのじいさんが言っていたとおり、まくらの中身は跡形もなく消えさり、外袋のみ、元あった場所にへたって横たわっていた。
怪しげな匂い。一年後の夢。 まくらの消失。
理由はわからないが、ただ真実味を感じた。
ということは、夢の中身も信じざるを得ないことになる。
俺は、死ぬ。一年後の、二十三歳の誕生日は、俺の命日でもある
死。死。死。そんなもの、これまで一度も、身近なものとして考えたことはなかった。
どうすればいい・・・。
けれどこれは現実なんだ。
どうしようもない・・・。
そんな風に結論の出ない問題を、ドードー巡りのようにいつまでももんもんと思っているうち、徐々に俺は開き直ってきた。
「どうせ一年後は死ぬんだ」
苦労して働き口を探したところで、ほんの二十三年で俺の人生は終わる。無駄なことは止そう。
俺はその日から、まるでスイッチが切り替わったかのように、就職活動はもちろん、大学に通うこともやめた。もう永遠に、就職なんてする必要がない。
残り一年。何をすればいい。何を。
まずは死亡保険に入り・・・と思ったが、自分が受け取れもしないものに金をつぎ込むのはつまらなすぎるだろう。ゴッホや宮沢賢治のように、死後に認められる作品を世に残せるほどの才能も、持ちあわせていないのは自覚している。
半ば自暴自棄状態で、むしろ一度はやってみたかったことを考えた。
しかし、履歴書に書く趣味すらろくに持たない人間に、なんら夢も展望も無く、食べておきたいものすら浮かぶことはなかった。
窓の外から、学校へ向かう小学生たちの笑い声が聞えてきた。
楽しそうな声、未来に向かう足取り。
俺は将来への希望を断たれて、絶望の淵に立たされているというのに、まわりの人間はそんなことおかまいなしに、楽しく過ごしている
どうして俺だけが・・・。
俺はだんだんと、腹が立ってきた。
突然俺は思いつきで、自分の携帯を取り出し、以前自分をふった女の携帯に連絡を入れ、会う約束を取り付けた。
待ち合わせ場所の、人け無い公園に、女はやってきた。
「もう一度、付き合わないかい?」
相変わらず美人で、プライドの高い彼女は、はなから俺など相手にするはずがなく、当然のことだが今にいたって首を縦に振るわけが無い。そんなことはわかっていた。
「ことわるなら、こうしてやるよ」
俺はおもむろに、両手で女の首をつかんだ。女は声も出せず、激しく手足を動かしている。
「さあ、縦に振ってみて。俺と付き合うんだろう?」
俺は更に力をこめた。更に、更に、力をこめた。
けれど結局女の首は最後まで縦向きに揺れることなく、女の動作も呼吸も永遠に静かになった。
「強情だなぁ」
予想どおりだった。気分が良かった。
自分にはかっこたる逃げ道があるという自信は、俺に罪の意識というものを消失させていた。
何という残り人生の横臥法なんだ。
そうして、あの女を締めたことではずみのついた俺は、気に食わない奴らを片端から殺してまわることにした。
次は誰だ。
俺の歯並びの悪さを笑った奴、先々月貸したバイト料の一万円をなかなか返さない奴、単に俺が必死の就職活動をしているのを横目に見ながら、青田買いであっさり意中の企業からの内定を勝ち取った体育会系の奴まで。
手当たり次第、居場所を探っては殺害スケジュールを練った。
殺害方法、凶器調達、殺害場所、逃走手段・・・。相手の血を浴びると、足もつきやすいし、自分も血を見るのは怖いので、なるべく自分の手が相手の血で汚れない方法をもくろんだ。
一人には、頭上に向けてたまたまそばにあったハーブの植木鉢を降らせた。
また一人には、奴のセコい性格を利用して、劇薬入りの栄養ドリンクに『試飲品』のラベルを付けて、アパートのポストにプレゼントしておいた。
別の奴には、混み合ったプラットホームで、特急電車通過時にさりげなくプッシュしてやった。
一人、二人と殺るたびに、笑いがこみ上げてきた。
いままでの人生で味わったことの無いスリルを感じた。俳優は時に、悪役を演じている最中に快感を覚えるという話を聞いたことがあるが、自分はまさにそれを実演している。
「みんな道づれだ。みんな一緒に死ぬんだ」
いよいよ明日が、俺の二十三回目の誕生日。そして、俺の人生最後の日。
しかし、これまでの自分の健康状態に何ら、問題は起きていなかった。
おそらく俺は、不慮の事故にでも遭うのだろう。
死因なんて何だっていい。
やることはやった。
もうこの際、何がどうなったって、おびえる必要は何も無い。
その時突然、ノックの音がした。
しかし俺はアセらなかった。もう何も怖くない。
今さら何をとがめられたところで、痛くも痒くもないさ。
そう思いながら、ためらいも無くドアを開けた。
するとそこには、例のまくらをくれた老人が立っていた。
「お久しぶりでございます」
何なんだろう、今頃。
予想もしていなかった彼の来訪に俺は少し驚き、声を出すのも忘れてボォっと直立していたが、俺のそんな反応はさて置いて老人は、ドアを開けたまま、黙って玄関口に足を踏み入れた。
「私は、特殊科学製品製造会社を経営しております、こういうものですが・・・」
そう言うと、おもむろに内ポケットから、会社名と取締役代表という肩書きの書かれた名刺を取り出し、俺に差し出した。ほぼ一年前、就職活動時の履歴書送付先に、そんな会社名があったような気もするが、今さら記憶はうつろだった。
「この度は我が社の噦夢まくら器をご試用くださり、ありがとうございます」
老人は、俺に向かって深々と頭を下げた。
「実はあのまくらの内部には、特殊な固体様物質が入っておりまして、それが体温によって昇華し、脳波リズムを調整する気体が発生するようになっております。
つまりはあのまくらを敷いて睡眠することで、どんな方にもこちらが意図する夢を見させることが出来るのです。
我が社が昨年度開発しました自信作で、近年中にはおそらく様々な分野の各企業において、多様化されるであろうと自負しております」
老人は、流暢な口調で続けた。
「この度我が社への就職をご希望下さった皆様には、『夢見まくら』というようなあまりにバカ気た話にどれほど耳を傾けることが出来るかという力量と、人生残り一年という状況で、どれほど有意義に時間を過ごされるかとの2点について、採用の判断基準にさせていただこうと試みさせていただきました。
貴方様は、絵空事のような話を信じてくださり、その時点で第一段階合格ということで、その後の一年間の行動を、引き続き遠目ながら拝見しておりましたが・・・」
俺の右手に握っていたはずの名刺が、音も無く老人の足元に落ちた。
何も言葉が出なかった。
老人は落ちた名刺に気にも止めず、俺の目をあわれ気に眺めながら、つぶやくように言った。
「・・・派手にされましたね。
ちょっとやそっとでつぐなえるもんじゃない。
これでは貴方様のお勤め先は、私どもではなく、あちら様に託した方が良さそうで・・・」
老人はドアの外に目をやった。
何も変わらない風景。
しかしそのうち老人の背後には、赤い点滅ランプの車群と、ちまたでよく聞かれるサイレンの音が、徐々に徐々に、こちらの方へと近づいてきた。