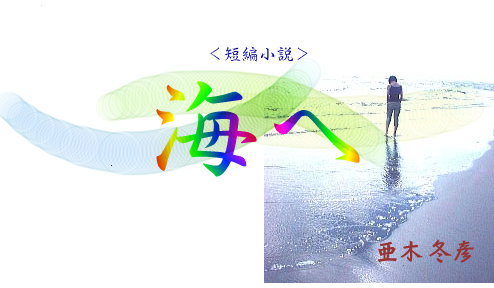
老いぼれの軽トラックは、悲鳴のようなエンジン音を響かせながらも、真夜中の高速道路を懸命に走っていた。
「眠かったら、寝ていいんだぞ」
カブ先生こと仲里惣八は、助手席の古寺(こでら)康子に声をかけた。
「大丈夫だよ。だって……、眠ったら、もったいないもん」
みんなからヤコと呼ばれている少女が、答えた。カーラジオのスピーカーから、北島三郎のコブシの効いた歌声が流れている。NHKのラジオ深夜便は、演歌特集だった。ラジオも古くて、選局が限られている。
(せっかく、花の女子高生と、ふたりでドライブしているというのにな)
抗議するように、エンジン音が呻りを増した。登り坂になったようだ。目いっぱいペダルを踏み込んでも、速度は落ちるばかりだ。贅沢は言えない。相手が無免許だということを知っていて、車を貸してくれる者はそうはいない……。
(若気の至りか)
かつてのことを思い出して、カブ先生は苦笑した。それは、カブ先生と呼ばれるようになる前の出来事だった。
いつも往診している患者宅から電話があったのは、すでに深夜の12時を過ぎていた。喘息の発作がひどくて苦しんでいるという。頓服の吸入薬を使っても効果
がない。カブ先生は、必要な薬品を往診鞄に詰め込むと、車で患者宅に向かった。患者は90歳近くの高齢で、心臓がかなり弱っていた。
途中で運悪く、警察の検問に引っかかった。忘年会シーズンで、飲酒運転の取り締まりをやっていたらしい。制限速度をかなりオーバーしていた。車を停めろとの警官の指示を無視して、カブ先生は検問を強引に突破した。サイレンを鳴らしたパトカーが追いかけてきた。患者宅の前で、車を降りたカブ先生を、警官たちが取り囲んだ。
「邪魔をするな! おれの患者が待ってるんだ」
カブ先生の一喝に、警官たちが退いた。それで、患者は危うく一命を取り留めたが、カブ先生は運転免許を失うことになった。晩酌の酔いがまだ残っていた。以来、カブ先生は一滴もアルコールを口にしていない。
車の運転ができなくなったカブ先生は、原付免許で運転できるバイクで往診に出るようになった。近所の家で使わなくなったホンダ・スーパーカブを、安い値段で譲ってもらったのだ。雨や雪の日は、看護師の山村さんの軽自動車に乗せてもらった。それで、支障はなかった。みんなからカブ先生と呼ばれるようになる頃には、履き古したズックのように、愛車は自分の足に馴染んでいた。
(おれは、あの頃から少しも成長していない……)
カブ先生は、自嘲した。中国山地の山間(やまあい)にある田舎町から、無免許で太平洋を目差して車を走らせている。しかも、こんな真夜中に、未成年の女の子を同乗させて、だ。発覚すれば、道路交通
法違反で処罰されることはもちろん、テレビのワイドショーの格好の餌食だろう。それで、医道審議会にかけられて医業停止処分にでもなれば、自分の患者に迷惑をかけることになる。
(今さら考えても仕方がない)
車の時計を見た。ヤコから電話がかかってきてから、まだ3時間も経っていないのだ。
「先生、こんな時間にごめんなさい……」
電話口が沈黙した。
「眠れないのか?」
「うん……」
無理もないと思った。明日は、故郷から遠く離れた病院に入院するのだ。
「お父さんは?」
口に出してすぐに後悔した。
「もう、寝ちゃってる」
泥酔して鼾(いびき)をかいている姿が思い浮かんだ。気の小さい性格で、何かあると、アルコールの靄の中に逃げ込んでしまう。それで、女房にも逃げられた。
「ヤコは、うどんは好きか?」
「うん、好きだよ。作るのも簡単だし、安上がりだからね」
「さすがに主婦の言うことは違うな」
控えめな笑い声が聞こえた。
「先生もうどんが大好きなんだ。だから、ヤコがうらやましい。明日からは、本場のうどんがいくらでも食べられるんだからな」
ヤコが入院する病院は、四国の徳島にあった。
「先生も食べに来るといいよ。おいしいうどん屋さん、見つけておくから」
「そうだな。うまくて安くて、量が多い店を頼む」
「欲張り過ぎだよ」
今度は、カブ先生が笑った。
「讃岐美人という言葉がある。讃岐うどんのように色が白くて、スラリとした美人のことだ。その秘密は、うどんにある」
口からデマカセだった。
「讃岐うどんを食べると、色が白くなるのかな?」
「白くてツルツルの肌になるぞ」
「本当?」
「ああ、ちゃんとした医学的なデータも揃っている」
ヤコがまた笑った。
「先生、ありがとう。もう寝るね」
「ああ、おやすみ」
「おやすみなさい」
カブ先生は、やるせない思いで、受話器を耳に当てたままでいた。我慢強い娘(こ)だった。中学に入った頃から、母親のかわりに家事をこなした。愚痴や不平をこぼすことなく、自分の境遇を受け入れていた。いや、受け入れているように見えていただけかもしれない。無邪気で人なつっこい女の子は、無口で笑わない少女になった。
「先生……」
ヤコの声が再び聞こえた。
「わたし、すっごく感動したドラマがあるんだ」
カブ先生は、受話器を握りなおした。
「高校生の女の子が、親友に裏切られて、暴走族のヤンキーたちに襲われちゃうんだけどね。恋人がかけつけて、ヤンキーたちをボコボコにしちゃうんだけど、もう姦られちゃったあとで、その女の子、ミサという名前なんだけど、歩道橋から身を投げて自殺しようとするんだよ」
ヤコの、こんなに興奮した声を聞くのは初めてだった。
「それからが凄いんだから。ミサを歩道橋から無理やり引きずり下ろしたコージは、『だったら一緒に死んでやるよ』と叫んで、ミサをバイクの後ろに乗せて、歩道橋の階段をキャリーで駆け上がるんだ。そのまま欄干にジャンプして、鉄柵の上をバイクで走っちゃうんだから、凄いでしょ?」
「それは、確かに凄いな」
歩道橋の細い鉄柵の上を、スーパーカブで走る自分の姿を思い浮かべた。カブ先生は、高所恐怖症なのだ。
「ミサが『やめて!』って悲鳴を上げると、コージはニヤリと笑って、『ドライブしようぜ』て、言ってね。ミサが素直に頷いて、ふたりで真夜中の街をバイクで駆け抜けるんだよ」
おいおい、病院に行くのが先だろうと、カブ先生は心の中でツッコミを入れた。洗浄して、一刻も早く避妊処置を施す必要がある。
「コージは野球部のエースかな?」
「ううん、サッカー部のキャプテン」
時代背景を読み間違えた。
「ミサが『あたし、海が見たい』って言うと、コージがコクンと頷いてね。途中で、暴走族に絡まれたりするんだけど、みんな蹴散らしちゃってね」
さすがにサッカー部のキャプテンだ。
「夜明けの海は、きれいだったなあ。波がキラキラ輝いて、これから新しい世界が始まるって感じ。コージは歓声を上げながら、着ているものを全部、脱ぎ捨てて、海に飛び込んで行くんだよ。ミサも全部、脱いじゃって、コージのあとを追うの。ふたりは海の中で抱き合って……」
そのシーンが目に浮かんだ。カメラアングルは、逆光だろう。水平線から昇る太陽をバックに、黒いシルエットの男女が唇を重ねて……。
「わたしも、夜明けの海が見れるかな?」
ヤコの問いかけに、俗っぽい青春ドラマの映像が霧散した。
「夢だったの。好きな人ができたら、一緒に夜明けの海に行くのが夢だったの。そのときわたし、夜明けの海を見ることができるのかな?」
声が震えていた。カブ先生は沈黙した。ヤコの手術を執刀する医師からは、命の方を優先すると宣告されていた。医師としては当然の判断だ。後頭葉にできた悪性腫瘍で、脳内の視神経が交錯する箇所を侵している。視神経を保存したまま腫瘍だけを取り除くことができる確率は30%にも満たない、それが、執刀医の下した診断だった。
カブ先生は答えられなかった。できれば、大丈夫だと言って、安心させてやりたい。しかし、その場限りの安易な励ましや空疎な慰めは、失明したときのショックを倍増させるだけだ。医師の言葉だけに、その責任は重い。
「先生、ごめん、くだらない話に付き合わせちゃって。今度こそ本当に、おやすみなさい……」
「今から行くぞ!」
受話器に向かって、怒鳴っていた。
「夜明けの海を見に行こうや。これから迎えに行くから、ちゃんと支度をしておくんだぞ」
「だって、先生……」
一方的に通話を切ってから、カブ先生はフーッと息を吐き出した。
「なんだか、どこか別の世界に行くみたいだね」
ヤコが、ぼそりと言った。長いトンネルに入っていた。山中を穿った広大な空間は、黄色灯でセピア色に照らされて、時間さえも遡っているような気がした。
「別世界か……」
カブ先生は、個人タクシーのトメさんに電話したときのことを思い出した。
「えっ、太平洋まで! ようがす。先生の頼みだったら、この世の果てでも行きまっせー」、威勢はいいが、寝ぼけと酔いで呂律が回っていなかった。
「『惑星ソラリス』という映画を知らないか?」
「見たことないよ。だって、映画館なんて、うちらの街にはないじゃない」
「ひと昔前の映画で、テレビでも何度か放映されたことがある。実は、先生もテレビで見たんだ」
「おもしろいの?」
「正直、退屈だったな。タルコフスキーというロシアの映画監督の作品でね。カンヌで審査員特別
賞を獲った名作なんだが、何を言いたいのかさっぱりわからなかった」
トンネルの天井に、飛行機のプロペラのような装置が設置されている。換気扇なのだろうが、現実離れした大きさで、奇抜なデザインをしている。
「その映画の中で、未来都市の地下通路を車で走るシーンがあるんだけど、こんな感じだったような気がする。もっとも、東京の首都高速道路で撮影されたんだから、雰囲気が似ているのは当然かもしれない」
トンネルの出口が見えてきた。道路灯に照らされた高速道路の光景に、カブ先生は苦笑した。トンネルを抜けると、あの映画の中の未来都市に入り込めるのではないか──、心のどこかでそんな期待をしていた自分に気づいたのである。未来の病院に、ヤコを連れて行ければ……。
しばらく走ると、「太平洋まで200キロ」という看板が視界をよぎった。
「海に行く相手が、こんな爺さんで悪かったな」
気になっていることを口にした。自分の思い込みで、突っ走ってしまった。
「先生は、大好きだよ」
冗談っぽい口調に救われた。
「ヤコは、好きな男の子はいないのか?」
ヤコが沈黙した。
「どうやら、いるようだな」
「ビリー……」
「ほう、外人さんかい?」
「ビリッケツのビリー。その子、運動が苦手で、いつも運動会の徒競走でビリだったの」
「いやな渾名だな」
「でも、色が白くて、髪の毛が栗色だから、ビリーていう名前、とても似合ってた」
「同じクラスの子?」
「小学生のときだけね。今は、違う高校に通っているから、たまにしか見かけることができないけど」
どうやら、ヤコの片想いのようだ。
「 急に雨が降り出して、バス停の小屋で雨宿りしていたら、ビリーが自分の傘を貸してくれたの。自分はずぶ濡れになって、そのまま走って行っちゃった」
ヤコがクスリと笑った。
「その傘、端っこが二カ所も取れていて、傘を差しても体の片方が濡れるんだよ。ちゃんと縫いつけてから返したんだけど、その傘、ビリーはずっと使ってくれていた……」
「初恋かい?」
「どうかな。三番目ぐらいじゃない」
はぐらかした。
「先生は、好きな人はいないの?」
切り返された。
「もう、引退だよ」
本音だった。あんなしんどい思いはしたくない。
「どんな人だったのかな」
「誰がだい?」
「先生が好きだった人」
ある女性の顔が、鮮明に浮かんだ。
「もう忘れちゃったよ。ずいぶん昔のことだからな」
「ずるいよ。わたしにばっかし、しゃべらせて」
「年を取ると、ずるくなるんだよ」
これも、本音だった。
ヤコに、いや、人に話せることではなかった。相手は人妻だった。それも、自分の患者の奥さんなのだ。
カブ先生が勤務していた大学病院に、加藤俊也が入院してきたのは、黄葉も終わりの晩秋の頃だった。膵臓癌の末期で、すでに手遅れの状態だった。病状を告知するカブ先生の話を、妻の聡美が強ばった顔で聞いていた。見開いたままの瞳から、涙が溢れた。
それが、夫に対する愛情の涙ではないことがわかるまで、さして時間はかからなかった。夫の度重なる浮気が原因で、夫婦仲は冷え切っていた。聡美は離婚を決意していた。それが、死病に取り憑かれた夫に、おれを見捨てないでくれと哀願された。夫の要望を受け入れざるを得ない自分に対する、悔し涙だった。
「どうせ、おれが早く死ねばいいと思っているんだろ」
「おれの遺産が目当てなのか?」
「このお茶、やけに苦いな。毒でも入ってるんじゃないだろうな」
自暴自棄になった夫の暴言を、聡美は黙って耐えていた。自分の感情を押し殺して、献身的に身の回りの世話をする聡美に、カブ先生は同情した。いつしかその想いは、恋情に変わっていた。
入院から半年後に、加藤俊也は亡くなった。臨終の場で、開放感を覚えている自分をカブ先生は恥じたが、担当医として全力を尽くしたという自負はあった。
「君、自分の患者の奥さんと付き合っているんだって」
教室の教授に呼び出されて、詰問された。
「今は、未亡人です」
「同じ事じゃないか。そんな破廉恥なことが、許されると思っているのか?」
「やましいことをしているとは、思っていません」
教授の口元に嘲笑が浮かんだ。
「たとえそうであっても、世間は違う見方をする。おもしろおかしく噂話が膨らんで、それをみんなが信じてしまう。デタラメの方が、事実になってしまうんだ。君が世間から糾弾されるのは勝手だが、この教室や大学の名誉を傷つけられるのは困る」
「わかりました、明日、辞表を持って出直して来ます」
教授が苦笑を浮かべた。
「君も、頑固だからな。まあいい、一週間、時間をやろう。頭を冷やして考えてくれ」
カブ先生は結局、辞表を書かなかった。聡美の方から別れ話を切り出したのだ。
「あなたがいくら優しい言葉をかけてくれても、わたしがあなたの将来を奪ってしまうことに変わりはないわ。わたしは、その重荷をずっと背負って生きることになる。愛情は、いつかは冷めるの。あなたはきっと、わたしを選んだことを後悔するようになる……」
年は三歳年下だが、夫婦の修羅場を経験した聡美の方が、言葉に重みがある。ビギナーのカブ先生に、抗する言葉はなかった。
(いや、違うな)
カブ先生は内心、ホッとしたのだ。大学病院の医局に対して未練があった。人並みに、いつかは教授になって医局のトップに立ちたいとの野望があった。
(おれの気持を試したのかもしれないな)
未練かもしれないが、今ではそう思う。それでも、自分を選んでくれることを聡美は期待していた……。そう、思いたいだけかもしれない。
「先生も、好きな人に傘を差しだしたことがあるんだ。土砂降りの雨でね。ふたりで傘に入ったんだが、穴だらけの傘で、てんで役に立たない。そのうち、雷まで鳴ってきてね。それで、怖くなって先生だけ、屋根のあるところに逃げ込んだんだ」
「ひどーい」
ヤコが 抗議した。
「ああ、ひどいな。それで、フラれちゃったんだよ」
「でも、その人、先生のこと、ずっと待っていたような気がするな」
ヤコも、カブ先生の話の寓意に気づいている。
「もう昔の話だよ。ボロボロの傘なんか捨てちゃって、今ではもう、自分の立派な傘を持ってるさ」
風聞で、聡美が介護事業を興して成功しているという話を聞いたことがある。
しかし、カブ先生は結局、大学病院を飛び出して、伯父がやっていた故郷の小さな診療所に帰って来た。医療過誤に巻き込まれたのだ。
明らかな医療ミスだった。脳動脈瘤だが、自覚症状もなく、緊急に手術を要する状態ではなかった。
それを、脳神経外科の講師が出張ってきて、担当医のカブ先生の反対を押し切って、強引に手術した。論文のために、一例でも多くの手術を経験したいとの勇み足だ。患者はその手術が原因で、一ヶ月後に脳梗塞を起こして他界した。
カブ先生は遺族側の証人として、裁判に臨んだ。それでも、敗訴した。裁判では、告訴した側が、医療過誤を証明しなければならない。すべてのデータを大学病院が握っている情況で、脳動脈瘤除去手術と、その後に起きた脳梗塞との因果
関係を実証することは、ほとんど不可能に近い。
仲間を売った裏切り者として、カブ先生は大学病院を去った。もうひとり、大学病院を去った男がいる。脳神経外科の川崎晋吾、学生時代はカブ先生と同級生だった。川崎はそのあと、単身でオーストラリアに渡り、現地の病院で手術の腕を磨いた。今では凱旋して、日本のトップクラスの脳神経外科医として活躍している。ヤコの執刀医である。
医療過誤裁判の時、カブ先生は川崎に、遺族側の証人として法廷に出てほしいと要請した。川崎は迷った。しかし、結局、川崎は証言台に立たなかった。いや、立てなかった。
「おまえには借りがあるからな」
ヤコの手術を快諾したあとで、川崎はそう言って、カブ先生に頭を下げた。
ライトアップされた瀬戸大橋を渡るとき、ヤコが何度も歓声を上げた。ラジオ深夜便は、演歌特集を終えて、ジャズを流している。MJQ、モダーン・ジャズ・カルテットのナンバーだ。
高松自動車道の豊浜サービスエリアで、休憩を兼ねてガソリンを補給した。深夜も営業しているスタンドはここだけだ。高知自動車道に入って、ひたすら南下する。終点の須崎東インターチェンジで、高速道路を降りた。
(ここからが問題だ)
カブ先生は緊張した。一般道の方が、警察と接触する確率は高くなる。軽トラの爺さんの調子は上々だった。制限時速の50キロをきっちり守って、足摺岬方面
に向かった。
「潮風のにおいがするよ」
ヤコの言葉に、カブ先生は大きく息を吸い込もうとしたが、徹夜の強行軍で鼻炎が悪化したのか、鼻が詰まっている。ただし、ぼんやりとだが、海岸のシルエットを確認できた。
(本当に、太平洋までやって来たんだな)
車のハンドルを、いたわるようにやさしく撫でた。
後続のワゴン車が、しびれを切らしたように、カブ先生の軽トラを追い越して行った。そのとき、赤色灯が小さな弧
を描いた。しばらくすると、街路灯に警官の姿が浮き上がった。
(こんな時間に、ネズミ獲りか。そこまでして、検挙率を上げたいのか)
カブ先生は、自分もヤコも、きちんとシートベルトを装着していることを確認した。
公園の空き地に誘導されるワゴン車の傍らを、徐行して通過しようとしたときだった。行く手を、警官に阻まれた。手のひらを突き出して、停車するように命じられた。
(何も違反はしていないはずだ)
近づいてくる警官を睨みながら、カブ先生の心臓は高鳴った。
「右側のストップライトが切れてますよ」
(この、老いぼれのポンコツめ!)
心の中で悪態をついた。万事休す。免許証の提示を求められれば、ここでジ・エンドだ。
「違う違う」
後ろで声が聞こえた。
「泥で汚れていただけだ。壊れちゃいないよ」
もうひとりの警官が、笑いながらそう告げた。
「失礼しました。でも、たまには洗車、してくださいよ」
警官が敬礼して、車から離れた。カブ先生は、焦る心を押さえつけて、車をゆっくりスタートさせた。
「神様って、本当にいるんだね」
興奮した声で、ヤコが言った。
「わたし、心の中で、ずっと神様にお願いしてたんだ」
カブ先生も頷いた。ハンドルを握る手に、べっとりと汗をかいていた。
見渡す限りの水平線が、茜(あかね)色に染まっている。その中央が黄金に輝いた。眩い光輝は大きさを増して、秋晴れの空を燃え立たせる。
「やったー!」
ヤコが歓声を上げて、海に向かって白い砂浜を走りだした。
(終わりではない……。これから、始まるんですよね)
黄金に抱(いだ)かれたヤコのシルエットを見守りながら、黎明(れいめい)の海に語りかけた。カブ先生は、静かに合掌した。
Copyright(c): Fuyuhiko Aki 著作:亜木 冬彦
◆
「海へ」の感想 (掲示板)
合い言葉は「ゆうやけ」
*タイトルバックに「CoCo*」の素材を使用させていただきました。
*亜木冬彦&赤川仁洋の作品集が文華別館に収録されています。