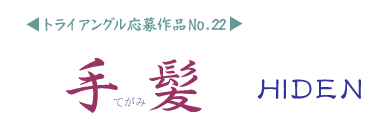
「ねえ知ってる?毎月二十三日って『ふみの日』って言うんだよ。手紙を出す日ってことなんだけどさ、なんか私の日みたいでしょ?」
芙美は俺と違って筆まめだった。彼女と付き合ってから、携帯で会話やメールのやりとりも当然していたが、どういうわけか彼女は手紙に人一倍こだわった。季節の挨拶や旅先からの便りを欠かさなかったのはもちろん、毎月二十三日はふみの日だから、と定期的に俺の元へ葉書をよこすくらいだった。彼女が言うには「手紙の方が気持ちが伝わるから」なんだそうだが、俺は正直そんな偏執的なところに次第に嫌気が指していた。
そしてついに我慢が出来なくなった俺は、ある日彼女に別れを切り出した。案の定、彼女は思いとどまるように様々に嘆願してきた。携帯、メール、もちろん手紙。お前のそういうところが大嫌いなんだよ、と何度言ってもそれは一ヶ月ぐらい続いた。
ところが、ある日を境にそれがぷっつりと途絶えた。俺はさすがに諦めたんだろう、と思っていたがそれは違った。三日ぐらい間が空いた頃だろうか、突然夜中に俺のアパートまで押しかけ、「別れてあげる。だから最後に抱いて」と彼女は呟いたのだ。
そのときの彼女は異常だった。目はまるで焦点が合っていないし、声は男のようにしわがれていた。しかし一番変わっていたのは、ばっさりと切り落としてまるで少年のようにすっかり短くなってしまった髪だった。よく失恋したから髪を切る云々という話があるが、それにしてもその切り方はまるで後先を考えてないような感じだった。
ともかく、彼女の最後の頼みだと思ったから、俺は求められるままに彼女を抱くことにした。もう眠いからいいだろ、と何度か言ったが、それでも彼女は「だめ。今じゃなきゃだめ」と耳を貸さず、俺の体を相変わらず執拗に求めてきた。
しばらく後、彼女が手首を切って自殺したという噂が耳に入った。先月の二十三日、そう、よりによって彼女がいつも手紙をくれるふみの日に。
ただ、俺はそのとき既に別の女と付き合っていたから、さっさと芙美のことは忘れようと懸命になっていた。芙美の痕跡とかそういったものを消したかったから、そいつをアパートに連れ込んで寝起きするようになっていた。
そんなある日のことだった。
朝、起きてみると、テーブルの上にノートの引きちぎった切れ端が置いてあった。
俺はそれを見て思わず噴出してしまった。まるで平仮名を覚えたての子どもが、必死に一生懸命書いたけど、途中で投げ出してしまったような、そんな感じで弱々しく横書きで「めし」と書いてあったのだ。
「おい、恭子。腹が減ったのか?」
冗談を言いながらまだ寝ぼけ眼の恭子に訊く。
「何言ってんの?」
「これ見ろよ。超ウケ」
恭子の目の前でひらひらと振って、一緒に馬鹿笑いした後、俺は丸めてゴミ箱にそれを放り込んだ。
でも、次の朝。またテーブルの上には紙切れが置いてあった。しかも昨日と同じように弱々しい字で「めい」と書いてある。さすがに冗談にしては変だ。
「おい、何のつもりだよ」
俺は恭子をたたき起こして尋問すると、寝起きで不機嫌なのか恭子がキレだした。
「知らないって言ってんでしょ?何で私がそんなことしなきゃいけないのよ。大体それ昨日のじゃないの?」
念のためゴミ箱を漁ると、やっぱりくちゃくちゃに丸まったあの紙が出てきた。
「ちげーよ。だれか書いたんだよ、これ。お前だろ」
「いい加減にしなよ!?あんたでしょ?」
「俺は昨日も夢見てねーんだよ。そんくらい熟睡してて、そんな書けるわけねーだろ?」
そんな調子でその日はお互いに一日中機嫌が悪かった。
しかし、次の日になったら機嫌が悪いなんてものじゃすまなくなった。また、テーブルの上に紙が置いてあったからだ。
「何だよこの『めいい』ってのはよ!冗談も大概にしろよ!?」
そう、明らかに字が増えていたが、問題はそこではない。
「私が書いたんじゃないって何度言えばわかんのよ、この馬鹿?」
「ああ!?」
「大体ね、夜中にごそごそ起き出してテーブルの方で何かやってたの、あんたでしょ?」
俺は思わず耳を疑った。そんな記憶は無い。
「ホント、自分のこと棚に上げて他人のせいにしてさ、こんなサイテーなのと付き合ってたなんて信じらんない!」
恭子はその辺に転がっていた紙袋の中に自分の荷物をぎゅうぎゅうと押し込める。
「おい、何のつもりだよ?」
「出てく」
「おい!」
「携帯の番号変えるからね。二度とかけんなよ。じゃーね!」
部屋中が軋む勢いでドアが閉められた。後に残った俺は、彼女が去ったことによる消失感ではなく、後に残された疑問だらけの状況に呆然とした。
「何なんだよ、一体よお」
その夜、俺は全てを確かめるために仕掛けをしておいた。テーブルの上にあらかじめノートの切れ端を置き、その側に黒の油性マジックでべたべたに軸を塗りつぶした鉛筆を添えておいた。こうすれば、暗闇の中でこのペンを掴んだ侵入者の指紋があちこちに残るはずだ。そして俺は肝心なことを忘れ、安心して寝入った。
翌朝。予想していた通り、部屋中のあちこちに真っ黒い指紋がべたべたとくっついていた。そう、真っ黒な指先によってつけられた俺の指紋が。
これではっきりしてしまった。俺は毎日夜中に起きだして、ノートのページを引きちぎり、そこに下手くそな字で謎の言葉を残し、また何事も無かったかのように寝付いているのだ。
でも何でそんなことをしているんだ?今まで夢遊病などにかかったこともない俺が何で毎晩そんな変なことを繰り返さなきゃならないんだ?
毎朝、テーブルの上に残される文字は次第に増えていった。
「『めいいく』って何だよ・・・」
俺の独り言はすでに泣き言になっていた。
筆記具を処分すれば醤油で書かれる。紙を無くせばナイフでテーブルに刻まれる。
奇行は続く。疑問は尽きない。ただ一つはっきりしているのは、この状況を続けていたら気が滅入るのを通り越して、きっと気が変になるんだろう、ということだった。
こうなったら何があっても起きられないくらい寝付いてしまうしかない。意を決した俺は酒屋で日本酒を一升瓶で買い、それをコップに注いでは次々と胃袋に流し込んだ。途中何度か吐いた。それでも飲んだ。今夜はぐっすり寝かしてくれ。明日だけでもいいから怯えない朝にしてくれ。頼むから。
外が明るいのと、頭痛と吐気で目が覚めた。ちらっと横目でテーブルの上を見る。が、テーブルの上には何も置いてなかった。足腰も立たないほど飲めばあの文字は無くなる、ということはわかったが、こんなことを毎日繰り返した日には気が変になるならないという以前に、アル中で死ぬのは目に見えている。
「うわ、最悪」
ふと身の回りを見てみると、枕や布団に反吐がぶちまけられていた。どうやら寝ながら吐いてしまったらしい。仕方がないので雑巾で固形物を拭き取った後、洗濯をするためにカバーを外した。
「うわああああああああああ!?」
反射的に汚物だらけの枕を放り投げ、壁に背中を打ち付けるほど後退った。
枕の中に入っていたのは、ぞろりとした黒く長い髪の毛。もちろん俺のじゃない。恭子は染めていたから違う。
芙美だ。あれは芙美の髪の毛だ。―――するとあれは?
俺はゴミ箱をひっくり返した。例のしわくちゃに丸めて捨てた紙切れを広げる。「めいいく」って書かれている?――違う。横画があまりにも薄くて見えなかっただけだ。俺は注意深く目を凝らしながら一文字ずつ声に出して読んだ。
あ、い、し、て、る。
震えて動かない体とは対称的に、頭の中は霧が晴れていくように明白になっていった。
芙美が髪の毛をばっさり切り落としたのは何故か。ここに髪の毛を仕込むためだ。芙美があの晩、俺を寝かさなかったのは何故か。何があっても起きないほどに熟睡させ、その隙にこれを枕に入れるためだ。そして何をしようとしたのか。自分の髪の毛を媒介に俺を操作し、死んだ後も俺に手紙を残そうとした。
では何故こんなに横画が頼りない薄い字しか書けなかったのか?
彼女は手首を切って死んだ。だから、霊となった今もうまく紙が押さえられない。それで、時間がかかっても最後まで慣れなかったのだろう。横に書くときに押さえる手に力が入る、横画は、特に。
俺はゴミ袋に枕を丸ごと詰め込み、指定の曜日でもないのに捨て場に追いやった。これで安心して寝られる。そう思えば今日驚いた分は安いものだ、と思った。
しかし、翌日もその翌日も手紙は続いた。
もう勘弁してくれ。頼むから止めてくれ。髪の毛は枕ごと捨てたのに、どうして。どうにか残り少ない理性をフル回転させて、何故なのか考えてやっと気づいた。
枕に入っていた髪の毛だけじゃ、量が少なすぎないか?
部屋中を捜索した。布団、収納ボックス、流し、トイレ、バス、フローリングの隙間。ありとあらゆるところから黒くて長い髪の毛が見つかった。そりゃそうだろう。彼女がわざわざ分けて仕込まなくても、部屋に連れ込んだことがあれば、自然に一本や二本どこに紛れたっておかしくない。
このままじゃ発狂する。逃れさせてくれ。せめて一日だけでも。
思い立った俺は、財布から万札を三枚抜き取り、駅前に向かった。服を全て新しく買いなおし、今まで着ていたのを店で処分してもらった。履いていた靴も同じように買い換えた。そして彼女が立ち寄るはずの無い、古いカプセルホテルに泊まることにした。
店に備え付けのガウンに着替え、カプセルの中で落ち着く。座ると頭が支えそうな、寝るだけの空間。それなのに、俺は心底安らいだと思った。ここには余計なものは何もない。筆記具もない。紙もない。彼女の髪の毛もない。何もないということがこれほど安心できることだとは思ってもみなかった。そう思ったら笑いがこみ上げてきた。はは、ざまあみやがれ。手紙でも何でも書けるものなら書いてみろ。
俺は久しぶりに楽しい夢を見るために寝た。
安心しすぎたのか、起きたのはチェックアウトの三十分前だった。
「ん、何だ?」
何故か右手人差し指が痛い。見てみると血が出ていた。どこかに引っかけたのかもしれない。まあ古いところだからそれぐらいの不備はあっても別に変じゃない。それより、またあのアパートに一回戻る前に、もう十分だけ寝ておくか。
そう思って寝返りを打った。
「あああああああああああああああ!!」
反射的に飛びのいて頭を激しく打った。周りにいるやつらが「うるせえ」と文句を垂れる。しかし、そんなことはどうでもいい。
壁に『あいしてる』って書いてあった。
俺に読める向きに、擦り付けるような血文字で。
俺は這うようにしてそこを抜け出すと、着替えるのもそこそこにホテルの外へ走り出した。
先生、そんなわけで俺はここに来たんだ。受付のねえちゃんに乱暴したのは悪かったと思ってる。でも、俺は焦ってんだ。今すぐ調べてもらいたいことがあるんだ。だってそうだろ?何でカプセルホテルにまで彼女が手紙を残せたんか、考えてみたらもうそれしか思い当たんないじゃないか。
なあ先生、彼女、髪の毛を俺の体内のどこに埋め込んだと思う?
先生医者だろ?うまく見つけ出してくれよ。場合によっちゃ手術したって構わないからさ。もちろん今日中に頼むよ。急いでいるんだよ。え、なんでかって?
明日は二十三日、ふみの日だよ?
俺が生きている保証が一体どこにあるって言うんだよ!?