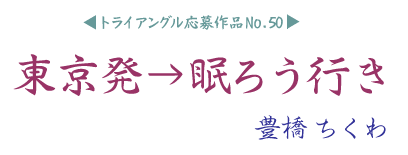
「山崎ッ! 今すぐ根室に飛んでくれ! 他社には抜かれるなよ。」
上司は電話を切り、僕に向かって檄を飛ばした。今日は朝から大きな事件もなく、スタッフ全員が、だらだらと終業時間を待ち望む、極めて平和な一日を終えるはずだった……
そんな僕も朝から時間を余し、いつも以上にタバコの本数が増え、机の上に置かれた灰皿に高々と吸い殻が山を造っていた。その山から崩れ落ちた吸い殻が数本、机の上に散らばる始末、後23分、どう時間をつぶそうか、そう考えながら西側の窓際に位置する自分の席から外の夕やけ空を眺め、「もう春だな〜」、などと詩人になって見たり、今日の夕飯は何にするか? 連日の生ビールと肉野菜定食も飽きた事だし、マーボ定食でも…… などと考え、すかっり僕的に今日の仕事を終業していた。
そんな僕に白羽の矢が立った。
誰もが嫌がるこんな時間に俺なのかよ? ついついその思いが言葉となってこぼれ出た。
「俺かよ!」その言葉は、しっかり上司の耳に届き、嫌みタラタラな口調で上司は僕に向かい、「お前だけだぞ、今月スクープないの! このままだと来月は減給だな。誰か行ってくれる奴居るか?」そう言って、辺りを見回した。
こんな時間から3時間以上もかかる取材先に行きたい奴など居るはずがない。そんな事はわかっていたが、僕はこれを逃せば減給だ、今でも生活が苦しいのに、これ以上、給料が下がったら…… そう思った時には、「行かないって言ってないですよ…… 今すぐ出ます」こう答えていた。
来月から肉野菜定食も食べられなくなる、いや! ビールの方が大事だ。そう思った僕の素直な気持ちの現れだった。
僕は、椅子にかけて有ったジャケットをはおり、取材機材のギッシリ詰まった10kg以上も有るカバンを肩から背負って事務所を出た。午後6時を過ぎたこの時間、事務所を出た通りはちょうど通勤ラッシュとなり、この路地からタクシーを捕まえるのは無理な事が一目瞭然だった。大通りまで出れば、そう思い、肩に食い込むカバンのショルダーを何度もかけ直し、大通りを目指して歩く事を決意した。それはまるで、オアシスを求め砂漠を放心で歩き続けるのに似ていた。
砂漠に行った事はないが、この時ばかりは、悲劇のヒーローを演じたい気分だった。
僕の感は的中し、大通りに出て直ぐにタクシーは捕まった。「やっぱ、俺って天才か?」などと心の中で囁きながら小さくガッツポーズを取り、タクシーへ乗り込んだ。
「お客さん、何処まで?」、愛想の良い運転手の声にホッ! と肩の力を撫で下ろす。
「東京駅まで。」僕は運転手にそう伝え、明日の取材内容を確認しようと、カバンから手帳を取り出していた。
「何処かへお出かけですか?」そう運転手が声をかけてきた。
「仕事で根室まで。」そう、ぶっきらごうに僕は返事を返した。明日の仕事の段取りを邪魔されたくなかったからだ。
「眠ろうですか、いい所ですよねぇ。」そう運転手が返事を返してきたが、僕は聞く耳を持たず、もちろん返事は返さずにいた。
二人の沈黙が続く中、多少、渋滞は有ったものの、40分程で東京駅に着いた。僕は重いカバンを抱え、足早に緑の窓口へと向かった。なんとしても日付が変わる前、今日中に現地入りだけはしたいと思っていたからだ。
緑の窓口に飛び込み、「根室行きの指定って取れます?」と、息を切らしながら窓口のお姉さんに問いかけると、「眠ろう行きですね。少々お待ち下さい。」、優しい雰囲気の彼女は、僕にそう言って微笑んだ。
その笑顔はカバンの重さや仕事の辛さなど吹っ飛んでしまう程、透き通った優しい笑顔だった。そんな彼女の笑顔は、根室が眠ろうと聞こえたとしても、それを不思議と感じる事さえ忘れてしまう程、安らぐ笑みだった。
「開いてますよ、丁度、お一つだけ。10分後の発車です。どうされますか?」
「それ、お願いします。」そう言って彼女に料金を渡し、引き替えに渡されたチケットと釣り銭をジャケットのポケットに投げ込み、乗車口へと急いだ。
発車ホームを見つけ、近くの乗車口から車両へ飛び込むと、それと同時に発車のアナウンスが流れ、チャイムが鳴りやみ、搭乗口が閉まった。チケットをポケットから取り出し、車両番号と座席番号を確かめ、くつろぎの場を目指し揺れる車両の中を進んで行った。
「やっと、少しゆっくり出来るな。」左右に揺れる自分の体を必死にこらえ、自分のチケットに記された席に座った時、一つの不思議なことに気がついた。
「僕の他に乗客が誰も居ない!」
辺りには人影一つ見当たらないのだ。窓口のお姉さんは満席だと言っていたはずだが…… この車両を含め、全ての車両に人が誰も乗って居ないのだ。
「──どうなって居るんだ!?」
キツネに摘まれた様な自分が置かれたこの状況に居ても立っても居られなくなり、立ち上がって乗車口方へ振り返った瞬間! そこに一人の女性が立っていた。
「こんばんは。私の席、隣なのですが、よろしいですか?」
そう彼女は声を掛けてきた。席を立ち、乗車口へ向かう為に通路をふさいでいた僕が彼女には邪魔だった様だ。
「ごめんなさい。邪魔ですよね…… ご旅行ですか?」
それまでの自分の慌てた姿が妙に恥ずかしく、ついつい照れ隠しで彼女にこんな言葉を掛けてしまった。
「ええ。」
彼女の優しく返してきたその一言は、どこか気持ちの落ち着く透き通った響きなものだった。こんな時に気の利いたセリフの一言でも言えたなら、楽しい車中での時間が過ごせるのだろう。しかし、僕ときたら女性経験が豊富な方ではなく、何をどう話して場を盛り上げれば良いのか見当もつかなかない。そんな時、彼女の方から僕に話を掛けてきたのには正直、驚きだった。
「ご旅行ですか? 眠ろうは静かな街ですよ、温泉も物凄くイイですし。」
彼女はそう言って微笑んだ。
「眠ろう!? 根室ですよね?」
とっさに言い返した。
「根室!? 眠ろうですよ。初めての方は皆さん間違えるのよね」
彼女のその言い草からすると、何度も眠ろうとやらに訪れているようだ、ならば僕が間違った事を言っているのか? 何が何だか、訳がわからなくなっていたその時、
「眠ろうまで、あと少しですね。このトンネルを抜ければ直ぐですから。私、少し横にならせて頂きますね。」
彼女はそう言って、大きめのパッチリ二重の目を閉じた。ほんの数分の会話のはずだった。しかし、それは僕の大きな勘違いだった。自分の目を疑い何度も時計を見直したが僕の腕時計が示すデジタル表示は既に日付がかわっていた。「眠い。」隣の彼女が奏でる微かな寝息を聞くうちに、僕のまぶたは自力で開いてる事さえ困難となって行った。
「終点、眠ろう。眠ろう。お忘れ物の無い様にご注意下さい。」このアナウンスで僕は飛び起きた。横を見ると彼女の姿はそこに無かった。慌てて荷物を抱え車内の外へ出ると、僕の視界に想わぬ風景が広がっていた。その場に立ちつくす以外のリアクションなどあり得ない。そこは辺り一面を見渡す事が出来る、民家など一つもない野原なのだ。夜行列車が止まるには程遠く、もちろん無人駅だった。
昨日から自分が夢でも見ているかと錯覚さえ感じる不思議な出来事の数々、思わず「イテッ!」、頬をつねって見たが、やっぱり痛かった。夢なら覚めて欲しいと、一度、目を閉じ、また開く、正気を取り戻そうと、ラジオ体操第一をしてみたり…… 無理だった。これは全て現実なんだ。
僕は途方に暮れ、仕方なく無人の改札を出ようとした時、前を歩く昨日の彼女が視界に飛び込んできた。
「すいません! 昨日の方ですよね!」彼女を呼び止めた。彼女は振り向き、昨日の笑顔でこう話しかけてきた。
「やっぱり、眠ろうに来られたんですね、良かった。」
「やっぱりって? 終点で下ろされたんですよ、僕は」
「そのまま、戻っても良かったのに。」
彼女はそう言って僕の手を引くと、バス停まで案内してくれた。
「この土地には宿泊施設が一つしかないの、そこで1日、ゆっくりして行きましょうよ。」
「そ、そんな。僕には仕事が有るんですよ。今日中に根室で取材しないと、クビになっちゃいますよ!」
「だから今、眠ろうに来てるでしょ!」
そう言って、彼女は僕の手を引き、強引にバスに乗り込むと急に黙ってしまった。僕が何を話そうと口を閉ざしたままだった。
やがてこの土地に一軒しかないという宿に到着した。どのくらいの時間バスに揺られたのだろう? 何故か彼女と一緒に居ると眠くて仕方がないのである。朝、眠ろうに到着し、数十分でバスに乗り込んだのだから長くバスに揺られたとしても……
「──16時! って、なんだよ。俺は9時間もバスの中で寝てたのか? 何だよこれ!」
「さぁ、着いたわ。ここの温泉は絶品なのよ。ゆくっり温泉でも浸かって休みましょう。」
そう言うと彼女はバスを降り宿の受付で自分の名前を宿帳に記すと、自分の部屋へ向かう為、僕を後にし廊下の奥へと姿を消していった。仕方なく僕も宿帳へ自分の名前を書き込みながら1行前の彼女の名前を覗き見していた。「中澤 魅夢(なかざわ みゆ)」変わった名前だ、「魅夢(みゆ)って読むのかな?」などと考えながら自分の名前「山崎 剛(やまざき つよし)」と、その次の行に記した。
「温泉、直ぐ入れますよ。ごっゆくり。」そう言いって、気さくそうな受付のおばさんが僕に会釈してくれた。
何が何だか理解出来ぬまま、指示された部屋で僕は今までの出来事を振り返る事にし、無理やりでも良いから全ての出来事を整理しようとしていた。タバコをくわえ何度も考えたが、「理解できない。全然変だよ! もうヤダッ! どうでもイイよ。」
これが僕の出した結論だ! 結局、理解など無意味な事だ、そう僕は悟りを開かざるを得なかった。ヤケクソとはこの事だ、温泉でも行くか、そう思い立ち、用意してあった浴衣に着替え温泉へと向かう途中、「混浴!?」だったら…… とも考えたが、まるで期待はずれな結果だった。
男ゆ、この文字の書かれたのれんをしっかり確認し、手ぬぐい片手に湯船へ向かった。「露天風呂か? こんなにゆっくり湯船に浸かるのどれくらい振りだろ?」、自分の家では毎日をシャワーで済ませる事がほとんどだったからな。そんな事を考えながら固く絞った手ぬぐいを頭に乗せ、この時を割り切って堪能していた。その時、扉の閉まる微かな音が聞こえた様に思えた。
「ご一緒してもよろしいですか?」
か、彼女の声だ! 聞き覚えの有る優しい響きのその声に僕はピンと来た。あまりにも突然に訪れた衝撃に驚きを隠す事が出来ず、僕はその場に立ち上がってしまい、頭に乗せて有った手ぬぐいを手に取ることも忘れ、両手でとっさに男のそれを覆い隠し、彼女を背にしたまま棒立ちになってしまった。
「あら? 混浴でしょう、そんなに驚かなくてもイイんじゃない? 座ってよ、私が恥ずかしいわ……」
「のれんに男ゆって書いて有ったんで…… 見間違えちゃった? ごめんなさい。」
そう言って僕は彼女に言われた通り湯船に肩まで浸かり、彼女の方をおそるおそる振り向いた。「か、可愛い! 綺麗だ! 」振り向いた先に居た彼女は、長めの髪が濡れない様にタオルを頭に巻き付け、湯船に肩まで浸かっている。細くて白いうなじが印象的だった。
どうした事だ? 僕は彼女に夢中で話し掛けている。彼女と話をしている事が楽しくて楽しくて仕方ない。どちらかと言えば僕は人見知りをするタイプだ、女性にこんなにも積極的に話し掛けることが出来たなんて…… きっと彼女の可愛らしさや積極性、いや! 違う、僕という男の置かれた立場、本能がそうさせたに違いない。
会話の内容などは全く覚えてないが、部屋に彼女を誘ったのは僕の方だ。夕食を共にしアルコールも入り、二人は自然に男と女の関係、一夜を共に過ごす事になる。柔らかくとける様な彼女の肌の感触、僕が触れる度に微かに漏れる彼女の声、お互いが強く重なり合う事で彼女は熱くなった僕自身に気が付いていた。「暖かい、なんて彼女は暖かいんだ……」
部屋の障子も突き破る強い日差しに目が覚め、右手を魅夢(みゆ)のもとへと伸ばす。すると、そこには魅夢(みゆ)の残した微かな温もりだけが残っていた。隣に魅夢(みゆ)の姿は無い。僕の記憶も無い。実は魅夢(みゆ)の胸に触れた感触や肌の温もりは今でもはっきりと僕の体に残っている、だが肝心な事の記憶が無い。まるで欲求不満な僕は夢でも見たのかと思うほどだ。「夢!?」
思えば、ここへ来てから不思議な事ばかりが続く。魅夢(みゆ)の事もそうだし、街の景色や時間(トキ)までも、何もかも全てが不思議なんだ、そんな事を考えながら枕元に置いて有ったタバコに手を伸ばし、火をつけながら時計に目をむけた。「今何時だぁ?8時すぎかぁ? か、会社! 行かなきゃ、帰らなきゃ!」とにかく必死で身支度を済ませ宿を飛び出した。
これが平凡なサラリーマン、一般ピープルの宿命なのか? こまま、この土地で暮らそうなどと思う前に、「上司に怒られる、素直に謝れば何とかなる、なんて言えばいいんだ? 間違って、眠ろうに行っちゃって…… そんなの変だよ、とにかく謝ろう。」誤る事、それ以外の事は考えられなかった。
このシチュエーションにも慣れた物だ。バス停に目を向けると、そこには魅夢(みゆ)の姿が有った。バスを待つ魅夢(みゆ)に歩み寄り、照れながら軽く会釈した。
「おはよう御座います。」、魅夢(みゆ)はそう挨拶をし、自分の持っていた紙袋を差し出した。どうやらそれは、お土産のようだ。
「これ、眠ろう名物、マクラまんじゅう。美味しいのよ。」
「マクラまんじゅう?」その不思議なネーミングに笑えをこらえる事が出来ず、「プッ!」、吹き出してしまった。
魅夢(みゆ)は1つだけ手に持っていたマクラまんじゅうの包みを開け、「あら、本当に美味しいのよ、食べてみて?」、そう言ってマクラまんじゅうを僕の口元に運んでくれた。
「う、美味い!」、その言葉、それは僕が魅夢(みゆ)に掛けた最後の言葉となった。まぶたが重い、まるで鉛でも張り付いているようだ、徐々に微笑んだ魅夢(みゆ)が歪み、ボヤけながら僕の視界から消えていく。
「眠い、またこれかよ……」そして、これが僕の眠ろうでの最後の記憶となった。
記憶を取り戻したのは東京駅のホームだった。そこは人々が慌しくすれ違い、ざわめきが溢れる世界だった。この世界に慣れるまでに、長く時間は必要無かった。とにかく事務所に帰ろう、そして正直に誤ろう…… 「クビかなぁ……」、上司の鬼の様な形相を思うと、前に向かって歩く事さえ苦痛だった。何度もこのまま逃げようかと思ったが、事務所に私物も置いてる、お世話になった人への挨拶もしたい、僕はすっかりクビを覚悟し、重い気持ちと足を引きずりながら事務所へと向かった。
目の前には見なれた事務所の扉が立ちはだかる。この扉がこんなにも大きく感じたのは入社の時以来だと思う。あの時は緊張と期待がそう感じさせた。しかし、今は不安と恐怖がそう感じさせている。
扉が開くと、思った通り上司の一声が僕に向かって放たれた。
「山崎! 良くやった! 大スクープだ。」
「……」
意味がわからなかった。上司は僕に歩み寄り、肩を叩きながら僕の席の有る窓際まで共に歩き、満面の笑みで僕を誉め殺した。
「お前には期待してたんだ、これで昇進間違えなしだな!とにかく良くやった。」
「あ、はぁ……」
「お! お土産か? 仕事が上手くいくと気持ちにも余裕が出来るって事か、アハハハ。」
上司は僕の持つ紙袋を見つけたらしい、
「えッ、あ、マクラまんじゅう、現地で食べて美味しかったので……」
「アハハハ、冗談まで飛び出すとはな。ヒヨコまんじゅうだろ、東京駅で買って来たのか? とにかくお茶にするか、中澤くん、山崎にお茶を入れてやってくれ。」
「違いますよ? マクラまんじゅう……」紙袋に目を向ける。するとそこには、確かにヒヨコまんじゅうと書かれた包みの入った紙袋が有り、それを僕はしっかり握り締めていた。
中澤 真実(なかざわ まみ)が僕の元へお茶を入れて持ってきてくれた。彼女は昨年の入社ながら自分の出した企画が上層部に通り、入社2年目にしてチーフというスピード昇格を果したスーパーOLだ。そんな彼女にお茶を入れて貰えるなんて夢のまた夢だった。もちろん、会社での立場は僕の方が各下という事も有ったからなのだが……
彼女は僕に湯のみを手渡しながら耳元で囁いた。
「お疲れ様、おめでとう御座います。私もマクラまんじゅう好きですよ。」
「──えッ!」
そう言って僕を見つめる笑顔、それはあの時見た、始めて出合った時に見せた中澤 魅夢(なかざわ みゆ)の笑顔その物だった。
背筋が凍り付き、全身に震えが走る。僕の手からは湯のみが滑り落ち、ゆっくり静かに物音1つ立てず、スロー再生で床に叩き付けられた。
──彼女だけは知っている。僕の失った時間(トキ)、自分に関わる全ての人から消失した僕の本当の真実を…… 人が夢から目覚めた時、それが本当の現実とは限らない事も有る。