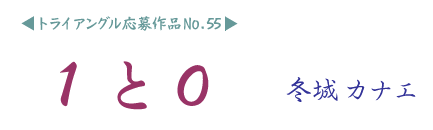
楠本晃は、自分が1と0で出来ていると思っていた。
目の前にあるパソコンも、マンションの外を走るゴミ収集車も、宅配のピザを届けにくるアルバイトの学生も、楠本にメールを送ってくる人間たちも、みんなみんな全て1と0の組み合わせで出来ている。
楠本は高級マンションの中から一歩も外に出ずに、国会議員並みの年収を稼ぐことができる。だから世の中のことに興味を持つことがない。彼にとっては1と0しかない世の中で、喜ぶのも悲しむのもただ面倒なだけだけだった。
そもそも毎日が時間との戦いで、彼には喜んだり悲しんだりするヒマさえない。プロのハッカーには無駄にできる時間など一分足りとも無いのだから。
だが、その楠本が、あろうことかパソコンのモニターを見つめたまま、先ほどから手を止めている。その間3分。2分で50万円稼ぐ男が手を止めていた。
『ボク、ヒカルちゃん。君はだーれ?』
そんな文章が目の前のモニターに映し出されている。味気ないノートパッドに、ただ一行。その下に“→”とあり、カーソルが点滅している。
こんなの、居たかな? それが最初の感想だ。
今操作しているパソコンはウィルス散布専用で、独立したメールアドレスを持っている。だから、たまにどこからか未知のウィルスが紛れ込んでくる。これもそのクチだろう。
まあ、こいつだったら壊れてもいいか。楠本はやがてそんな考えに至り、適当な言葉を打ち込んだ。データを消失させるような破壊系のウィルスが起動しても、元々ウィルスだらけのパソコンの一つや二つ、壊れたところで痛くもかゆくもない。
ノートパッドを閉じつつ保存すると、新たなウィンドウが立ち上がった。
『名前教えっこしたから、キミとボクはお友達だね(^o^)。ねえねえ、もっと教えてよ。キミはいくつなの? 男のコそれとも女のコ? 教えないと、このパソコンのデータを消しちゃうぞ』
脅し付きの文章が現れる。妙にリアルだと思ったが、この程度のセリフを返せる人工頭脳は今や珍しくない。
『二十代前半、男。ルックスはイケてる方』
楠本はキーボードを叩きながらふと思う。彼はれっきとした犯罪者で、以前にも一度だけ手が後ろに回りそうになったことがある。今の状況をざっと頭の中で計測し把握した。このヒカルちゃんが勝手に他のパソコンへデータを送信している可能性はないか、等々。
『なーに言ってんだよ(^^ゞ しかも今どき“イケてる”だなんて言わないよ。その分じゃあ、どうせカノジョもいないんでしょ?』
さすがにギョッとした。
楠本は思わず居住まいを正して、部屋の中をキョロキョロと見回してしまう。それからまたモニターを覗き込んだ。なかなかどうして精巧な人工頭脳じゃないか。
『彼女はいない』
『ほぅら、やっぱり。ボクが見つけてきてあげるよ。どんな女のコが好きなの?』
また手を止め、少し考えてからなるべく難しい言葉を使って文章を入力した。
『ヤセ型、ペチャパイ。それでいて顔はエンクミっぽいの』
『難しい注文だね。職業の指定はないの? 看護婦とかスチュワーデスとか』
『なんでもいい』
『分かった。じゃあ、明日ここに来るように、エンクミに似た子に片っ端からメール送ってあげるね』
「オイ待て!」
思わず口に出して言ってしまった。それから我に返って、独り赤面する。
『いらない。あんまり女に興味がない。もちろん男にも興味がない。余計なことはしなくていい』
『余計なことじゃないでしょ。華のない人生はツライよ(^^)』
ヒカルちゃんはウィルスのくせに、なかなか食い下がらなかった。また新しいウィンドウを立ち上げる。
『せっかくルックスがイケてても、それじゃダメだよ。今度ちゃんと女のコとの付き合い方をレクチャーしてあげるからね。ちなみにボクは「トロイの木馬」で「Light」って言ってくれれば、出張先のハードディスクをキレイにできるからね。好きなときに使ってよ。キミは友達だから、それぐらいはやったげる。じゃあね(^^)/ ̄ ̄ ̄』
と、勝手にウィンドウズが終了してパソコンの電源がプツンと落ちた。後に残るのは呆けた顔をして黒いモニターを見つめる楠本晃24歳。職業ハッカー生活もそれなりに長かったが、ウィルスに名乗られたのは初めてだった。
それから、ちょうど2分後に楠本は人差し指でチョンとパソコンの電源を入れた。
ウィンドウズの画面が現れると、すぐにノートパッドが立ち上がる。
『やあ、キミってけっこう寂しがり屋なの? なんつて』
楠本はそれを無視しF3キーを押して、様々な拡張子を叩き始めた。
ヒカルちゃんはこちらが“返事”をしないと反応しないようだった。楠本はノートパッドを放置したまま、調査を進めた。彼は業界に名を馳せるウィルス作家だ。すぐにヒカルちゃんの正体を知ることができた。
確かに“本人”が言うとおり、ヒカルちゃんは「トロイの木馬」型ウィルスだった。無害なプログラムの振りをして目標のパソコンにもぐりこみ、データを盗んだり破壊行為を行ったりするタイプだ。
中身をいろいろ見ているうちにプログラムの構成に見覚えがあることに気づく。さらに詳しく調べたら、ヒカルちゃんは過去に楠本が作った何某かの破壊系ウィルスをベースにしたものだった。誰か他の“作家”が、楠本のウィルスに手を加えて新しいものを作ったのだろう。
里子に出していた我が子が変わり果てて帰ってきたようなものだ。
なるほどね。と、楠本は納得して一人ニヤリとする。
『出張に行ってきてくれ』
彼はヒカルちゃんの使い方をもう理解していた。こちらに危険をもたらすことも無さそうだった。指定言語を使って命令を下す。
『オーケェ。ドコに行けばいいの? アドレスを教えて』
楠本は適当な企業のサーバーのアドレスを打ち込んだ。
『可愛いじゃん。エンクミって』
『まあな』
『こういうコが好みなの? ボクはキョンキョンみたいなのがいいな』
『小泉今日子だろ。今どきそんな呼び方しねーよ! 前から思ってたが、お前わりとオヤジだろ? なあ?』
『そんなことないよ。ボク1歳5ヶ月。まだバブバブオギャーってトコロ』
『何ワケわかんないこと言ってんだよ』
楠本は普段もウィルスやプログラムと会話をする。使う言葉はマシンにしか理解できないアルファベットと数字から作られる言語だ。
でもヒカルちゃんは違っていた。
彼──どうやら本人曰くオスらしい──は、日本語で会話ができる。しかもなかなか優秀なウィルスだった。元は自分が作ったものだから使い勝手も非常にいい。
ヒカルちゃんと会話を交わし始めてから三ヶ月。楠本は彼を相当気に入って使い込んでいた。仕事のないときには話し相手にもなってくれた。彼には人工頭脳が付属しているので、楠本が言葉を教えればそれを会話の中にまぜて使ってくる。
ヒカルちゃんはウィルスのくせに知ったかぶりをするクセがあった。エンクミもモー娘も知らなかったので教えてやった。教えてやったら今度は馬鹿みたいにそればかり繰り返したり、くだらない下品なジョークを言ったりする。
おそらくヒカルちゃんに人工頭脳を付けた人物の性格がそこに反映されているのだろう。
『そろそろクリスマスだね』
ヒカルちゃんが唐突に、そんなことを言った。ああそうか、と楠本は思った。彼の仕事にはとにかく季節感がないから、言われて初めて気づいた。
『なんだよ、パーティーでもやりたいのか?』
『うん。それもそうなんだけどね……』
ヒカルちゃんはなぜか煮え切らない口調だった。
『今までありがとう。キミと一緒に働けてホント楽しかった』
『何だよ。ウィルスのくせに改まるなよ』
そう返したら、不思議と返事がくるまでに時間がかかった。
『ボク、死ぬんだ』
その発言に、楠本は驚きのあまりパソコンの前で凍り付いた。
『どういう意味だ?』
『ボクの寿命が、あともう少しで終わるってこと』
文字は感情を表さず、ただ事実だけを述べる。楠本はノートパッドを放置して、また調査を始めた。元は自分の作ったものだ。相手が何を言っているのかはすぐに分かった。
確かにヒカルちゃんには時限タイマー機能がついていた。指定された日に何かのアクションを起こすようにプログラムされているのだ。
『お前はどうなるんだ?』
我ながら、馬鹿な質問だと思った。
『このパソコンのデータと一緒に消えて無くなるよ。ボクは0になる』
冷静に考えれば、ヒカルちゃんが精巧な二重のトロイの木馬だったというだけの話だ。会話で楽しませて安心させ、使った持ち主のパソコンを破壊する。それが彼の機能なのだ。
しかしヒカルちゃんはウィルスにしてはあまりに人間的だった。
『解除の方法はないのか?』
どうすればいい? どうすれば回避できる? 楠本は珍しく混乱していた。
『方法はあるよ。ボクを作った人に会って聞いてみればいい』
住所が出てきた。横浜市山下町のホテル。このマンションから徒歩十五分の距離だ。
『彼ならキミとボクの助けになってくれる』
アッ、と思った。
文字を見て、電流が走ったかのような衝撃が楠本の中を駆け巡った。やがて身体から力が抜け、彼はだらしなく椅子の背に身体をもたせかけていった。
──罠だったのだ。全て。
そこでやっと分かった。誰が自分を待っているのか。もう逃げ場が無くなってしまったのだということも。
彼は目を静かに閉じ、また開けた。
そして、立ち上がり黒いコートを掴む。
ホテルのロビー横の喫茶店のガラス戸を押し開けると、窓際で手を上げる男がいた。楠本は迷わずそちらへ向かう。
そばに立つと、男は吸いかけの煙草を灰皿に押し付けて、ニッと笑った。30代半ば。少し猫背気味の身体を紺色のスーツで包んでいる。シャツは白。ノーネクタイ。
「よく来たな。まあ座れよ」
会うのはこれで二回目だが、楠本はこの男のことをよく知っていた。星隆雄という名前の他にも、年齢・職業・出身校・妻子の有無・住民基本台帳の番号に到るまで。
「逮捕状、持ってきたんだろ?」
「いいから座れってんだよ、オネーチャンが困ってんじゃねえか」
男──星に言われて、楠本は後ろで気まずそうにしていたウェイトレスを通すように椅子に腰を落とした。星がコーヒーを二つ頼んで、彼女をカウンターに帰してやる。
「なあ、楠本」
星はショートピースにマッチで火を付けながら、ゆっくりとした口調で言った。
「天照皇大御神(あまてらすおおみかみ)って知ってるか?」
「何だよ、いきなり。……太陽の神かなんかのことか?」
「そうだよ。そいつはさ、世の中が嫌になっちまって岩の中に立てこもってボイコットをしたことがあるんだよ。そしたらお日様が照らないってんで、他の奴らが大慌てで集まってさ。それで建雷神(たていかづちのしん)っていう神様が岩戸の前で踊ってみせて、彼女がちょっと覗いたときに、えいやっと外の世界へ引っ張り出したわけなんだよな」
回りくどい状況説明だった。ストレートに“ざまあみろ”とでも言えばいいのに、と楠本は思う。彼は、まんまとおびき出されてここに来てしまったのだから。
「博識だな」
「……なんだよ、ふてくされるなよ」
星は楽しそうに言った。明らかにこの状況を楽しんでいる。楠本とは正反対に。
「アレはアンタの作品か?」
無駄な時間は一秒足りとも無いと言わんばかりに、楠本はいきなり本題を切り出した。
「そうだよ。ヒカルちゃん、なかなかお茶目なヤツだろ?」
まるで俺みたいにさ。そんなことを言いながら、男はハハハと口を開けて笑った。対する楠本は刺すような視線を相手に浴びせている。
「アンタはアイツのタイマーを外せるのか?」
「はあ? 何言ってんだよ。楠本晃大先生のおっしゃることとは思えないねえ」
星は大げさに耳に手をあててみせた。「アレは“YL2359”のタイマー機能を流用してるだけだ。解除したいんだったら自分でやれよ。俺は知らねえな」
「えっ……?」
楠本はこの時になって、初めてヒカルちゃんの正体を完全に理解した。
ヒカルちゃんは楠本が一番最初に流通させたウィルス“YL2359”をベースに作られていたのだ。このウィルスは12月31日の23時59分に、パソコンのハードディスクを破壊するものだ。
「うっそ。今、初めて知ったみたいな顔してんじゃん」
星はそこでやっと、真顔になった。
「お前、疲れてるんじゃないのか」
言われて楠本は苛立ったように下を向いた。
「実はさ……頼みがあるんだ。聞いてくれるか?」
楠本はゆらりと顔を上げて相手を見る。
「あの話、もう一度考え直してくれ。俺の部下になってみる気はないか」
ウェイトレスがやってきて、コトリ、コトリと神妙にアイスコーヒーを二つを置いて、薄い伝票を紙立てに挟み、そそくさとその場を去った。
楠本が何も答えずにいると、星が引き続き言葉を紡いだ。
「前に会ったとき、母ちゃんも姉ちゃんも0になって……それで終わりだったって言ってたろ? その話がどうしても気になってなあ」
楠本はただ無言でテーブルの上の灰皿を見つめていた。よく覚えていないが、どうやら自分はあの事件のことを彼に話したらしい。なぜだろう。なぜ話したんだろう。
「確かに人は死んだら、ただ0になるだけなんだな。どこにも存在しなくなるんだって妙に納得しちゃってさ」
あの日の朝のことはよく覚えている。20世紀が終わる最後の日だった。友人たちとスキー旅行に出かけようとする楠本を母親が呼び止めた。彼女は楠本に小遣いを渡して、笑顔で送り出してくれた。
「でも、俺に言わせれば、今のお前だって0になってるよ」
その日の昼に、母は眠っていた姉の顔に枕を押し付けて殺した。その後、自分も台所で首を吊って死んだ。
姉は交通事故に遇ってからずっと家に居た。右半身が動かず、脳に少し障害が残って言葉もたどたどしくなっていた。それでもがんばって生きようとしていたように思う。それなのに。
「お前はプロフェッショナルだ。どこにも存在を残していない。そんじょそこらのハッカー気取りのボウズとは明らかに違う」
楠本が旅行先から駆け戻ったとき、二人は家の和室に寝かされていた。顔には白い布。脇には5年ぶりに会う父親がただ独り座っていた。一言も会話はなかった。最後の記憶は時報を鳴らす時計のネジが回る音。楠本は顔を上げて時計を見た。23時59分だった。時計の針が一つ進み、ベルが鳴った。
「どうだ? 楠本。サイバーテロ課に来いよ。歓迎してやる」
星に問われ、楠本は我に返った。自分が勝手に笑っていることに気づく。
「その話は、前に断わったはずだろ。アンタだって二度目はないって言ったじゃねえか」
「だから俺が血を流した」
星は小さく言って視線をそらした。煙草を持ったままの手でコーヒーを掴んで中身をすする。楠本はその先を聞くことができなくなって、また言葉を失う。
「俺のことはいいんだ。所詮はノン・キャリだ。だが俺は、お前のことが惜しくて仕方ないんだ。お前の才能は闇の中にあるべきじゃない。そろそろいいだろ? 光の下に出てきたってさ」
返す視線を楠本に向けて。星はこぶしを作ってテーブルをトンと叩く。
「お前は家族を失ったときに、自分で自分の時間を止めちまったんだ。時計の針を進めてみろ。0から1になれ。お前ならヒカルちゃんになれる」
「なんだよ、それ」
楠本はプッと吹き出した。
「なんで俺がヒカルちゃんになるんだよ」
「人は変わることができる。ヒカルちゃんとお前を助けられるのは誰だ? お前自身だけじゃないのか。まずはヒカルちゃんを助けてみろよ」
ゆっくりと諭すように言う星。楠本の瞳に迷いが浮かぶ。そのわずかな間の後、星は視線を和らげ微笑んだ。
「あと、もう一つ頼みがあるんだ」
楠本は星を見る。
「俺にこのコーヒーを奢ってくれ。お前、儲けてんだからいいだろ?」
言いながら、星は伝票をスッと押し出した。
口元には笑みを、瞳には楽しむような色を宿して、自分より十歳ほど若い青年の様子をじっと伺う。
対する楠本は、相手の目を見たまま、人差し指と親指でその伝票をつまんで受け取った。がさがさと開いてみると、コーヒー以外にもカレーピラフとタマゴサンドという表記があることに気付く。
鼻でフンと笑って、星を見た。相手は微笑んだまま、サッと視線をそらせて知らぬ振りをする。
「分かったよ。それならアンタの頼み、一つだけなら聞いてやる」
まるで悪ふざけを楽しむように。笑顔になった楠本は、渡された伝票を折り曲げて、星の手の中に押し戻してやった。