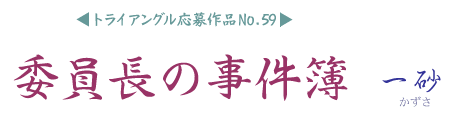
その夜の枕投げの勝者は、どうやら野球部の関谷のようだった。部活動で鍛えた腕力をいかし、記録物の剛速球……もとい枕を投げる。
「ふッ、俺に勝とうなんざ100億光年早いんだよ!」
どこかのアーケードゲームで聞いたような決め台詞を吐く。一人得意げな関谷を尻目に、僕はそれ以外のみんなに呼びかけた。
「そろそろ消灯時間になって先生たちが見回りに来るから、一度寝た振りでいいから寝てくれる」
「消灯時間〜?」
「って、まだ10時50分じゃん。あと5分くらいいいだろ」
文句を言うクラスメートに、
「ダメだよ。ここがどれだけ散らかってるか分かってんだろ」
目線を戦場だった空間に向ける。布団はあらかじめ脇に避けておいたからいいものの、ペットボトルや空き缶、お菓子の袋までがルールに反して飛び交ったため、あまり寝る場所とはいえない状態だ。というか、個人的にはこんな場所じゃ寝たくない。
しかし、僕は何でこんな遊びに付き合ってるんだろう。前日は楽しみか、はたまた緊張からか、2時間しか眠れなくて、今日は今日で委員長だからというだけで先生やクラスメートに散々こき使われ、とどめにこの「大枕投げ大会」だ。昔ながらの大部屋に、男子総勢30人が雑魚寝。女子でもあるまいし、大人しく布団に入るわけがないのだ。誰が最初に言い出したか、それとも前々から打ち合わせでもしていたのか、東西2軍に分かれての枕投げが始まったのが今から30分前。
「10分で片付けろよッ!」
言いつつ、散らばったゴミを片っ端からゴミ箱のある方角に投げていく。
「おい、委員長! 乱暴すぎるって!」
知ったことか。早く寝るためなら何でもやる。
ふと、目の端にすでに床に入っている人物が映った。――秀才とマザコンで知られる、中里啓吾(なかさと けいご)だ。アルミ製らしい眼鏡ケースを枕もとに置き、いびきもかかず丸くなって寝ている。あれだけうるさかったしドタバタ震動もしていたはずなのに、最初から参加の意を示さず一番端で寝てしまったのだ。できることなら僕もそうしたかった……。
まだ興奮さめやらぬアホどもも、何とか体を動かし現状復帰を試みる。結構エキサイトした為、暑くなったのか誰かが窓を開け……げッ、網戸が破れてる……。障子とかふすまには気をつけてたけど、まさか網戸が被害に遭うなんて。先生にどう言い訳しよう。
同じものに、関谷も気付いたようだった。僕のほうにそっと近付いて、耳打ちしてくる。
「おい、あれどうすんだよ。先生にばれたら……」
「隠そうだなんて考えるなよ。ばれるのは時間の問題だ。この場合、大人しくこっちから言った方が罪は軽いさ」
自己流の処世術。名付けてワシントン桜作戦だ。
「お前……いい性格してるよな」
関谷は苦笑いしながら作業へと戻っていった。
消灯時間まで残り5分というところにきて、何とか様になってきた。と、
「委員長、枕が一つ足りないんだけど」
「はぁ?」
――もしや、あの網戸の穴から抜けていったのでは? そう思い当たって青くなる。確か、この外は駐車スペースだったはず。そこに枕が一つ唐突にぽつんと落ちているというわけだな。どこかシュールな光景だ。いや、そんなことを考えてるときじゃない。
「おい、杉崎、そこの窓から下覗いてみて。枕、落ちてない?」
「え? ――何だこれ、穴あいてるじゃん。そっか、ここから抜けていったんだ〜」
納得しながら、杉崎は窓の下を除いた。がしかし、
「あれぇ、ないよぅ委員長……」
予想外の返事に、僕は思わず窓に飛びついていた。
「な、ないわけないだろ。この大穴が枕のせいじゃないとしたら一体何が……」
駐車スペースには、猫一匹いず、もちろん枕の陰も形もなかった。嘆息しつつ部屋のほうに向き直ると、
「――あのさ、委員長」
申しわけなさそうに、巨体を縮こませる男が一人。
「なんだよ、樋口」
「その網戸の穴、俺のせいなんだ……。枕を避けようとしたら、ちょっとよたついて……」
「……なるほどね」
その巨体なら、なるほど穴も開くだろう。先生にはこの真実を言うべきか言わざるべきか、少しの間真剣に考えてしまった。だから今はそんなこと考えている時間はないんだって。
「わかったよ樋口。その件はまたあとでじっくり考えよう。今は、消えた枕の謎だ」
僕の言葉のどこに感動したのか、樋口は「ありがとう、委員長」を繰り返し呟きつづけた。
「枕消失のトリック、ってか? 名探偵委員長、謎は解けそうかい?」
クラスメートが茶化す。うるさいなぁ、どうせ僕は探偵マニアさ。
「枕がないと、俺寝れねえんだよな」
「はぁ? 誰の台詞だよ。枕どころか布団がなくたって快眠してたろ」
どつき漫才のような二人組もいたりして、残り時間はあと1分を切った。
「どこかの布団の下にあったりしない?」
「いや、もう全部くまなく探した」
「それでもどこか探し忘れてたりしないか……」
「こんな殺風景でテレビもないような部屋のどこに盲点が?」
「――確かに」
あぁ、どうしたものか。耳を澄ませれば、先生が近付いてくる音が聞こえる気がする。
「あ、じゃあこうだよ。枕は、最初から一つ足りなかったんだ!」
楽観的な答えを導き出してみるが、
「いや、ちゃんと人数分あったよ。30個ぴったり」
あっさり覆される。八方ふさがりだ。それぞれが、自分のものと決めた布団の上で所帯なさげにこっちを見る。こっちを見ても何も出ないし何も変わらないんだけど。
「……あ、時間になった」
誰かのそんな台詞とともに、ニュース23の音楽が流れてきた。――あれ、テレビはないはずなのにどうして……。
「あッ、内藤、それってポータブルテレビ?」
「うん。うまく隠せたみたい」
布団の下に隠しつつ、ずっと電波を探していたようだった。嬉しそうにこっちを見る。だからさぁ……。
と、そのときだった。
「3組、ちゃんと寝てるか……おい、明かりを消すぞ」
勢いよくふすまを開けて入ってきたのは、よりにもよって女尊男卑で有名な体育の橘先生だった。なぜか竹刀を片手に持っている。怒気を含んだ声に、男子全員が震え上がった。でも、言わなくてはいけない。
「――先生、枕が一つ足りないんです」
「あぁ? ちゃんと人数分用意させただろう」
「どうやら途中でなくなったみたいなんです……」
「途中って?」
「あの、枕投げの……」
先生は黙って僕のほうを見た。いや、見下ろし見下した。万事休す。
先生は竹刀をパシパシと肩に当てて、
「枕がないってことは、今日は一晩眠らないぜ、という意思表示ととっていいんだな」
どうしてそうなるんだよ、という突っ込みは、誰も出来なかった。
「言ったはずだよな。消灯時間に明かりを消してなかった奴は、漏れなく俺が一晩中寝かさない、って」
――言ってました。目が本気でした。でもまさかその餌食になるとは思ってませんでした。
「枕投げの首謀者は誰だ? ――あ、委員長はもちろん責任とってもらうからな」
何で僕は委員長になったんだろう。
それから、結局総勢4人が廊下で一睡もせず正座するという古典的な罰を受けた。4人の内訳は、まず僕。それから、勝者の責任感からか、関谷が自主的に来た。同じく、網戸を破ってしまった責任感からだろう、樋口もその隣に座っていた。それから内藤。タイミング悪く、ポータブルテレビが見つかってしまったのだ。
でも、一体枕はどこに消えたんだろう。隠せるような場所はなかったのに。
まさか、と思うけれど、ふいに一つだけ可能性が頭に浮かんだ。
うつらうつらしながら迎えた朝の6時。起床時間だ。先生に、部屋に戻ってもいいとのお許しを受け、痺れる足を何とか動かしてみんなで部屋に入る。
みんな、踏みつけてやりたいくらいにぐっすり寝ている。布団は人数分あったのに、僕たち4人の寝るべき場所はいくら探しても見つからなかった。寝相が悪すぎる。
「叩き起こしたる……」
関谷の声はマジだった。そして、実行していった。朝の光差し込む和室に響き渡るのは、小気味のいい肉を打つ音とむさ苦しい悲鳴。
「関谷……もっとやっちゃえ」
感情のこもらない声で言ったのは内藤。眠らなかったせいで性格が変わってしまっている。
僕は、そしてちらりと部屋の端を見た。――やっぱり。
「おい関谷、みんなを起こしたか? 今から、枕消失のトリックを暴いてやるよ」
「何だって?」
辺りは動揺した。すでに起きていたものは、「おい、委員長がトリックを暴くって」とまわりを起こす。っつーか、トリックなんてそんな大胆なものでもないんだけど。
大体が起きて、眠い目をこすっているのを確認し、僕は部屋の隅へ行くと一気に布団を引っぺがした。
そこに寝ていたのは、かのマザコン秀才、中里啓吾だった。昨晩と変わらない格好で寝ている。枕もとにはアルミ製の眼鏡ケース。その腕には幻の30個目の枕を抱いて……。
「あぁーッ!!!」
3組、総勢28名の絶叫がこだました。