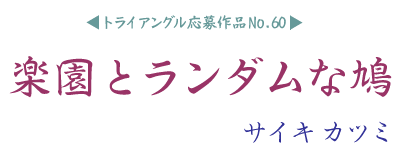
猫を喪失したということは、枕がかわって眠れぬ夜に似ている。ぽっかりと大きなものが消失して、そのブラックホールにどうしてよいのかわからなくなるのだ。そして旅先の枕も同じ。あったはずの確かな睡眠との関係が崩れ、僕らはそこにあったものの周囲をぐるぐると戸惑いながら浮遊する。そしてその戸惑いが苛立ちに変わるのにそれほど時間は必要ない。というのは、恵が何故腹を立ててるのか僕はちょっと合点がゆかなかった。
「だからいったじゃないのよ」と口をとがらせて暗闇の中で恵は僕の方を向いた。いいじゃないかと宥めながら僕は恵の背中を軽く小突いた。まあよくある夜の光景だ。だからそういうのは嫌いなのよと、恵はわざわざ僕をむしゃくしゃさせようとこぼし、その物言いに気分を乱されるが嫌で、僕はベッドから這い出てバスルームに向かった。どうしてそのように不機嫌になったのかという理由が見当たらない。というより、いつから機嫌が悪くなったのだろう。そう。枕が変わると些細なことで人は諍いを始める。僕は半勃起に起きあがってきて始末の負えないものを宥めながら小便をして顔を洗った。苛立ちも洗い流してしまいたかった。
鏡に投影された濡れた顔は、なんと情けないのだろうかと苦い味が口の中を匍い回った。僕は唾を吐き出し、口を濯いだ。なぜあのような話になってしまったのだろう。恵の腹を立たせるために話を始めた訳ではなかったはずだと、ああ、そうだったんだなと探った記憶がある一点を指ししめしたとき丁度、部屋の方から声が聞こえた。「なにか言った?」と僕はバスルームから声をかけたが、どうやら届かなかったらしい。恵のいらえはなく、そのかわりに何かの話し声が聞こえた。バスルームからでると、恵はテレビのちらちらとした明かりの中でベッドに腰を下ろしてじっと画面を見ていた。広大な青と黄色に上下に分かれた地平線が見えた。
「電気ぐらい付けろよ」
「いいの。見て。サバンナよ。アフリカ。アフリカ」
僕はそれがどうしたんだと口には出さなかったが、うんざりしてベッドに潜り込んだ。入れ替わりに恵は立ち上がって両手を広げた。鳥にでもなったつもりか、緩やかに腕を上下する。映像はドキュメンタリー番組だろう。ちらちらと暗闇に瞬く画面では現地のマサイ族か何か、僕には判別がつかない黒人が、フランス人のカメラマンに何かを言いながら地平線を指さしていた。恵は両腕を広げたまま目をつむっていた。
「目をつむっても光が入ってくるんだよね。そしたら私、サバンナで裸みたいな気分」
「サバンナで裸だとライオンに食べてくれといってるようなものじゃないか」
黒人が指差していたのはまさにライオンだった。目を開いて恵は口を尖らせて何かをいおうとした。が、突然軽快な音楽が鳴ってその旅は中断された。さわやかな顔をして西洋人のカップルが頬を寄せ合ってグラスの飲料水を飲むCMだった。爽やかで心地よい炭酸飲料がはじけた水滴が映る。マルボロの煙草と同じで、その商品は世界中どこにでもあるだろう。「ん、もう」そして両手を下ろしてベッドに戻りかけて「あ、でもコーラも飲みたい。確か置いてあったよねえ」と冷蔵庫に向かった。あっさりとCMに引っ掛かるのか。「一成もいる?」
「一口頂戴」
「いいわ」と先程までの様子を忘れたかのように、軽快にベッドに潜り込んでプルタブを開けて僕に渡しながら、恵は「まだ子供いらない」と言った。やはりそうだったのか、ほんの軽い気持ちで口にした言葉で気分を害していたのかと分かったので、僕は「ごめん」と謝った。
旅というほど大仰なものでもなく、遠出よりは僅かばかり遠かった。死んだハナのかわりに子猫を譲り受けようと僕らは車を借りてせっかくだからということで鎌倉で一泊して、そして明日には静岡に向かった。ハナの小さな頃に似た子猫の里親をインターネットのサイトで探していたのは静岡市のはずれの街に住む「ねこっぴ」と名乗る女子高生の管理人だった。拾ってきた猫が子供を産んだとのこと。近隣の人に、というのを、恵は是非にとねだったので、僕は長距離を運転する羽目になった。もちろんハナがいなくなってぽっかりと抜けたのは僕も同じだったので、一も二もなく恵のわがままに同意したのだったが、付き合い始めて五年、一緒に住み始めて二年。籍も入れていないのだが、恵がハナがいなくなったことをとても悔やんでいて、今度も執拗にハナの代わりをねだったので、僕は俗な感情が沸いて子供でも欲しがっているのかと思ったのだった。
ハナはキャリコ(三毛)入りのメイクーンで、どうしてこんな可愛い子が野良なのと思うほど美しい子だった。ちょっと左耳が外反していて、鼻の辺りにちょっとだけ茶色の毛が生えていたので、ハナとなったのだけど、しばらく前から僕の部屋に餌を食べにやってきてた白い野良のために玄関先にだしたいた煮干しを、見たこともない猫が囓っていたのが最初で、それがハナだった。ハナは玄関を開けると、好奇心と不安にに溢れて首を捩って僕を見た。そしてすぐに慣れたようにすたすたと部屋に入った。何度かやってきているうちに、いつのまにか公然のようにうちの猫になった。まあ、そういうことだ。
八幡宮の実時の大銀杏は若葉を輝かせるように千年変わらず屹立している。恵は由来書きを見ながら「征夷大将軍の暗殺って今でいえば総理大臣を暗殺するってこと?」と訊いた。
「変ねえ。誰が殺したかってことが何で分かったのだろう。だって、それって誰も分からなかったから暗殺なんでしょ。その人達はずっと前に死んだのに、木はあって、その同じ場所に私達は立ってるじゃない。遠いところと近いところが一緒だなんてやっぱり変」
時々恵の突発的な想像力には舌を巻くけど、この時も同じで、僕は「ねえ、やっぱり変じゃない?」という恵に「本当に変かも知れない」と答える。決まって僕は理屈で思考を巡らせるのだけど、理屈ではそれが歴史遺物の実証として、千年の樹齢の樹木はずっとこの場所に屹立していていただけで、だからこそ歴史の証人や事件を起こす人々やらいろいろな理由で、僕らはその場所を訪れるのだというふうに考えるのだけど。音がしたので振り向いたら広場になった参道で子供が鳩を追いかけて散らして遊んでいた。まるで鳩達はその場所に千年変わらず巣くっているのかもしれない。僕らの方がランダムなのだ。ハナがいたので僕らはほとんど旅行をしなかった。以前は野良だったせいもあるだろう、カーゴを嫌がって逃げ回ったので、病院に連れて行くだけでも大変だったし、僕らは特別旅が好きだったわけでもなかったので、よく考えれば恵と二人で歩くのなんて久しぶりのことだったかもしれない。毎年のように二人とも春先には仕事で手一杯だったので花見もパス。週末も近所に買い物に出掛ける程度だった。そうした時とはちょっと違うのだという、いってしまえばしごく当然のことだけども、奇妙な新鮮さがあった。だから恵は暗闇で鳥になりたいという変な気を起こしたのかもしれなかった。
道が分かり辛いので静岡市内の中心に出て車を右折させた。田園があり山があり、その奥に富士が見えていた。晴天の休日らしく、交通量はそこそこあったし、その全てが行楽ではなかろうが、猫も杓子も外ではしゃぐような、空だった。こういう日は車を運転していて、気分がいい。僕らは首都圏のラジオから地方の局にチャンネルを合わせた。恵はポップスのメロディに合わせて鼻歌を歌った。
「今度の休みに徹と優美を誘ってカラオケでも行くか」
二人は学生のころからの友人で、徹は冗談ばかり言う癖に案外内気で優美をなかなか落とせずにいた。
「あの二人どうなるのかなあ」
僕らは二人をネタにして笑った。がんばれ徹、わかってやれよ優美っていう感じだ。
「この前なんて、徹ったら、酔っぱらって優美に抱きついたりして」
「そんなことがあったんだ」僕はその様子を知らなかった。「一成は居なかった時よ」
まあ、そんな感じに学生の頃のノリが残ってるのは楽しい。僕らの周囲には幾人かの仲間がいて、時々集まって莫迦騒ぎしていた。そんな中で人と人はひょんなことでくっついて、そして離れる。僕らもその中の一つの成果だった。付き合い始めたというと散々囃されたり羨ましがられた。そしてお祝いを貰った。いい友人たちだった。
そういうくだらないことが大事だ、とか愁傷に思っていると、斜面に並ぶ建て売りの住宅地の真ん中で僕らは道に迷った。目的地のかなり近くまで来ているはずだったが、どうしたことか右へ行っても「西三丁目」で左に行っても「西三丁目」だった。二丁目にねこっぴの家があるはずだった。恵は苛々しながらも、わくわくしているようで「ねえ、どんな娘だろう」「かわいいよね」「一成もかわいい娘だったら嬉しい?」なんて訊いて、一ヶ所、人々が並んでいる奇妙な通りがあったが、その中をかき分けて通るのはちと面倒だと思ったし、道も反対向きの一方通行だった。でも、回り回った揚げ句にやはり他の道はなかったので僕はその道を選択した。
角を曲がった瞬間に長いクラクションが鳴るのが聞こえた。黒塗りの車が、碁盤の目のようになった住宅地を去って行くのが見えて、人々がじっとその後を見て、タクシーで後をつける姿も見えた。葬儀だった。人々の姿が若い女の子達だと気がつかなかったのは全くの迂闊で、僕らはその真ん中を通り抜けようとして、ようやくそれに思い至った。僕はねこっぴの本名で尋ねた。彼女たちはハンカチで目を拭いながら首を縦に振った。葬儀は彼女のものに間違いなかった。
恵は唖然とした表情で窓から顔を突きだした。知らぬ振りもできなかったし車の周囲に女子高生の制服が囲んだし、相違ないものは相違ないものだ。僕らはとにかく車を降りて靴が並んだ玄関をまたぎ、招かれるまま、玄関脇の八畳部屋の祭壇の前にあがって焼香をした。学生服姿のにこやかな笑顔が祭壇の上で僕らを見下ろしていた。奥からばたばたと親類だろうか、「早く早く」と急かされてかけだしたねこっぴの母親は僕らを見て、「遠いところを来ていただいて。ごめんなさい。急いで斎場に参りますが、よろしければ一緒に来ていただけますか」といった。勿論、僕らは辞退したが、是非にというので、ねこっぴの母親と一緒にタクシーに乗り、高校生たちも遅れてやってきたタクシーに乗った。僕らと母親とねこっぴの友人の一人が同乗した。
「助かります。あの人、義姉ですがどうにも苦手で。ほんとうに遠いところを来ていただきまして、ありがとうございました。こんなことになってるなんてさぞや驚かれたのではないでしょうか」
もう一度母親は頭を下げた。僕らはなんていっていいのか当惑したまま返礼して、恵はようやく気を保ったのだろうか、ハンカチを下ろした。タクシーは住宅地を抜けだして水田が広がる農道の中を走った。くねくねとした曲がりくねった道で木々に囲まれていた。「本当に突然でびっくりしたでしょう」と母親はもう一度気強くいった。「ええ。それにしても、何故」
「わたしだって突然でどうして良いか分からないのです。昨日の朝」と言葉を切って、窓を向いた。
「昨日の朝、明日、植田さんたちがいらっしゃるというので、写真屋さんへ行くっていって自転車に乗ってでていったのです」とそこで、母親は顔をうつむけたが、すぐに向き直って、ごめんなさいといった。「アオイはねえ」と母親は僕らにねこっぴがどれほど猫に傾倒していたかということを話した。
「あの子は本当によく猫を連れて帰って来るんです。そんなに遠いところに通ってる訳じゃないのに。猫って好きな人が分かるのですね。だって、一年に二十三匹もって、おかしいじゃないですか。そのうえ」
「そのうえ」掠れた声で僕らに話した。もともと掠れた声なのかも知れない。しかし崩れないギリギリの線で踏ん張っている様子が痛々しかった。おぼろげに把握した状況では父親がいなくて親子二人だったはずだ。黒服の母親は背丈はそれほどでもないその背中を曲げたり起こしたりしながら「あの子はほんとうにいい子でした」と繰り返した。くねくね曲がる道を通り抜けて坂道を登り切った緑の木々の間に空に向かって垂直に屹立した煙突が見え、空にはちょっと雲が出ていた。帰りは雨になってしまうのだろうか、と不意に思った。16歳だ。
帰宅すると仕出しの御膳が並べられていて、女子高生のかたまりは部屋の隅でぼそぼそと雲を掴むように話していた。近所の手伝いの主婦と一緒に「どうぞ、お食べくださいな」と帰宅早々母親は人々を席に着かせてお茶を配った。女子高生のひとりは私も、と手伝おうとするのだったが、母親は断った。やがて一段落のぐるり一回りの親戚連中(だろう)への挨拶が終わると、僕らの前にきて「そうだわ。今なら丁度いいわ。こちらにきて頂戴」といって奥に案内された。キッチンでは例の義姉が湯呑みを並べてお茶を煎れていて、主婦達は慌ただしく働いていたが、更に奥の部屋には段ボールでついたてを作って囲ったものがあって、その中で数匹の猫がじゃれて遊んでいた。「あっ」と声を漏らして僕らは言葉を失った。その一角だけはまるで楽園のように見えたからだ。
二匹の子猫が後足で半ば立ち上がって両腕でペダルを漕ぐように上下に振り下ろし(いわゆる猫パンチ)、その後ろで自分も仲間に入りたそうな表情で見ているのもいて、それは確かホームページに掲載されていた写真の猫で、ボクシングをしている白いロシアン系とショートヘアーらしき彼らは、それぞれ別に拾われたのだそうだ。隅っこのトイレに新聞紙を敷いていたのだが、その切れっぱしの三角になったところに頭を突っ込んで左右にごろごろ転がっているショートヘヤーもいる。メイクーンの兄弟だろうか四匹、固まってすやすや寝ているのもいた。「可愛い」恵は声をあげてしゃがんだ。「でしょ」と顔を綻ばす母親。
「触っていいですか」「どうぞ。どうぞ」
恵は段ボールを跨いで楽園に足を踏み入れて舌を鳴らして手を差し伸ばした。しゃがんだ恵の足に頭を擦り寄せてくる黒いやつの頭を撫でたがそれほどの興味を持たず、じっと凝視しながら警戒しているメイクーンに向かって変わらず呼びかけた。黒い小猫が諦めず人懐っこい様子を示したので、恵は抱き上げて開いたほうの手で読んだ。「このコ名前なんていうんです?」
「どっち」
「三毛」
「さくらよ」と母親は答える。
「さくら。こっちへいらっしゃい」恵はようやく件のメイクーンを抱え上げる。母親はにっこり笑った。
「親はあっちのカーゴ」と母親が指した薄暗い別の部屋にはいくつか大きめのカーゴがあって、その中で身体を起こしてじっとこっちを見ている立派な顔立ちの猫と目があった。あれは母親のミミです。
「酷いことをする人もいるんですね。お腹のおおきい母猫を捨てるなんて」
恵が声を上げた。「ねえ、みてみて。やっぱりハナとそっくりだわ」
僕は頷いた。耳の外反はなくて鼻の斑も僅かに場所も違ってて形状も違ってたけど、なんとなくその模様のせいで愛嬌のある顔立ちなのはハナと同じ感じだ。恵は指先をそのメイクーンの顔の前に突きだして、手でおちょくって反応を楽しんでいる。母親はちょっと微笑んで「その猫でよろしいですか」と訊いた。「ええ」と恵ははっきりと母親の顔を見ていった。「アオイさんとはこのコの約束でしたから」
「他のコでもいいのですよ」
「いいえ。このコが」
恵の顔にはもう梃子でも動かない頑固さが宿っていた。こうなるともう誰も敵わない。母親は穏やかに「じゃあ、さくらちゃんをよろしく」といった。
僕がトイレの砂を貰ったり、親猫のカーゴの布を一切れ貰っている間に、恵は小猫のカーゴを取りに車に戻った。葬送の座敷をカーゴを持って通るのは気が引けたので、裏口からでた。僕はだんだん申し訳ないような気分になってきた。娘が死んだ家から猫を貰うということがだ。
「さくらの様子をお手紙くださいね」
「ええ。必ず送ります」と僕は答えたが、母親の顔を見れなかった。
電話が鳴った。
母親は義姉に電話に出るように頼んで、廊下から返ってきた答えは馴染みの駅前のカメラ屋で、写真の現像があがってますが、取りにくるといったきり、いつになったら取りにくるのですか、というものだった。母親は一瞬押し黙って、それから顔をあげて「明日行きます」と伝えた。その写真を取りに行く最中に事故が起こったのだった。場違いな明るい様子で恵は女子高生たちを連れて戻ってきた。屈託なく「外で見つかったちゃった」と照れ笑いをした。
「おばさん。猫見せて」
彼女達はずっと遠慮していたのか、押し殺すような沈黙に耐えきれず、ちょっとでも明るさを求めたのか、はしゃいだ声をあげた。「この猫の名前は?」「マナ」「この猫は」「キジトラ」嬉しいのか悲しいのか分からない顔になりつつ答えていた母親は、そうだわ。どうせ明日写真屋に行くのだから写真撮りましょう、といって、真新しいフィルムを入れながら僕らのいる楽園に戻ってきた。
「みんな並んで」と構えたカメラをひとりの女子高生は奪い取って「おばさんは中だよ。なか」と、真ん中に恵がさくらを抱いて、そのとなりが僕で反対側に母親、そして女子高生達が周囲を囲んで写真を撮った。
何枚かの後、母親はカメラを交代して「この写真、でき上がったら庭で焼いてアオイに送ってやるの。だからみんな、あのコが寂しくないように、笑って」といいながらシャッターを切った。僕らが戸惑ううちに何枚も、何枚も写真を撮った。そうして母親はフィルムがなくなるまで切り続けた。
1週間後届いた写真の僕らは笑っていて、やがて泣いていた。僕と恵は新しい部屋ですやすや眠るさくらの写真を数枚送った。「さくらは元気です」と添えて。