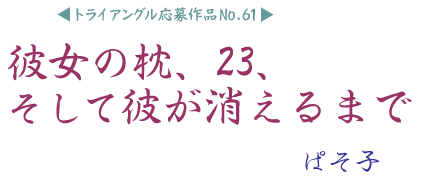
男は錆びついて固くなっている窓を無理矢理開けると、外の空気を招き入れた。夜にしては生温い、濁った空気が窓の隙間から流れ込む。水の流れる音がする。川が近いらしい。散らばっていた下着だけ身に着けて、くわえた煙草に火をつける。眼下にこの建物に向かって走ってくる車のライトが見えた。到着したかのように見えた車は、すぐにUターンすると遠ざかって行った。満室なのだ。今夜はどこもいっぱいだよ、ついさっきまで同じように車を運転してさまよっていた男は、同情の意を込めて小さくなる車を煙草の煙で見送った。
バスルームの戸が開く音がして、彼は煙草の火を消し窓を閉めた。白い湯気をバスローブ代わりにして、桃色に上気した素裸の彼女が現れた。セックスの余韻までは洗い流されていない。彼女の湯上り姿に男は満足した。
女は髪の毛をタオルに挟んで水気を絞っている。男が彼女を見るともなしに見ていると、長い髪の毛の隙間から彼女の黒い目が覗いて笑った。彼女は髪をかきあげると、器用にくるくると頭の上で束ねて、タオルで巻いた。そして、ねえ、と彼に話しかけた。
「ねえ、例のあのくじ、やってみましょうよ」
くじ? 男は一瞬きょとんとして彼女を見るが、あの受付でもらった……と言うのを聞いて彼女が何のことを言っているのか思い出す。
彼女の言っているくじというのは、部屋のキイと一緒に差し出されたちゃちな用紙のことだった。B6の紙に4桁の数字を書く欄があり、その下に住所、氏名、電話番号を書く欄が設けてあった。ただいまキャンペーン中でして、とカーテンの陰から口しか見えない男が言った。お好きな4桁の数字を書いてお帰りの際に渡してくだされば、もしかすると豪華景品が当たるかもしれませんよ。
「ゴーカケーヒン」
と、後ろで彼女が囁いてくすりと笑った。彼は黙ってその用紙と部屋のキイを受け取って階段を上る。モーテルでは従業員に声を聞かせる義務なんてないのだ。ましてや、住所氏名電話番号だって? 豪華景品。4桁の数字。どこかの大型くじの真似かもしれないが、一体このちっぽけなホテルのどこから10の4乗分の1の確率に見合う景品が出ると言うのだろう。
と、彼が憤慨すらしていた代物だ。でも今ではそのくじの存在をすっかり失念していたのだった。
「あなたが選んでいいわ、数字。こういうの意外に当たるかもよ」
彼女はくすくす笑いながら、椅子に座りペンを握って、用紙を前に男が数字を答えるのを待っている。いつの間にか部屋に備え付けの室内着を身につけていた。
「1、2、3、4」
と、彼は投げやりに答えた。何しろ彼は眠いのだ。長時間の運転の疲れとセックスのあとの心地よいけだるさ、そしてベッド。あらゆる要素が今にも彼を眠りの淵へ引きこもうと誘惑している。
「いいわ、意外に当たるかもね」
彼女は大真面目に彼の言った数字を順番に書き留めた。それっきり彼女はそのくじに関心を失ったらしく、テーブルの上に紙とペンを放り出したまま、彼の寝そべっているベッドにやってきた。テーブルから勢い余ってペンが転がり落ちる。男はベッドから手を伸ばしてペンを拾うと、再びテーブルの上にペンを戻した。彼女は髪の毛を包んでいたタオルを外して遠くへ放り投げると、ベッドに、男の隣に滑りこんだ。
男の隣に寝転んだ彼女は、細い腕をベッドから出すと手探りでベッドの下から彼女の持参物である大きなスポーツバッグを探し当て、引きずり出す。最初、家出するつもりかと男が思ったほど、でかい代物だ。バレーボールが何個も入りそうな大きさ。下手したら猫だって犬だって小さな子供だってこの中に入れて運べるかもしれない。
彼女の細い指がバッグのジッパーの上を滑っていく。秋の夜半虫が鳴くような音をたててジッパーが開いていく。彼は肩肘をたてて体を半分起こすと、その様子を見るともなしに眺めていた。着替えか何かが出てくるのだろうか。ジッパーの隙間からぼんやりと白い物が覗く。
そこから現れたのは、枕だった。彼は眠いのも忘れ、あっけにとられたまま彼女がその枕を取り出してベッドにセットし終わるまでを見守った。
「それ、いつも持ち歩いてるの?」
と、彼は出来るだけ控えめに尋ねた。
「ええ、これじゃないと眠れないもの」
と、彼女は答えた。そしてその枕に頭を乗せる。枕は白く飾り気がない。しかし、形態は少し変わっていた。枕は彼女の頭をしっかりと抱きとめ、首をそっと支えていた。確かに見るからに寝心地のよさそうな枕だった。
「彼がね、買ってくれたの。私が夜眠れなくて苦しんでいた時、いろいろ手を尽くして調べて私にぴったりの枕を探してくれたの。これ、オーダーメードなのよ」
彼、というのは彼女の夫のことだ。彼女の夫であり男の友人でもある。女は結婚して二年たつというのに、まったく家庭の匂いがしない。むしろ、男が以前から知っている友人の「恋人」であった時の彼女よりもいっそう初々しく奔放な感じがした。彼女と今ホテルでこうして過ごしているのも、友人の妻と寝たという後ろめたさも後悔もないのも、彼女の持つその雰囲気が無関係ではない、と男は思っていた。
「この枕を買うまではね、夜が長くて辛くて大変だった。『今日』という日がいつまでたってもずっと続いていて、そのままもやもやと連続して『明日』になる。頭の中がいろんなことで―――多くはくだらないことでいっぱいで、処理できなくて、古くなった記憶が頭の隅で腐臭すら放っていた。たとえじゃないの、本当に腐臭がしたの。いつもその臭いが私から離れなかった」
たとえじゃないのよ、と彼女はもう一度繰り返した。「うん、分かるよ」と言ってから、彼は「古くなった記憶」が実際に頭の中で有機的に腐っていく様を想像しようと試みた。しかしうまくは行かなかった。
「でもこの枕で眠るようになってからは、その臭いも消えたわ。この枕で眠ると、すっと意識が飛んで、世界が切れるの。世界のスイッチがオフになるの」
彼女は枕の上で目を瞑る。半分寝言のように喋り続ける。
「世界が、というのはちょっと違うわね。世界は私が眠っている間も変わりなく進み、存在し続けてるもの。むしろ、私の方だわ。私が世界から切り離される。そう、自分が消えてしまう感じがするわ」
彼は彼女の話をぼんやりと聞きながら、枕のない彼女のからっぽの寝床の横で一人眠りについたのであろう友の姿を思い浮かべている。彼女は彼のプレゼントした枕を抱えて外出する。それはどこかで泊まるかもしれないからだ。今、彼女はモーテルのベッドで、枕をプレゼントした男とは別の男を相手に喋り続けている。枕の上で。
「最近はね、この枕を使い始めてからは起きている間も感じ方が違うの」
いつのまにか目を開けた彼女が彼を見ていた。彼は彼女の夫についての想像を止め、体の位置を変え彼女の方に向き直って、話に集中する。
「感じ方が違うだって?」
「そう。私の立っている場所以外は前も後ろもなくなった感じがする。そうね、」
彼女は手を伸ばし、テーブルの上の紙を引き寄せ、紙の両端を縦に折り曲げる。彼女の几帳面な楷書で書かれた数字の1と4が隠れて23だけが紙の上にぼんやりと存在した。
「こんなふうに、1と4がなくなって23だけになる。前も後ろもないの。忘れるとか考えないとか思い出せないとかではなく、消えるのよ、前後がまったく無になったの」
雀の鳴く声が聞こえる。西向きの窓からは相変わらず重苦しい夜の気配ばかりが漂ってくるけれど、きっと夜は明け始めているのだろうと男は思った。結局彼は眠れなかった。折り曲げられた紙を開く、1234。そして再び折り曲げる、23。薄く窓を開けて煙草に火をつける。頬に当たる風が冷たい。煙草の煙が頭を刺激する。
隣で彼女は深い眠りについている。まるで存在していないかのような深い深い眠りだ。昨日から連続し続けている彼の頭の中は未整理で鈍く、ぼんやりと霞んでいた。彼女が180度の大きな寝返りを打った瞬間、彼は無性に、彼女から枕を奪って彼女をベッドから転げ落としたい衝動に襲われた。彼女の体がしなやかにベッドの上でバウンドし、弧を描いて床へ着地する。そして、今度は彼がその枕で眠るのだ。深い深い眠りにつく。彼自身がこの世界から消失してしまうまで。