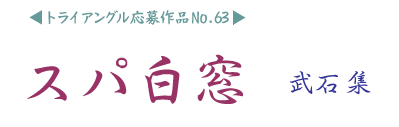
イエイ。
僕が住んでいる町はとても静かだ。とても小さい。パチンコ屋が二店しかない。深夜営業しているレンタルビデオ・ショップは一店だ。近くのコンビニは二三時で閉まる。道は狭くて入り組んでいるし、自販機なんか数えるほどしかない。だから(かどうかは知らないが)暴走族さえ寄り付かない。夜にはみんなが寝静まる。だからとても静かだ。昼間も、とんでもなく静かだ。ベッドタウンですらない町なんてそんなもんだ。犬や、おばあちゃんや、ご近所の仲良し主婦の皆さんや、現場終わりのオイちゃんや、外回りの営業マンや、女子高生や、とにかくみんながみんな昼には散歩している。こんな辺鄙な田舎町では、何の事件も何のイヴェントも何の楽しみもない。散歩するくらいが関の山だ。本当だ。死ぬほど静かなんだ。
町議会が地域活性化のために向こう三年分の予算をつぎ込んで完成させた総合娯楽施設『スパ白窓』は、平日には死ぬほど閑散とし、日祝日にも、いい具合に閑散としていた。健康ランドだのスーパー銭湯だのと呼ばれるひところ流行ったこの手の施設には、確かに子供からお年寄りまで幅広い年齢層に訴求可能な受け皿がある。だが、もともと町民自体が少ないのだし、外から利用者を誘致するというのも、何か大がかりな話だ。そろって棺桶に片足を突っ込んだような町議会のお歴々は、何を物狂ってこんな施設を僕らの町に建てたのだろうか。
とはいえ、僕は『スパ白窓』を典型的な箱モノ行政の悪しき象徴として弾劾しようというのではない。そんなつもりはまったくない。なにしろ僕は、ここのレストラン・バー『児笑児』で平和に気楽に、ウェイターのバイトができるのだから。
午前一〇時。そろそろなじみのオジさんオバさんたちがちらほらと顔を見せ始める時刻である。ある人は朝の一番風呂を浴びにくるし、ある人はちょっとした軽食をつまみにくる。そしてある人は、買い物ついでにここで井戸端会議を開いていく。デートの待ち合わせ、商談、町内会の寄り合い、お茶会、少年野球部の反省会、何でもござれだ。
たとえばこんな感じだ。
「おい、ナツオ」
僕を見つけて声をかけてきたのは、石川さんである。以前郵便局に勤めていて、この春退職した言わば新人のおじいさんだ。そのほっぺたには小豆大のほくろがあり、それは彼の小粋なトレード・マークとして皆に知られていた。
「お前、中澤んとこの息子と友達だったろう」
「そうだけど、何?」
「家出したらしいんだよ。お前、何か聞いてないか?」
「ユウイチが?」
僕は驚いて石川さんの顔を見つめた。そのほくろをだ。
「おお、ユウイチつったけかな。もうこの三日、家に戻ってないとさ」
石川さんは、メニューをとんとんと叩いて僕に示した。
「ご注文ですか?」
「おお」
「お会計、お先に失礼いたします」
石川さんはちゃりんと小銭を出した。二三〇円。
僕は厨房に行って、フレッシュ・ジュースをグラスに注ぎ、石川さんの所へと持って行った。今月のフレッシュ・ジュースは葡萄だ。
「どうだ、ナツオ?」
さっきの話の続きだ。
「さあ、知らない。あいつ最近、つきあい悪かったしね」
「そこだ」
石川さんはぐぐっと葡萄のフレッシュ・ジュースを飲み干して、グラスを持っていない方の手で「ばん」とテーブルを叩いた。この町の老人は何かというとテーブルを叩きたがる。なぜだろう。この町には老人カルチャー・スクールでもあるのだろうか。老人心得第八条、テーブルとは叩くものである。強く、美しく、直角に叩くべし。
まさか。
「だいたい付き合いが悪くなるってのは、何かの信号なんだ。それでだな、周りの人間がその信号をちゃんとキャッチしてやらなきゃならんのだ」
石川さんは、またとんとんとメニューを叩いた。見ると、今度はビールを指している。
「四五〇円」
ちゃりん。僕はまた厨房へ行って、今度はビールのジョッキを持ってきた。
「でもさ、おれらも子供じゃないんだからさ。だいたい家出なんつったって、どこにも行くアテがあるわきゃないし。すぐに戻って来るって」
「ばかか、お前は」
石川さんは大きな溜息をつきながら、またテーブルを叩いた。ぐぐっとビールを飲み干して――なぜ飲み干すのだ。なぜ一息なのだ。老人心得第一四条か? 僕はさりげなくメニューを石川さんの手元から回収した。
「行くアテのない人間などどこにもおらん。その気になれば、お前ら若いモンは何だってできるんだ。何だってだ。わしらの年になると、そうはいかん」
「家出くらい石川さんだってできるんじゃない?」
「ともかくだ」
石川さんは僕の尻を叩いた。ともかく何でも叩く人なのだ。
「お前、ちょっと周りに当たってみろや」
「はいはい」
「あと、ビールお代わり」
「……はいはい」
僕は石川さんがテーブルに置いた小銭を連れて、また厨房へと向かうのだった。
あるいはこんな感じだ。
「ナツオちゃん、元気?」
客のはけたテーブルの上を布巾で拭いているとき、高橋さんが上品なよそ行きの声で呼ばわりながら、小走りに僕の所へ駆けてきた。高橋さんは僕のいきつけのクリーニング屋で働いているおばさんだ。日曜日の温泉スイミングスクールに通っていて、レッスンの後は必ず『児笑児』に寄ってくれる。だが今日は日曜日ではなかったはずだ。聞けば非番を利用して、四階のミニシアターで上映されている『眠狂四郎』を見に来たのだと言う。僕はふうんと頷いた。
「ねえねえ、聞いてよ。私ね、今度運転免許とろうと思うの」
「自動車、ですか?」
そうなの、と高橋さんは身をくねらせて、
「うちの亭主はぐうたらでしょ、だから買い物とか、孫ができたらドライブに連れて行ったりとか……。ね、いいでしょう?」
「いいですねえ」
僕は愛想良く請け合ってみせた。どのみち町には、あんまり車が多くないのだ。それに高橋さんのことだから、十日もすれば熱も冷めて、やる気を消失してしまうだろう。愛想良くしたって、何の害もない。
「ナツオちゃんは免許持ってるの?」
「原付だけです」
「あらまあ、じゃ彼女とドライブにも行けないわね」
「彼女なんていませんし」
「まあ、まあ、ナツオちゃんを放っとくなんて、今日びのお嬢さん方には、見る眼がないのねえ」
「どうも」
今日びのお嬢さん、なんて、久々に耳にする言い回しだな。この町でなければ、文科省が絶滅危惧日本語のひとつに指定していたって、おかしくはない。
「お紅茶下さる?」
「あ、はい。二八〇円です」
僕は高橋さんの出した小銭と絶滅危惧日本語リストに加えるべき新たなセンテンスとを回収して、厨房からティー・セットを持ってきた。真っ白い陶器のティー・カップと、ダージリン・ティーのミニ・ポットと、シュガー・ボトル、それにガム・シロップだ。
「……でも高橋さん、孫ができるのなんてまだまだ先じゃないんですか? お子さんって確か、大学生でしょう?」
「そうなのよ。でも今はあれでしょ、できちゃった婚とか多いじゃない。うちの子もいつお腹を大きくして帰ってくるかと思うとね。免許くらい取らなくっちゃ、って」
おかしな気の回しようには違いないが、これが高橋さんなのだ。
「ね、ナツオちゃん、どう? うちの子。姉さん女房だけど、年上はだめ?」
僕は表情の選択に困ってしまった。
「娘さんも高橋さんみたいな人だったら、きっといい人見つけて帰って来ますよ。僕なんか出る幕はありませんって」
「あら、上手いわね。うふふふ。今度クリーニング、おまけしたげるね」
そして高橋さんは紅茶が完膚なきまでに冷めきってしまうまで喋り倒し、最後に、思い出したように一口すすって、「じゃあね」と言って帰っていくのだった。僕は『眠狂四郎』と絶滅危惧日本語とできちゃった婚とを枕詞にした平和で安直な交通標語を考えながら、その後姿を見送った。
そしてたまにはこんな感じだ。
「よう、安倍ッチ」
ぽんと僕の背中を叩いたのは、元クラスメイトの飯田マリだった。胸に大きな星のついた黒いタンクトップに、白い短パン、白いサンダル――いや、ミュール? というラフな格好だった。無造作なポニー・テールが何かと言うとぴょんぴょん跳ねる。
「おう、どした。珍しい」
「今日暑いからさぁ。友達と上の図書館に来てんだ。あとでプールに入ろうと思って」
そう、『スパ白窓』には図書館もあるのだ。とにかく町の中にないものは、ほとんどここにあると言ってもいい。
「夏休みの課題かよ、受験生は大変だな」
「石黒先生さ、まじシャレになんないって。問題集全部重ねたら、三センチくらいあんだよ。ねえ、三センチよ、三センチ」
マリは左手の人差し指と親指とで、その「三センチくらい」の厚さを再現して見せた。僕も、石黒のまるで教材会社と結託したかのような問題集主義には、ずいぶんと苦しめられたものだ。
「ねえ、安倍ッチ、戻って来ないの?」
「戻らないよ」
マリはふうんと頷きながら、手首の腕時計のバンドを締めたり緩めたりした。
「安倍ッチ、どうすんの? このままここで働くの?」
「何も考えてない。しばらくは多分、ここにいるんじゃないかな」
マリはまたふうんと頷いた。
「おまえは?」
「アタシ?」
ポニー・テールが、透明人間によってジャグリングでもされているかのように、宙で激しく踊った。マリはちょっと唇をゆがめて、
「親は大学行けって言ってるけどさぁ」
まあそうだろう。いくら田舎とは言っても、進学志向くらいはある。僕のようなドロップ・アウト組は別だとしても、普通の家庭なら、大学くらいは……、となるのが、当然なのだ。
「いいじゃん、大学。行けよ」
「うーん」
マリは曖昧に唸った。
「そういえばユウイチ、家出したんだって? 何か聞いてる?」
「ユウちゃん? ああ」
そんなことはどうでもいいでしょ? と言いたげな表情で、マリは僕を見やった。
「なんかね、エッチビデオが捨てられたからって、怒って飛び出したみたいよ。ヨッシーの所に転がり込んでるって。バカよ、バカ」
僕は大笑いした。確かにバカだ。石川さんが来たら教えてやろう。彼は何と言うだろうか。とりあえずはまたテーブルを叩くに違いない。景気良く叩くに違いない。それだけはまず間違いない。
「アタシも学校やめちゃおっかなぁ。でね、どっか南米あたりの田舎町で、子供たっくさん作ってサッカーさせるの。兄弟の中から三人くらいはプロになって、一人はワールドカップにも出場するのよ」
「いいねえ」
「安倍ッチも応援に来てくれる? アタシの子供の」
「もちろん」
マリはにっこりと笑った。ポニー・テールも笑っていた。
そんなわけで、僕が住んでいる町はとても静かだ。とても小さい。ペットショップが一軒もない。理髪店と美容院とその中間ぽい店がそれぞれ一軒ずつある。近くのスーパーにはちょっと他では見られないほど種類豊富な漬物コーナーがある。高いビルなんて町のどこへ行ったって影も形も見えないし、マンホールなんか数えるほどしかない。町議会が地域活性化のために向こう三年分の予算をつぎ込んで完成させた総合娯楽施設『スパ白窓』は、今日も静かに国道沿いに寝そべっている。ある人は朝の一番風呂を浴びにくるし、ある人はちょっとした軽食をつまみにくる。そしてある人は、買い物ついでにここで井戸端会議を開いていく。デートの待ち合わせ、商談、町内会の寄り合い、お茶会、少年野球部の反省会、何でもござれだ。そして僕は今日もそこのレストラン・バー『児笑児』で平和に気楽に、ウェイターのバイトをしている。
イエイ。