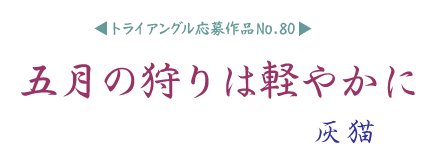
五月にしては暑すぎる日が、もう三日続いている。初めは「平年より高い」などと控え目だった天気予報も、ここにきて「真夏のような気候」と率直に表現しだした。
今さら言われなくたって、そんな事はとっくにわかっている。教室にこもる熱気、何もかもを白く見せる日の光、外水道の水の温さ。これを真夏のものと言わずに何と言おうか。
土埃のもうもうと立つテニスコートは、昼前の殊更強い日差しにさらされて、どこか外国の砂漠のような不思議な空間を思わせる。その光景に目が眩みそうになって、美和はコート脇の木陰に避難した。太い幹に背を預け、斜面に膝を抱えて座る。ラリーの練習をしているクラスメイトをぼんやりと眺めていると、眼前に突然黄色いボールが差し出された。
真理子だった。
「やらない? 」と、空いた面を指す。
「冗談でしょ。こんな暑い中で運動なんて」
「冗談よ。あたしもやる気ない」言うなり彼女は草の上にラケットを放り投げた。「あんたなら断ってくれるだろうと思って誘ってみただけ」
「あっそ」
横目で見やると、彼女はすでに腕をまくらに寝る体勢になっている。眩しいのか幾分細められた大きな目は、陰のせいでいつもより濃い色に見えた。
「なんか青春みたいだよね」何となく見とれていた綺麗な形の唇から、いかにもだるそうに言葉が発せられる。「馬鹿みたいに暑い日に、馬鹿みたいにテニスをする十七歳」
「ほんと、いかにも青春。身体的には大人の女が、まだ子供だよって顔して体操着で奇声を上げながら何でもかんでも大騒ぎする」
十七歳はそういう時期。箸が転げても可笑しい時期。そういうことになっている。
「じゃあ、あたし達は? 青春に乗り遅れたニセモノの十七歳? それともお子様すぎてああいう良さがわからないのかしら? 」
「情緒的に問題のある、ただの十七歳よ」
心にもない軽口を返すと、真理子はふわりと微笑んだ。いつもの、美和にだけそうとわかる、ちょっと歪んだ笑みだった。
「ねえ美和ちゃん、さっき小野さんと喋ってなかった? さっきの体育の時」
急いで戻った教室は外よりは大分涼しい。着替えを済ませて、早々にお弁当とする。
「喋ってたけど? 」首を傾げて見せた。「それがどうかした? 」
「別にどうもしないんだけど・・・・・・」慌てて首を振った佳織は、すこし顔を赤くして俯いた。「小野さんってグループ違うから、珍しいなあと思って」
「テニスでは同じ班だから。別に仲良しじゃないけどね」
「そうなんだ」
安堵の色を隠そうともしない佳織を見て、美和はそれ以上からかうのを止めた。素直で可愛らしく、高校生の社会で何の疑いも抱かず生きていける少女。信じるとか信じないとか、愛だとか夢だとかを現実として見ることができる彼女は本物の十七歳なんだろうと思う。
「小野さんってすごい人よね。綺麗だし、頭もいいし、性格もいいし」
佳織は離れた席でパンを齧っている真理子を窺いながら言った。彼女もいつものように、数人の友人と一つの机を囲んでいる。
「この前の県一テスト、学内で9番だって。さすがよね」
「すごーい。でも、佳織だって相当上の方でしょ。20番だっけ」
「23番。わたしは頑張ってこれだもん。小野さんはがり勉じゃないのに一桁だから」
「たいしたもんねえ」
自分も真理子の方をちらりと振り返って美和は言った。ご多分に漏れず佳織も真理子に憧れているのは前から知っていた。ジュニア小説の定番よろしく、それが恋によく似た感情であることも。
でも、佳織は気付いているだろうか?
自分の憧れのクラスメイトが、実は自分とは相容れない種の人間だってことを。思春期など待たずに大人になって、対岸から自分達を見下していることを。そして、唯一の親友だと信じているあたしが、彼女の側の人間であることを。
窓際の男子生徒が思い出したように煙草を取り出し、自然な仕草で火をつけた。煙は海草のように教室を漂い、吹き込んできた強い風に消えた。
真理子と自分が同類だと気付いたのは、随分前のことだ。
あれは確か一昨年の文化祭。異常に盛り上がるクラスの雰囲気に息苦しくなって逃げ込んだ図書室に、同じように居場所をなくした彼女がいた。
「まいっちゃうよね。本当に、物理的な意味で行き場がなくなっちゃうんだもん。文化祭にも振り回されないで残ってくれるのは、職員室とここだけよ」
面倒くさそうにページを繰る指先。あれは何という本だったか。芥川や太宰だったら会話すら成立しなかったかもしれない。
「こういうのは中学までだと思ってたんだけどね」
「お互い、甘かったってやつ? やっぱり立場はまだガキだからね」
顔に似合わないそんな口調が、多くの時間を共に過ごす彼女の友人たちの前では決して出ないものだと知ったのは、それほど後のことではなかった筈だ。
どんなに好きなものだって、そればかりを食べ続けたら飽きてしまう。
それなりにうまくやっている日々に、傷を付けたくなる時もある。女性の身体の周期のように完全だったり不完全だったりしながら、毒のある会話を何となく求めて、美和は真理子と時々話した。
でも、ただそれだけ。
同じクラスになったからって友達面をするでもなく、互いに別の友人を確保した。友達ではない、だからこそ居心地のいい関係を、高校レベルの教科書は決して理解しないだろう。
真理子はいつだか言っていた。
「あたしがいきなり皆に混じって青春しはじめたりしたら、あたしを消してね」
あたしは何と答えたのだったか。覚えているのは、ぐっと寄せられた綺麗な顔に、思わず目を伏せてしまったことだけだ。
バイト先のパン屋は駅の構内にある。暇つぶしのつもりで始めたわりに、思ったより実入りがいいのと余ったパンを貰えるのが気に入って、美和はもう半年以上続けている。
長く売り子をやっていると、常連客の顔も覚えてくるものだ。仕事帰りに寄り、毎日焼きたてのクロワッサンを買って帰る女性。毎週金曜日にフランスパンを一本買いに来る上品な老紳士。それから、他校の制服の背の高い男子生徒。彼は部活帰りといった風情でふらりとやってきては、メロンパンだのクリームパンだの、いかにも子供が好むような甘いパンを二、三個買っていく。冷めた表情の整った顔とは余りにもかけ離れた買い物に、美和はいつも笑いをこらえるのに苦労していた。
彼は今日も来た。トレイに載せて持ってきたのは、やはり甘いものばかり。しかし今日はいつもより数が多かった。
「792円になります」
代金を差し出した彼は、小さくどうも、と呟くとふらりと出て行った。
ふたり分?
思わず浮かんだそんな考えに、美和は苦々しく眉を寄せた。
あたしは何を考えているんだ。そこらのガキじゃあるまいし。
しかし、いったん浮かんでしまった考えはバイトを上がる頃になっても頭から消えてくれなかった。
久しぶりに雨が降って、気温は平年並みに戻ったようだ。
それでも午後の美術室には熱気がこもって充分暑い。油絵さえ描いていれば席は自由というこの授業は、当然のように大騒ぎの時間となる。
佳織と並んで座った美和は、彼女と取りとめのない話をしながら黙々と描いていた。自分のものではない長い髪が頬に触れて振り向くと、すぐ後ろに立った真理子が美和の絵を覗き込んでいた。
「どうかした? 」
真理子は絵に目を釘付けにしたままで「これ、いいわね」と呟いた。
「やだ、全然よくないよ、こんなの。滅茶苦茶手抜きだし」
美和は身体で絵を隠すように、真理子から遠ざけた。
よりによって、自画像なのである。自分らしくもなく、何故か結構いい出来の。
真理子はゆらりと身体を起こすと、
「これ、描きあがったら私にくれない? 」
身体中の血が、一気に顔に集まった気がする。
「冗談言わないでよ。こんなものもらってどうするって」
真理子は至極真面目な顔で言った。
「気に入ったのよ。いけないかしら? 」そして佳織の方に顔を向けて、「それとも、もう先客がいる? 」
「わたしはそんな・・・・・・」
真っ赤になってしまった佳織の前で、真理子は弾けるように笑みをみせた。
「それなら、お願い。あたしの絵、大した物じゃないけど、それと交換ってことで」
彼女が軽く掲げて見せた絵は、目を刺すようなコバルトの空を背にした、後姿の自画像だった。
「さっきのは何? 」
「何って、なにが? 」
ふざけるように可愛らしく小首を傾げて見せる真理子に、冷静でいようと努めながら美和は続けた。
「佳織をからかって、あんたらしくないじゃない」
真理子はすっと目を細めた。
「からかったわけじゃないんだけど。あんたこそ何? 一人で何熱くなってるの」
「熱くなんかなってないわよ。意味もなく人を傷つけるなんて悪趣味だって言ってるの」
「意味なんかいらない。どんなことにも」
強い視線に、一瞬息が止まるかと思う。
「でも、あったのよ、ちゃんと。意味が」真理子は諭すように言葉を継ぐ。「あたしはあの絵が欲しかった。でもあの子が同じ事を言ったら、あんたはあの子に渡すでしょう? だから早目に確認しておきたかったのよ。返ってくる言葉がわかっていたとしても」
「ガキじゃないんだから」並んで歩いていた足が校門で止まっていた。門を出てしまえば、逆方向に分かれられる。「あんたはもっと大人だと思ってた」
吐き捨てて歩き出そうとした美和の背に、真理子は静かな声で言った。
「ガキじゃないからよ」
振り向いて見た真理子の顔は、いつかのように真剣だった。
「ガキじゃないから、あの子みたいな素直なお子様には勝てないのよ。わざと傷つけたのは悪いと思ってる。でも、あんたにそれを責められる? 同じことしてるじゃないの」
わかっている。あたしは佳織を傷つけている。いつもいつも、意味もなく。
「あたしってさ」
風が吹いてばらける髪を片手で押さえながら、真理子は少し和らいだ声で言った。
「小さい頃は、結構夢をみる方だったの。なんとかになりたい、とか、そういう夢じゃなくて寝てる時に見るやつ。今はほとんど見ないけど」
「ふうん」
真理子は何を言い出すつもりだろう。またあたしを言いくるめるつもりなのだろうか。
「すごくよく見る夢があって、それがまた嫌な夢でね。消失マジックってあるじゃない。多分テレビであれを見たのね」
箱に入った人が1、2、3で消える、あれだろうか。美和は無言で頷いた。
「夢ではあたしは客席にいるの。派手な仮面のマジシャンが出てきて、ステージから母をステッキで示すわけ。お客さん、アシスタントしてください、って」
あなた、そう、そこのあなた。ちょっと消えてみませんか。
「母は嬉しそうにステージに上がって、変な箱に押し込まれる。マジシャンは次に父を呼ぶ。兄も、飼ってた犬も、みんな呼ばれて箱に入るの」
「それで」
真理子は表情を変えることなく言った。
「みんな消えたわ。あたし以外は」
幼い真理子は、どんな顔をして空の箱を見たのだろう。無数の空箱を見つめながら、ぽつんと客席に座る少女。自分が呼ばれるのをずっと待っている少女。
「ガキだから連れて行ってもらえないんだと思ったの。邪魔になるから置いていかれたんだって」
夏が近づいて日が暮れても明るい空の下で、冷たく湿ってきた風だけが今の時間を示している。
「そのときから、真理子は大人になったのね」
真理子は小さく笑って首を振った。
「多分そこで、あたしの人生終ってたのよ。気付いたら、やっぱりあたしは置いていかれたままだった。みんなは普通に十七歳やってるのにさ」
口を尖らせた真理子はやっぱり綺麗な顔をしていて、外見と行動のギャップはパン屋にやって来る彼のようだと美和は思った。
夕暮れの校門で夢を語る十七歳。
こういうのを、世間では青春とかいうのではなかったか?
「真理子」
どうしても顔が笑ってしまうところを見ると、真理子もまだまだ子供かもしれない。もちろん、あたしも。
「言わなかったっけ? あたしたちは、ただの十七歳なのよ」
時計を見る気などなかったけれど、駅についた時間から逆算すると、どうやら随分長く喋っていたらしい。ぎりぎりで間に合ったバイト先でいつものようにレジを打ちながら、それでも美和は明日学校で真理子と顔を合わせた時に何を話そうかなんて考えていた。