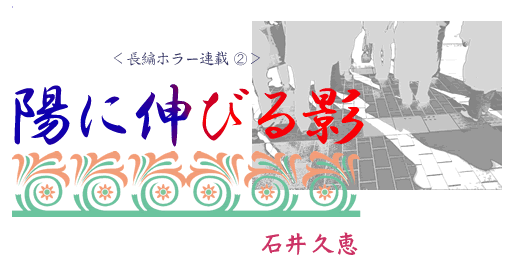
【 第2回・告 白 】
「来るかなぁ、本当に……」
祥子はドアを出て通路の手すりから下を眺めた。真夏の平日の午後は、日差しを避けて誰も外に出ていない。眼下には道が見え、そこはマンションの影になっていたが、猫の子もいない。世界中が何かを待って沈黙しているような静けさだ。
「まだか――」
つぶやきを残して、祥子は部屋に戻り、冷蔵の中を確認する。
――ヘルシー嗜好みたいだから、飲み物は健康茶系、お菓子は自然食品の店から買ってみた。アイスはソフトからアイスバーまで五種類。冷凍庫がいっぱいだ。それから、意外な注文にも応えられるようにと、スイカも買った。これが一番高価だった。
リビングに行こうとしたとたん、呼び鈴が鳴った。
――来た!
祐樹の気配のようなものを感じた祥子は、覗き穴も見ないでドアを開けた。祐樹が汗にまみれて立っていた。
「暑かったでしょ、入って」
黙ったまま、祐樹は入り、ドアを閉めた。祐樹は布製のバッグを持っていた。
「何を持ってきたの?」
「参考書と筆記用具だよ」
「へえ……」
「友だちのところに勉強に行くって行ったんだ。一応持ってないと」
「歩いてきたの?」
「自転車だよ。下に停めたけど、いい?」
「大丈夫でしょ」
祥子はウーロン茶をグラスに注いだ。
「どんな自転車?」
「マウンテンバイクだよ。去年、誕生日に買ってもらったんだ」
「へぇ〜子供用の? すごいね、盗まれなきゃいいけど」
「あんたの車にチェーンを巻きつけてカギかけたよ。無理すればキズがつくね」
ヒヤリ、と何かが祥子の心に当たった気がした。冷たいグラスを持っているせいかもしれない。
「まず、冷たいものをどうぞ」
祐樹はエアコンの下に立っていた。
「アイスはどんなのが好き? スイカもあるよ」
「ぼく、時間がないんだ。さっさと始めよう」
「そうね、そうしよう!」
祥子は胸に浮かびかけた違和感を無視してテーブルに向かった。祐樹も向かい側に座った。
「N県の共同農場に行ったのはいつ?」
「……よく、覚えてないよ」
「昨日はけっこう話してくれたじゃない。覚えてるんでしょ?」
「ずっと前のことだからだよ。前のことのほうが覚えてるんだ」
「お父さんは一緒だったの?」
「初めて農場に行った時は、二週間の体験コースだったんだ。行きたいっていったのはお母さんで、お父さんは車で送ってっただけだよ」
「お父さんは、反対してたのね?」
「その前から、よくケンカしてたからね。お母さんの買い物がすごくて」
「買い物?」
「太陽の絵の壁掛けとか、土で作った人形だよ」
「ああ、それって……」
いきなり祥子は立ち上がって本棚に向かい、さっと一冊を引っ張り出した。
「これ?」
祥子は雑誌のバックナンバーから写真を見つけ出して示した。グラビアページのそこには、金色の刺繍で不思議な文様を作り、それで太陽のような円を形作られたタペストリーが写っていた。十五万円で売られていた、とキャプションに書いてある。
「そうだよ」
「太陽のエネルギーを呼び込むんですって?」
「よく、知らない。あ、それから、丸い鑑と刀みたいなのも買ってた」
身代わりとなる土偶は五十万円、『霊鏡』と『霊剣』はそれぞれ百万円だったと、雑誌の説明にあった。
「とにかく、お金のことでいつもケンカしていた。でも、お母さんには応えなかったよ」
「お父さんは信じてなかったんだ」
「ぜんぜん、だね」
「きみは?」
「つきあいだよ」
「お母さんに?」
「……」
「……つまり、例のトンネルでの事件から、お母さんが変になった、だから……」
「変じゃないよ! その頃はまだ変なんかじゃない! 疲れただけなんだ! いけないのはお母さんの友だちだ! 相談したら変な人をどんどん連れて来て、おかしくしたんだ」
「でも、きみがつきあったのは……」
ギラリとした視線が祥子の言葉を遮った。
「あんた、誰かと何かするとき、つきあいでしか、したことないの? あるだろ? 一緒にやんなきゃいけない雰囲気って」
静かな口調がヒタヒタと祥子に迫った。タブーだ、この話は後回しだ――祥子は機敏に切り替えることにした。
「東京の道場とか、神殿には行ったことなかったの?」
「ぼく? ぼくはないよ。パパがきつく止めていたからね。パパが家にいるときは、祝詞(のりと)もあげないし、教団の人たちと連絡もしてなかった」
「それでよく、農場へ行くのは許可したね、きみのパパ」
「そりゃ大変だったよ。ママは一人で行くって言ったんだ。パパは行くんならぼくを連れて行けって言った。ママがそのまま帰ってこないんじゃないかと思ったんじゃないかな? パパは」
「なるほど、お目付け役ね」
「お目付け役?」
「で、初めて行った共同農場はどうだった?」
祐樹の実の父・天城一志が妻の照美と息子を車に乗せ、N県に向かったのは、夏休みが始まったばかりの七月下旬だった。
前世紀の村落、それが初期の共同農場の印象だった。高速を降りて二時間、第三セクターの鉄道の駅からはバスを乗り継がなければならない。
標高千メートルほどの山の連なりに隠されて、およそ文明というものからは完全に遮断されている。のどかに田畑が広がり、民家が点在していた。近くを流れる川のせせらぎが、どこからでも聞こえた。廃村をそのまま利用し、修理して使っているという。
「けっこう、いいところじゃないか、自然村ってとこか」
――行ってみて、パパの表情が変わったっけ……祐樹は当時の父の様子を鮮明に思い出した。遠足か校外学習みたいだと、祐樹も思った。
「ここは御食館です。初めての方には、こちらを使っていただきます」
世話係の粟田というおばさんが、祐樹たち母子を共同住宅に案内した。四階建ての寮のような建物だった。村の中央付近に建物はあり、これだけは新しく、ちょっとした旅館のようにも見えた。
祐樹の父は駐車場の停めた車からスーツケースを出し、部屋まで上げた。部屋は三階にあり六畳の和室に小さな洗面台がついていた。窓からは童謡に謡われそうな懐かしげな風景が見えている。
「殺風景だな」
一志は部屋を見回して言った。
「食事は食堂で用意されたものをいただくことになっています。全て無農薬の自家製野菜ですよ。トイレは共同ですが、お風呂は大浴場があります。近くに温泉が涌いていて、そこからお湯を引いているんです」
世話係の粟田が説明する。
「温泉かぁ」
一志ははじめて心が動いた声を出した。林間学校よりはちょっと豪華だ、と祐樹は思った。
「御神体様は、どちらでしょうか?」
うつろな光を宿らせた目で、照美が粟田に聞いた。粟田は面食らったように目を瞬き、それが奇妙だったと、祐樹は記憶している。
「御神体様は最上階にいらっしゃいます。上に神殿がしつらえてあるんです」
「ここにいる皆さん、そこで礼拝されるんですか?」
「ここにあるのは簡易神殿で、本殿は村の奥にあるんですよ。すぐに行く機会が得られるでしょう」
「大御神主様もそちらに?」
「大御神主様はときどきこの村にいらっしゃいます。毎月四のつく、祭日には必ずみえますよ。じゃこの中を案内しましょう。荷物はこちらに置かれて……」
粟田は先に立って館内を巡りながら説明を始めた。食事は六時と十八時の二回、入浴は十九時から二十一時までに自由に入ることになっている。浴場は男女用別々に用意され、かなり大きかった。
食事と掃除、浴室の準備などは当番せいで、毎日どれかをやることになっていた。粟田の説明は、その一つひとつが自慢げで、まるで宝物を見せびらかすような響きがあった。
「パパはすぐに帰ったの?」
祥子が聞いた。
「すぐだよ。荷物を置いて、館の中を見て歩こうとしたときに、帰った」
じゃな、と感情のない声を祐樹にかけて、そのまま館を出ていった。すぐに車が走り去る音がした。一秒もここにいたくないような素振りだ。
「ママはなにも言わなかったの?」
「言わないよ、パパもママも」
こいつは言いたくないことばっかり言わせる。祐樹は心の壁がささくれるような気がした。氷が解けかけたグラスの液体を、ぐっと流し込む。
「で、そこには何人くらい来ていた?」
「夏休みだからね、部屋は六畳か八畳くらいで、全部で三十くらいあったけど、みんな入ってたよ」
「家族づれ?」
「家族の人もいたし、一人もいたよ。恋人同士で来ている人もいた」
「恋人同士で? モンダイありだね」
「問題があるから来てるんだろ?」
「……どのくらいいたの?」
「二週間だよ。初心者体験コースだからね」
「タダじゃないんでしょ? たしか法外な値段なのよね? その体験コースって」
「いくら払ったかはよく知らないけど、そんなに高くなかったよ。海外旅行に行くより安いって、ママが言ってたから」
「入村希望者は、寄付、一人あたり百万とか、言われたけどね。払った人もいたはずだけど」
「最初はそんなじゃないよ。うちにそんなにお金払ってないもん」
「ふ〜ん……」
正確な金額をどこかで確認しなくちゃ、と祥子は考えた。
「毎日、なにしてたの?」
「田んぼとか畑の仕事を手伝うんだ。大人も子供も一緒だよ。あとは修行」
「修行?」
「きついハイキングみたいなの。山奥には瀧もあって、もっとハードな修行をしてる人もいるらしいけど、そのときは見ていない」
部屋には何もなかった。テレビもCDもラジカセも。折りたたみの小さなテーブル、押入れに寝具、家具はそれだけだ。エアコンももちろんなく、開け放たれた窓には網戸もなく、虫が入り放題で、祐樹は蚊の襲撃に悩まされた。闇雲に虫を追ったり叩いたりすると、母は決まって厳しく咎(とが)めた。
「虫は必要があって、虫でいるのよ。痒いからって殺しちゃダメ」
「でも、寝られないよ」
「虫と共存する事も大事なんですって。でもそのかわり、ここは山が近くて朝夕はしのぎやすいわ、冷房なんかいらないでしょう?
なんと言われても、祐樹は防虫剤とエアコンが恋しい気持ちから逃れられなかった。
草むしりと山歩きが日課だった。一応、夏休みの宿題もリュックに詰めていったが、粟田は、そんなものはやらなくていい、と言った。実際、村には子供も多かったが、だれも勉強をしている様子はない。田畑の仕事の他に、母たち女性は山菜取りにも出かけていた。村では養蚕も行なわれ、これも女性が手がけている。男性は土木作業、大工仕事などの共同作業だ。薪割りのようなことから、農家を一軒建てるような大仕事もあった。
そうした作業はきちんとプログラムされ、管理され、村にいるかぎり、誰も逃れることも逆らう事もできない。しかし、実際に逆らおうとか逃れようとしている人を、祐樹は見たことが無かった。
「理想郷ってところね」
祥子は感嘆を込めた声で言った。
「ナチュラル・ブームとかいって、けっこう注目されたのよね、あの頃。マスコミでも取り上げてたし」
「でも、それってほんとの生活じゃないんだ」
「ほんとの生活?」
「本気であの村に引っ越すわけじゃないし、農業を仕事にするわけじゃない。逃げてきたったかんじだよ」
「現実逃避ってやつ?」
「よくわかんないけど、林間学校より、よくないような気がしたよ」
「けっこう、厳しい批判、言うじゃない」
祥子の言葉を賞賛と受け取った祐樹は、少し得意げに頬を上気させていた。
「ママは、そこに住みたいって言い出したの?」
「考えていたみたいだけど、言わなかった。二週間たって、約束どおりパパが迎えにきたんだ」
「そのときは、帰ったんだ」
祐樹はうなずいて、グラスの底を天井に向けて、ウーロン茶を飲み干した。すでに生ぬるかった。ここに来てから、もう二時間は経過している。
「もう……帰らなくっちゃ」
「ちょっと待って、スイカ、食べてかない?」
祥子は立ち上がって冷蔵庫の野菜入れに手を入れた。
「それにしても、よく覚えてるじゃない? いい調子よ」
「だんだんと、思い出すんだ……ひとつ思い出すと、もう一つ思い出して」
――期待できる! 祥子は口元に笑みが浮かび上がってくるのを遮れない。ザクッ、と包丁の音が響き、スイカの傷口から透き通った赤い液体が、まな板の上を伝い流れた。スイカの味も期待できそうだ。八分の一にカットしたスイカを皿に乗せ、祥子は上機嫌で祐樹に差し出した。
「冷えてるよ」
理想郷の朝は早かった。五時には最上階の神殿から聞こえてくる太鼓の音で起こされる。それからみんなで神殿に行って、祝詞を唱える。そのあとが食堂で朝食だ。夜は九時半になると廊下とトイレ以外の電灯が一斉に消される。虫の襲撃とともに、祐樹は薄暗がりの建物の中が不気味だった。
もうひとつ、祐樹を悩ませていたのは空腹だった。毎日、食事が二回しかなく、それも野菜中心だったので、祐樹は物足りなく感じ、いつも腹をすかせていたのだ。さらに言えば、食事はどれこもれも、何か味が足りないようで、はっきり言えば不味かった。だが母は不平を言うことはなく、いつになく明るく、生き生きしていた。
「どうしたの? おなかすいてないの?」
皿に盛られた野菜のくずのような料理を睨んでいると、必ず母は覗き込むように聞いた。
「そんなことないよ」
嘘だ。こんな野菜を毎日見ていたら、どんなに空腹でも胸が焼ける気がする。
「食べなきゃだめよ。今までと違う食事で、慣れないかもしれないけど、つらいのは、身体に毒素があるからですって、だんだん、浄化されていくのよ。食事も大事なの」
「わかっているよ……」
祐樹はいつも、野菜をよくかまずに、丸呑みしていた。
「どうしたの? おなかすいてないの?」
真向かいに座っている直美が、不思議そうに声をかけたので、祐樹はいきなり現実に引き戻された。
「大好きなハンバーグなのに。今日は安全なオーストラリア牛肉、百パーセントだぞ!」
イスの上でちょっと体をゆすって、直美がおどけて言った。
ハンバーグ、オムライス、カレー、フライドチキン、この家に来た頃、この新しい母は息子を気遣って、子供が好みそうなメニューを毎日作った。
以前は仕事もしていなかったので、彼女は、おやつも自作を出してくれた。プリン、アップルパイ、クッキー、タルト、そういうものを食べているうちに、祐樹の体の細胞は徐々に入れ替えられ、普通一般の小学生になっていったような気がした。
「ちょっとね、お父さん遅いのかなって思ってたんだ」
「さっき会社を出たって、電話があったわよ。もう駅には着いたころと思うけど」
「うん」
祐樹はナイフを持ち直してハンバーグに切込みを入れた。肉の抵抗が手に伝わり、それを引き金にして何かを思い出しそうになった。ジワリと肉汁が皿に広がる。
「おいしいよ、最高!」
食事もおやつも自信を持って出すだけあって、料理は上手だと思う。だから学校の給食なんかまったく口に合わない。いや、それよりひどかったのはあの……。
こういうの、餌付けっていうのかもしれない。何かの本で読んだ記憶がある。そんな考えが出し抜けに祐樹の頭の中に沸き起こった。
「そう? でも失敗しちゃった」
「なにが?」
「ちょっと肉料理が続いたでしょ?」
「そうだっけ?」
祐樹がハンバーグを大きく切り取って、四分の一ほども一気に食べたので、直美は安心したような顔になり、自分もフォークとナイフを取り上げた。祐樹の胃袋の中で、生臭い肉とスイカがごっちゃになった。
「明日は魚ね」
「……野菜がいいよ」
「しぶいね」
「ベジタリアンなんだ、ホントは」
祐樹は、ハッとした。直美の顔が曇ったのだ。いけない。挽回しなくちゃ。
「冷たい野菜スープがいいな」
「うわぉ、ヴィシソワーズとか? そんなのよく知ってるのね?」
「知ってるさ、それくらい」
笑いが戻ったので、祐樹はホッとした。同時に玄関の呼び鈴が鳴る。
「お父さんよ、ウワサをすれば」
祐樹は反射的に食卓を立って玄関に向かい、直美は夫用のハンバーグをレンジに入れた。
「気にしすぎだよ」
深夜テレビに視線を当てたままで、口から出たセリフを、直美はありきたりだと反論しそうになり、慌ててその言葉を喉の奥に押し戻した。夫・靖則は四十一歳になる。自分より六歳年上だ。
建築会社に勤める建築家だが、家やビルの設計図を書いているわけでもない。リフォームやインテリア・コーディネイト、あるいは海外の建材を扱うなど、なんでもやっている。おかげで不況でも生活できたが、ふとしたときに直美は夫の背に滲み出た疲れを見て取る時があった。
そう、こんなふうにリラックスしているときなどとくに。無神経なセリフのひとつやふたつは、聞かないフリをしなければならないと思う。だがこの問題は別だ。
「ベジタリアンって言ったときには、ドキッとしたわ」
「野菜だから、だろ? どっかで聞いて覚えたんだ。深い意味はないよ」
まだ、視線はテレビに向けられている。もう少し吸引力のあることを言ってもいいかもしれない。
「覚えているわよね……たしか、あそこでは野菜中心の……」
「そりゃ覚えてるさ、ほんの二年前のことだからな。でも、野菜を我が家のタブーにするわけにはいかないだろ?」
やっと、テレビから視線を外した。
「でも、今ではあのことに触れそうなものは全部タブーになってるわ。かえってよくないのかと、思うこともあるの」
「記憶喪失ってことにしてたからな……」
「何気に話題にしたほうがいいのかしら?」
「……難しいな……」
「今さら、どうやって、何から話せばいいかもわからないわ……」
直美は顔半分を手のひらで隠すように頬杖をついた。
「……上手くやってきたと思うよ、実際、俺たちは……きみもよくやってるし」
「今のままでいいと思う?」
「何か、アイデアは?」
「カウンセリングに相談するとか……」
「何も起こっていないのに、相談するのも妙だよ」
「でも、何か起こってからじゃ……」
「そんな気配があるの?」
「そうじゃないけど……」
確かに不安な予兆だけでは、相談にならないかもしれない。
「ちょっと心配になっただけなの」
「思春期ってこともあるよ」
「それなら、なおのこと難しくない?」
「とにかく、様子を見よう」
また、ありきたりだ、と直美は思ったが、今度も言葉を飲み込んだ。
「テレビ、見てないなら、消す?」
「いや、見てるんだよ」
靖則の視線は、再びテレビに当てられた。毒にも薬にもならないような深夜番組は、直美は苦手だった。それ、どこがおもしろいの? と何度聞きそうになったか知れない。彼女は入浴の準備のために立ち上がった。階段の付近まで歩いてきた直美は、ちょっと足を止めて二階の気配をうかがう。物音一つしていない。
――眠ってるわね。
様子を見る、今はそれしか方法はないかも知れない。自分はできるだけのことをしたという自信もあった。無理に母親になろうとはしないで、友だちのような関係を作ろうと努力した。だからほら、何だって話せる……ただしたったひとつのことを除いては……。
――記憶喪失だったんだろ?
夫の言葉が蘇る。確かに自分たちはそういった。あの子を引き取ったあともマスコミがしつこくて、何も説明しないで、そういうことにしていた。子供なのだ、傷ついている。だからこれ以上、傷つけないで欲しいと、言い張ったのだ。それ以外にあの子を守る方法もなかった。あの子だって何もいわなかった。本当に記憶喪失みたいに……
本当に……?
直美は自分の思考に、ひっかかりを感じた。
――ぼく、知らないよ、覚えてないよ。
あの子は繰り返し、何を聞いても、そう言った。だから記憶喪失ということになった。でも、自分達が記憶喪失だと言い出したのが先だったのか、あの子が何も覚えていないと言ったのが先か、それは覚えていない。
そこまで思考を進めて、直美は頭を振って笑みを浮かべた。気にするなんておかしい。あの子はまだ小五なのだ。何も話さないのだから覚えていない、気にしてもいない。それでいいではないか。やはり様子を見ているのが一番だ。
今日は入浴剤を入れて、薬草風呂にしよう。直美は自分だけのリラグゼーション・タイム充実のために、頭を切り替えた。
どんよりした雲が、どんどん重さを増して、今にも頭上に触れそうになっていた。暑さに加えて湿気が淀み、夕立の匂いが濃厚になってくる。車をガレージに滑り込ませ、祥子がドアから出たとたん、大粒の雨がポタリと頬にあたった。
――来た!
急いでカギをかけ、車から離れてなにげなくガレージの奥に視線を投げたとき、視界の端に見慣れない自転車が入った。シルバーに輝く、子供用のマウンテンバイクだった。
祥子の目には、そのマウンテンバイクが彼女に抗議しているように見え、慌ててエレベータに飛び込んだ。三階に着き、廊下に出ると、自分の部屋のドアの前に、祐樹が立っているのが見えた。予想していたはずなのに、祥子の胸がドキリとした。
「ごめん! ごめん! ちょっと仕事、入っちゃってさ」
彼女は駆け寄りながらバッグに手を突っ込んだ。カギを探したが、持たずに出たようだった。祥子は電機のメーターの後ろに爪を入れ、金具に針金で引っ掛けてある合鍵をつまみ出した。雨が音を立てて降り始めていた。
「カギ、忘れちゃって……雨、大丈夫だった?」
「十分前に来たんだ」
「それはラッキー……じゃないか? 待たせたもんね。でもよく待っててくれたね」
「……十分待って来なかったら、帰ろうと思ってたよ」
雨を逃れるように、二人は部屋に入った。
「仕事って、なに?」
「大した仕事じゃないの。リライトよ」
「リライト?」
「テープ起こしでね、対談を録音したのを聞いて、原稿にするの」
「そんなのも、やってんだ」
「ライターだけじゃ、食べていかれないからね。頼まれれば、やりますよぉ」
祥子は大きなバッグを、リビングの片隅にドサリと置き、電話の着信をチェックし、次いでエアコンのスイッチを入れた。
「除湿って機能がありがたいわね」
「ぼくの話が本になれば、売れる?」
「話題にはなる、これは絶対!」
冷蔵庫を開けてグラスに氷を落とした。
「そしたら、お礼しなくちゃね。さ、今日は健康茶を作っておいたのよ、飲んでみて」
祐樹はいつものように、床に座った。ベランダを背にテーブルを挟む、もう、ここが彼の指定席になっていた。
「でさ、この間の続きだけど、二度目に共同農場に行ったのは、いつ?」
祥子が向かいに座り、セカセカと聞いた。
「一年くらい後の秋……十月だよ」
「また、体験コース?」
「夏休みじゃないから、そういうコースはなかった。でも二回目からは、いつでもその村に行けるんだ」
「パパも一緒だったんだよね? 二回目からは参加したんだ」
「うん」
「どうして、行く気になったの?」
「会社が、倒産したんだ」
「証券関係だっけ? きみのパパ」
「そうだよ。よく知らないけど、けっこうニュースにもなったらしい」
その辺りのことは事件当時も話題になっていた。ふいに道を断たれたサラリーマン、失業の罪悪感と失望が、ふらふらと宗教に近づけたと伝えられている。仕事を失った空虚に入り込む宗教……よくありそうな、いかにもの図式が想像される。
「そうとう、ショックだったんだね。で、宗教にすがろうと思ったわけだ」
「そこまでは思ってないよ。時間が出来たから何かやってみようと考えてて、ママがちょうどいいからって誘ったんだ」
「自然村だっていって、気に入ってたんでしょ?」
二度目に共同農場に行ってみると、村落はさらに拡大していた。高速から舗装した道路が続き、それがメインストリートにつながって、村の中央を走っていた。そして合宿用の建物は三軒に増え、駐車場も広くなり、大型バスが二台見えた。
そして何よりも、村の入り口に巨大な門が出来ていたことが一家を驚かせた。以前はこんな入り口などなく、開けた印象だったが、今は奇妙な威圧感がある。
「なんかすごいな、前より立派になったんじゃないか?」
門の前で停車し、車から降りて辺りを見回しながら、一志が言った。
「写真では知ってたけど、立派になったわ、確かに。最近じゃ体験コースに参加するのも順番待ちのよ。私たちは二度目で、浄化されているから、入村も優先されるの」
照美の声は自慢に溢れていた。いつものように、そんな様子を父が咎めるかと、祐樹は思ったが、一志は何も言わなかった。むしろ、追っ手から逃れきって、ほっとしているかのような印象がある。
「ようこそ! また御目にかかれて、嬉しいですわ!」
門の近くの事務所らしき建物から、粟田が走り出てきた。その姿を見て、祐樹と一志はギョッとした。白い、布切れ一枚の衣装を着ている。まるで埴輪のようだった。
気がつくと、門で車を誘導した人も、受付に座っている人も同じものを着ている。制服のようだった。
「……前も、そういうの、着てましたっけ?」
一志が聞いた。
「いいえ、今年からですよ。村の人となった者、浄化された者だけが、だけが着用を許されるのです」
衿元に手を当てながらの説明が、自慢そうだった。
「浄化?」
父の声が意外に大きく響き、祐樹は思わず顔を見た。困惑が隠しようも無く押し出されている。反射的に母の顔も見た。照美の目は羨望の色が浮かんでいる。
「じゃ、今日からよろしくお願いします」
代表するように一志が頭を下げた。
「三週間のご予定でしたね?」
「? 二週間じゃなかったのですか?」
「いいえ、体験コースではありませんので、こちらの規則どおり最短滞在期間は三週間、そう決まっております」
「二週間と言わなかったか? 前と同じだって」
一志が振り返って照美を見た。
「三週間よ、そう、言ったわ」
「ばかな。二週間のはずだ。第一、祐樹の学校もそんなに休めないぞ」
祐樹は両親の間で、両方の顔を交互に見上げた。
「どうせあなたの仕事が変わったら、あの家も出るんだし。転校するんだもの、いいじゃない」
照美の視線は一志のそれとかみ合っていなかった。
「まだ決まったわけじゃない」
「祐樹はまだ三年生よ。勉強なら見てやれるわ」
「ぼく、大丈夫だよ。ちゃんと取り返すよ」
たまらずに祐樹は口を開いた。思いがけず、自信に満ちた声になったのが、自分でも不思議だった。そんな祐樹を、粟田がじっと見つめていた。
「さすがに農場体験者だわ。祐樹君、しっかりしてるわね」
粟田が誉めたので、照美は笑顔になったが、一志と祐樹は複雑な表情を変えられなかった。
「ここなら、学校にいる以上に、気高く貴重な経験が得られますわ。子供は聖なるものにも自然にも近いのですから、大人より多くのことを吸収できるんです。さぁ、お部屋へ」
粟田は一家を促したので、一志も諦めたように従い、御食館の一つに向かって歩き出す。
「また、この建物ですか?」
「一戸建ての家は、永久入村者でなければ使うことは出来ません。天城さんは、今回二回目ですから、少し広いお部屋ですよ」
照美は一戸建ての家が並ぶ村の中ほどを眺め、再び羨望込めた目つきをした。
案内された部屋は、確かに広かった。六畳と三畳の二間続きである。窓も大きかった。祐樹は窓に近づいて、村を眺めた。こうして見てみると、村は拡大されたと思う。
一戸建ての家も以前は三十件くらいだったが、今はかたまって点在し、百件はありそうだった。田畑の間に家は数件ずつ集落を作り、それが山の裾野のほうまで広がっていた。道も用水路も整備され、あちこちに電動の農具も見えている。人も増え、白い服がせわしなく動く様子が奇妙だった。
童謡に謡われるような風景だった村は、一年数か月のうちに、大変貌を遂げたようだった。
「計画経済の農場ってのは、こんなかんじかな」
いつのまにか背後に立っていた一志が、誰に言うともなく、つぶやいた。 (つづく)
Copyright(c): Hisae Ishii 著作:石井 久恵
*石井久恵さんの作品集が、文華別館
に収録されています。
*光文社が一般公募していた「奇妙におかしい話」(阿刀田高選、文庫457円)に石井さんの作品が入選、収載されています。